「北海道」という共通の軸を通し、様々な年齢や職種の方から話を聞いてきた本シリーズ。最後となる今回は、東京に舞台を移し、人材育成のプロフェッショナルである私たち自身に立ち返りたい。長崎の壱岐島出身で、グロービスのマネジング・ディレクターを務める西恵一郎が考える、地域活性化を通じて生まれるリーダーとは。
地域活性化のカギは雇用を創出し続ける仕組みづくり
篠田:「地方創生」という言葉についてはどう思うか。「地方創生」という言葉は地方と中央という対比をベースに、中央の視点で考えられた言葉だという議論がある。
西:そもそも地方は「創生」されるものではないし、地域に住んでいる人たちはきっと満足していて「創生してほしい」とは思ってない。子供世代や孫世代が自分の住む地域に同じように住めるようにしたい、ということがみんなの願いなのでは。つまり、この地域のエコシステムを持続させていきたいという想い。
一方で、日本全体で人口が減るのは目に見えている。日本の人口問題の根本は、出生率の高い地域から出生率の一番低い東京に日本中の人が流れ込んできていること。地方に住んでいたら出生率は比較的高いレベルで維持されるはずだが、東京に一極集中していけばいくほど人口減が加速してしまうという構造的な問題がある。
篠田:地方で雇用機会が少ない状況が続けば、東京に流れ込んでしまうと。
西:こうした機会の偏りがある程度改善され、地方に住んでいても仕事ができる環境が整えば人口集中しないが、そのためには雇用機会が集中しない仕組みが必要だ。
篠田:人口流動によって地元を離れている人が多い中、「地方創生」「地域活性化」は誰のものかというのも重要な話。各人が故郷の活性化を自分事化として取り組まなければ、日本全体の地域が衰退していくことが見え始めている。
西:そこで大事になるのが「シビックプライド」だ。自分が外に出た時に自分の出身地に対してポジティブに話ができ、他の人が行きたい・住んでみたいと思えるような話ができるかどうか。でも「シビックプライド」は小さい時から教育しないと生まれにくい。
篠田:最後に今後の抱負を教えてほしい。
西:地域活性化について、「なんとかしたい」とすでに動いている人はいる。問題はその方々だけでは足りないということ。想いを持って活動する人が増えない理由はいくつかある。アイデアがなくて行動できていないのかもしれないし、自分が取り組むべきだと思えていないかもしれない。こうした人達を「行動を起こせる人」に変えていくことを、僕らはやっていかなければいけないと思っている。彼らの想いに火を燈して促していくことはできると思うので、そこに携わっていきたい。
きっかけは小さなことかもしれない。「意外と自分にもできる」と思えば自信を持って動くかもしれないし、「自分の地元のことだ」と思ったら自分事化できるかもしれない。そこを後押しすることが使命だと思う。
インタビューを終えて
今回のインタビューで見えてきたことは、地域に「第三者」として関わる難しさや意義だった。確かに、実際に地域に住んでいなければ見えてこない魅力や気づけない課題があるのは事実だが、それゆえに「地域活性化には携われない」ではなく、「第三者」でありながら「自分事化」して携わっていく可能性を感じて頂けたら嬉しい。都市部に住んでいたとしても、地元や故郷がある人は多い。今は住んでいないからこそ、地域間を繋いだり、地域にいるドライバーとなる方の背中を押すこともできるのだ。




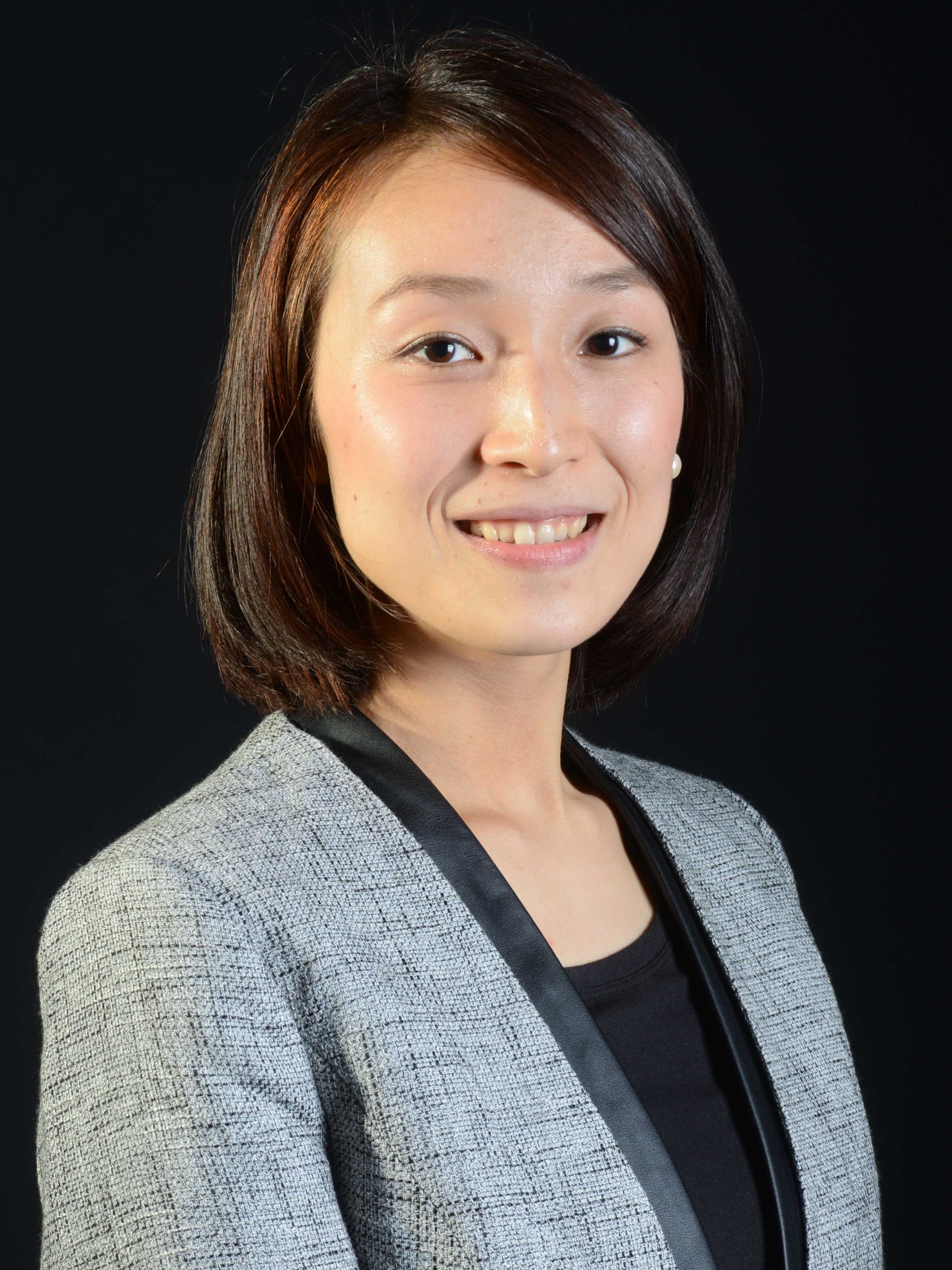
































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)



