
前回は、日本的大企業のイノベーションは組織戦で戦うこと、またその際、組織内外をつなぐ役割を担うことが重要であるとお伝えしました。さらに、アンケートやインタビューを通して、新規事業で成功体験を積んでいるミドルには、5つの共通した資質があることがわかり、この資質・要件について頭文字をとって「NINJA」(忍者)とネーミングしました。
N=Network(社内外の人脈、ネットワーク力)
I=Insight(課題抽出力、本質を見抜く力)
N=Nemawashi(根回し力、巻き込む力)
J=Joy(自分の仕事も、困難も楽しむ力)
A=Ambition(圧倒的当事者意識・大志)
今回は、そのうちのNとI の事例を見ていきます。人脈やネットワーク、課題抽出力は、なぜ必要なのでしょうか。そして、どのように使うと効果的なのでしょうか。
ケース1:社内の強いネットワーク
大手電機メーカーに新卒入社したHさんは、女性初の技術者として新商品の開発部門に配属されました。彼女はユーザー視点で考えることにこだわりながら、家電開発に20年以上携わり、それまでの常識を覆す機能が盛り込まれたヒット商品を連発しています。
しかし、これらの商品の発売にあたっては、経営会議どころか、
ある年の新商品検討会議の目前、新機能アイデアに困っていた彼女を救ったのは研究所の先輩だったYさんでした。過去の関連論文を洗いなおし、新機能に活かせそうなアイデアを提示してくれたそうです。「お客様からも間違いなく支持されます」と営業部門からも援護射撃をうけ、この新機能は会議承認され、搭載商品も大ヒットとなりました。
「長く勤めていると、知り合いも増えるでしょ(笑)。同じ釜の飯を食った仲間だからこそ理解できることもあるし」とHさんは語ります。
日本的大企業は縦割り組織が強く、他部門からの理解や協力は得にくいと考えられがちですが、ジョブローテーションや過去の業務実績から得た個人的な社内ネットワークを使えば、部門を越えた理解者や協力を得ることも可能で、それがイノベーションを成功させる1つの要因にもなるのではないでしょうか。
ケース2:社外の緩やかなネットワーク
接客サービス会社で新規事業部門を立ち上げたKさん。自社は国内でトップシェアを持つ転職者も少ない大企業。優秀な人材は多いものの、同質な意見が多く、新しい発想やアイデアが出にくい状況だったそうです。Kさんは、ある有名な経営者が主催した異業種横断型の勉強会に参加したことで、社外に目を向けるようになりました。
Kさんは、勉強会での経験について、このように語っています。
「XX塾は、良い気付きやヒントをいただくきっかけになりました。自社の強みに社外の異質なアイデアを組みあわせることでイノベーションは生まれるのだということを実感しました」
「ただし、漠然と付き合っていてはダメです。『彼らのやっていることを我々のビジネスに生かすにはどうしたらいいのか?』という視点を持ちながら参加することが大事です」
セミナー、ハッカソン、勉強会、SNSなどは、ミドルであってもやる気さえあれば参加可能です。積極的に参加すれば、社外に緩やかなネットワークを作ることは難しくないはずです。社外のネットワークを活用した異能の組み合わせは、新しい事業やイノベーションが生み出されていくきっかけになりそうです。
ケース3:課題抽出力、本質を見抜く力
食品メーカーで新規事業を立ち上げたSさん。自社は食品事業に携わることが出世の王道とされており、事業部ごとの派閥が強いそうです。失敗を恐れ挑戦しない企業文化もあり、20年ほど前に亜流の新規事業部門で研究を行っていたSさんは、あるアイデアの事業化に挑んだものの、諦めた経験がありました。
研究者は亜流事業に積極的にチャレンジはしたがらなかったし、予算も簡単に取れなかったとのこと。しかしこの技術が社会に貢献でき市場に求められていることを、Sさんは顧客の声から確信していたそうです。
「いつかまたチャレンジしたい」――その気持ちをずっと胸に秘めていました。その後、主流事業を経験し、北米拠点の駐在員となり、その後また新規事業部門の担当となりました。北米市場では、Sさんが考えたアイデアに対してニーズがあり、一方で日本ほど市場は大きくないことがわかりました。「技術も進歩しているし、仮にうまくいかなくても、全社へのインパクトも大きくない。小さくスタートすれば、失敗の痛手も小さい」と感じたSさんは、「北米市場で試させてほしい!」と本社に相談しました。
主流事業を担当していたときに人脈を広げていたSさんは、この時は社内で信頼を得られるようになっていました。研究者、開発者、順調に支援者を揃えていき、予算も確保できました。ずっと課題意識を持ちながらチャンスをうかがっていたからこそ、適切な展開拠点、実現可能性を見抜けたということが言えそうです。
課題抽出に関しては、他の方もこのように語っています。
・会社がお客様ではなく競合の方ばかり見ていることに疑問を感じ、逆に徹底して「お客様に喜ばれることって何?」という視点を持つようになった
・技術者は自分のやりたいことをやってしまいがち。自分はそれではダメだと思って、顧客が抱える本当の課題について考え抜くことを意識した
まとめ
今回は「N=Network(社内外の人脈、ネットワーク力)」「I=Insight(課題抽出力、本質を見抜く力)」に関する3つのケースをお伝えしました。
社内の強いネットワークは、協力者を集め、自分がやりたいプロジェクトを実行するための武器になりそうです。一方、社外の緩いネットワークは、自分がそれまで持っていなかった多様な考え方や知見を効率的に収集でき、事業の0→1のフェーズでの発想や、創世期において重要な要素になるでしょう。そして、与えられた課題を解決するだけでなく、顧客視点に立ち、「そもそも何が問題なの?何が必要なの?」と課題を抽出する力がなければ、イノベーションのタネが見つけられないことが分かりました。
次回は、「N=Nemawashi(根回し力、巻き込む力)」「J=Joy(自分の仕事も、困難も楽しむ力)」「A=Ambition(圧倒的当事者意識・大志)」について紹介します。
■次の記事
イノベーションでは「根回し」や「楽しむこと」も必要
■前の記事
日本企業のイノベーションは組織戦で勝負



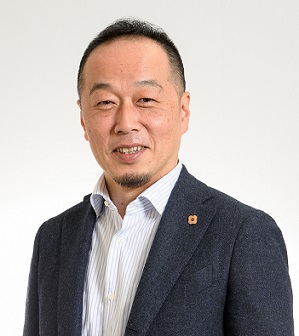
























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

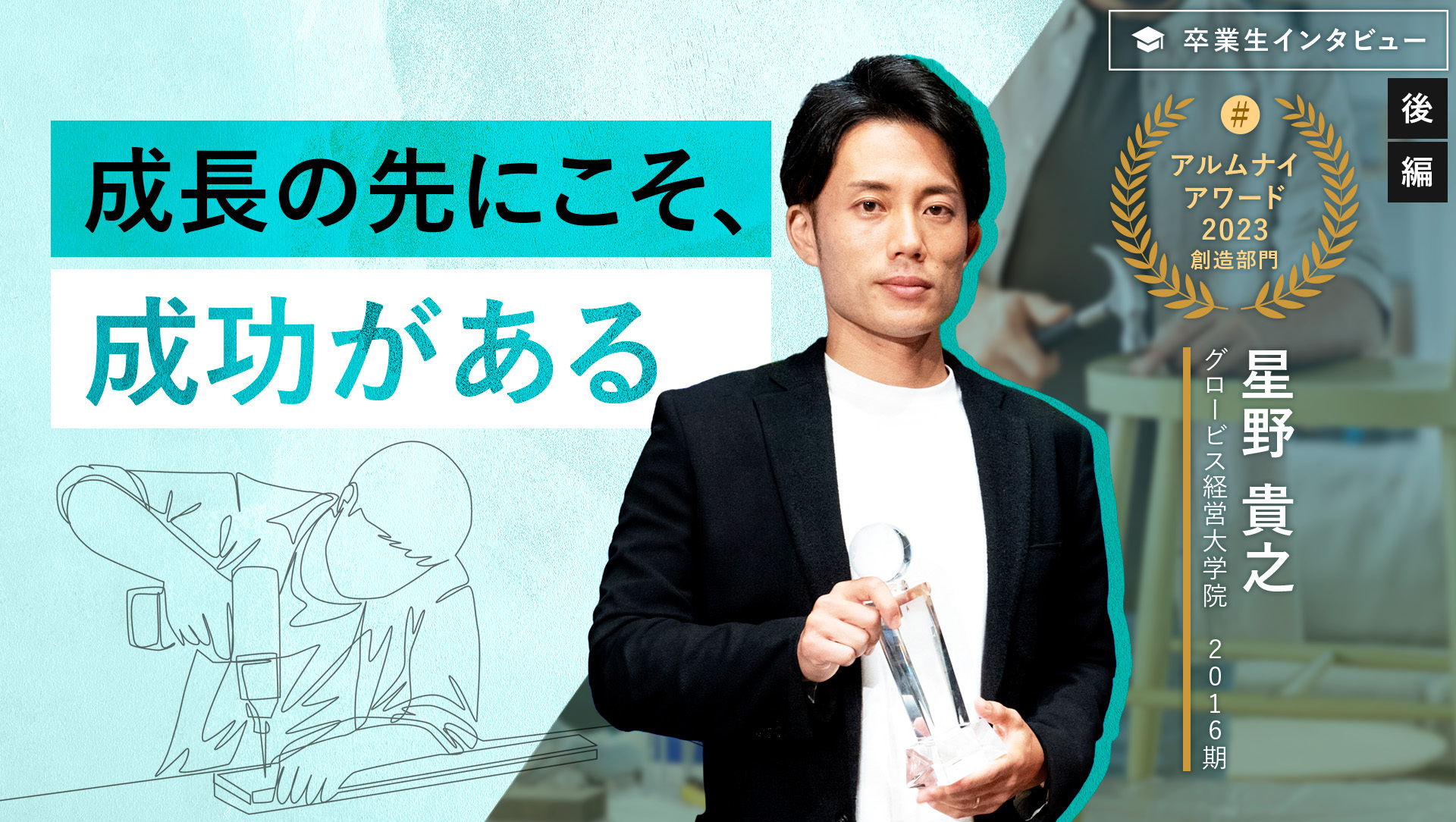











.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




