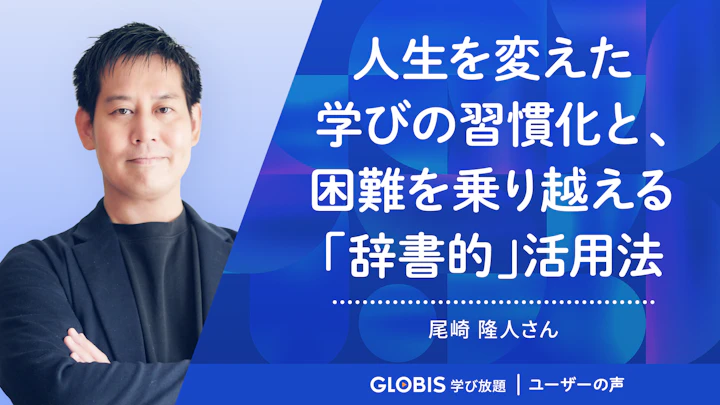「べき論」に依らない理念
【Googleが発見した10の事実】
1.ユーザーに焦点を絞れば、「結果」は自然に付いてくる。
2.1つのことを極めて本当にうまくやるのが一番。
3.遅いより速い方がいい。
4.ウェブでも民主主義は機能する。
5.情報を探したくなるのは机に座っているときだけではない。
6.悪事を働かなくても金儲けはできる。
7.世の中の情報量は絶えず増え続けている。
8.情報のニーズはすべての国境を越える。
9.スーツがなくても真剣に仕事はできる。
10.すばらしい、では足りない。
いまや勝ち組IT企業の代名詞ともなったGoogle。同社サイトの経営理念のページは非常にユニークだ。
ページの冒頭に「最高に甘んじない」という理念(英語ではOurPhilosophy)が掲げられているのは一般の企業とそれほど変わらない。が、その次に続くのが上記の「Googleが発見した10の事実」(英語ではTenthingsGooglehasfoundtobetrue)なのだ。「行動規範」でもなく「指針」でもなく、「事実」という言葉を使っている企業は他には思いつかない。
では「事実」と、「行動規範」や「指針」との違いは何なのか。一言で言えば、「事実」は事業展開をしていく中で確信するに至ったまさに「ファクト」であり、「行動規範」や「指針」は経営者の「願望」であるという点だ。もちろん、企業によっては、その願望を実現すべく、人事システムや採用基準、あるいはトップからのメッセージに徹底的にこだわっているところもある。しかし、多くの企業において、行動規範や指針がお題目にとどまり、従業員の意識や行動と乖離しているのもまた事実である。
その点、Googleの「事実」は、願望や「べき論」ではない、客観的なファクトである(中にはファクトというには微妙なものもあるが)。ファクトの強みは、その説得力である。ただし、「こういうファクトがあるからこうすべし」という形にしていない点に、Googleのこだわりを感じる。たとえば、「悪事を働かなくても金儲けはできるから、悪事は避けよ」ではなく、ましてや「悪事は働くな」ではなく、「悪事を働かなくても金儲けはできる」とだけ示し、あとは関係者の自主性、自由意志、自己選択に任せている。
まあ悪事云々は常識人であればそこからの判断もぶれないかもしれないが、たとえば「世の中の情報量は絶えず増え続けている」は、人によってそこからの解釈はぶれそうだ。しかしそれでも、そこから何を引き出すかは、やはり個々人に委ねられている(多少のヒントは提示されているが)。筆者はこうしたところに、「個」を活かすことこそが競争力の源泉であると考える21世紀の企業らしさを感じる。つまりGoogleは、これらの「事実」を突きつけられた上で、「SoWhat?」(だから何がいえるのか、だから何をすべきなのか)を自主的・自律的に考え、行動できる人材以外は欲しない、という姿勢を打ち出しているのだ。
時代に即応できるGoogleらしさ
ところで、「事実」はただ客観的であるだけでは説得力を持たないし、求心力も生まれない。上記の「事実」が求心力を持つためには、成功が不可欠である。大成功を収める中で確信した事実だからこそ、「この事実を踏まえて思考・行動していけば、新しい成功が待っているはずだ」という確信を持てるのである。その意味で言えば、成功(できれば大成功)してきた企業には馴染みやすいが、通常の企業が真似をするには難しい手法なのかもしれない。もっとも、失敗から学ぶ教訓もあるはずだから、それもうまく交え、成功のための事実と、失敗を回避するための事実を併記するなどのバリエーションも考えられそうである。ぜひ、読者の皆さんも、ご自身の会社の「我々が発見した10の事実」を考えてみていただきたい。
ちなみに、「Googleが発見した10の事実」の中で、個人的に最も気に入っているのは、10番目の「すばらしい、では足りない」である。これは実は理念の「最高に甘んじない」を別の角度から言い換えたものとも言えよう。激化するグローバル競争の本質を言い当てていると同時に、顧客や社会に対するコミットメントを示し、高い挑戦心を持つ人々を引き付けるはずだ。また、具体的なサービスだけではなく、従業員自らの成長も重視している(当然その裏側には成長を重視する企業文化や成長につながる機会があるはず!)ことを暗示している。
さて、近年の経営環境の変化は著しい。昨日の競争ルールが明日も通用するとは限らない。勝ち組の代表とも言えるGoogleとてそれは例外ではない。となれば気になるのは、どのくらいの頻度でこれらの「事実」を入れ替えたり追加したりするべきなのかという点である。もちろん正解はない。正解はないが、少なくともGoogleは柔軟にそれに対応していくはずだ。そうした変化を提案、実行できる人材を集めているはずだからである。


































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)





.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)