組織構造は戦略との整合性を持つように設計される。組織のサブシステム、部署間の関係も一定のルールの下に調整される。したがって、各人の能力や経験の相違を考慮しなければいけないもの、目的合理性に基づいて組織構造を設計すれば、組織は目的、戦略を達成できるように思える。
しかし、組織をいくら精緻に設計しても回避できない問題がある。意思決定の問題である。
(1) 「限定合理性」の下での意思決定
まず、サイモンが指摘するように、われわれ人間は、「限定合理性」に基づいてしか意思決定できない存在である。どんなにたくさんの情報が手元にあっても、どのように優れた分析手法を駆使しても、最終的に意思決定する人間自身の合理性には限界がある。
限定合理性を考える上では、「間違いを犯すことがある」というよりも、「考えが及ばない」という表現のほうが適切であろう。自身が合理的に判断したと自覚しても、その基準の合理性が不十分という意味であり、だからこそ厄介である。
そこで、1人ではなく複数で考えるという手段を取る。複数の視点で限定合理性の補完を試みるわけである。「三人寄れば文殊の知恵」ということわざでは、複数で考えると補完どころかさらによい判断ができるとしている。しかし、社会人としての経験を振り返れば、「知恵」が生まれるのは極めて稀である。このことについて次に考えたい。
(2) 集団意思決定の特徴
複数の人間が集まり意思決定することは日常的に行われるが、「会社の会議はつまらない、退屈だ」という声もまたあちこちから聞こえてくる。会議の主宰者である上司の長々とした演説を聞くだけで、上司の意向に沿った発言しか出ないといったことが退屈の理由になっているようである。あるいは「やたらと会議が多い」という声もある。この場合は個々の会議で意思決定できず、先送りされるからである。つまり、意思決定するという責任を回避あるいはあいまいにした会議が多いと、会議を重ねざるを得なくなるのであろう。
こうなると文殊の知恵どころではなくなるが、集団での意思決定がこのような特徴を持つことが社会心理学では知られている。代表的なもの2つを紹介する。

(3) 不確実な環境での意思決定
このように意思決定を合理的に行うことはそれ自体が難しいものだ。さらに、必要な情報がすべて手元にあり、それを分析し判断できるということは稀なケースであろう。限定された情報を、さまざまな経験や知恵を総動員しながら、より的確な意思決定を試みているというのが現実である。組織の外にある情報を入手することが難しいことはもちろんだが、組織内だからといって必要な情報が必ずしも手に入るわけではない。多数の人間が協働するシステムにおいて、自分以外のメンバーが何に関心があり、何を知っているかということは、よほど特別な関係でない限り、共有されていることは滅多にない。
そこで、組織が的確に意思決定するためには1人ひとりの自律性が条件となる。実務の現場で起きているわずかな変化を見逃さず、違和感を抱き、その理由を考え行動するということが環境の不確実性に対応する手段の一つだからである。不確実性を事前に予測することが不可能である以上、変化の兆候を読み取り、素早く行動することがポイントとなる。
特に問題が発生している現場では、上位者の判断を求めていたのでは対応が遅れることがある。訪問先の受付の雰囲気が暗い、職場の空気が淀んでいる……といった経営不振の兆候を感じ取り、素早く対策を打つことができるのは現場の営業担当者である。もちろん、重大な案件であれば、担当者レベルの判断だけでは難しいこともある。その場合でも、自発的に情報を伝えるという行為が大切だ。つまり、どのような情報を上位者に伝えるべきかという判断は担当者に委ねられる。
もう1つのポイントは、組織全体として整合性のある判断ができるように、行動ルールを明確にして共有することである。行動ルールとは、例えばメンバーが守るべき行動規範であり、会議の運営ルールでもある。
自律的行動は有効だが、バラバラに行動していたのでは資源や時間の無駄使いになるし、効果も限定的になる。そのため、組織メンバーが相互に行動を調整することになるが、都度調整していたのではコミュニケーション・コストが掛かる。行動ルールを共有することで、このコストは低減できる。
例えば、東日本大震災のとき、日産自動車の生産ライン復旧が早かったのは、日頃から災害対策の訓練を重ね、緊急時に何をすべきか社内で共有していたためだといわれる。なお、日産自動車は訓練を繰り返すたびに、マニュアル自体を改善するそうだ。
高まる「環境不確実性」への対応
今後、企業を取り巻く環境の不確実性はますます高まると予測される。その大きな理由は、企業組織の活動がグローバル化に代表されるように多様化していることだ。企業活動は外部環境から影響を受けるが、同時に外部環境に働き掛け、変更を迫る。例えば、日系企業が中国に進出すれば、中国の労働市場を変えることになり、賃金の上昇などを引き起こす。そうすると、低賃金を前提として進出しながらも今度は優秀な人材を確保するために対応を迫られることになる。環境とは単なる外部条件ではなく、企業組織が何らかのアクションを起こしたときに、立ち現れ変化していくものなのである。企業活動が活発になるということは、環境の不確実性が増すことに直結する。
しかし、われわれはプロメテウス(ギリシア神話に登場する神の1人、先見の明を持つと知られる)でない以上、未来を予測することができない。
そこで、不確実性へ対応するために、2つの方向性を考えてみよう。
(1) 規模の拡大による対応
1つは、組織の規模を拡大し、潜在的な不確定要素をできるだけ内部に取り込む方法である。
例えば、資材の調達の安定化に向けて、別会社を設立するとか、M&Aをするといったことである。このような規模拡大にはガバナンス(企業統治)という問題が生じるが、組織構造の面から見ると、1997年に持ち株会社が解禁されたことによって、ガバナンスを効かせながら規模拡大ができるようになったといえる。
ただし、規模が大きくなればなるほど、組織としての方向性を一定に保つことは難しくなる。理念や戦略を共有することが一層大切になる一方で、個人の能力、自発性に依拠する部分が大きくなるので、人材育成が大きなテーマとなる。両者を担当するのは人事部であるが、人事部自体も規模が大きくなる。
例えば、ある保険会社では、採用担当者、教育研修担当者、人事評価担当者などの間で、人材要件や戦略について擦り合わせすることが必要になっているという。
(2) ネットワーク化による対応
もう1つは、不確実性をできるだけ外部化するという方法である。ある機能を組織内に長期的に保持していれば、さまざまな問題に遭遇する確率は高まる。そこで、機能を組織外に置き、必要なタイミングだけ協働する。それが「ネットワーク型の組織」で、生産機能を持たないアパレルメーカーなどが典型例である。
このような組織では、他の組織との信頼関係をいかに構築するかが課題となる。内々の論理ではなく、常に外部の組織の論理を理解し対応できる能力が必要となる。ここでも1人ひとりが自律的に行動できることが求められるが、さらに自ら外部にネットワークを作り、協働できる能力も期待される。つまり、行動原理が違う相手を巻き込んで価値を生み出すような意思決定ができなければ、ネットワーク型の組織は機能しなくなる。
現実には大規模組織とネットワーク型組織を両極として、いろいろなバリエーションが生まれることになろう。
そもそも、血縁も地縁関係もない人間同士が、ある目的を達成するために作ったのが組織であり、その起源は産業革命に遡ることができる。人間の歴史から見れば、つい最近のことであり、組織構造や意思決定の在り方はさらなる模索が続くことになろう。
次回は、適切な意思決定を可能とするための条件についてです。
※労政時報に掲載された内容をGLOBIS知見録の読者向けに再掲載したものです。


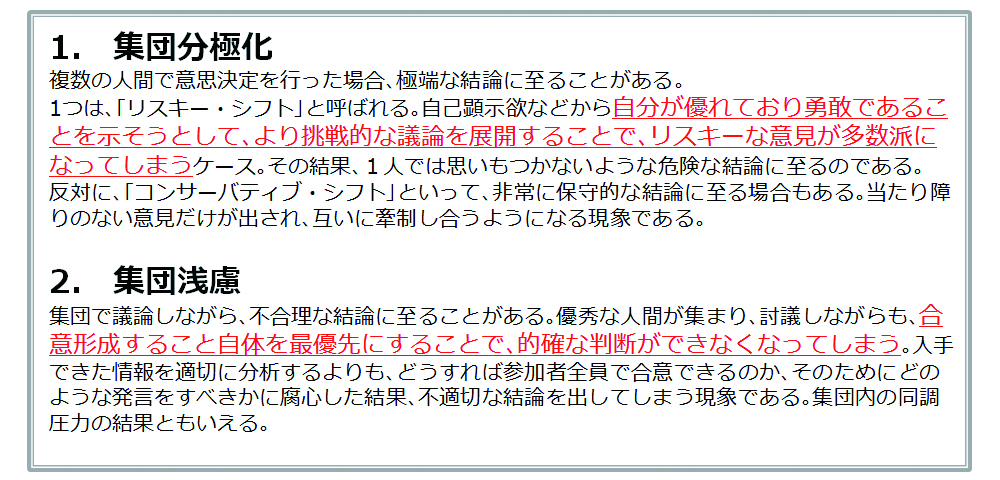





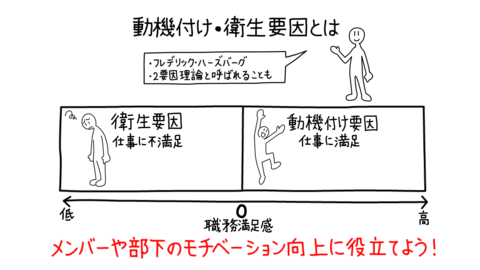






























.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




