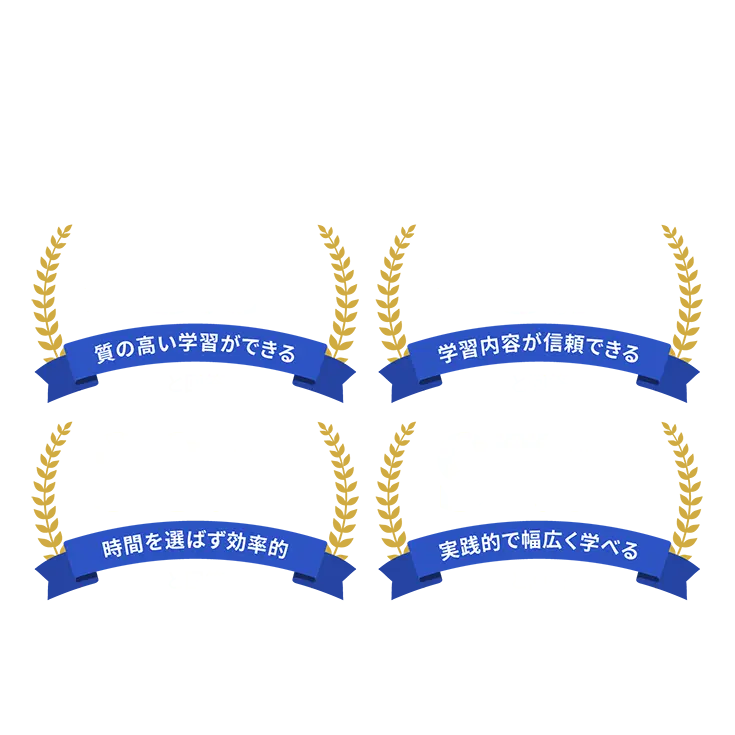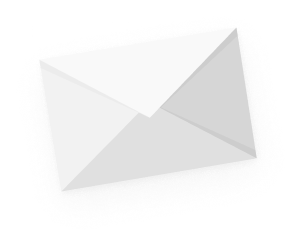世界的に物価に上昇圧力が掛かっています。米労務省が2022年1月12日に発表した米21年12月消費者物価指数は前年同月比+7.0%となり、上昇率は39年半ぶりの高さとなりました。
欧米の物価上昇と比べると日本の消費者物価指数(CPI)の伸びは鈍いものの、実際にスーパーやコンビニエンスストアなどで買い物をした時に、「物価は上がった」と実感する読者は多いのではないでしょうか。前回の「経済指標の備忘録」では消費者物価指数の概要を整理し、日本のCPIが伸びにくい個別要因を取り上げました。今回は一歩踏み込んで、日本銀行の金融政策にCPIがどう関わっているのか、基本知識を押さえていきます。(全2回後編。前編はこちら)。
日銀が重視するコアCPI
前回は日本のCPIの伸びを抑えている品目として、直近数カ月レベルの話では通信各社によって引き下げられた携帯電話料金があり、そのほか家賃、公共料金の3つがあることに触れました。
あらためて2021年12月のCPIの中身をみてみると、前年同月との比較ではコロナ禍で20年に大きく落ち込んだ宿泊料が反動で+44.0%と大きく上昇し、CPI(全国総合、前年同月比+0.8%)を0.29ポイント押し上げる要因となっています。
宿泊料の上昇は、携帯電話と同様、一時的な価格変動ととらえることができます。このほか、食料品やガソリンなどがCPIの上昇に寄与しているのが分かります。

短期的に価格のブレの大きな品目の影響を受けたCPIをもとに、中長期の国民生活に影響を及ぼすような政策を立案することは、あまり適切ではないという意見があります。世界各国の中央銀行によって重要視する物価指標は異なりますが、日銀の場合、現行の金融緩和策を継続するにあたり、価格変動が大きい生鮮食品を最初から除いて算出する「コアCPI」を重視して政策を運営しています。
2%目標と金融緩和策
日銀は黒田東彦総裁の就任後、2013年1月に物価上昇率を前年比+2%に高める目標を掲げ、国債の大量購入をはじめとした異次元の金融緩和策に乗り出しました。一般的に2%という水準は、国家が安定的な経済成長を遂げるためのひとつの目安とされています。物価の安定的な上昇に伴う企業収益の拡大で賃金が上昇すれば、消費は底堅く推移し、経済に好循環が生まれるという考えです。
より具体的には日銀は、生鮮食品を除いたコアCPIの上昇率が安定的に2%を超えるまで、マネタリーベース(日銀が世の中に供給する資金量)を拡大する、などの方針を示しています。
ところがコアCPIには、携帯電話の値下げによる一時的な影響が含まれています。この影響を除いた21年12月のコアCPIは2%前後になるとも報じられている_ほか、22年4月には携帯電話料金引き下げの影響が剥落するため、コアCPIそのものも2%に接近するのではないかとの見方が広がっています。
もっとも日銀の展望レポート(22年1月)をみると、政策委員による2022年度のコアCPIの見通しは+1.0〜+1.2%となっています_。原油など資源価格の上昇によるCPIの押し上げ効果は、リーマン・ショック前の2008年にみられたように、一時的だとみているとのことです_。
「刈込平均型CPI」の算出方法
エネルギー価格の上昇が収まったにもかかわらず、生鮮食品の価格上昇トレンドが続いたと仮定しましょう。その際、生鮮食品を除いたコアCPIが横ばいとなったら、消費者はどう感じるでしょうか。おそらくほとんどの消費者は「実感としては物価は上がっているのに、政策面で重視される物価指標が横ばいなのはおかしい」と感じるはずです。
生鮮食品など初めから品目を指定して除外するコアCPI、コアコアCPIと異なり、一時的に激しく価格が上下した品目をその都度、選んで控除した指数を「刈込平均型(トリム平均)指数」と呼びます。
米国ではFRB(米連邦準備銀行)の1つであるクリーブランド連銀が、刈込平均型CPIを算出しています_。同連銀の刈込平均型CPIは、品目ごとの物価変動率の分布を取り、上下の両端からそれぞれ8%(計16%)に相当する品目を除外するものです。
日本でも刈込平均型CPIは発表されています。総務省による全国CPI公表の2営業日後に、日銀が「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」のひとつとして、変動率分布の上下端の各10%の品目を控除して公表しています。
日米の刈込平均型CPIを示したのが以下のグラフです。米国の21年12月は前年同月比+4.8%と、米労務省発表の同月のCPI(+7.0%)からは下がりますが、それでも5%前後という高水準です。日本は+0.9%と、緩やかに上昇が続いていますが、米国の伸びには及びません。
日銀は金融政策の運営にあたっては、コアCPIだけでなく、生鮮食品とエネルギー価格を除外したコアコアCPI、刈込平均型CPIを含めた「基調的なインフレ率を補足するための指標」、需給ギャップ、為替相場、商品市況などをもとに、総合的に判断するとの姿勢もみせています_。

※米クリーブランド連銀、日銀の公表データより作成。日本は高校教育無償化とGotoトラベル政策、消費増税引き上げの影響が除外されている。
デフレマインドとの闘い
日本の物価の伸びが米国よりも鈍い要因として、携帯電話や持家の帰属家賃、公共料金といった具体的な品目のほかに指摘されるのが、伝統的に消費者の低価格志向が強いということです。
過去を紐解いても、終戦後のハイパーインフレは復興途上の日本の生活者に大きな打撃をもたらしました。1970年代のオイルショックも、景気後退と物価上昇が同時に進行するスタグフレーション(景気悪化と物価上昇が同時進行する状態)となり、トラウマとして日本人の記憶に刻まれています。日銀の黒田総裁自身、講演で、日本人のデフレマインドは「予想以上に手強い」などと過去に指摘したことがありました_。
さらに足元では社会保障負担の増加も、現役世代の節約志向を後押しているとみられています。以下のグラフは、財務省が公表する「国民負担率」の推移です。国民負担率とは、国民所得のうち、租税負担が占める割合(租税負担率)と、社会保障負担が占める割合(社会保障負担率)を足したものです。

※財務省「国民負担率の推移」より作成
租税負担率が高止まりするなか、社会保障負担率は上昇の一途にあることが分かります。社会保障負担率の21年度見通しはやや低下する見込みですが、それでも高水準であると言えるでしょう。可処分所得を増やしにくいなかにあって、物価が上昇しているだけで抵抗感を示す現役世代は少なくないのではないでしょうか。
日銀は「物価の番人」とも呼ばれます。現行の金融政策は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」という、一般的な国民視線ではかなり複雑なものとなっています。ただ物価そのものは国民生活に直結するものです。これまで見てきたように、CPIを含む物価指標は、今後も日銀の金融政策を左右する重要なデータであり続けると言えるでしょう。
「経済指標の備忘録」シリーズ記事はこちらから
#1 「GDP」「日銀短観」…景気の読み解き方は?
#2 奥深き「GDP」の基礎を知る
#3 「GDP」、その甚大な影響力─
#4 「日銀短観」─Tankanと訳される理由
#5 「鉱工業生産指数」 製造業だけが日本の景気?
#6 <前編>消費者物価指数、日米間で格差 その理由は?
#6 <後編>消費者物価指数、日銀との関わりは?
#7 6年7カ月ぶり円安水準、巨額の「経常赤字」が起点?「国際収支」編
#8「最大級」のインパクトを持つ米雇用統計 <米国編vol.1>
#8「利上げ確率」で解釈が変わる? <米国編vol.2>
#8_ ベージュブック、「原文」の変化を読み解く <米国編vol.3>
#8_ FRBは「物価」だけで動くのか? 経済指標の備忘録<米国編vol.4>
<参考URL>
1 日本経済新聞電子版「12月の消費者物価0.5%上昇 『携帯』除けば2%迫る」(2022年1月21日)
2 2022年1月日銀「経済・物価情勢の展望(展望レポート)」より
3 「日銀総裁記者会見(2022年月1月18日)要旨」
4 Federal Reserve Bank of Cleveland, Median CPIより16 percent trimmed-mean CPIを参照
5 「教えて! にちぎん」より
6_ ロイター日本語ニュース「デフレ心理『予想以上に手強い』、期待上昇に相応の時間=黒田日銀総裁」(2018年5月10日)





.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)