「治療用アプリの開発と医療サービスの提供を通じてメンタルヘルス医療を当たり前にする」を掲げるスタートアップ・emol。2025年始にグロービス・キャピタル・パートナーズからの支援を含めた3.15億円のシリーズA調達を発表した同社は、過去グロービスのアクセラレータープログラム・G-STARTUPの採択を経ており、グロービスの「創造の生態系」を活用する企業のひとつだ。
今回はemolのCEO・千頭氏にこれまでのグロービスとのかかわり、またGCPのemol担当キャピタリスト・中安による自身の活動や日本のヘルスケア領域の可能性、そして今後の展望を聞く。聞き手はG-STARTUP事務局長の田村菜津紀。
(前編はこちら)
グロービスの「創造の生態系」を活用し続ける理由

田村:千頭さんには、改めてグロービスのエコシステムの中での体験についても振り返っていただきたいです。グロービス全体の印象や、これまでのスタートアップの軌跡の中でグロービスと関わり続けてきて感じて頂いている価値をお聞かせください。
千頭:最初にG-STARTUPを知ったときは、「面白そうなアクセラレーターだな」くらいの印象だったのですが、プレイベントに参加するとメンターの方と1対1でしっかり話せる機会があり、「こんなに時間をかけてくれるんだ!」と驚きました。そこで応募すると、初回はIncubate Trackでの採択でしたが、プログラム中の講座が充実していて、他のスタートアップの方々ともつながることができ、コミュニティとしてもすごく面白かったです。
田村さんにもサポートしていただき、「次はMain Trackに挑戦しよう」と決め、2度目のチャレンジで採択していただきました。ここではGCPの磯田さんにメンターになっていただきまして、1対1で手厚く伴走してもらいました。
起業家として事業に向き合っていると、心細くなることもあります。でも、しっかりサポートしてくれる人たちがいるというのは、本当にありがたいし、安心感につながりました。
田村:今回の調達でもGCPを選ばれた一番の理由は、やはりその支援体制だったのでしょうか?
千頭:もともとGCPから出資を受けている起業家の方々に、「GCPってどう?」と聞いていたんです。すると、「勉強になるし、経営者として成長できる」「いろいろ教えてくれるし、本当にいいよ」という声が多くて。悪い噂もほとんど聞かなかったんですよね。起業家同士で「どこのVCがいいか」という話をすることがあるんですが、その中でも評判がすごく良かったです。そういった話やこれまでのグロービスさんとのかかわりから、ぜひ支援をお願いしたいなと思っていたのですが、中安さんと実際に関わってみても見守りつつ必要な時に助けてくれるのが本当にありがたいし、信頼できると思っています。
田村:グロービスはグループ全体として起業家ファーストの姿勢を強く意識しているので、そういった体験を褒めていただいて嬉しいです。
千頭:しかも特定フェーズに限定されていないのもありがたいです。アーリーステージなら、成長フェーズなら、上場準備中なら……と、どんなフェーズにも幅広く知見があり、相談できる。大きなファンドだからこそできるサポートだなと感じています。
共創を生むネットワークでヘルスケア領域を変える

田村:ここまでお話を伺ってきて感じているのが、ヘルスケア領域の難しさ、やりがいと同時に、中安さんの領域への思い入れです。
中安:私はヘルスケア領域に対してオタク気質すぎるかもしれません(笑)。でも日本のVC業界全体を見たときに、こういった“オタク”な投資家がもっと増えていかないと、産業は伸びていかないと思っています。
この領域に限らず、エコシステム全体が成熟していく中で、海外のように特化型VCがもっと増えるべきだと思います。投資家が、企業側と対等に領域について議論できるくらい詳しくなる。それが、本来あるべき姿だと思います。現状、日本ではまだジェネラリスト型のVCが多いですが、VC間の競争も激しくなっていく中専門性の高いVCが増えていくのではないでしょうか。
田村:ご活動としても、まさにその領域に特化しながら、ご自身がオピニオンリーダーとして行動されていると感じます。特にコミュニティ活動にも積極的ですよね。そのあたりについてもぜひお聞かせください。
中安:本業としてVCをやる傍ら、Japan Healthcare Innovation Hubという一般社団法人を運営しています。これは、ヘルスケアやライフサイエンス領域のイノベーションに関心がある方々のプロフェッショナルコミュニティで、スタートアップやVC、事業会社のみならず、厚労省や経産省などの規制当局、医療従事者、研究者の方まで、世界中で活躍する方々がいらっしゃいます。主に勉強会やネットワーキングイベントを開催したり、Slackチャンネルで情報交換をしたり、業界の横の繋がりを作っていく支援をしたりしています。
繰り返しますが、ヘルスケアやライフサイエンスの領域はステークホルダーが多く、規制も関わってくるので、人を巻き込むのが非常に重要なんです。ただ、すべてのイノベーターが全ステークホルダーにアクセスできるわけではありません。面白いことをやろうとしても、規制側の考えが分からず前に進めなかったり、医師のアドバイザーがいればスムーズなのに、そもそも出会えなかったりする。そうしたボトルネックを解消するために、カジュアルにつながれる場を提供しています。
千頭:私も年明けのイベントに参加させてもらったのですが、想像以上に人が多くて驚きました。しかも、そこで出会った方とすでに一緒にプロジェクトを進めているんです。他にも、経産省や厚労省の方々と知り合えたり、他のスタートアップともつながったりして、本当に有益な場だと感じました。
中安:コミュニティの運営がエコシステム全体への貢献にもなりますし、VCとしては、投資先の皆さんにより良い出会いの機会を提供したいという思いもあります。投資先のPRの場にもなりますしね。
今では2000人のネットワークがあり、ほとんどの主要プレイヤーがこのネットワーク内にいると言っても過言ではないのではないでしょうか。私の方でも、「この人とこの人をつなげたら面白くなるな」と思ったらマッチングも積極的に行っています。実際に、40%以上の方がこのネットワークを通じて「少なくとも1回は個別面談をした」と回答していますし、大手事業会社とスタートアップが正式に契約を結ぶきっかけになったケースもあります。
日本の医療産業は非常に大きな市場なので、国としてもイノベーションの力を活用して改革を進めようとしています。経産省や国会議員の方々とも連携して、「どうすれば医療産業を活性化できるか?」という議論を進めています。今後は医療AI領域でも、経産省の関係部署と連携して取り組んでいく予定です。
「メンタルヘルスといえばemol」の世界を目指して
田村:おわりに、emolの今後についてお聞かせいただけますか。
千頭:まずは今、一番頭を使って取り組んでいるPatient Care Program(以下PCP・前編参照)を進めていくことが最優先です。疾病啓発から予防、治療、再発予防までのピースを埋めていくために、一番大きな課題になっているのは、やはり精神科医療へのアクセシビリティだと思います。
まず、偏見があるせいで治療を受けない人が多い。そして、いざ受診しようとしても病院が混みすぎているんです。「行かない」と言っている人が多いのに、実際には予約が取れない(笑)。重症化してからようやく受診するケースが多く、それだと治療も難しくなります。もっと早い段階で診療を受けていれば、働きながらでも治療を続けられるのに、悪化してから受診するので、休職が必要になってしまうんです。
「薬漬けになる」というイメージを持っている人も一定数いると思いますが、実際にはそんなことはありません。でも、それを知らない人がほとんど。「薬を飲みたくない」という理由で治療を敬遠してしまうケースも多いんですよね。
だからこそ、認知行動療法という選択肢をもっと多くの人に知ってもらう必要があります。ただ今の医療現場では、人的リソースの問題で認知行動療法を提供できる体制が十分に整っていません。だからこそ、emolではアプリで認知行動療法を提供することで、もっと気軽に治療を受けられるようにしたい。「精神科は薬しかない」というイメージを変えて、「こういう治療の選択肢もあるんだ」と知ってもらうことができれば、もっと早い段階で専門機関に行こうと思う人が増えるはずです。まずは治療アプリを通じた医療の分野で、そうした変化を起こしていき、次第にPCPもビジネスとして成長させ、周辺のヘルスケア事業も育てていきたいと考えています。
中安:メンタルヘルスに対する考え方が変われば、社会そのものも変わっていくはずですよね。本当に、偏見をなくすことの大切さを改めて感じます。
千頭:メンタルヘルス領域のプラットフォームを一緒に作ってくれる仲間も探しています。さまざまなステークホルダーと連携していく必要もありますし、そこに向けたネットワークの拡大を含め、中安さんには今後もいろいろ相談させてもらいながら進められれば。
中安:正直、この領域はやることが多すぎて大変ですよね(笑)。ですがこれを乗り越えて、「メンタルヘルスといえばemol」「自分のメンタル管理にはemolがある」という世界観を実現できたらいいですよね。
千頭:emolのサービスを通じて、メンタルヘルスケアを日常の一部として取り入れるのが当たり前になる社会を目指していきたいですね。日本のメンタルヘルス業界に貢献する、大きなプラットフォームを作っていけたらと思います。

(おわり)
<おすすめの動画>
- 職場におけるメンタルヘルスについて関心をお持ちの方に
- マネジャーが知っておくべきメンタルヘルス用語 ~職場のメンタルヘルスケア~|GLOBIS学び放題
- 職場のメンタルヘルス・マネジメント|GLOBIS学び放題
- ヘルスケア領域ほかでのビジネスや起業・事業開発に関心のある方に
- 製薬・医療メーカーのマーケティング「業界のカギ」|GLOBIS学び放題
- はじめてのビジネスプランニング|GLOBIS学び放題








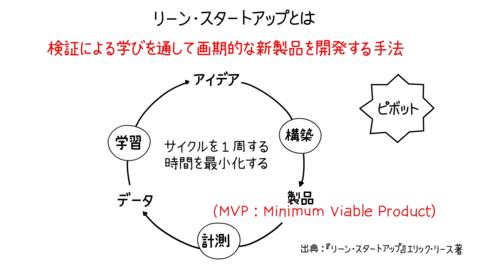





























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

