サクセッション・プランニングとは - 組織の未来を描く戦略的人材育成
サクセッション・プランニング(succession planning)とは、現在の重要なポジションの後継者を計画的に育成していく人事戦略のことです。
「誰がこの部長の後を継ぐのか」「この役職に就くためには、どのような経験を積む必要があるのか」といった疑問に対して、短期・中期・長期の視点で答えを用意していく取り組みといえるでしょう。
これは単なる人事異動や昇進の計画ではありません。組織の継続性を確保し、優秀な人材が適切なタイミングで適切なポジションに就けるよう、戦略的に人材を育成していく仕組みなのです。
なぜサクセッション・プランニングが重要なのか - 組織存続の鍵を握る理由
現代のビジネス環境では、サクセッション・プランニングの重要性がますます高まっています。その理由を見ていきましょう。
①組織の継続性を守るリスクマネジメント
突然の退職や異動により、重要なポジションが空白になってしまうリスクは常に存在します。特に、その人にしかできない業務や知識が集中している場合、組織運営に大きな支障をきたしかねません。
サクセッション・プランニングがあれば、こうした事態に備えて複数の候補者を育成しておくことができます。まさに「転ばぬ先の杖」として機能するのです。
②優秀な人材の定着とモチベーション向上
将来のキャリアパスが明確に示されることで、従業員は自分の成長に対する期待を持てるようになります。「この会社で頑張れば、将来こんなポジションに就ける」という展望があることで、優秀な人材の流出を防ぎ、長期的な成長意欲を促進できるのです。
また、計画的な育成機会の提供により、従業員一人ひとりのスキルアップにもつながります。
サクセッション・プランニングの詳しい解説 - 効果的な仕組みづくりの秘訣
サクセッション・プランニングを理解するために、その特徴や運用のポイントについて詳しく見ていきましょう。
①「ポジションありき思想」に基づく計画的アプローチ
人事を考える際には、大きく2つのアプローチがあります。一つは「人ありき思想」で、優秀な人材がいるからその人に合うポジションを用意するという考え方です。
もう一つが「ポジションありき思想」で、必要な職務から発想して適切な人材を配置するという考え方です。サクセッション・プランニングは後者の代表例といえます。
具体的には、「営業部長」「製造部長」といった特定のポジションを起点として、そこに必要なスキルや経験を整理し、候補者を育成していくのです。
②短期・中期・長期の時間軸での候補者管理
サクセッション・プランニングでは、時間軸を意識した候補者の管理が重要です。
- 短期(1〜2年): すぐにでも昇進可能な即戦力候補
- 中期(3〜5年): 適切な経験を積めば昇進可能な有望候補
- 長期(5〜10年): 将来性があり長期的な育成により昇進可能な候補
この3つの層を常に把握し、それぞれに適した育成プランを提供することで、組織として安定した人材供給体制を構築できます。
③継続的な見直しと柔軟な運用
ビジネス環境の変化は激しく、求められるスキルや経験も常に変わっていきます。そのため、一度作成したサクセッション・プランを固定的に運用するのではなく、定期的な見直しが欠かせません。
「デジタル化の進展により、IT知識がより重要になった」「グローバル展開により、語学力や異文化理解が必要になった」といった環境変化に応じて、育成内容や候補者の評価基準を柔軟に調整していくことが求められます。
また、候補者個人の成長状況や意欲の変化も考慮し、プランを適宜修正していくことが大切です。
サクセッション・プランニングを実務で活かす方法 - 成功への実践ステップ
ここからは、実際にサクセッション・プランニングを導入し、効果的に運用するための具体的な方法をご紹介します。
①重要ポジションの特定と要件整理から始める
まずは、組織にとって特に重要なポジションを洗い出すことから始めましょう。すべての役職を対象にする必要はありません。経営への影響度が高い、専門性が求められる、代替が困難といった観点で優先順位を付けます。
次に、各ポジションに必要なスキル、経験、資質を具体的に整理します。「リーダーシップがある」といった抽象的な表現ではなく、「10人以上のチーム管理経験」「新規事業立ち上げ経験」など、できるだけ具体的な要件を定義することがポイントです。
また、現在の要件だけでなく、将来的に必要になると予想される要件も含めて検討しましょう。
②候補者の発掘と育成計画の策定
要件が整理できたら、社内から候補者を発掘し、それぞれの現状とのギャップを分析します。不足している経験やスキルを特定し、それを補うための具体的な育成計画を立てましょう。
育成方法は多様で、異動による実務経験、社外研修への参加、メンタリング制度の活用、プロジェクトリーダーの経験など、候補者の状況に応じて最適な組み合わせを選択することが重要です。
また、候補者本人との対話も欠かせません。キャリアに対する希望や意欲を確認し、本人の納得と協力を得ながら進めることで、より効果的な育成が可能になります。
さらに、定期的な進捗確認とフィードバックの仕組みを作ることで、計画の実効性を高めることができるでしょう。






































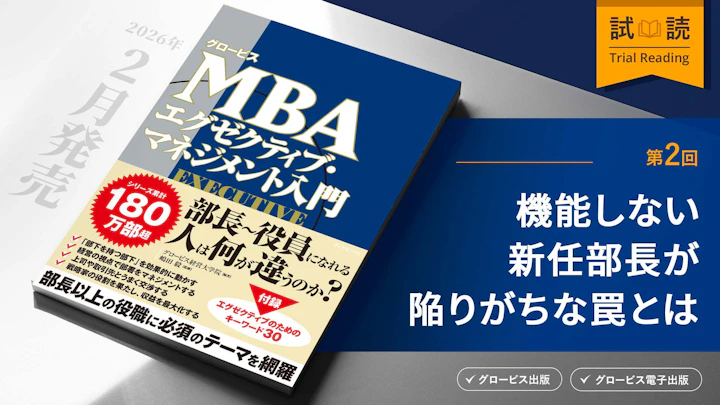




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
