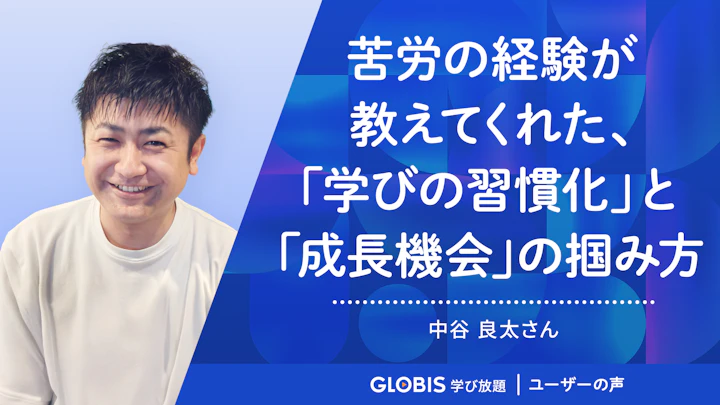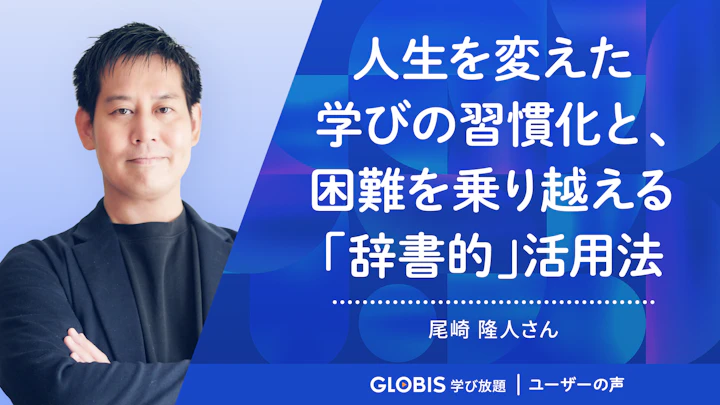これまで2回に渡って、競争しないで実現する顧客価値、つまり「プラットフォーム価値」とは、戦略における「協調」と密接な関係があり、その価値が毀損する場合というのは、プレーヤー間の協調・信頼の関係が損なわれる場合、すなわちゲーム理論における「囚人のジレンマ」のような状態であることを説明してきました。
今回はそれを踏まえて、プラットフォームを実際に構築し、プレーヤーにその価値を守り育てるようにしむけるためにはどのようにすれば良いのか、考えてみたいと思います。
あるビジネスにおいてプラットフォーム価値を前提としたマーケティング競争の最適化を行うためには、前回述べたような「囚人のジレンマ」回避の手だてに対する考察から、「『場』のルールとして決まったことに従う強制力」と「ルールを無視して勝ち逃げしようとする者への強いプレッシャー」という2つをその仕組みに備えるプロセスが求められると言えるでしょう。私は、そのプロセスには以下の3つのステップがあると考えています。
(1)顧客への提供価値からプラットフォームの部分を切り分ける
1つめのステップは、まずそのビジネスが顧客に提供すべき価値のうち、業界全体が提供する「プラットフォーム価値」と個々の企業が競争しながら提供する「アプリケーション価値」を、明確に切り分けて認識することです。
この切り分けをするためには、そもそも顧客はそのビジネスの商品・サービスに対して、どのような価値を見出して購入を決めるのかをはっきりと知らなければなりません。顧客が何に価値を見出しているのかは、当たり前のことですが供給者の側の視点から見ていたのではなかなか理解できません。ゆえに、顧客側の視点を導入する必要があります。
例えば観光サービスを考えた場合、私の知っている「成功している観光地」の活動では、たいていその土地出身ではない、よその地域の出身者でその土地に惚れ込んだ人が中心になっていることが多いです。いわゆる「ヨソ者」のほうが、その地域の最も価値ある観光資源が何であるか、すなわちプラットフォーム価値が何であるかがよく分かるからです。
顧客視点を知るための参考になるのは「ヨソ者の視点」だけではありません。観光で商売をしようとしている立場の人ではなく、その土地に根付いて日々生活している人、たとえば主婦や子供の視点から地域を見直してみることも、顧客視点を知るために役立ちます。前回登場した観光コンサルタント氏は「地域振興をやる際には旅館や料飲店といった企業ではなく、主婦と子供に自分たちのまちの観光プランを作らせる」と話していました。
(2)プラットフォームを共有する「場」と利益循環の仕組みを作る
こうして「プラットフォーム価値」が明確になったら、2つめのステップは会議体や推進組織などの「場」を作り、顧客視点から見たプラットフォーム価値を共有している企業や団体を集めて、そのプラットフォーム価値をどのように守り磨いていくべきかについての行動プランを作ります。
このとき、非常に重要なことがあります。その1つめは前述したように、プラットフォーム価値を守り、磨く役割を、リーダー的プレーヤーによる「善意のボランティア活動」に頼ってはいけないということ。2つめはその裏返しになりますが、プラットフォーム価値の恩恵を受ける大勢のプレーヤーの「ただ乗り」を許すような甘い仕組みを作ってはいけないということです。
プラットフォーム価値が顧客に提供される重要な「価値」である以上、当然ながらそれを共有し利用する人々には「利益」が発生するはずです。この利益の一部を共有する人々全員からうまく集めて使うことでプラットフォーム価値を守り磨き、さらに大きな利益を上げられるというサイクルを作り、それをその場の全員に見せながら仕組みとして回すべきなのです。
ここで言う「利益」とは、プラットフォームによっては必ずしも金銭の徴収である必要はないと思います。労役の負担というかたちもあり得るでしょうし、またノウハウの提供という場合もあるでしょう。いずれにせよ、共有する価値の維持向上とその恩恵を受けるプレーヤー全員の利益とが循環する仕組みを作ることが重要なのです。それがきちんとできれば、そのプラットフォームから得られる利益に「ただ乗り」しようとする人が出るのを防ぎ、きちんと仕組みの中に組み込もうとする力が働くと同時に、誰か特定のプレーヤーの善意にその他全員がおんぶだっこして、リーダーがプラットフォームを支えきれなくなり潰れてしまうのを防ぐことにもなります。
(3)プラットフォーム上で個々のプレーヤーに独自戦略を作らせる
プラットフォーム価値を守る「場」の形成とそこで個々のプレーヤーの利益と価値の維持向上が連動する仕組みを作れたら、最後のステップは個々のプレーヤーがお互いにバッティングしない個別の戦略を考え、実行することです。
そのプラットフォーム価値の上に全面的に乗っかってうまく稼ぐ方法を考えるも良し、あるいはプラットフォームに積極的に価値を付加することでその「場」におけるリーダーの役割を自任し、社会的名声を獲得するのもありでしょう。プラットフォーム価値を享受しようとする顧客の、ごくわずかの最も上澄みだけを狙う「ブランド重視」なプレーヤーもいれば、ボリューム層をターゲットする「庶民派」、ファミリーやカップルなど特定のセグメントだけを狙う「ニッチ派」といった位置取りも可能だと思います。
個々のプレーヤーの戦略を「場」の中で調整する必要はないと思いますが、「他人の猿真似をせずに異なる戦略を取る」ことの重要性を強調し、理解させることは重要です。一種のアイデア勝負の側面もありますので、うまい戦略が思いつかないというプレーヤーには、最初は外部の第三者によるコンサルティングを受けさせることも必要かと思います。
プラットフォーム上での競争戦略を考えるには、「探し物ゲーム」と同じような発想が必要です。誰かが隠されたアイテム(顧客)をたくさん見つけて拾い集めているからといって、そのプレーヤーの後にくっついてアイテムを探していたのでは、先にそのプレーヤーに見つけられてしまい、自分は1つも拾うことができないでしょう。顧客を取ってくるのが上手なプレーヤーがいれば、そのプレーヤーと同じ顧客を取ろうすることよりも、そのプレーヤーがまだ取っていない顧客を探しに行った方が顧客を得られるチャンスは高まります。
以上、サービス産業なかでも観光業のマーケティングを念頭に置きながら「プラットフォーム価値」の作り方について考えてきましたが、こうした発想がマーケティングのみならず、自分の目の前の仕事に当てはまるかどうか考えてみるのも重要でしょう。共有すれば、取り合うよりもずっと多くの価値が得られるものというのは、実はたくさんあると思います。こうした発想を、今後の日本企業があらゆる局面でもっと持ってもらいたいと切に願う次第です。























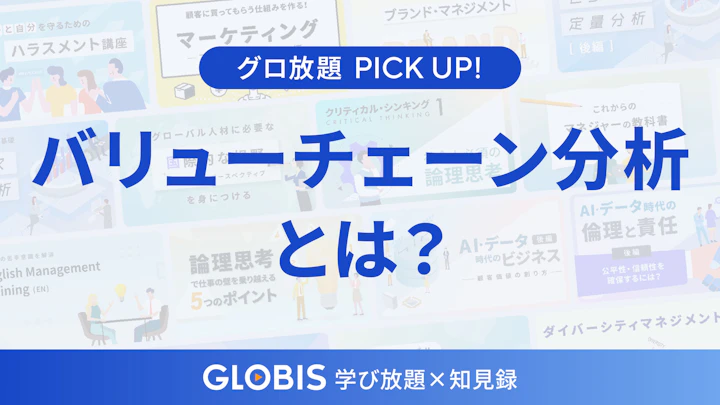
















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)