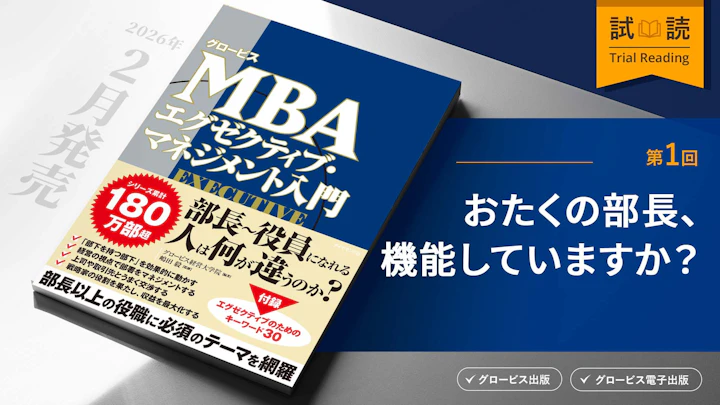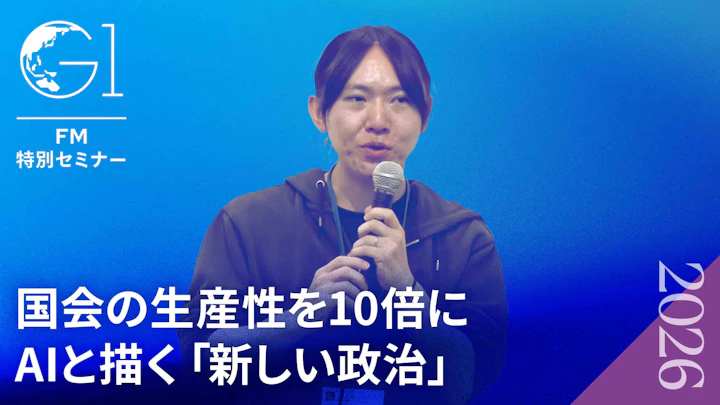2023年始、セコム株式会社の創業者飯田亮氏が逝去されました。同社は、今から約60年前に人的警備を請け負う会社として誕生し、その後まもなく機械警備へと主軸を移しました。
今回は、世界的にも例のない機械警備サービスを始めたセコムが、なぜ新市場で成功できたのかについてポイントを分析し、現在への示唆を考えてみたいと思います。
前例のない事業への転身
1962年に日本初の警備会社として誕生したセコム(当時:日本警備保障株式会社)が社会に広く認知されたのは、1964年の東京オリンピックでの大規模警備と、その翌年から放映された、同社をモデルとした警備員の奮闘を描いたテレビドラマ『ザ・ガードマン』放映の後でした。
認知度の高まりと共に順調に売上を伸ばし始めた頃、飯田氏は人手ではなく、機械による警備ができないかと考え始めます。当時のセコムの主力サービスは、夜間に警備員が契約先の建物を数回訪れ、建物内を点検する巡回警備でした。しかし人手による警備は、ビジネスの規模拡大に伴い、人員管理が難しくなることと、高度経済成長による人件費高騰への懸念を生じさせます。
そこで飯田氏が発案した新サービスは、契約先に不審者の侵入や火災を感知する機械を設置して、通信回線で自社の管制センターと結び、緊急事態が発生したら最寄りの警備員が現地に急行するという機械を中心とした警備でした。人が巡回する必要がなくなり人件費や管理コストを削減できると同時に、常時監視できるため防犯力を高めることもできるという画期的なアイディアです。
この日本初の機械警備は「SPアラーム」と名付けられ、1966年にサービス開始されます。
山積する課題
こう書くと、特にITの普及したいま、あたかも蓋然的にスタートしたかのように聞こえる機械警備サービスですが、新サービス開始にあたっては課題が山積していました。セコム(飯田氏)がそれを乗り切った過程には新規事業参入の際のヒントが詰まっています。
まず、当時のセコムが直面していた課題と、それをどのように乗り越えたかを見てみましょう。大きくは以下の3つの「ない」でした。
- 実現するためのハードウェアがない
- サービスを行うための法律が整備されていない
- 顧客の理解が得られない
実現するためのハードウェアがない
機械警備を行うには、侵入や火災をキャッチする感知器(センサー)と、キャッチした信号を送信する制御器(コントローラー)が必要です。しかし、人的警備の会社である当時のセコムには、機器開発の知見やノウハウは全くありませんでした。
そのため、セコムは技術のある会社を探し、共同開発を依頼してサービスを具現化していきました。ただし、最初の試作の段階では金額がまったく折り合わなかったといいます。開発元がよかれと思い、侵入経路分析や原因箇所の特定など高度な機能を盛り込んだためですが、セコムは「窓が開いた」「鍵が壊れた」といった単純な事象を感知するだけのものに絞り込み、1年かけて希望通りの金額に収めることに成功しました。
サービスを行うための法律が整備されていない
異常を検知するために、客先に設置した制御器はセコムの管制室と通信回線で結ぶ必要がありましたが、ここで法律が立ちはだかります。当時は電電公社(現NTT)が独占的に通信事業を運営しており、また公衆電気通信法は企業が電電公社から借りた回線を他社に利用させることを禁じていました。セコムが借りた回線は、他社である顧客企業と結ぶことができない、というわけです。
飯田氏は電電公社と何度も面会を繰り返し、最終的に(非公式ながらも)同法の例外規定に該当するとして利用を許可されました。「理由はよくわからない」と飯田氏本人が回顧していますが※1、どうしてもサービスを実現させたい飯田氏の熱意が担当者を動かしたのだろうと推測できます。
顧客の理解が得られない
課題の中でも最もクリティカルだったのが、その新規性がゆえか、顧客になかなか受け入れてもらえなかったことでしょう。サービスを開始したものの「SPアラーム」の導入は遅々として進みませんでした。導入初年度(1966年)の受注はたった13件で、巡回警備(341件)の4%にも及びません。3年後の69年4月には「SPアラーム」システムが連続射殺魔逮捕に貢献し、大きな話題になったのですが、同年の年末になっても巡回警備2000件超に対し機械警備500件と、依然人的警備が主流のままでした。社員でさえその効果を疑っていたといいますから、ましてや顧客に伝わるはずもありません。
この状況を打破すべく、飯田氏が下したのは、主流の巡回警備サービスを廃止し、機械警備サービスに一本化するという大胆な決断でした。退路を断つことで社員と顧客の意識を一気に動かすことにしたのです。結果、71年末には「SPアラーム」の契約は5,000件を超え、一方で巡回警備は急速に縮小しました。
未知のサービス立ち上げを成功に導く3つのポイント
このようにセコムはいくつもの課題を乗り越えて、世の中に例をみなかった新サービスへの転換を実現させました。セコム(飯田氏)の取った行動からは、未開拓の市場・事業参入の成功のポイントが見えてきます。
まずは最小限の機能からスタートする
制御器の開発を他社に依頼したとき、セコムは開発元が提案した便利機能を付加することを避け、事象を感知するだけのシンプルな機能のみを実装しました。必要最小限の機能から始め、市場の反応を見ることは、昨今のリーンスタートアップやアジャイル開発などに通じる手法です。金額が折り合わなかったことが大きな要因とはいえ、理に適ったスタートだったといえます。
目先の利益よりも、事業目的を優先させる
「SPアラームを売り出すにあたり、大いに迷ったことがある」と飯田氏は述べています。※2それは機械を「売り切り」にするのか、「レンタル」にするのかという選択です。資金繰りの点で言えばすぐに入金のある「売り切り」の方が好ましかったはずですが、「売り切り」にすると故障時の連絡は顧客の責任となり、その間システムが作動しなくなってしまう可能性が生じます。飯田氏は「自分の商売は機械を売ることではなく、『安全』を売ることだ」と、敢えてシステムの継続性が保証できる「レンタル」を採用しました。後日、機械警備が増え始めてから機器の生産・販売について複数メーカーから提携話があったときも、自社で『安全』を保証することができなくなるからとレンタル制を堅持したと言います。
新規事業ではできるだけ早く利益を確保したい欲求に駆られるものですが、それを堪えて事業目的にこだわることは、顧客や社会からの信頼を得て持続的な成長を遂げるために重要な姿勢です。
不退転の決意で行動し続ける
主軸サービスだった巡回警備から撤退するという決断は、なかなか変わらない人の認知を一気に動かすためとはいえ、よほどの覚悟がなければできないものです。もちろん機械警備に自信があったことは想像に難くありませんが、新規事業に100%はありませんので、飯田氏のこの行動には並々ならぬ決意を感じます。この行動があったからこそ、機械警備を軌道に乗せることができたと考えられます。また電電公社との件にも、飯田氏の粘り強い行動の成果をみることができます。
誰も経験のない未知のサービスへの参入はさまざまな課題を乗り越えるのに時間がかかります。その時間を超えて成功にたどり着くには、小さくスタートしつつも、長期的な目的を見据え、何があっても推進するという覚悟を持つことが重要であることをこの事例は教えてくれます。
半世紀以上前のこのセコムの機械警備事業参入からは、今でも学べることが多そうです。
<参考>
※1 出典:日経新聞「私の履歴書」
https://partsa.nikkei.com/parts/ds/pdf/200106/18.pdf
※2 出典:日経新聞「私の履歴書」
https://partsa.nikkei.com/parts/ds/pdf/200106/19.pdf








































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)