子会社か関連会社かで異なる連結財務諸表の作成方法
企業グループ全体の業績や財産の状況を表す連結財務諸表の作成方法には、連結法と持分法があります。「連結財務諸表ってどういうもの?」で説明しましたが、子会社に対しては連結法、関連会社に対しては持分法を用いて連結財務諸表を作成します。
いずれの場合も、連結損益計算書(連結P/L)の「親会社株主に帰属する当期純利益」や連結貸借対照表(連結B/S)の純資産(正確には純資産の内の「株主資本」)に与える影響は同じですが、連結P/Lの売上総利益、営業利益、経常利益といった各項目や連結B/Sの資産、負債の内訳項目への反映の仕方は異なります。これは、経営を実質的に支配している子会社の業績や財産の状況については連結法によって詳細に連結財務諸表に表現し、一方、経営に対して一定の影響力は持つものの支配まではしていない関連会社については簡便的な手法に留めるという考え方によります。
連結P/L、B/Sで見る連結法と持分法の相違点
連結法と持分法による連結P/L、B/Sの相違を具体例で説明します。仮に、親会社が70%の議決権を持つ子会社を連結法と持分法のそれぞれで連結財務諸表に取り込んだ場合を見てみましょう。


連結法は、一旦子会社のP/L、B/Sの各項目を親会社のP/L、B/Sに足し合わせてから親会社の持ち分以外(「非支配株主持分」と言います)の30%分を控除しています。これに対して、持分法では親会社の持分である70%のみを親会社の連結決算に取り込みます。いずれも結局は親会社の持分70%を連結財務諸表に取り込むことに変わりないのですが、そのプロセスの違いによって連結財務諸表への反映が異なる部分があるというわけです。
連結P/Lでは、連結法による場合、子会社の業績を子会社P/Lの売上高から当期純利益に至る各項目が逐一足し合わされますが、持分法では営業外収益に「持分法による投資損益」として表されるに過ぎません。同様に、連結B/Sでは連結法では子会社が保有する資産、負債が逐一連結B/Sに反映されますが、持分法では親会社の投資勘定(図では子会社株式)と株主資本が増減されるに過ぎません。このため、連結法はフルライン・コンソリデーション又はライン・バイ・ライン・コンソリデーション、持分法はワンライン・コンソリデーションと言われます。連結法の方がより子会社の業績や財産の状況が詳細に把握できることが分かると思います。
※コンソリデーションは「連結」という意味です。
さらに詳しく知りたい方へ、
おすすめの動画をご案内します。
■(ここに学びたい内容入る)について学べるおすすめの動画はこちら
- 経営管理の基礎固め!日商簿記2級「商業」 ~第15章第1-2節 連結会計①~
- 経営管理の基礎固め!日商簿記2級「商業」 ~第15章第3節 連結会計②~
- 経営管理の基礎固め!日商簿記2級「商業」 ~第15章第4-6節 連結会計③~
■GLOBIS 学び放題で、さらに学びを深めませんか?
GLOBIS 学び放題は、ビジネススクールを運営するグロービスの動画学習サービスです。
上記でご紹介した目標設定、マネジメントに関連する動画を始め、マーケティングや経営戦略など、14カテゴリのビジネススキルが学び放題。
▼特徴▼
- MBAほかで教える講師監修の高品質なビジネス動画を提供
- 14,000本以上の動画(※2024年2月時点)を毎月書籍1冊分の価格で見放題
- 1動画3分〜、スマホやアプリでいつでもどこでも学べる
- ビジネスの原理原則〜最新トレンドまで、仕事に役立つ実践的な知識を体系的に網羅
- 初級・中級・実践まで自分に合うレベルを選べる
- オンラインイベントやユーザー主催の勉強会などで、一緒に学ぶ仲間に出会える
- 第20回日本e-Learning大賞で厚生労働大臣賞を受賞!
- 20代〜30代ビジネスパーソン334名を対象とした調査の結果、オンラインビジネス学習サービス部門、4部門で高評価を達成!

.png?q=75&fm=webp?w=904&h=300)
GLOBIS学び放題で、あなたの可能性を広げる一歩を始めませんか?
▼さらに詳しい情報や、無料体験はこちらから▼
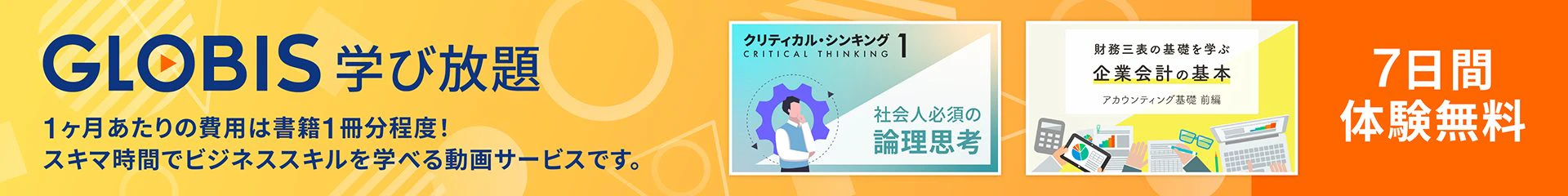





































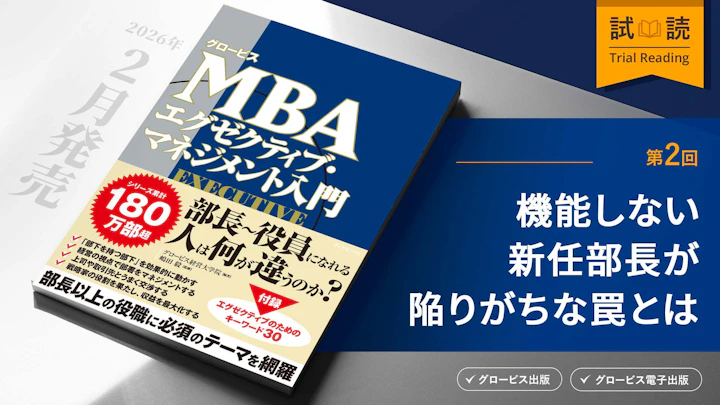




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
