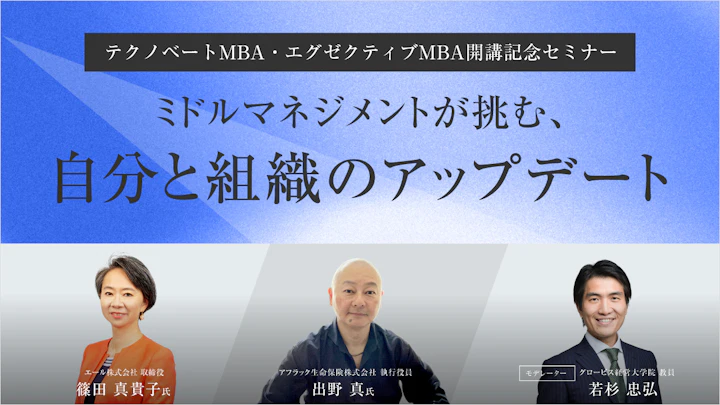私たちは日々、事業の現場で雑多な情報や状況に対処しながら仕事を進めています。そのときに、物事を抽象化してとらえる能力はきわめて重要です。それは目の前の課題を処理する直接的な知識や技術よりも重要かもしれません。なぜなら、物事を個別具体的にとらえるレベルに留まっていると、永遠に個別具体的に処置することに追われるからです。そのことを次の例で押さえてみましょう。
「on=~の上に」ではない!?
下に並べたのは英単語の問題です。それぞれのカッコ内には前置詞が入ります。1つ1つ答えてください。
・a fly[ ]the ceiling (天井に止まったハエ)
・a crack[ ]the wall (壁に入ったひび割れ)
・a village[ ]the border (国境沿いの町)
・a ring[ ]one’s little finger (小指にはめた指輪)
・a dog[ ]a leash (紐につながれた犬)
……さて、どうでしょう。
正解は、すべて「on」です。ところで、私たちは前置詞「on」を「~の上に」と習ってきました。習ってきたというか、暗記してきました。そうした暗記的なやり方で英語と接してきた人は、「天井にさかさまに止まった」とか「壁に入った」とか、「国境沿いの」などの言い回しと「on」が直接的に結びつかないので、それぞれの問題にすぐさま「on」が思い浮かばなかったでしょう。そして正解を見た後に、「そうかonだったか」と言って、また1つ1つ丸暗記していくことになります。
これに対し、いま私の手元にある一冊の英和辞典『Eゲイト英和辞典』(ベネッセコーポレーション)の帯には、こんなコピーが記載されています───
「on=『上に』ではない」と。
 さっそく、この辞書で「on」を引いてみます。すると、そこに載っていたのは、右のような図でした。
さっそく、この辞書で「on」を引いてみます。すると、そこに載っていたのは、右のような図でした。
「on」は本来、縦横・上下を問わず「何かに接触している」ことを示す前置詞だというのです。確かにこの図をイメージとして持っておくと、さまざまに「on」使いの展開がききます。
この辞典は、その単語の持つ中核的な意味や機能を「コア」と呼び、それをイラストに書き起こして紙面に多数掲載しています。10個の末梢の使い方を暗記するより、1つの中核イメージを頭に定着させたほうがよいというのが、この辞書づくりの狙いです。まさにこの「コア」に基づく単語学習が、物事を抽象化して把握することにほかなりません。
私たちは、物事の抽象度を上げておおもとの「一(いち)」を本質としてつかめば、以降、一貫性をもってそれを10通りにも、100種類にも応用展開することができます。逆にいえば、抽象化によって「一」をとらえなければ、いつまでたっても末梢の10通りや100種類に振り回されることになります。1,000パターンにも覚えることが広がったら、もうお手上げでしょう。
「一」をつかんだ者は、1,000のパターンにも対応がきくし、その「一」から発想した1,000のパターンは、抹消にとどまっていたときの1,000パターンとはまったく異なったものになるでしょう。独自性のある強い発想というのは、必ずといっていいほど、その本人が見出した本質の「一」を基にして、それを現実に合うように具体化するというプロセスを経ているものです。
すなわち「多」→「一(いち)」→「多」。

上図のように、「多から一をつかみ、一を多にひらく」ための抽象化→概念化→具体化の流れを、私はその形から「π(パイ)の字思考プロセス」と呼んでいます。私が実施する「コンセプチュアル思考研修」では、抽象と具体の往復をさせ、概念化を文章や絵図で表現させる作業を通して「多」→「一」→「多」をトレーニングしています。
「成功本」ばかり読んでも成功しない人
書店に行くといわゆる成功本がたくさん並んでいます。そこには仕事・人生で成功するための具体的方法が、著者それぞれの観点から説き明かされています。また本ならずとも、成功事例は、新聞にも雑誌にもテレビにも溢れています。
昨今は、ともかく具体的に、具体事例を、という情報要求が強まっています。確かに具体的なハウツーの話はわかりやすく、すぐに真似ができます。しかし、あまりに具体の次元で埋没してしまうと、抽象の能力を衰えさせることにもつながります。成功本依存の人は、ある種、マニュアルどおりにやることに安心を得る状態になってしまいます。
成功本・成功事例を具体的に知るということは、「型を覚える」という入り口にしかすぎません。それをそのまま漫然と真似し続けるだけでは、根本的な成長や成功はありません。多くの具体事例をいったん抽象して、自分なりに本質や原理をつかんでみる。そしてその本質・原理をもとに、自分の現下の状況に合わせて具体的な選択肢を発想する。この思考プロセスを踏んで、仕事をみずからつくり出せるようになるのが「自律的創造性」ということだと思います。下図に示したとおり、
表面的な模倣に終始する「多」→「多」なのか
本質をつかんだ上での「多」→「一」→「多」なのか
この差は実に大きいものです。

ケースメソッド学習に宿る“具体の罠”
MBAの現場では、具体的事例を教材にしたケースメソッド教育が普及しています。私もみずから行なう研修プログラムでケース(事例教材)を活用しています。もちろん教える側の狙いは、学習者にその事業の当事者の立場に立たせ、具体的にディスカッションさせ、意思決定のシミュレーションをさせることです。そして本質的な答え(すなわち「一」)をとらえさせ、担当職場に戻ったときにその応用をさせることです。
しかし、学習者を観察したり、解答シートを採点したりする中で、本質の「一」をつかまずに終えてしまう人が少なからず出てしまうことに気づかされます。また、その学習者の受講満足度がかえって高いことがさらに悩ましい問題です。
その主な理由をいくつかあげると───具体的事例は当然ディスカッションの過程で具体的アイデアを呼びます。するとそのアイデアの次元での着想やら批評やらが刺激的で面白い時間になります。そしてグループで素晴らしいアイデアにたどりついたりすると、素晴らしい解答が出せたと勘違いしてしまうことが一つ。さらには、具体的事例は感情移入がしやすいため、容易にその設定状況に没入してしまい、解答が知的な論考というより情緒的な作文に陥ってしまうことも一つです。
また、覚えたての思考ツールや分析フォーマットに要素をはめ込んで、何か分析したような気になってしまうことも理由にあげられます。いずれも「多→多」という具体次元にとどまっていて、「一」の次元にまで抽象による洞察が及んでいません。でも、本人たちは熱中できたという事実。これが“具体の罠“というものなのでしょう。ただ、そうした“青い”学びも、長い目で見れば決して無駄にならないことは確かです。
「抽象的」という語は、「その話、チューショー的だよね」というふうに何かネガティブなニュアンスが付きすぎている感があります。それとは逆に、「具体的」という語はだれもが歓迎するポジティブ色が付いているように思えます。ですが、あまりに具体に浸っているとそこには罠があります。人が敬遠する抽象は、本質の「一(いち)」をつかむためになくてはならない能力です。要は、抽象と具体を力強く往復する思考力が必要なのです。






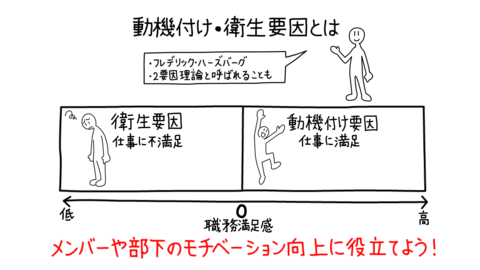



























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)