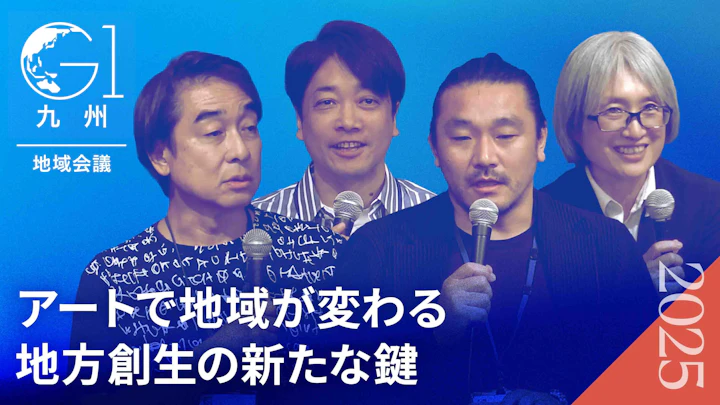「運転資本」も、よく耳にはするけどイマイチよくわからない、という声が多い項目です。運転資本はワーキングキャピタル(=WC)とも表現され、以下のような式に表されます。
「運転資本」も、よく耳にはするけどイマイチよくわからない、という声が多い項目です。運転資本はワーキングキャピタル(=WC)とも表現され、以下のような式に表されます。
運転資本(WC)=売上債権+たな卸資産-仕入債務
以下の簡単なモデルを使って説明します。
- 1月末に商品100を仕入れ、支払は1か月後(2月末)
- 2月末に商品100を100で販売(商品は仕入れた1か月後に販売)
- 4月末に商品代金100を回収(販売の2か月後に代金回収)
→このサイクルを毎月繰り返す。(仕入と売上が同額なのは単純化のため)
上の式に当てはめると、
運転資本=売上債権200(2か月分の売上)+たな卸資産100(1か月分の在庫)-仕入債務100(1か月分の仕入)=200
となり、計算上、運転資本は200となりますが、これがどういう意味なのかピンとこない方もいるのではないでしょうか。
まず、売上代金の回収(4月末)の前に2月末に仕入の支払100が必要なので、おカネを100前もって用意しておく必要があります。しかし、実はこの取引を毎月繰り返しているので2月仕入分の支払いが翌月の3月末にやってきます。この時まだ2月に売上げた商品の代金は未回収なので、さらに100の仕入の支払いのためのおカネが必要となるのです。つまり、売上代金回収の4月末までに合計200の「つなぎ資金」が必要になることになります(3月仕入分は4月末の売上代金回収で賄うことができます)。
このつなぎ資金が運転資本であり、言い換えると借入金(借金)になります。仕入の支払から売上代金の回収までの期間が長くなればなるほど「つなぎ資金」が多く必要になるため、この期間(キャッシュ・コンバージョン・サイクルと言います)を厳しく管理する会社も増えてきています。
キャッシュ・コンバージョン・サイクル=売上債権回転日数+棚卸資産回転日数-仕入債務回転日数
また、運転資本の図からも分かるように、次のようなケースでは運転資本が大きくなります。
- 売上債権が大きくなる⇒売上が成長する。売掛金の回収が遅れる
- たな卸資産が大きくなる⇒売上が成長する。在庫が売れずに溜まる
- 仕入債務が小さくなる⇒売上が減少する。買掛金の支払いサイトが短縮される
売掛金の回収を早める、無駄な在庫を持たない、よく言われることだと思いますが、運転資本、つまり不要な借入をしないという点からも理解できますね。
さらに詳しく知りたい方へ、
おすすめの動画をご案内します。
■おすすめの動画はこちら
■GLOBIS 学び放題で、さらに学びを深めませんか?
GLOBIS 学び放題は、ビジネススクールを運営するグロービスの動画学習サービスです。
上記でご紹介した目標設定、マネジメントに関連する動画を始め、マーケティングや経営戦略など、14カテゴリのビジネススキルが学び放題。
▼特徴▼
- MBAほかで教える講師監修の高品質なビジネス動画を提供
- 14,000本以上の動画(※2024年2月時点)を毎月書籍1冊分の価格で見放題
- 1動画3分〜、スマホやアプリでいつでもどこでも学べる
- ビジネスの原理原則〜最新トレンドまで、仕事に役立つ実践的な知識を体系的に網羅
- 初級・中級・実践まで自分に合うレベルを選べる
- オンラインイベントやユーザー主催の勉強会などで、一緒に学ぶ仲間に出会える
- 第20回日本e-Learning大賞で厚生労働大臣賞を受賞!
- 20代〜30代ビジネスパーソン334名を対象とした調査の結果、オンラインビジネス学習サービス部門、4部門で高評価を達成!

.png?q=75&fm=webp?w=904&h=300)
GLOBIS学び放題で、あなたの可能性を広げる一歩を始めませんか?
▼さらに詳しい情報や、無料体験はこちらから▼
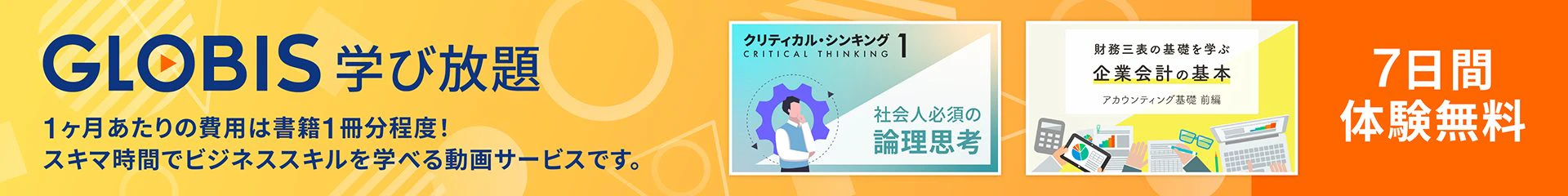






































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)