有事の際の一過性の変革ではなく、変革を常態化し、平時でも変革し続けていくために、どのように組織能力を身につければよいだろうか。そのためには組織として学習していくことが求められる。ここでは組織学習に関する2つの理論を紹介する。
学習する組織
MIT(マサチューセッツ工科大学) のピーター・センゲ教授は、環境に適応し変化する能力を継続的に開発している組織を「学習する組織」と名づけた。そしてその実現には、「自己マスタリー(自己実現と自己研鑽)「メンタルモデルの克服」「共有ビジョンの構築」「チーム学習」の4つの原則と、それらを統合する「システム思考」が必要であると主張する。
[caption id="" align="aligncenter" width="478"] 「学習する組織」の実現に向けた五つの原則[/caption]
「学習する組織」の実現に向けた五つの原則[/caption]
(1)自己マスタリー(自己実現と自己研鑽)
自らのビジョンや欲求が何であるか探り続けると同時に、現状を的確に見極めることによって両者のギャップを認識し、ビジョンや欲求の実現に向けて行動すること。
(2)メンタルモデルの克服
物事の見方や行動に大きく影響を与える固定概念や暗黙の前提のことをメンタルモデルという。自社や競合、市場に対して組織で共有しているメンタルモデルを認識し、それを打破するための取り組みが求められる。
(3)共有ビジョンの構築
各個人のビジョンから共有されたビジョンを導ことにより、お題目ではなく、組織の構成員が心底望む将来像を構築することができる。
(4)チーム学習
構成員間のダイアローグ(対話)を通して、複雑な問題を探求することにより、個人で考えるときよりも優れた解決方法が発見できる。
(5)システム思考
独立した事象に目を奪われずに、各要素間の相互依存性、相互関係性に着目し、全体像とその動きを捉える思考方法。「木だけではなく森も見る思考」「高い視座、多様な視点から全体像を見る思考」である。このシステム思考が、ほかの4つを統合する「第5のディシプリン(原則)」である。
では、これらの原則を基に、どのように学習する組織を作るのだろうか。それは日本における研究に見ることができる。
日本における研究
どのように組織学習を進めるのか。実は日本発の世界的に有名な研究がある。経営学者である野中郁次郎氏、竹内弘高氏による「SECI(セキ)モデル」である。
[caption id="" align="aligncenter" width="460"] 「SECI(セキ)モデル」[/caption]
「SECI(セキ)モデル」[/caption]
野中・竹内氏は日本企業におけるイノベーション、新たな知識創造を研究し、「形式知」と「暗黙知」に着目した。「形式知」とは言葉や数字で表すことができ、データ、方程式、明確な手続き、普遍的原則などにより容易に伝達・共有できるものである。一方の「暗黙知」とは、主観に基づく洞察、ノウハウ、思い、知覚など非常に個人的なもので他人に伝達して共有することは難しいものであり、これらの知識変換を進めることでイノベーションが起こることに着目した。
知識変換は、個人の暗黙知からグループの暗黙知を創造する「共同化=Socialization」、暗黙知から形式知を創造する「表出化=Externalization」、個別の形式知から体系的な形式知を創造する「連結化=Combination」、形式知から暗黙知を創造する「内面化=Internalization」の4つのモードがあり、これらの頭文字をとってSECIモデルと呼ぶ。
野中氏は、このSECIモデルの最初の起点はリーダーの暗黙知にあり、暗黙知こそが知識創造の源泉にほかならないと考えた。イノベーティブな成果を出せる組織と出せない組織とを分けるのは、リーダーがいかに「高貴な」暗黙知を有しているかにかかっているという。
SECIモデルにおける知識変換の第1の段階である「共同化」とは、経験を共有することにより、メンタルモデルや技能などの暗黙知を創造するプロセスである。人は言葉を使わずに他人の持つ暗黙知を獲得することができる。伝統芸能の場において、弟子が師匠を観察、模倣し、練習することによって技能を学ぶのはその一例だ。ビジネスの場におけるOJTも同様である。
また、これはサクセッションプラン(後継者育成計画)においても重要な要素である。GEのジャック・ウェルチは、自身の後継者候補22人を7年間かけて徐々に3人まで絞り込んだ。その過程でウェルチは、候補人材にそれぞれの成長に必要な経験・チャンスとフィードバックを与え、最終的にジェフリー・イメルトを後継者として指名している。つまり、経営に関する暗黙知の共同化を7年間かけて行ったのである。
第2の段階である「表出化」とは、暗黙知を明確なコンセプト(理念) に表すプロセスである。暗黙知をメタファー(暗喩)、アナロジー(類推)、コンセプト、仮説、モデルなどを用い、次第に形式知として明示的にしていく、知識創造プロセスの真髄である。前述したアップルの「1000曲をポケットに」や、コマツの「ダントツ商品」という言葉は、ジョブズや坂根氏のイメージする像を見事に「表出化」しているものだ。
第3の「連結化」とは、コンセプトを組み合わせて1つの知識体系を創り出すプロセスである。異なった形式知を組み合わせて新たな形式知を創り出すもので、ミドルマネジャーが企業ビジョン、事業コンセプト、製品コンセプトなどを分析し、具体化する際によく見られる。例えば製品コンセプトで言えば、アップルのiPhoneは、MP3プレーヤーと携帯電話、ネット情報端末を結合させたものである。
第4の「内面化」とは、形式知を暗黙知へ「血肉化」するプロセスである。それは、行動による学習と密接に関連している。形式知を暗黙知に内面化するためには、書類、マニュアル、物語などに言語化・図式化されていなければならない。こうした文書化は、体験を内面化するのを助けて暗黙知を豊かにする。例えばトヨタでは、トヨタウェイや問題解決について言語化し、その実践を行うことで内面化を促している。
このSECIモデルについて、前出の7Sモデルの(6)経営スタイルに当てはめると、トップダウン、ボトムアップに分けて考えることができる。野中・竹内氏は、GEのジャック・ウェルチを典型とする欧米型のトップダウン・モデルは連結化(形式知から形式知へ)と内面化(形式知から暗黙知へ)に絞ったものであり、米国の化学・電気素材メーカー、スリーエムのイノベーションを典型とするボトムアップ・モデルは、共同化(暗黙知から暗黙知へ)と表出化(暗黙知から形式知へ)に絞ったものであるという。
このようにグローバル企業を分析した上で、日本型の変革モデルとして、トップダウンでもボトムアップでもなく、「ミドル・アップダウン」を提唱している。すなわち、チームのリーダーを務めるミドルマネジャーが、組織内の縦と横の知の流れが交差する結節点に立ち、トップとフロント(第一線社員)を巻き込んでイノベーションを起こしていくというものである。あるべき姿を描き、社内を巻き込んでいくミドルを増やすことが、組織変革につながるのである。
さて、最後にあらためて考えたいことがある。人事部門の役割は何だろうか。単に社員の採用、配置、評価、報酬のプロセスを繰り返すだけではない。人事制度や組織体制の変更を実行するだけでもない。ましてや、人員や人件費を削減することでもない。経営学者ピーター・ドラッカーはその著書『現代の経営』においてこう述べている。「我々が利用できる資源の中で、成長と発展を期待できるものは、人間だけである」と。環境変化や戦略変更、そして企業の理念を踏まえ、いかに変化を起こし続けられる人・組織を作れるかが何よりも重要だ。そのために、プロアクティブ(予測的)に変化をしかける存在が人事部門であると筆者は信じている。
※労政時報に掲載された内容をGLOBIS知見録の読者向けに再掲載したものです。








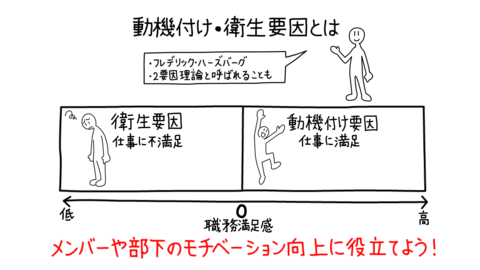



































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
