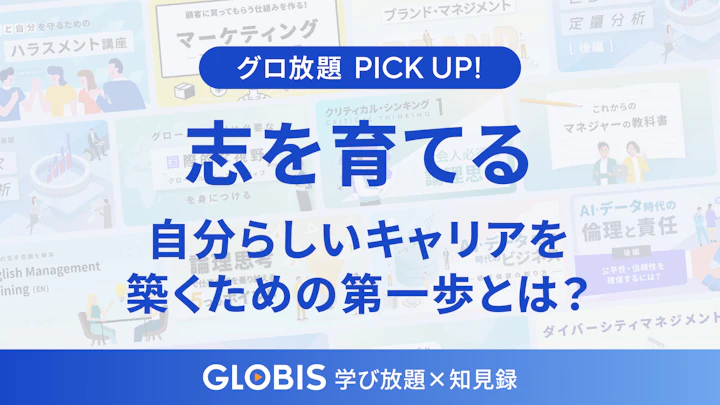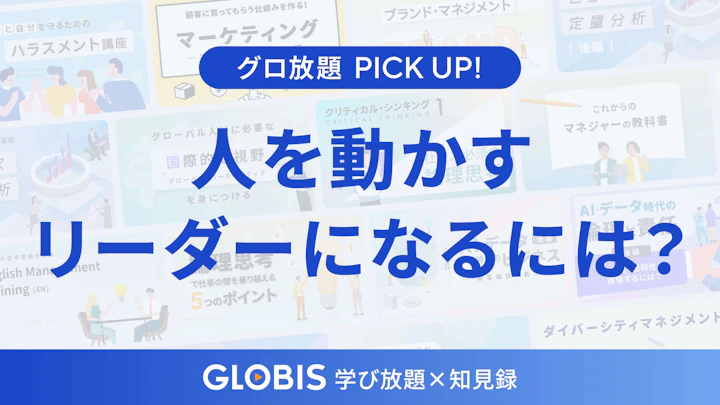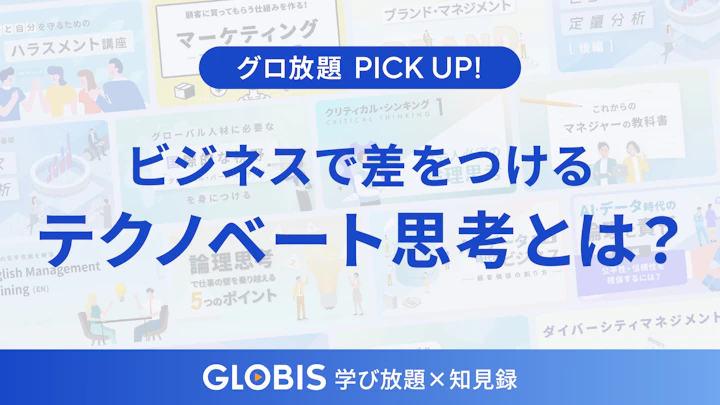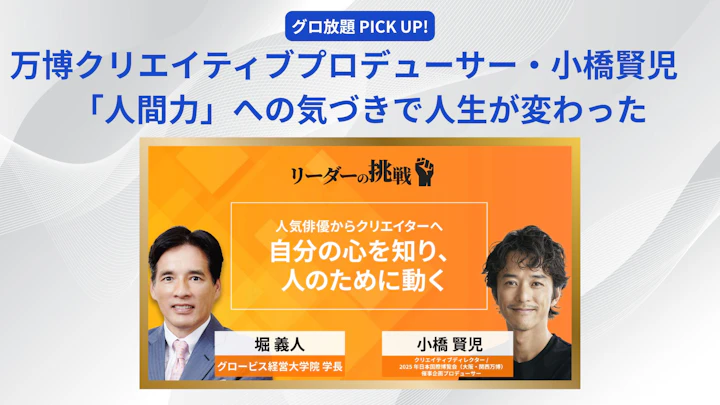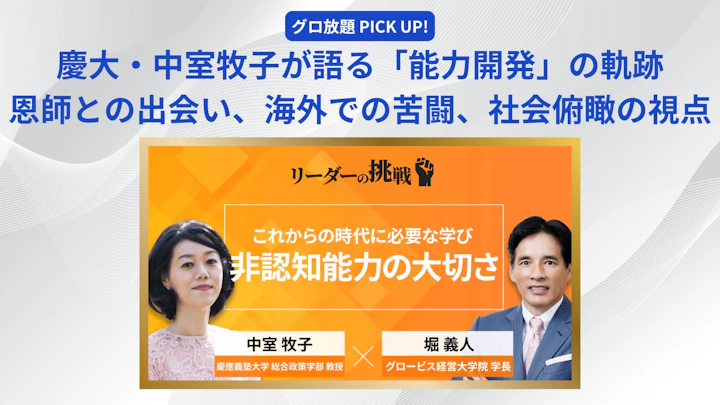活動に必要な資源・能力をどのように獲得・構築・運用するか?
前回で明らかになった(5)価値を生み出す活動の仕組みを、組織としてどのように動かすのか検討する。企業が活動をしていくために必要な経営資源や技術・ノウハウをどう調達、活用するか、そして人・組織を動かすマネジメントの仕組みをどうすべきかを考える。
注:一般に経営資源は、ヒト・モノ・カネ・情報と言われるが、ここでは「モノ」は事業活動の中で、また「情報」は人に紐付けて考えるため、「カネ(資金)」と「ヒト」を中心に考える。なお、企業にとって資金の調達・利用・管理は極めて重要だが、本稿では説明を省略し、以下、人・組織を中心に考えていく。
戦略的HRの役割
組織は、多数の人間が集まり、それぞれの役割を分担し、相互に関係しながら成果を生み出すという「分業と統合」によって動く存在だ。このため、以下の2点がここでの大きな論点となる。
● 個人やチーム、部署など、分業単位ごとの成果をいかに最大化するか?
● 各分業単位の活動を、いかに効果的、効率的に統合するか?
あるべき活動ができるように、人の認識、能力、意欲をどのような状態にし、判断の仕方や行動をどのように変えていくのか。そして部門間、チーム間で効果的に連携するためにどのような組織形態やマネジメントの仕組み、環境が必要なのかを考えていく。
なお、人事部門がつかさどる、採用・配置・教育・評価・報償といったHRシステムはもちろん重要な要素だが、人と組織に影響を与えるのはこれらだけにとどまらない。現場での業務の与え方、管理会計の仕組み、情報システム、職場の物理的、心理的環境など多くの要因が関係する。これらを広く押さえた上で整合性のある打ち手を企画し、その実行に向け経営層やさまざまな部門を巻き込み、リードしていくのが「戦略的HRマネジメント」の役割だ。重要な部分なので、今回と回を分け、詳しく見ていくこととしたい。
人・組織の動き方に影響を与える4つの要素
まず、人・組織の動き方に影響を与える要素は何だろうか。多くの要素が複雑に絡み合うが、4つの視点で捉えると整理しやすい。
1. 組織形態のデザイン [骨格]
2. 情報の流れ・調整・意思決定の仕組みの設計運用 [神経]
3. 人材の認識、能力、意欲、行動のコントロール [筋肉]
4. コミュニケーション・リーダーシップ [血液]
まず、一連の価値を生み出す活動を、部門、部署、チーム、個人といった階層ごとに、どのように切り分け、分担していくかを考える。これは同時に、多様な活動をどのような単位でくくり、誰は誰と共に活動するのかについて決めていくことでもある。これが「組織形態のデザイン」であり、人体に例えると「骨格」のようなものだ。
分業された各組織の活動は、それぞれをつなぎ、調整、統合する仕組みが必要となる。部署やチーム間でどのように情報を共有するか、誰がどのように意思決定するか。計画策定のプロセス、管理会計など成果・行動のモニターと評価のプロセス、会議や情報システムなど情報共有の仕組み、また組織内のルールや標準の決定などが主要な要素だ。人体における、さまざまな情報を伝え動かす「神経」のようなものとイメージするとよい。
そして、骨格と神経の基盤の上で、「筋肉」が力強く動くことが必要だ。「人材の認識、能力、意欲、行動のコントロール」である。採用・配置・教育・評価・報償の仕組みなどいわゆる人事施策はここに入るが、職場での業務の与え方、日々接する情報の種類、職場の物理的・心理的環境なども強い影響を与える。最後に、こうした筋肉に栄養をもたらす役割を果たす「血液」の働きをするのが、リーダーのコミュニケーション、リーダーシップの発揮だ。魅力的なビジョン・方向性を示し、動機付け、望ましい行動に駆り立てていく。
次回は、1. 組織形態のデザイン[骨格]について詳しくみていく。
※労政時報に掲載された内容をGLOBIS知見録の読者向けに再掲載したものです。