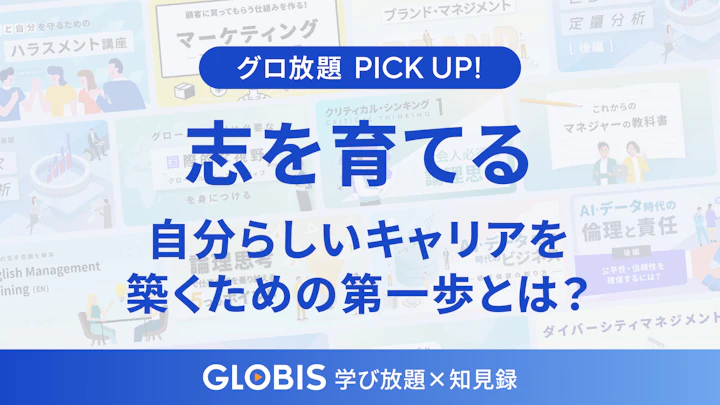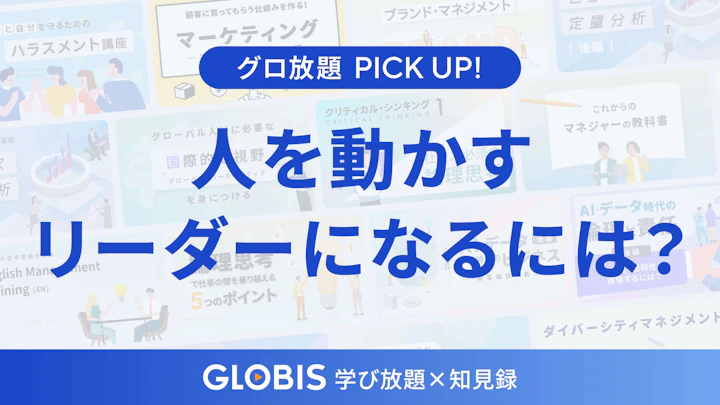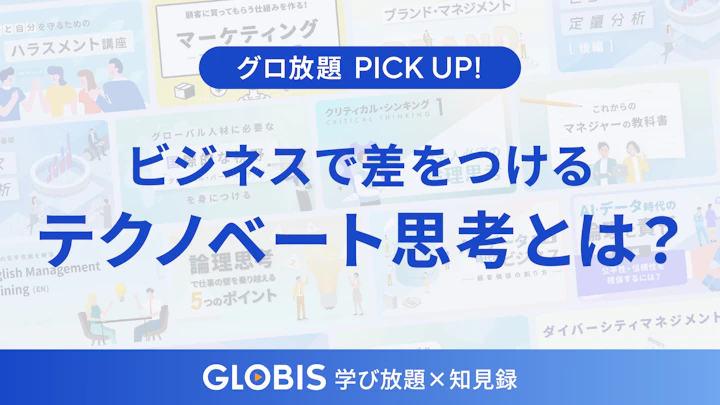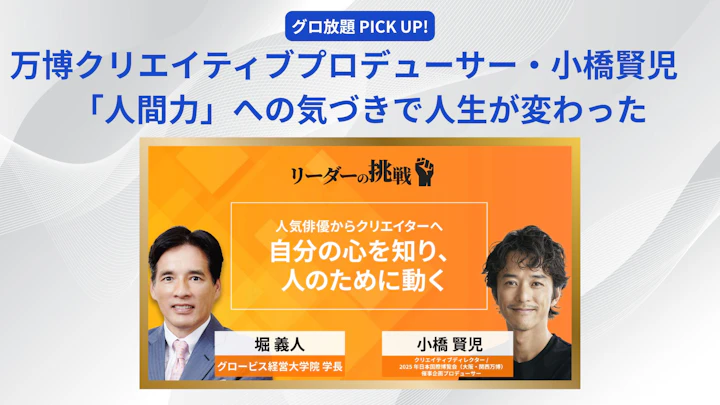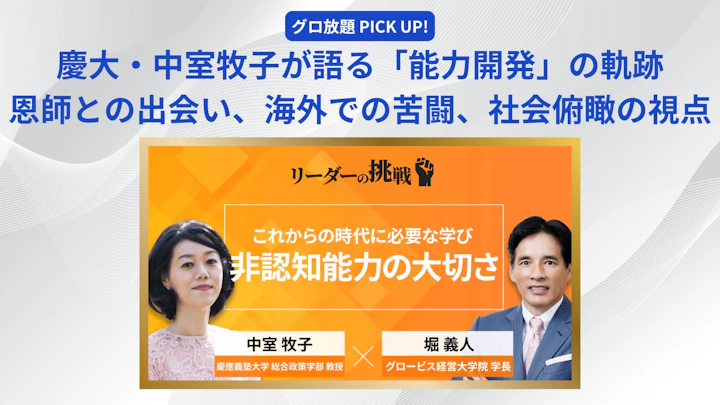あるべき人材像を明確化し、現状とのギャップを具体化する
●『グローバルリーダーを育成したい』というご要望ですが、具体的に、どんな人が、どこで、何ができる必要があるのでしょうか?
●『製品開発者の創造性を高めたい』とのことですが、そもそも御社の製品にはどのような点で創造性が欠けていると見ていますか?
日本企業の人材育支援研修の際、事前にクライアント企業の要望を詳しく伺うようにしている。その企業が将来に向けて目指す企業像、そこに至る戦略の方向性と課題、そして戦略を実行するために、どのような人材がどのように動くことが必要かを聴く。あるべき人材像を明確に把握し、現状とのギャップを具体化してこそ、最適な学習機会をデザインできるからだ。
そこで冒頭のような問い掛けをするのだが、明確な答えが返ってくる場合ばかりではない。特に人事部門のマネジャーと打ち合わせをした際に、話が「人事」や「教育」の分野を離れ、開発、生産、営業、サービスといった企業の実際の活動の在り方、またその活動を通じて達成すべき戦略的方向性の議論になると、とたんに話が抽象的になってしまうことが多い。
もう1つ、異なる場面を紹介しよう。
●人事制度をより前向きなチャレンジを促すものに変えるべきだ。制度の具体的変更点は…
●人事部として何をやりたいかは分かった。だが、今はむしろ拠点拡大中の海外工場のマネジャーの定着率をどう高めるかが緊急の課題ではないか?
これは、ある会社のアクションラーニング(研修参加者が会社の事業・組織課題に取り組み、解決策を役員に提言するスタイルの研修)の中間報告会での参加者と社長の会話だ。その参加者は人事部の課長でとても優秀な方であり、具体策自体はよく練られたものだった。
しかし問題は、そもそもの課題意識が経営陣のそれとは大きくずれてしまっていることだ。“海外での事業拡大をどのように成功させるか”が経営陣の最大の関心事なのに対し、参加者は人事の業務範囲の中だけで考え、課題を設定していた。このように、発想自体が「人事」の枠にとどまってしまうケースも少なくない。
日本企業が直面する課題の本質は何か
人事部門は人事制度の企画実行、人の採用、配置、教育、評価、報償などの実務を担っており、そこで求められる専門性も高いものになっている。仕事の性格上、確実な業務執行が必要とされるため、しっかり人事ルーチン業務を回せる状態を維持するだけでも一苦労だ。しかし、多くの企業の置かれた状況を考えると、人事部門が伝統的人事業務を粛々と実行するだけでは、役割を十分に果たせなくなってきている。
なぜか。多くの日本企業は戦略の転換点にあり、新たな方向に早急に踏み出していく必要がある。そんな中で、「とるべき戦略は分かっている。しかし、それを実行する組織・人に変化していけない」ところに最大の課題があるからだ。新たなビジョンを打ち出し、組織形態や人事制度にさまざまな手を打っているのに、その中で働く人の判断の仕方、行動がなかなか変わらない。グローバル化を推進したいが、そこをリードできる人材がいない。課題の難易度は高まり、緊急度が増している中で、人事部門が変革を強力にリードしていく必要性が高まっているのに、それに応えていけていない。
そこで肝になるのは、伝統的な人事業務の範囲を超え、高い視座、広い視野で組織課題を捉え、すべての部門の人々を巻き込んでの課題解決力だ。組織の戦略的方向性を踏まえ、そこから組織がどのように動き、人をどのように活かしていくべきかを描き、そのために必要な施策を実行する。それが「戦略的HRマネジメント」だ。本連載では、「戦略的HRマネジメント」を実現していくために、これからの人事のリーダー・責任者が持つべき視点・考え方、問うべき在り方・役割、取り組むべき課題について考えていく。
掲載内容は以下を予定しております。 ※週1回更新予定です。
・日本が直面する戦略・組織課題 【吉田素文】
・経営の全体像を捉える 【吉田素文】
・組織構造と意思決定のデザイン 【佐藤剛】
・グローバル化と人事システム 【佐藤剛】
・ダイバーシティ・マネジメント 【林恭子】
・人材育成とリーダーシップ開発 【竹内秀太郎】
・組織変革と組織学習 【新村正樹】
・理念経営と組織文化のマネジメント 【芹沢宗一郎】
・個を活かす生態系としての新しい企業の形 【林恭子】
・これからの経営とHRに期待されること 【竹内秀太郎】
※労政時報に掲載された内容をGLOBIS知見録の読者向けに再掲載したものです。