今年3月発売の『海外で結果を出す人は「異文化」を言い訳にしない』から「本質を見極めるために、これだけは押さえておきたいビジネススキル」の一部を紹介します。
異文化ゆえに価値観や習慣の違い等で悩む人は多いでしょう。一方で、異文化だからといって、あらゆるものが異なるというわけではありません。国や文化の壁を越えて共通のものもあります。異文化の人とコミュニケーションをする際、そうした「共通言語」を持てるかどうかは大きな差につながります。そのような共通言語の典型は、数字やクリティカル・シンキングです。たとえば数字の3は、どの国に行っても3ですし、平均値の定義なども世界共通です。何かを主張する際に根拠としてファクトに基づいた数字を使うことはやはり大きな武器となります。クリティカル・シンキングも世界中で通用するものです。「私はこう思います。なぜなら…」の論理構成に文化の壁はありません。何か話がかみ合わないなと感じた時に、根拠とする暗黙の前提の違いに気づけるか否かも、クリティカル・シンキングの力に大きく左右されます。クリティカル・シンキングや数字力は幸いなことに、国内でも磨くことができます。海外に行って慌てて習得しようとするのではなく、極力早い段階でこれらを身につけることが、世界で活躍するビジネスパーソンには必須と言えるでしょう。
(このシリーズは、グロービス経営大学院で教科書や副読本として使われている書籍から、英治出版のご厚意により、厳選した項目を抜粋・転載するワンポイント学びコーナーです)
◇ ◇ ◇
クリティカル・シンキングで違いを読み解く
海外で仕事をするために身に付けるべきスキルを1つだけあげろと言われたら、迷うことなく「クリティカル・シンキング」だと断言できる。経験したことのない場面で、進むべき道も分からない五里霧中の状況で、物事を的確に捉えて理解し、他者とのコミュニケーションを進め、ともに解決を目指すためのスキルだ。
グロービスでの定義を引用しておこう。
「クリティカル・シンキングとは、あらゆるビジネスパーソンに必要不可欠な、問題解決力、コミュニケーション力、仮説構築力、論理思考力などを総合したスキルである。ビジネスで直面する課題に対して、考慮すべき点を抜け漏れなく押さえながら、自分の考えを組み立て、強化するためのスキルである。また、ある情報から仮説を立て、仮説の検証を進めながら、ビジネスを進めていくうえで成果につながる結論を生み出すスキルである」
海外で仕事をするビジネスパーソンだけでなく、どんな場面でも必ず役立つスキルだと言えよう。とはいえ、いまの説明では「ロジカル・シンキングと、どう違うのか」と疑問に思う方もいるかもしれない。ロジカル・シンキング(=論理的に考える)は、クリティカル・シンキングの1要素であると捉えればいい。人によってそれぞれ「論理」は異なるし、時間の経過によって前提条件が変化すれば、従来の「論理」が通用しなくなることもビジネスの世界ではよくあることだ。
海外であればなおさら、前提が違う状況に必ずといっていいほど直面する。まず、初めて直面する課題でも、経験がないからといって避けて通ることはできない。また、生まれ育った環境が異なる初対面の相手とも、やり取りを進めなければならない。こうした状況のなかで、個々人が持つ論理の前提の違いに目を向け、「客観的にどう〈考え・見て・話す〉ことがより妥当か」を意識するのが、クリティカル・シンキングだ。
本書でクリティカル・シンキングのすべてを伝えることはできないが、ここでは海外でのビジネスに関係する部分に特に触れながら、ポイントを見ていこう。クリティカル・シンキングでは、以下のような段階を踏んで物事を客観的に捉え、相手が納得する形で伝える。
①イシューを押さえる(何を考えるべきかを、まず考える)
②イシューに答えるための枠組みを考える(どんな切り口で考えるのかを、考える)
③イシューと枠組みに従って、主張と根拠を明確にする
最後に、この①~③の筋が通っているかを確認する(構造化できているかを俯認する)のである。
(中略)
海外では、どんなに気をつけてコミュニケーションをしていても、こんな場面に遭遇する。
「何を言わんとしているか分からない」
「何で急にこんなことを言いだすのだろうか?」
「何でそういう結論になるの?」
そんな場面に出くわすと、こんなふうに決めつけてしまう。
「外国人は変わった人が多い」
「何を考えているのか分かりづらい」
「○○人とは付き合いづらい」
しかし、第2章で説明したように、外国人は文化が違うからやりにくいと嘆くのはまちがいだ。「変だな」と違和感を持ったときは、ぜひ、「チャンス到来だ」と思ってほしい。何のチャンスかというと、軌道修正のチャンスだ。具体的には、これまで述べたように、
「イシューが、ずれているのではないか?」
「適用している枠組みに、ずれがあるのではないか?」
「仮説の構築の方向性が違うのではないか?」
といった具合に、ずれた軌道を合わせるチャンスにしてほしい。したがって、「それはおかしい!」とか「何でそんなことを言うのか!」と感情的に反応するのではなく、「イシューを改めて確認しておきたいのだが」とか「あなたが着目しているポイントは?」といったように、一度冷静になって、思考の前提を確認する問いを投げてみよう。
私自身の感覚値として、海外で仕事をしていて結論が何か変だなと感じたとき、その原因の約8割は前提の違いからきている。「変だな」と感じたことこそが「正しさの源泉」であるというマインドを持つことだ。この感覚を身に付けないと、目の前で起こっている問題が、本当に文化の問題なのか、ビジネス上の問題なのかを見分けることは困難となる。
グロービス経営大学院では、世界で通用するリーダーに必要な「国際的視野」を習得するための「グローバル・パースペクティブ」の授業を行っています。
『海外で結果を出す人は「異文化」を言い訳にしない』
著者:グロービス(著者)、高橋亨(執筆者) 発売日 : 2021/3/22 価格:1,980円 発行元:英治出版
























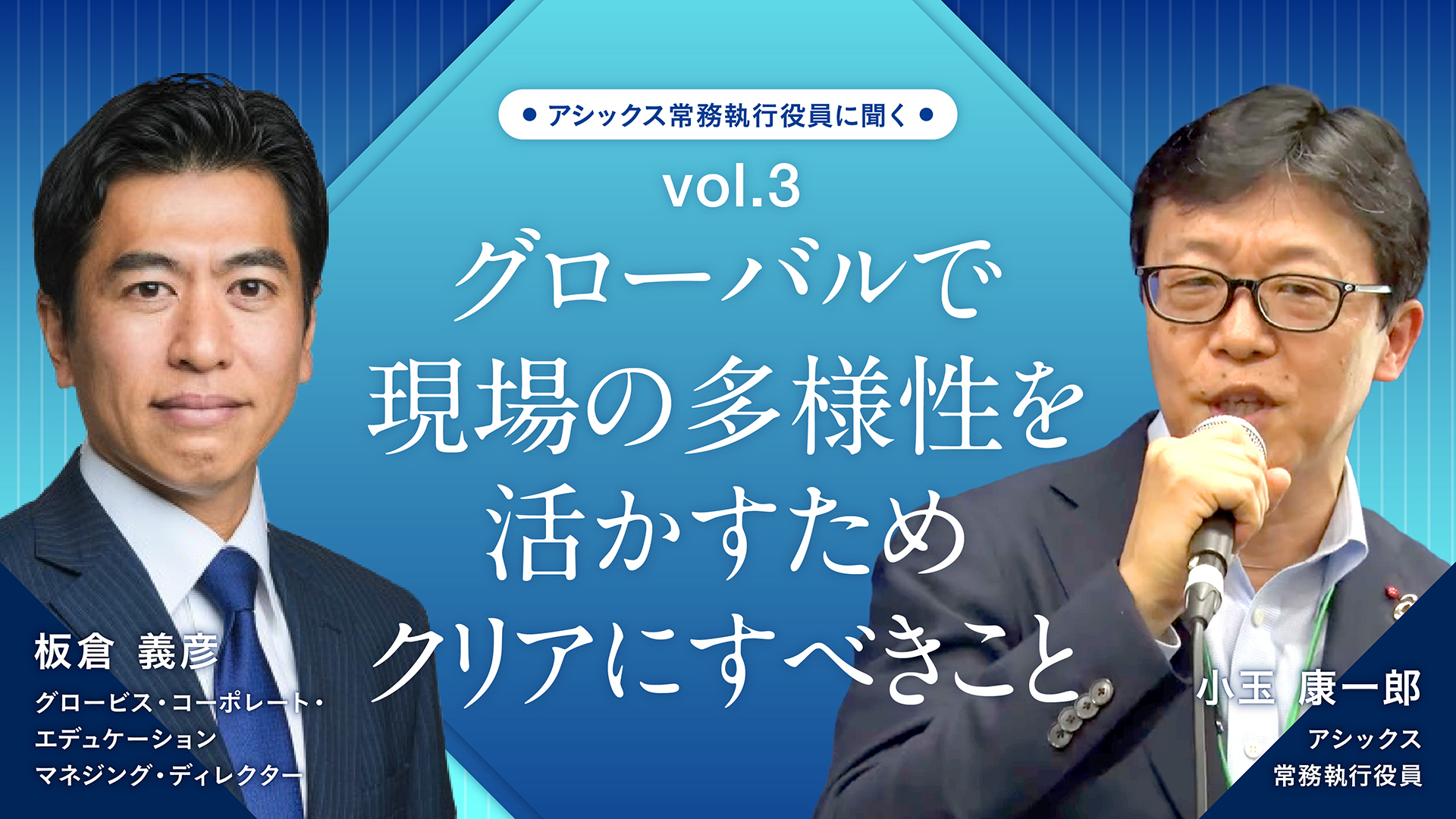











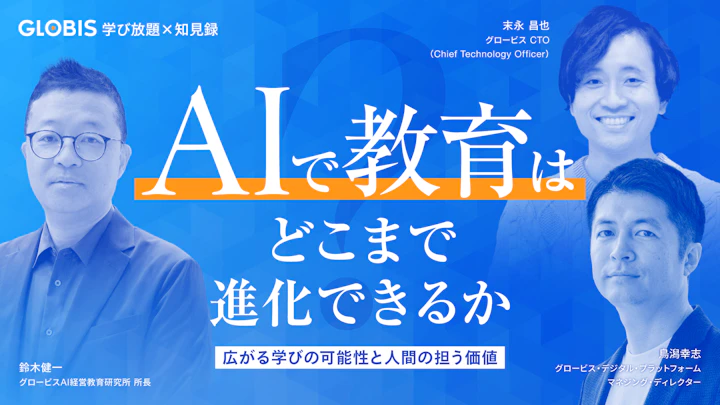
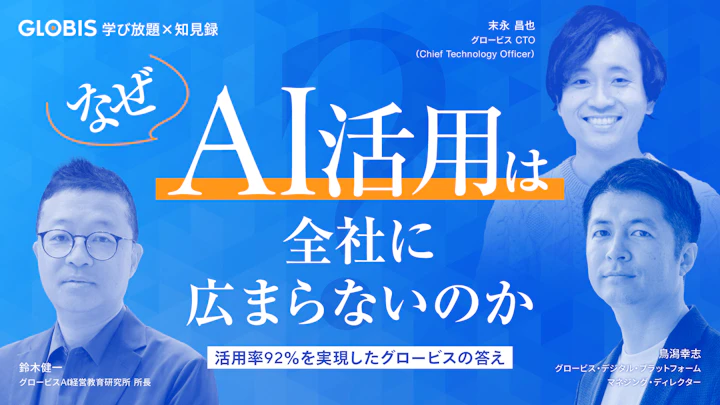

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




