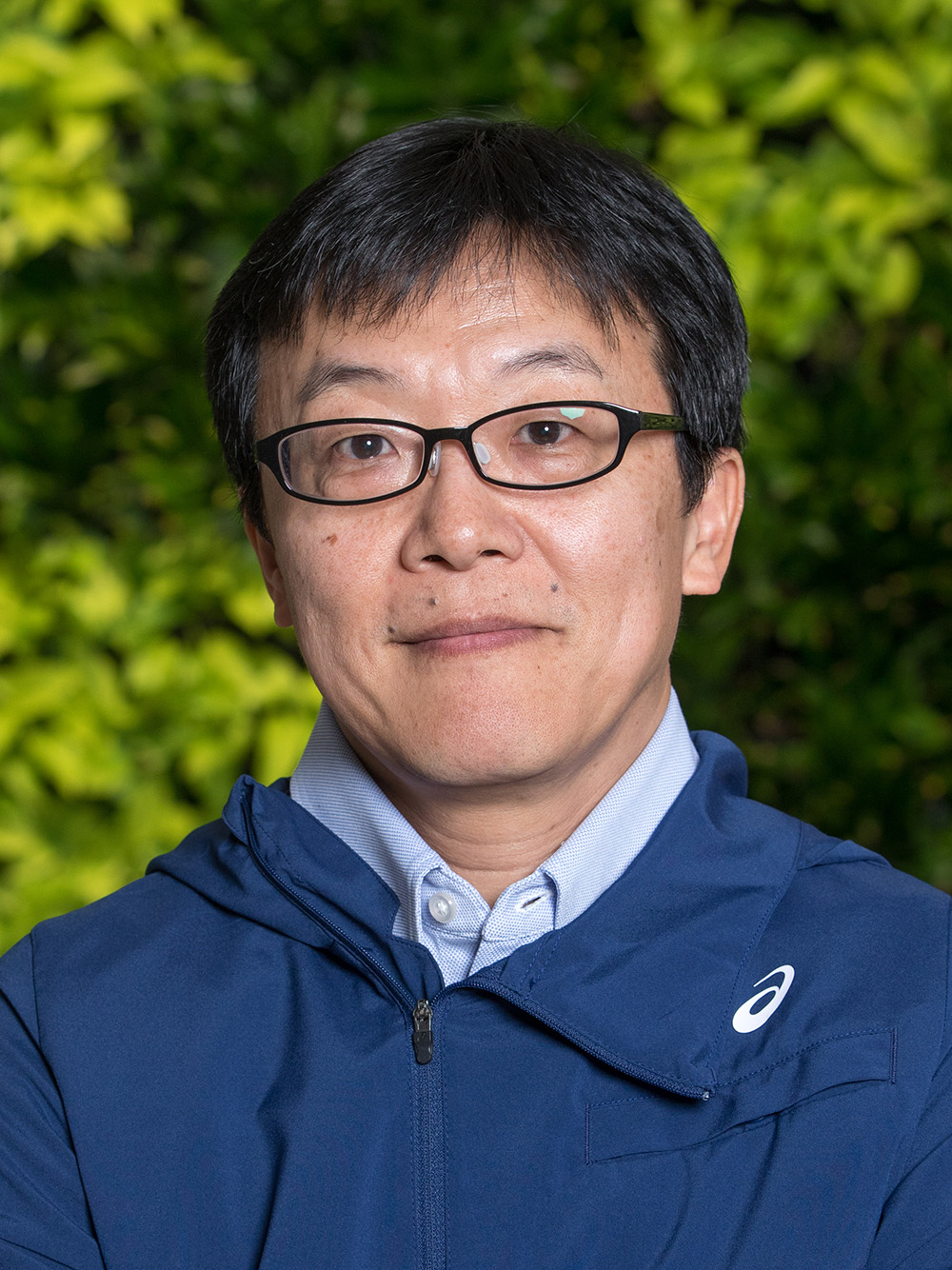少子高齢化による人口減少が加速する中、さらなる成長を目指し、グローバル化に注力している日本企業は少なくありません。この中で、海外事業を牽引するリーダーは、どのように組織を動かしていけばよいのでしょうか。
今回は、海外事業全体の統括として世界三十数か国に広がる販売会社を束ねる、株式会社アシックス 常務執行役員の小玉 康一郎氏にお話を伺います。今回のテーマは、事業変革を進めながら掴んだグローバルでの組織マネジメントの要諦についてです(全3回、第1回)。
メンバーのやる気を引き出し、具体的な施策に反映していけるかが肝
板倉 小玉さんは、北米事業の立て直しに取り組まれてきたとお聞きしています。2017年から4年間、販売会社であるアシックスアメリカに駐在され、特に後半の2年間はCEOを務めていたとのことですが、グローバルで事業変革を進める上で、どんなことに留意されたのでしょうか。
小玉 最初にこぼれ話になりますが、米国で最も気を付けていたのは単語・表現・言葉の使い方です。社外向けは当然ですが、社内向けであってもほぼ全てのメッセージを現地の信頼出来るメンバーに添削してもらってから発信していました。「そういう意味で言ったんじゃない」というその場の勘違いを避けるのと、「将来の不要な係争のネタに使われないように」等の中長期的なリスクも考慮していました。
また米国で認識を改めたことのひとつが、本音を見極める必要性です。我々は何となく「アメリカ人はコンフリクトを恐れずに、自分の意見をストレートに発言する」と思い込んでいるのではないでしょうか。実際は、当然のように本音と建前を使い分けています。言い方はストレートでも、自分にとってどうなのかをよく見極めて発言をしている(常に本音を言っているとは限らない)ということです。
板倉 本音を言わないという意味では、日本も米国もあまり違わないわけですね。
小玉 米国のメンバーが「意見を言う姿勢」を持っている、というのも事実です。なので日本のメンバーによく言うのは「米国メンバー相手であっても意見を言うのに遠慮は不要。言い方の配慮は必要だけれども、まず自分の意見や考えを口に出してみて」ということです。
米国の社内会議でもメンバーによって発言の多い少ないはあります。なので会議等でも出来るだけ参加者にふって、色々なメンバーに口を開いてもらうことを心掛けました。当方からの一方通行のコミュニケーションではなく、また当方管下のレポートラインからだけでなく、現場のメンバーの声にも出来るだけ耳を傾け発言してもらうこと、現地メンバーが考えるアイデアや意見を出してもらうことに腐心しました。
板倉 メンバーから意見を引き出す場合は、考えるべき範囲、論点などを具体的に示して議論してもらうのでしょうか。
小玉 例えば中期のビジネスプランを策定する場合には出来るだけ「我々のあり姿(ありたい姿)」をクリアにすることでしょうか。
例えば、米国のメンバーには本社側からの様々な期待を嚙み砕いて説明し、理解してもらう。並行して本社側には米国側の置かれている市場・状況・競合が想像しやすいように適宜情報共有を心掛け、データ・数字等で説明を尽くす。そういうやり取りを積み上げて、出来るだけ課題感や何をしなければならないのかのイメージが同じになるよう共有していくことがベースになります。
そして現場のメンバーに議論をしむけてアイデア出しを誘導する。本社側からの押し付け施策ではなく、マーケットを一番知っている販売会社側で考え、提案してもらう、というアプローチでした。出来るだけ納得性を高めることがメンバーのプライドやエンゲージメント、そして実現性を向上するためにも重要なプロセスだと思っています。
板倉 そのために海外側の「あり姿」をクリアにし、本社との間で状況認識をしっかりと揃えておくことが大前提となる。その上で、現場メンバーからのアイデアを引き出していくということですね。
「経歴にプラスになるかどうか」が重要なモチベーションの契機
板倉 一方、個々の人材のコンピテンシーに日本との違いを感じますか。
小玉 自身の経歴を積み上げる意欲が強く、それを他人に伝えるプレゼンテーションも上手だな、という点です。特に米国では、経営層に限らず様々な階層の人財がセルフプロデュースとプレゼンテーション能力が磨かれるような場数を多く踏んでいます。それがビジネス全体のエネルギーになっているんだろうな、と感じさせられますね。
反面、特に幹部採用やプロモーションの決定には、その磨かれたプレゼンテーションから本質や人間性の真贋を見極める眼と耳を持たなければなりません。また外部からの幹部採用においては、その人物の情報を裏取り出来る業界ネットワークも重要です。この感覚は非常に磨かれました。
板倉 日本人とは様子が違いますね。なぜ、そういう考え方になるのでしょうか。
小玉 おもに2つの理由が考えられると思います。ひとつは「会社はセーフネットにはならず、結局は全て自己責任」との考え方が主流であること。自分・個人でどう状況を切り開くか、個のプロアクティブ性が重要となっています。
もうひとつは、「ポジション、タイトル、レポートライン等へ貪欲に固執する」という点です。「すべては自己責任」という考えから、伝えようとしないと他の人には伝わらないという前提になっていきます。すると、伝える能力とその際にわかりやすい、自分がどのように重要な規模の組織やビジネスをマネージしたか等の「実績」をポイントとして捉えることになるのです。それが「管理者としての優秀さ」や「対応力」の裏付けになり、自分を売り込めるからです。
海外トップは本社の方向性や戦略を理解し、それを元に現地での「あり姿」を実現させる
板倉 そうした違いがある米国販売会社のメンバーを、小玉さんはどのように事業変革に向けてリードしていたのでしょうか。
小玉 個人の経験ですが、私自身が販売会社のトップとして米国での陣頭指揮をとる場合と、本社のグローバル管掌として各販売会社のヘッドと対峙して行く場合とでは、アプローチが異なります。
板倉 どのように異なるのでしょうか。
小玉 北米のヘッドだった時には、現場主義を徹底しマイクロマネジメントも厭わず対応しました。販売会社のヘッドは責任範囲が明確で現場が目の前なので、方針や戦略の確立~実行への落とし込みに現実感が出せるからです。メンバーの納得感を向上させるためにも「自分の目で見て耳で聞いて体感した事をベース」に「メンバーと一緒に仕事をする姿勢」で対応しました。現場任せではなく、現場に期待したいことを明確に落とし込むようにしましたし、現場のモチベーションをいかに向上させるかに注力しました。
一方本社側の立場だと、各ヘッドの裁量に委ねるケースが多くなります。本社からのグローバル方針・戦略がしっかり落とし込まれていても、現地の事情にズレがあったり、現場では想定外の問題も多々出てきたりします。そういった問題や課題が見逃されずに共有されるように、各ヘッドやキーメンバーとより丁寧なコミュニケーションを取り、状況の指さし確認に腐心しています。
板倉 後者の場合は、各国・地域の各販売会社のヘッドが現場の陣頭指揮を行うのですね。
小玉 とはいえ、販売会社経営を現地に任せきりにするのではなく、お互いの信頼感の醸成とともに、本社側からでも現地側の状況が把握出来る会議体の構築や、計数の把握をシステム面でのデータガバナンスを掛けてチェックして行ける体制の導入等を進めています。
どちらの体制においても、本社と各販売会社の間で戦略や計数目標をクリアに持ち、常に「あり姿」に沿った進捗となっているか立ち返りながら、出来るだけ同じ理解の上で運営して行けることを目指しています。
(次回へ続く)