サルトルはかつて「Birth - Choice - Death/人間は生まれて死ぬまでの間に選択をし続ける」と説いた。活躍中のリーダーに何を「選択」してきたのかを問い、リーダーシップが醸成された過程を紐解いていく本連載。第1回は、工場直結ジャパンブランド「ファクトリエ」を展開する山田敏夫氏に話をうかがった。(文: 荻島央江)
<プロフィール>
ライフスタイルアクセント CEO&Founder 山田敏夫氏
1982年、熊本県生まれ。創業100年の老舗婦人服店の息子として育つ。大学在学中、フランスへ留学しグッチ・パリ店で勤務し、一流のものづくり、商品へのこだわり・プロ意識を学ぶ。2012年1月、工場直結ジャパンブランド「ファクトリエ」を展開するライフスタイルアクセントを設立。1年間に訪れるものづくりの現場は、100を超える。
業界のタブーを打ち破る
伊藤: まず「ファクトリエ」について伺いたいのですが、ファクトリエを一言で表すと?
山田: 今までになかったコンセプトで説明が難しいのですが、メイドインジャパンの工場直結ファッションブランドです。
伊藤: 自社工場を持っているわけではなく、既存の工場を使ってファクトリエというブランドの服を作っているのですね。
山田: そうです。まず僕らは業界では画期的なことを大きく2つやっています。
1つは、その洋服を製造している工場の名前を公開するほか、例えば「Factelier by HITOYOSHI(工場名)」というように商品名にも付けました。今までファッション業界では工場名を公開するのはタブーだったのです。
もう1つが、作り手にとって適切な環境を整えました。ファッションは一見華やかな世界ですが、その裏に非常に暗い部分がある。お客様は神様、ものづくりの人は奴隷のようになっているのが実態です。
先進国で販売されている洋服のほとんどが、賃金の安い国で作られています。例えば、労働者の時給が日本の20分の1のミャンマー、80分の1のバングラデシュなどです。それでも最近は「ちょっと(採算が)合わない」と言われ出して、商社やアパレルメーカーなどは南米もしくはアフリカに次の生産地を探し始めています。
そもそも生地の原料となる綿花の栽培には大量の農薬が使われています。それはベトナム戦争で使用された枯葉剤と同じ成分が含まれた有害なもので、年間に4万人のコットン農家がガンで亡くなっているといいます。また、子供たちを学校に行かせないで働かせる児童労働も大きな問題です。
こうして作られた洋服が日本に年間40億着ほど供給されて、その6割から7割が袖を通さずにそのまま捨てられています。これは10年前の3倍です。
伊藤: 袖を通さずに捨てられてしまうのはなぜですか?
山田: 店頭の在庫を切らさないように多く作られるのに加え、最近では、本来売れ残ったものを売るはずのアウトレット用にも服が作られるようになったからです。
だから百貨店などで販売する正規品で売れ残ったものは行き場がない。安売りするとブランドが棄損するので、売れ残りはすべて焼却処分されるのです。米国の場合、衣類の廃棄金額は年間5兆円と言われています。
きらびやかな業界の裏では、これだけ人が死んで、子供たちが働かされ、なおかつ供給しても多くの洋服が誰も袖通さないままゴミとして捨てられていく。でも、ここの部分はずっとぶ厚いカーテンで隠されてきました。
ものづくりの奴隷からの解放
山田: 僕がファクトリエで実現したかったのは、こだわりを持ったものづくりができる人たちがちゃんと生きていける経済圏をつくることです。
というのも、日本製がすべていいというわけではなくなってきた。服の原価率は1割から2割です。例えば5000円のTシャツなら、単純計算で生地代も入れて1000円で作らないとなりません。生地代は600円から700円なので、残る金額は300円程度です。
そうなると工場は人件費を考えると30分以内で生産しないと採算が合わなくなり、仕方なく手を抜き始める。メイドインジャパンの手を抜いて作ったTシャツと、中国製の最新の機械で作ったTシャツのどちらのクオリティーが高いか、という話です。
世の中にはメイドインジャパンを信仰している人が多い。でも僕が現実に工場回って目にしたのは、「これだったら中国のほうが勝つのではないか」という光景です。
とはいえ日本も工場が持っている技術をすべて出したら、まだまだ中国はもちろん、世界の一流ブランドにも勝てる力を持っていると思います。そのためには、世界と勝負できる服を作らなければなりません。ひいては、作り手も買う側もちゃんとこだわりの持てる経済圏を構築しないと駄目でしょう。
ただ一方で、現実問題として、どんなに良い服でもそんなに高い値段では買ってもらえません。だから、インターネットを活用し、中間流通は省きました。きちんと価値を発揮できるものを、工場やお客様とコミュニケーションを図って作り、販売するというのが、僕らが取り組んでいることです。
伊藤: 日本のブランドが生み出す、世界に誇れる服をちゃんと届けたいから、いいものを安くでもなく、高くでもなく、適正な価格で提供するようにしているのですね。
工場を自走する組織に
伊藤: 通常、アパレルの世界は、ブランド側が協力工場に製造を委託しているというイメージがあります。ファクトリエの場合は、工場と山田さんたちのチームが共同でつくっているわけですよね。
山田: 完全に共同ですね。結局、ものづくりは作り手一人ひとりが自走する意識がなければ良いものは作れません。僕らがデザインからパターンから渡していたら、彼らは自走しようとしない。今までの工場は、アパレルなどから殴り書きで@300円と書かれたFAXが送られてきて、「はい、分かりました。1枚300円ですね」と、相手に言われるがままという姿勢でした。
彼らに「考えて」と言っても考えない。「どうやればいいですか」と聞かれる。考える余裕がないし、そんなことより早く取りかからないといけないからです。でも、彼ら自身が考えるようにならないと、日本のものづくりは良くならないと思うんです。
だから彼らには「最初はゆっくりかもしれないけど、一緒に歩きましょう」「ただ、最後は二人三脚で走ってオリンピック出ましょう」みたいに話しています。僕らが仕事を発注して終わりではなく、彼らを巻き込んで世界に打って出たいのです。
いつも工場には「僕らのブランドではなくて、自分たちの名前が入っているのだから、自分たちのブランドと思ってくださいね」と言っています。かといって、自由すぎるとデザインに統一感がなく、工場によってはおかしなデザインを上げてくるかもしれない。そこで僕らとしては1つの基準を持たないといけない。それがファクトリエというブランドで、いわば僕らの基準をきちんとクリアしたものですよという認証マークのようなものです。主役はやはり工場です。
それでも海外ブランドを選ぶ
伊藤: ファクトリエのポロシャツを愛用していますが、ポロシャツを作っている工場は複数あるのですか?
山田: 複数あります。今は1つですけどね。共に走りながらも、そこは競争原理を働かせています。
一緒に取り組み始めるときに、まず工場と一緒に未来を描くんです。多くの工場はフル回転していても、大抵赤字なんですよ。下請けで、受注金額が安すぎるからです。
その点、私たちと一緒にやると、彼らが販売価格を自分で決められるので、適正な利益が得られる。ファクトリエブランドの取扱量が概ね全体の25%から30%ぐらいになると、黒字化します。「今、売り上げがこのぐらいであれば、10年後にはここまで持っていきましょう。だから今年はこの数を一緒に作っていきましょう」と話します。
もっとも、ときどき「海外有名ブランドの仕事が来たので」といって、そちらの仕事を入れてしまう工場があります。海外有名ブランドといっても、受注額が安いので利益なんて出ない。どう考えてもファクトリエのものを作ったほうが儲かるのに、彼らは海外有名ブランドのほうを選ぶんですよ。今までそこからの依頼を断った経験がないからです。
そういうときは、工場に「順番待ちしている工場がある。御社が作らないならそっちで作りますよ」という話をします。そういう競争原理も働かせながら、多くの工場が永続的に生きていけるように取り組んでいます。
伊藤: パートナーとしてサポートもするけど、互いに責任を持ってちゃんとやることをやろうということですね。
山田: そうです。工場の経営者もそれぞれ未来と目標がある。会社の数字をこのぐらいにして黒字になったら息子が(跡取りとして)帰ってくるかもしれないとか、それぞれ見ている未来がある。未来を実現するには、儲けの少ない仕事より、儲けの多い仕事を選んだほうが間違いなく利益が出る。名より実を取ったほうがいいのに、従来のやり方を変えられないという工場も多いんです。
今が工場にとっても過渡期だと思います。本当に自分たちのものをちゃんと作っていこうという志のある工場に成長してほしい。
全国600の工場を回って、50に絞った
伊藤: 表面的には、消費者に対してメイドインジャパンのいい服を提供しているように見えますが、山田さんが最終的に目指しているのはサプライヤーである工場に自立してもらうことなんですね。
山田: この5年で日本全国600の工場を回って、「これは」と思う工場50に取引先を絞りました。この50は僕のエゴかもしれませんが、絶対に残すべきだと思っているんですよ。だからこそ彼らが信用金庫にお金を借りるときに同席したり、学生100人ぐらいを集めて50の工場への就活イベントを開催したりしているのです。
生き残るためには一つひとつの工場に自立してもらう必要がありますが、僕らも彼らへの発注量を増やさなければならないし、後継者も一緒に育てないといけない。メイドインジャパンのいいものを後世に残していくためには欠かせないことだと思ってやっています。
伊藤: 政や官なら分かるんですけど、営利を目的とする民間企業がそうした取り組みをして、なおかつ伸びている例は見たことがない気がします。
山田: 政府関係であれば全員を救わなければいけないのでしょうが、僕らは600ある工場すべてを救おうと思っていません。僕らは営利のためにえこひいきしました。
これがビジネスになると思っているからやっているのです。ファッション業界で通用するのは、世界広しといえども、メイドインイタリー、フランス、ジャパンの3つのブランドしかない。そんなブランド力があるのに商売にしないなんてもったいないですよね。
しかもタイミングとしてすごくよかった。東京五輪開催が決まってみんなが帰属意識として日本人というものを意識し、メイドインジャパンに改めて興味を持ち始めた時期でした。これに加え、アパレル不況で工場側も「自分たちも何か新しいことにチャレンジしないと生き残っていけない」と考え始めていたし、ECもますます発達していた。地方創生という文脈もそうかもしれません。時がすべて重なりました。
もしこれが10年前だったら、相手にしてもらえなかったと思うんですよ。工場ももう腹が減ってたまらないときだったから話を聞いてくれて、「じゃあ賭けてみようか」という気になってもらえた。やりたかったことをやっているだけなんですけど、手前味噌ながら、今の時代にマッチしている。ファクトリエは奇跡的なタイミングで生まれたと思っています。










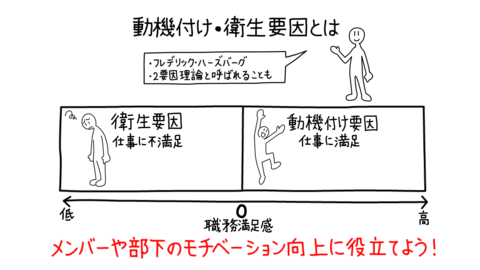



























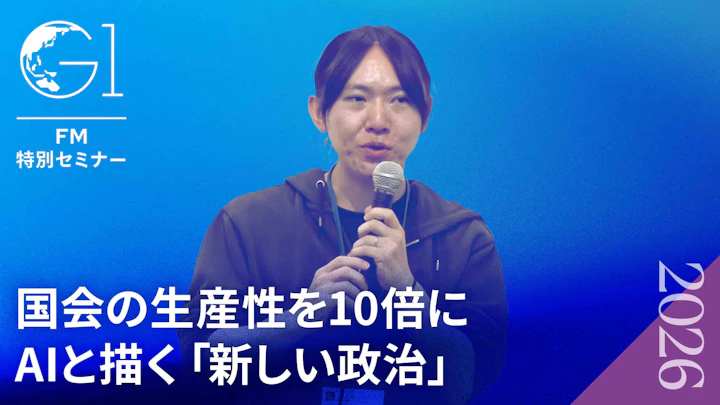



.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

