
活躍中のリーダーたちにリーダーとして目覚めた瞬間を問い、リーダーシップの出現メカニズムを解き明かす本連載。第13回は、6大陸の最高峰を制覇し、インターネット生中継登山にも挑戦する登山家、栗城史多さんにお話を伺いました。(文: 荻島央江)
<プロフィール>
登山家 栗城史多氏
1982年北海道生まれ。大学3年生のときに北米最高峰マッキンリー山(標高6190m。2015年からデナリが正式な呼称)に単独登頂。その後、6大陸の最高峰を登り、2007年から8000m峰の単独・無酸素登頂や、スキー滑降を始める。2009年「冒険の共有」としてインターネット生中継登山を始めるが、2012年気象条件の厳しい秋のエベレスト西稜で重度の凍傷により手指9本の大部分を失うも、2014年7月ブロードピーク(標高8047m)に無酸素・単独登頂。復帰を果たす。2017年エベレスト北壁に挑戦する。
山に登るときは何も考えない
伊藤: 今日は東京にいらっしゃいますが、次のチャレンジはいつですか。
栗城: 次回はエベレスト北壁に挑戦します。4月10日ぐらいの出発を考えています。
伊藤: 今はどんな準備をされているのですか。
栗城: トレーニングをしたり、活動資金調達のためにスポンサーを回ったり、講演をしたりしています。
伊藤: そういう活動しながら、徐々にモチベーションを高めていくのですか。
栗城: やるべきことに淡々と取り組んでいる感じです。よく「山を登っているとき、何を考えているんですか」と聞かれますが、何も考えていません。淡々とリラックスして登っています。僕は酸素ボンベを使わずに登るのですが、一番のポイントは脳だと思っています。脳が消費する酸素量は全身の約3割近くを占めます。だから脳の酸素消費量をいかに抑えるかが重要で、脳に余計なストレスをかけてはいけない。普段からそれを意識しています。
別れた彼女への未練で登山を始めた

伊藤: 登山家の方に1対1でお話を聞くのは初めてなので、色々お伺いしたのですが栗城さんはもともとどんなお子さんだったのですか。
栗城: 僕は北海道出身なんですけど、小学生のときはあまり授業に出ずに裏山に遊びに行って、給食になったら帰って来るという感じで、勉強したという記憶がほとんどないですね。当時、なりたかったものがピーターパン。そのまま現在まで来たかなとは思っていますけどね。
伊藤: ピーターパンになりたかったんですか!
栗城: 子供ながらに、子供のままでいかに生きていくかということを考えていましたね。
伊藤: なるほど。登山を始めたきっかけは何ですか。
栗城: 高校卒業後、ニートをしていた時期があるんです。当時、僕は東京に住んでいて、北海道で暮らす彼女と遠距離恋愛をしていました。彼女が「将来、結婚するなら公務員がいい」とか「車があればいいのに」と言っていたので、北海道へ戻って大学に入り、アルバイトをして車も買いました。それなのに、彼女とドライブに出掛けたとき、「2年間付き合っていたけど、あんまり好きじゃなかった」と言われて、ふられてしまったんです。
ものすごく落ち込んで、家からも出なくなった。苦しいながらも「このままじゃ自分がおかしくなってしまう。何か始めないと駄目だ」と思ったとき、頭に浮かんだのが山でした。彼女は趣味が登山で、雪山にも行くような人だったんです。
付き合っていた頃は「どうして雪山になんかわざわざ行くのかな。大変なことばっかりじゃん」と思い、山に全く関心がありませんでした。そんな僕が「山岳部に入ったら何かが変わるんじゃないか」と登山を始めた。要は彼女への未練ですね。高尚な理由ではなく、安易な気持ちで始めました。
大学の山岳部は厳しかった。先輩によく言われたのは「登頂癖を付けろ」。途中で諦めることを許してくれないんです。悪天候でも、「風邪をひいて熱が出たので参加できません」と電話しても、「行けば治る」とかわけの分からないことを言われました。
伊藤: よく山岳部をやめなかったですね。
栗城: 自分でもそう思います。大学2年の冬に先輩と2人で、年越し縦走に挑みました。この先輩が僕を変えてくれた恩人で、縦走での経験が大きなターニングポイントになりました。
札幌市と喜茂別町の境にある中山峠から小樽市の銭函までの55km近い距離を、尾根伝いに歩くんです。僕は行く前から「無理だ」と思っていました。電波も届かない場所で遭難したらおしまい。実際、本当に遭難しかけましたからね。
初めて何かを成し遂げて泣いた

生きて帰るためには必死で足を前に出すしかなくて、気付いたらゴールしていました。ゴールの小樽に着いたときに、うわーっと泣いている自分に自分で驚いた。悔しくてとか悲しくて泣いたことはあっても、何かを成し遂げて泣くという経験は初めてでしたから。
帰りの電車の中で、これまでを振り返りました。何かやりたいことがあっても、「どうせ自分にはできっこない」と言い訳して遠ざけていたなと。無理だと思っていた縦走を達成して初めて、限界は自分がつくった幻想だと気が付きました。山が自分の壁を全部取っ払ってくれたんです。それから山の世界にどんどんのめり込んでいきました。
伊藤: そのときにスイッチが入ったわけですね。それからどうしたのですか。
栗城: 大学3年のときに、北米最高峰のマッキンリー(6190m)に挑戦しました。大学4年になったら海外遠征するのが山岳部の慣わし。僕はまだ3年でしたが、常々海外の山を登ってみたいと思っていました。さすがにエベレストにチャレンジするほどの経験はまだない。そのとき浮かんだのがマッキンリーでした。
ただ、行くまでが大変でした。実は僕を育ててくれた山の師匠である先輩もマッキンリーが目標で、しかも「栗城と行きたい」と思ってくれていた。でも僕は断ってしまった。先輩がいると、僕は先輩の後ろを付いていくだけ。それが僕のやりたいことじゃない。僕は自分の力を試してみたかった。最後は「どうしても1人で行きたいなら、山岳部を辞めて行け」と言われたので、退部してマッキンリーに行きました。
「マッキンリーに単独で登りたい」と言ったら、先輩だけじゃなく周囲の人みんなに反対された。反対というより、否定ですね。「お前には無理だ」と洗脳のように聞かされて、それはきつかった。大学は退学届の用紙を送ってきました。何かあったときに困ると考えたのでしょうね。
伊藤: 周囲の反対をどう振り切ったのですか。
栗城: 最終的にマッキンリーに行けたのは父のおかげです。新千歳空港からいよいよ飛び立つというときに父から電話がかかってきた。「これだけ反対されているのだから、やめておけ」と説得されたら、やめようと思ったんです。父は一言だけ、「信じている」と言ってくれた。それがすごくうれしくて、「父のために絶対に登頂して帰ってこなければ」と決意を新たにしました。
父の言葉が支えでしたね。よく考えてみると、「栗城には登れない」と言われたけど、そう言う人の誰もが同じ挑戦をしたことがない。それなのに、みんなどうして無理だと決めてかかるのかなと。
伊藤: ほとんどの人が自分で自分の可能性や限界を決めてしまうのでしょうね。
栗城: そう、むしろ敵は自分自身です。損得やできる、できないを考えていたらすごくもったいない。自分の心が少しでもこっちだと思ったら、まずはつかんでみる。つかんだら、おのずとその先は見えてくると思います。ただこのとき、あまりにも周りに反対されたので、マッキンリーで終わりにするつもりでいました。
下山中の事故が7割
栗城: 山の事故の7割が下山中に起こっています。下山中に事故が多いのは技術的に難しいからじゃない。頂に向かっていくことには100%の力を出せても、登頂後は燃え尽きてしまう。目標が大きければ大きいほど心の反動も大きいのです。
伊藤: 栗城さんは無事に帰ってきた。
栗城: 山岳部の先輩に出発前、「次の山のために生きて帰ってこい」と言われたんです。その言葉を思い出して、「ここで終わりじゃない」と自分に言い聞かせ、日本まで帰ってきました。
帰国後、いくつか新聞社が取材に来て、「今度はどこに行くんですか」と聞かれたので「南米の山ですかね」と答えたら、「次は南米最高峰のアコンカグア」という記事になっていた。しかも12月と書かれていたんですよ。それがわーっと広がり、ご縁を感じて本当に行きました。
登ってみると、山によって空気も雰囲気も違う。「地球を感じながら山に登ってみたい」と思うようになり、6大陸の最高峰を登り、さらには気象条件の厳しい秋季エベレストを目指すところまで来ました。最初から大きな目標があったわけではなく、目の前の山を越えたら次の目標が見えてきたという感じです。
ずっと続けている「冒険の共有」というインターネット生中継登山のおかげで、新しい課題や目指したいものが見えてくるというのもあります。
「おめでとう」より、「ありがとう」

伊藤: どんなきっかけで生中継を始めたのですか。
栗城: そもそもは2007年に配信された第2日本テレビの企画、「ニートのアルピニスト栗城史多 はじめてのヒマラヤ」が発端です。ヒマラヤのチョ・オユー(8201m)挑戦の模様を僕自身がビデオカメラで撮影して、現地からほぼ毎日映像を送りました。これをきっかけに自分でも生中継を始めたんです。
2007年はテレビ局がインターネットとテレビを融合させたら何ができるかを試験的にやり始めた年。「現地から動画の配信をやらないか」と声をかけられたとき、「冒険の世界を日々動画で見せるというのは画期的だな」と思って、引き受けたんです。
以前から自分でも撮っていました。その映像を縁あって「電波少年」で有名な日本テレビプロデューサーの土屋敏男さんに見せたら、「君の映像はおかしい」と。「普通、山にカメラを持っていったら山に向けるよ。栗城君の場合、8割は自分を撮っている。どれだけナルシストなんだ」と面白がってくれた。それが企画につながりました。
企画のタイトル「ニートのアルピニスト栗城史多 はじめてのヒマラヤ」が波紋を呼び、全国のニートから誹謗中傷されました。「そもそもニートは頑張らない」とか(笑)。悪天候のために登頂を断念して下山したら、「やっぱり栗城は駄目だ」とさんざん書かれました。それが悔しくて、再度チャレンジして登りました。最後はギリギリだったんですけど。
登頂できたことのほかに、もう1つうれしいことがありました。「栗城は登れない」とかいろいろ書いていたやつが一言だけ「ありがとう」と書いてくれたんです。わぁと思って、鳥肌が立ちました。それまで山に登ってきて、「頑張ってください」とか「登頂おめでとう」と言われたことはありましたが、「ありがとう」はなかった。このメッセージを見たときに「これこそが冒険の力なんだ」と思ったんですよね。登山家である僕にとって何よりうれしい言葉でした。(続きはこちら)








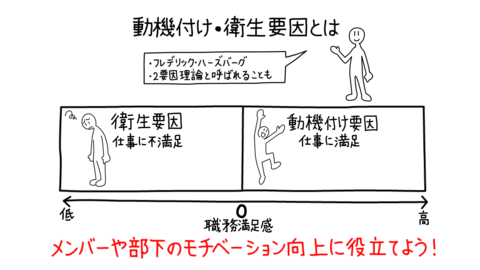

































.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

