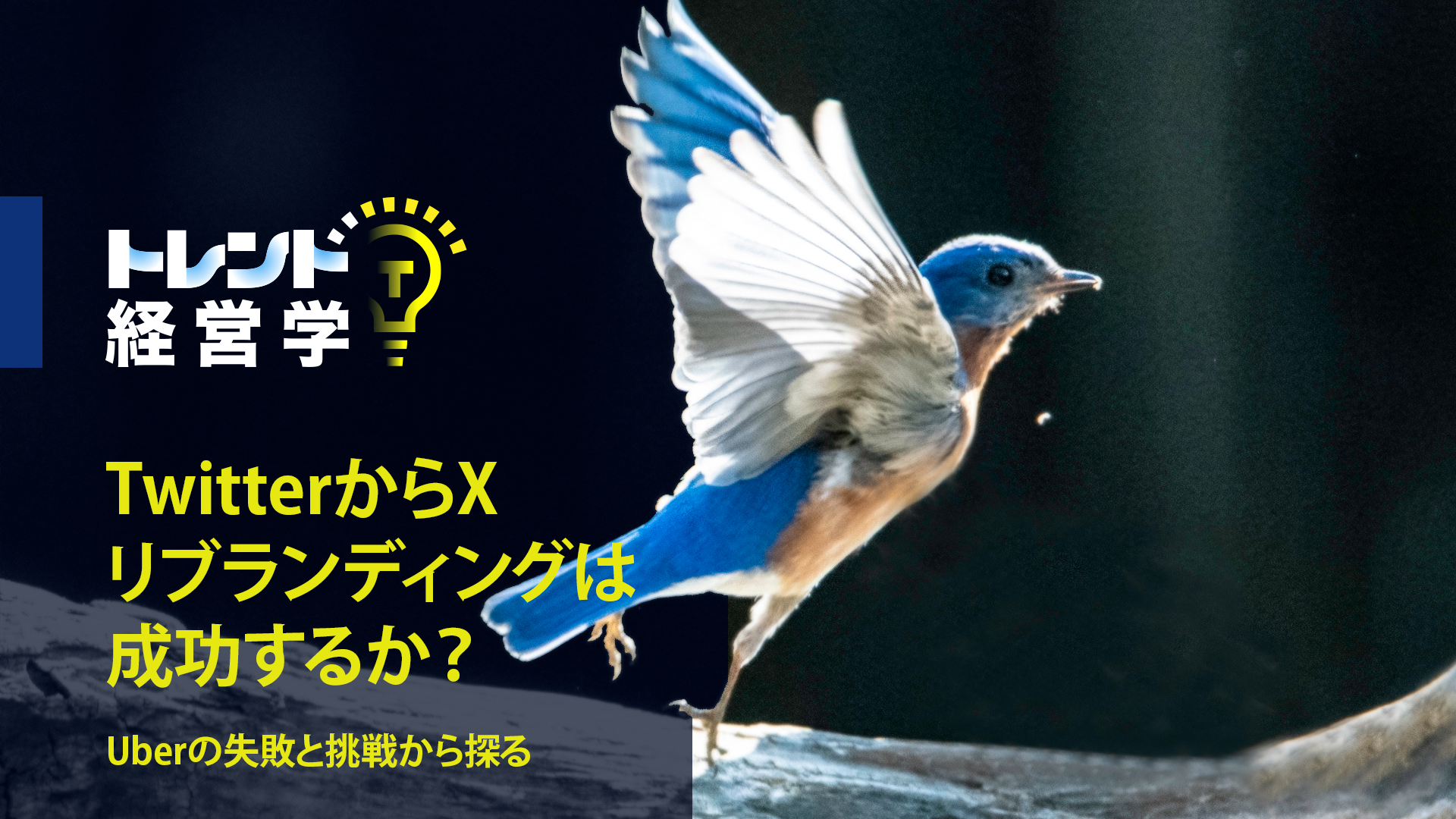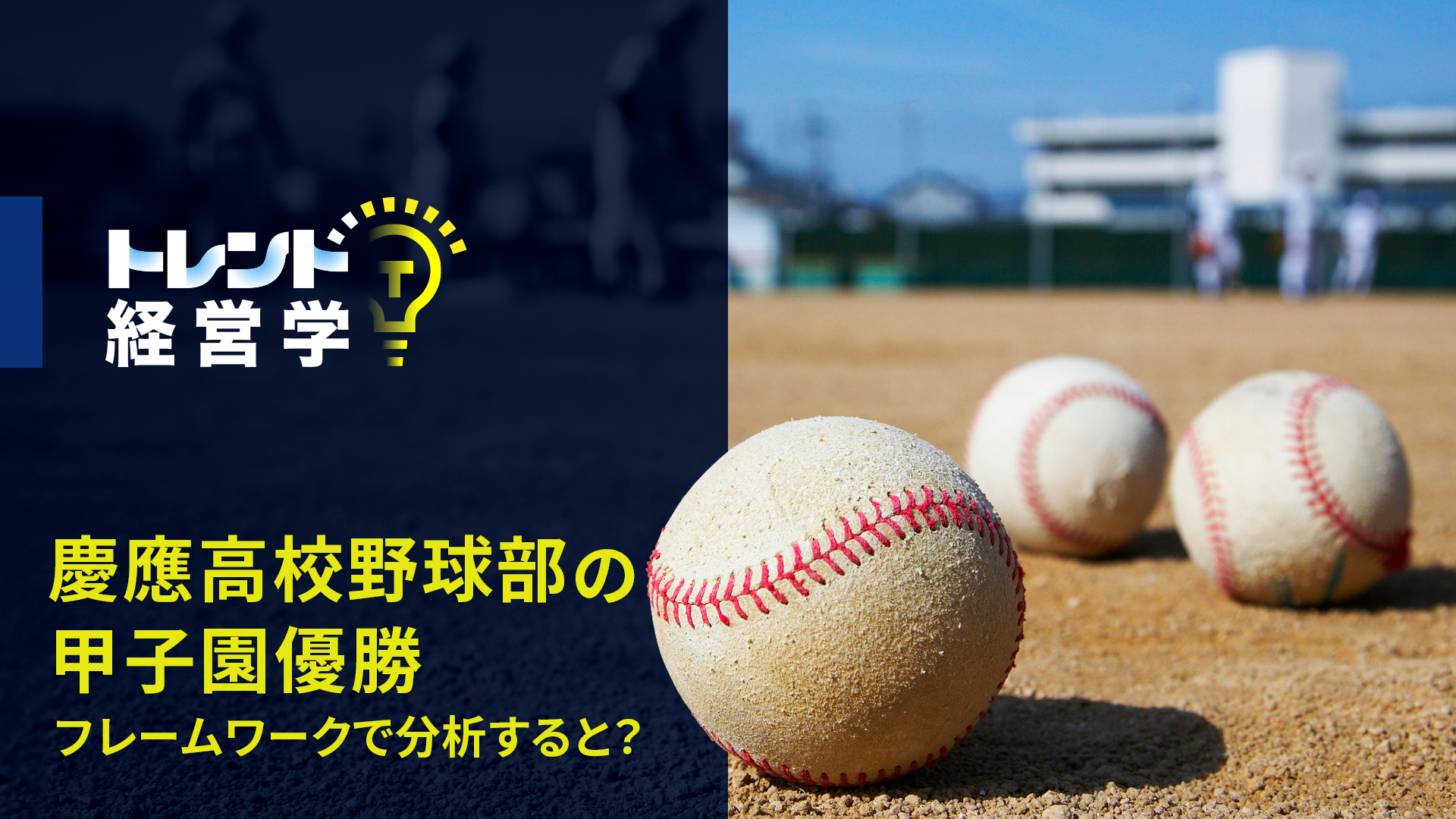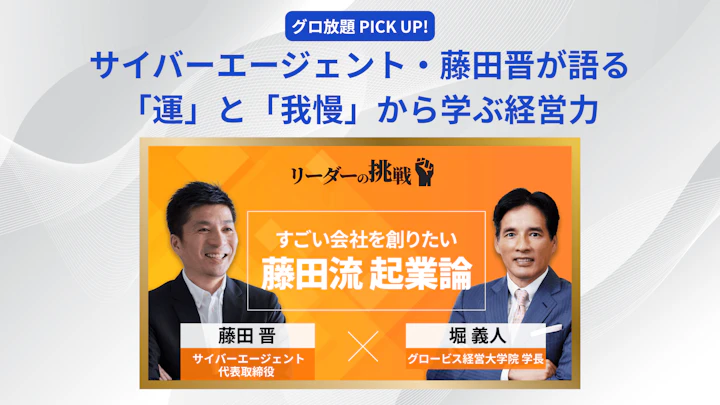前回に引き続き、人間の行動に影響を与える要素について考えてみましょう。
前回に引き続き、人間の行動に影響を与える要素について考えてみましょう。
人をある方向に駆り立てる要素として、前回はインセンティブ、特に金銭的インセンティブの話にフォーカスしました。金銭的なインセンティブや、それをもたらす成功は確かに人を大きく駆り立てますが、人を駆り立てるのはそれだけではありません。その他の代表的なものとして、まず以下があります。
・面白い仕事
・同僚や上司からの影響、彼らとの良い関係
・承認(他人から認められること)やお祝い
・夢、ビジョン、経営理念
これは、マズローの欲求5段階説で言えば、上位3層に対応しているのがわかります。つまり、「面白い仕事」や「夢、ビジョン、経営理念」は一番上の「自己実現欲求」に、「承認(他人から認められること)やお祝い」は上から2つ目の「承認欲求」に、「同僚や上司からの影響、彼らとの良い関係」は上から3つ目の「愛と所属の欲求」に対応しているのです。
欲求5段階説はやや古いフレームワークではありますが、やはり普遍的な要素を含んでいます。皆さんが適切にこれらを与えられているか、逆に、管理職の立場であれば、部下とコミュニケーションをした上で適切にこれらを与えているかを再確認してみてください。
その他に、やや「変化球的」な人を駆り立てる要素として、以下のようなものもあります。
・ライバルとの競争
・コンプレックス(劣等感)
皆さんも思い当たる節はあるのではないでしょうか。まず、ライバルとの競争は、うまく働けば非常に大きなパワーを発揮します。
たとえば今からおよそ20年前に、メジャーリーグで当時のホームラン記録更新を2人の選手――マーク・マグワイアとサミー・ソーサ――が争うということがありました。最終的には2人とも従来の記録を大きく更新する新記録を作ったのですが、もし1人だけが孤高の挑戦をしていたら、最終的な新記録はもっと低いものになったかもしれません。ライバル関係が不断の努力を生み出すという要素は、まさに使い方によっては大きなエネルギーになります。
一方で、そうした競争心が悪い方向に働くこともあります。最も分かりやすい例は足の引っ張り合いです。ライバルを陥れるためにネガティブキャンペーンをしたり、仕事の邪魔をするというケースは決して珍しいことではありません。上司の立場として、もし部下同士のライバル関係をうまく使うのであれば、そうした後ろ向きの行動をとらないように適切に指導することが必要になります。
コンプレックスは非常に微妙です。歴史上の偉人を見ても、これをばねに大きな仕事をした人は少なくありません(例:野口英世など)。しかし、これは先のライバル意識以上に危険性を内包しています。
第一に、コンプレックスの克服が目的化してしまい、必ずしも好ましい方向にベクトルが向くとは限らない点が挙げられます。第二に、ビジョンや理念が伴いにくいという側面もあります。結果として視野狭窄や、かりに成功したとしても、成功後の方向性の欠如にもつながりがちです。
コンプレックス克服という動機は、なまじ強いエネルギーがあるだけに、いったんベクトルがずれてしまうと、暴走した機関車のようになってしまいます。一般に、こうした動機は上司と部下との面談でも語られることが少ないので、上司側のマネジメントも難しくなります。人間観察力が強く求められるシーンと言えるでしょう。
人の行動を好ましくないことから遠ざけるものは?
さて、ここまでは人を駆り立てるものについて見てきましたが、人の行動を好ましくないことから遠ざけるものについても見ておきましょう。これは、ちょっとしたことが企業のブランド価値を下げる可能性がある昨今、非常に重要な要素です(なお、これに関しては一部を「グロ斬る」でも喋ったことがありますが、重要なことなので再度述べたいと思います)。
人の行動を制約するものとしては、大きく4つがあります。
・ルール
・常識
・宗教
・信念
ポイントは、どの制約要素も、それを破った時に罰を与える人間がいるということです。たとえば、ルールの代表とも言える法律、特に刑法は、破れば国に罰されます。企業においても、就業規則を破れば、何らかのペナルティが科されるでしょう。
それに対して、常識は、国や企業が罰を与えるわけではありません。裁いたり罰を与えるのは「世間」です。これは、文字通りの世間である場合もあれば(例:自動車メーカーによる排ガス規制逃れ)、組織の構成員の場合もあります。後者はつまり、その組織の明文化されていない常識(いわゆる企業文化です)を破れば、「あいつはこの組織に相応しくない奴だ」と見なされ、居心地が悪くなるのです。
宗教は、日本人にはややイメージが湧きにくいですが、罰するのは神です。世界レベルで見れば、宗教に突き動かされて何かをしたりしなかったりという人間は非常に多いので、そうしたセンスを日本人としても意識したいものです。
最後の信念は、罰するのは自分自身です。ただ、これを外部からコントロールするのは難しいですし、自分に甘い人間にはあまり効かないという弱点もあります。
さて、組織にとって好ましくない行動をどのように防ぐかという観点に戻ると、現実的に有効なのはルールと、組織の常識である企業文化ということになります。ありとあらゆることをルールで定めることは費用対効果を考えると現実的ではありませんし、往々にして人々を委縮させたりと副作用も大きくなります。前回も触れたように、好ましくない方向へのルールのすりぬけも起こります。ルールで縛るのはミニマムに留め、組織文化や企業理念などで人々の行動を律するのが、適切と言えるでしょう。
こうして見てくると、良き組織文化を作ったり、それと強く連動する経営理念やビジョンを魅力的なものにすることこそが、人を駆り立てるにも律するにも効果的なことがわかります。
皆さんの組織はそれができていますか?