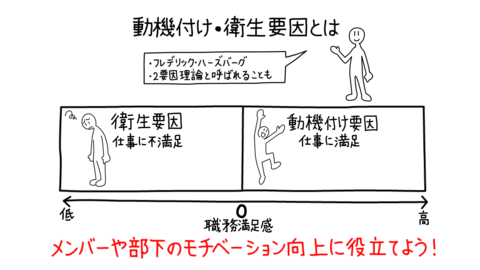<プロフィール>
Kaizen Platform CEO 須藤憲司
1980年生まれ。2003年、早稲田大学を卒業後、リクルート入社。同社マーケティング部門などを経て、史上最年少でリクルートマーケティングパートナーズ執行役員に就任。13年にKaizen Platformを米国で創業。現在はサンフランシスコと東京の2拠点で事業を展開。ウェブサイトを容易に改善できるオンラインソフトウェアと、約2900人のウェブデザインの専門家(グロースハッカー)から改善案を集められるサービスで構成されるUI改善プラットフォーム「Kaizen Platform」を提供。エンジニアやデザイナーがいなくてもウェブサイトの継続的な改善ができると、大手企業150社、40カ国3000カスタマーに活用されている。
証券マンの父が突然退職
伊藤: スドケンさんのリーダーシップの原点を探りたいのですが、子供の頃はどんな少年でしたか。
須藤: あんまり勉強はしませんでしたね。僕の親父は証券会社に勤めていたのですが、中学校2年生くらいのときに辞めちゃった。何かの映画みたいに、いきなり夕飯のときに「俺は会社を辞めるから」と言い出して、家族全員がざわざわしたという。「ただいま」と家に帰ると、「お帰り」と親父が迎えてくれる。そんな状態だと、家庭はいかにぎくしゃくするかということを学びました。
伊藤: そのときのことが、今のスドケンさんに何か影響を与えていますか。
須藤: 与えているような気がします。親父は会社を辞めた後、1年半くらい仕事をしなかった。おしゃれな言い方をすると、ロングバケーション。当然のごとく家庭は崩壊寸前でした。
当時、僕は私立の中学、高校に通っていました。学費がかなりかかるので、さっさと働こうと考えました。思いついたのが、すし職人。努力次第で若くして一人前になれると考えたからです。
「僕はすし屋になる」と周りに言っていたら、担任の先生に止められた。「お前はすし屋として本当に一流になれると思うのか」と聞かれたので、「分かりません」と答えたら、「分からないなら、もっと勉強しろ。親御さんに言ってあげるから」と諭されました。結局、両親は僕をそのまま学校に通わせてくれ、今に至ります。
証券マンの父親は僕にとって憧れの存在で、「サラリーマンってかっこいい」と思っていました。ただ、辞める直前はあまりいい顔をしていなかった。後になって「そのときに販売していた商品や会社の方針に納得していなかったから、辞めてよかったと思っているよ」と話していました。
そんなことがあって、つまらない顔をして会社に行くような人間にはならないようにしようと思ったのです。
伊藤: 大学時代はどんな学生でしたか。
須藤: 大学のときはサークルの幹事をやっていて、本当にちゃらちゃらしていましたね。当時の僕を知っている人たちからすると、「お前、よく会社員をやっているね」というくらいの自由人でした。でも面白くなかった。遊んでいても、何をしていても中途半端な感じ。「何か打ち込めることをしたい」と思っていました。早く仕事がしたかったですね。
僕が思う楽しい会社員のイメージは「アサヒスーパードライ」のCMのハイタッチ(笑)。就職活動の面接のときに、「どんな仕事がしたいか」と聞かれると、「アサヒスーパードライのCMでカンパーイとやっているあれがいい。毎日乾杯する、ああいう人生を送りたい」と言っていました。
伊藤: そんなことを面接で言っていたなんて、ちょっと普通じゃないですよね(笑)。
須藤: そうですか(笑)。いろいろな会社に受かったり、落ちたりしましたが、最終的にリクルートに決めたのは、あの会社の人たちが面白かったから。仕事が好きな人の集団で、「この人たちはいい。昔、俺がかっこいいと思っていた親父と似ている」と思ったんです。
リクルートに入ることに親父はすぐに賛成してくれました。でも母親は頑なに電力会社とかもっと安定した企業に行けと言う。寄らば大樹の陰の発想ですね。「息子がそういう会社に合うと思うのかい」と言いましたが、そのときは聞く耳を持ってくれなかったですね。最終的に「一度きりの人生だからリクルートに行くわ」と自分の意思を通しました。
褒められるためにやったことがない

伊藤: リクルート時代は異例のスピードで出世しましたよね。
須藤: そのときの親の反応が面白かった。一応、実家に電話するじゃないですか。「やばい。マネジャーになっちゃった」と報告したら、母親が「部下は何人いるの?」と聞いてきた。「8人」と答えると、「8人だったら、何かあったらお父さんとお母さんが(メンバーの)ご両親に『ごめんなさい』とご挨拶に行くから、精いっぱいやりなさい」と言ってくれた。
部長になったときもそう。「部下は30人」と伝えると、「30人くらいだったら(挨拶に)行けるから、大丈夫」と。次に執行役員になりました。「今度は部下110人か。それくらいなら何とかなる。頑張れ」と言ってくれました。
伊藤: 素晴らしいお母さんですね。
須藤: 褒められないことで、リーダーシップが養われていたのかもしれません。何かできても、できなくても「ふーん」でしたから。
伊藤: なるほど。そういう環境を学生時代や社会人になってから疑似的につくれるかというのは、すごく大事なことなんじゃないかと思います。
須藤: 褒めてくれる人じゃなくて、怒ってくれる人って貴重ですよね。僕はいまだに怒ってくれる人のところに必ず行きますね。
伊藤: フィードバックを受けるわけですね。リクルートで怒られたことはありますか。
須藤: 怒られましたよ。それはもう大変な怒られようでした。「遊んでいるんじゃねえ」とか「やる気があるのか」とか。それはもう1000回くらい色んな人から怒られましたよ。企画書を目の前で破られたこともありました。
伊藤: 真面目に取り組んでいてもそう言われてしまう?
須藤: きっとどこかに甘い部分があるんだと思います。当時のリクルートには化け物みたいに怖い人がめちゃくちゃいました。今、思い出しても震えが止まらないミーティングとかありましたよ。でもそれで相当鍛えられたので、怖い人って大事ですよね。それに理不尽なことでもしょっちゅう怒られていましたから、理不尽には慣れっこになりました。
伊藤: Kaizen Platformにそういう人っていますか。
須藤: あんまりいませんね。一番理不尽なのは僕じゃないですか。そもそも社会って理不尽じゃないですか。会社を一歩出たら理不尽なことばかりだし、社内が少しくらい理不尽でもいいかなって思うんですよね。
伊藤: 今、社会全般に理不尽イコール駄目とされがちですが、時にはそれも必要だよなと思うことがありますね。
須藤: 僕はコンプライアンスという言葉がよくないと思っています。ちゃんとしようとし過ぎていて、その圧力が半端ない。すべて白と黒で分けて、グレーな部分をなくそう、なくそうとしている気がします。そうすると理不尽なことは全部駄目みたいになって、かえって理不尽になると思うんですよね。適度に理不尽な人がいると、「あの人、本当に理不尽だよね。はっはっは」で終わるのに。
伊藤: Kaizen Platformのマネジメントで、何かそれを踏まえてやっていることはありますか。
須藤: すごく単純に、グレーなことを残しています。ぼんやりとぼけるというか。全部決めることが正しいとは思っていないので、みんなから「決めてください」と言われても、むにゃむにゃごまかす。正しいことで100%埋めちゃうのは駄目だと心から思っています。
誤解を恐れずに言えば、アンダー・ザ・テーブルは大事です。僕は上司に何の報告や相談もせず、こそこそやるのが大好きでした。「あいつ、また何か勝手なことをやっているな」とみんな気付いていても、見て見ぬ振りをしてくれた。それは大人として結構大事なことだと思っています。グレーにしておいて、「何か分からないけどうまいことやっておいて」みたいな部分がないと、筋肉質だけど、風邪をひきやすいという会社になってしまいそうで。少し脂肪があったほうがいいと思っています。
伊藤: 無菌状態をよしとせずに、菌がある状態で力強く生きていこうという感じですかね。
須藤: 完璧なマネジメントなんて存在しませんからね。あまり仕組みに頼りたくないというのはあります。
中庸を取らず、偏らせる

須藤: 考えることの中毒かというくらい、とにかくずっと考えています。意識してやっていることは中庸を取らない、偏らせることですね。
伊藤: 偏らせる?
須藤: はい、自分の思考を円にしないことをすごく大事にしています。円は中心点が1つ。だから何かの正解に近づくようなプロセスが働いてしまう。僕が意識しているのは楕円です。楕円は中心が必ず2つある。それだと答えが1つじゃなくていい。すると、こういうこともあるし、こういうこともあるよねと説明できることがすごく増える。それってどっちなんですか。いやいや、どっちがあってもいい、という考え方でいないといけないと思っています。要はきれいに着地させすぎないということですね。
伊藤: それは2軸を持つということですか。
須藤: そうです。2軸を持って、今日はこっち、明日はこっちかもしれないというふうに考えています。
伊藤: 2軸あって、こっちとこっちのバランスを取るというのではなく?
須藤: バランスは取りません。先ほどの理不尽に近いのですが、世の中ってそんなにちゃんとしていない。むしろちゃんとしてないことに、ちゃんと対応しようとしすぎているような気がします。そんなに真面目に考えちゃったら疲れちゃうじゃないですか。不完全な人間が、不完全なシステムの下に、不完全なビジネスをしているのだから、きれいな円で考えると対応できることが少ない。だけど2軸にすると、意外といろいろなことが楽ちんに考えられると思ったんですよね。
伊藤: 中庸に走らないということですね。だけど、どちらかの極に行くわけでもない?
須藤: 例えば、スポーツ競技だと上半身、下半身の両方を鍛えないと伸びないですよね。それに近い感覚です。
毎日普通に仕事が始まり、終わる会社はつまらない
伊藤: Kaizen Platformを今後どんなふうにしていきたいですか。
須藤: ある程度ドタバタしていたほうがいいなと常に思っています。普通に仕事が始まって、普通に仕事が終わる会社であってほしくないという、経営者としては駄目なことをまず思っています。なぜかは分からないけど、ざわざわしているとかドタバタしているというのが僕は好きなので、ずっとそうあってほしい。今はたぶん全員がドタバタしているので、もう少し落ち着いてもいいかなとは思いますが、会社がでかくなろうが何をしようがドタバタしていたい。
伊藤: 自分自身はどうありたいですか。
須藤: 僕は社長じゃなくていいと思っています。理想は、社長でなくてもこの会社で仕事をしたいと思える会社ですから。だから自分の上司を採用したいし、「誰の下に入ってもいい仕事をしますよ」と言える自分でありたいなと思ってやっています。
伊藤: 10年後、こんな姿でいたいというのはありますか。
須藤: 10年後ですか。仕事をしていたいです。現場でというか、一線で。何か上がっちゃった人みたいになるのは嫌なんですよね。やっぱり仕事をしていたい。みんなから煙たがられようが、みんなと仕事がしていたい。誰も僕に何も言わなくなるとか、誰かがお伺いに来て「これはこうしておきますね」みたいなのは絶対に嫌なんですよね。根がワーカホリックなんでしょうね。
インタビュー後記
スドケンさんは、本当に不思議な魅力をお持ちの方です。
最初にお会いした3年前は、まだ起業したばかりでサービスを立ち上げておられず、他の会社にオフィスを間借りされていまして。「これからこんなサービスを作ろうとしてるんですよね~」と、ひょうひょうと僕にプランを語ってくれました。バリバリアピールされる感じではなく、全く肩に力が入っていないんです。リクルートで名をなした方とは聞いていたのですが、その自然体さに驚いた記憶があります。
今回、スドケンさんから「ぜひオフィスに来ていただいて社員の前でやりましょうよ」と言われ、Kaizen Platformさんのオフィスにお邪魔しました。社員の皆さんの前で話されるスドケンさんが、これがまた自然体で。社員の方から時々突っ込まれながら、楽しそうに、ひょうひょうと自分の思いを語られる雰囲気は、以前にお邪魔したときと全く同じだな、と思いました。
醸し出す雰囲気は自然体ですが、その思考は、どちらかといえば複雑系。といっても、「わけがわからない」ということでは全くなく、すべての事象を「スドケン流」に解釈しなおしている感じです。聞いてみると、記事中にも出てきますが、中毒のように徹底的に考えられるとのこと。詳しく色々お伺いしてみると、ご自身の行動や思考を常に客観的に捉える「メタ認知」に極めて優れた方だなぁ、という思いを強くしました。
全編、楽しんでいただければ、と思うのですが、特に「自分の思考を円にしない、楕円にする」という部分。ひとつの正解に至るのではなく、どちらかに偏らせるわけではなく、一方で、バランスもとらない。だから楕円、という考え方は非常に刺激的でした。これはぜひ、多くの方に(その通り考えるかはさておき)参考にしていただきたいな、と思いました。
聞かれていた社員の方々より、明らかに、聞き手の僕が楽しませていただいた、本当に楽しい対談でした。
Kaizen Platformさんの今後ますますの成長を、心から楽しみにしております。
次回は、「One Panasonic」を立ち上げた濱松誠さんにインタビューします。
https://globis.jp/article/4476