映画を通じて人や組織のマネジメントを紹介する本連載「シネマで学ぶ組織論」の第5回は、「逃亡者」。威圧的で強引だけれども部下がついてくる保安官ジェラードの姿から「権威」について考えます。
上司に従うのはなぜ?
こんにちは。林恭子です。皆さん、いかがお過ごしですか。
さて、唐突ですが、皆さんには上司はいますか?
トップの経営者でない限りは、きっとほとんどの方に、少なくとも1人はいらっしゃるでしょうね。では、皆さんは上司からの命令に従っていますか。これも、ほとんどの方はYesと答えるかもしれません。でも、なぜ皆さんは上司の命令に従うのでしょう。
そんなこと、真面目に考えたこと、きっと少ないですよね。でも、改めて考えてみると、一体なぜか。上司が偉いから?怖いから?権威があるから?今日は、そんな素朴な疑問について、考えてみたいと思います。
今日ご紹介する映画「逃亡者」は、1993年公開の作品。60年代にアメリカで放映された人気テレビドラマの映画化で、無実の罪を着せられ逃亡する医師キンブルをハリソン・フォードが、彼を追う連邦保安官補ジェラードをトミー・リー・ジョーンズが演じています。
その年のアカデミー賞で、トミー・リー・ジョーンズが助演男優賞を受賞したので、記憶にある方もいるかも知れませんね。
威圧的で強引な上司ジェラード
シカゴの名門病院の優秀な医師キンブルは、最愛の妻を何者かに殺され、かつ妻殺しの濡れ衣を着せられ、有罪の判決を受けてしまいます。苦悩するキンブルを乗せた車は刑務所へと向かいますが、途中、移送車の中で他の受刑者達が暴れ、車は道路から転落。そこへ列車が突っ込み、命からがら難を逃れたキンブルは、意図せず、囚われの身から放たれるのです。
彼の頭にあるのは、一体なぜ、妻があのような悲劇に見舞われたのか、その真相を突き止めることだけ。怪我、飢え、そしていつまた捕らえられるか分からない恐怖と戦いながらも、一人、真犯人を追及する。キンブルの「逃亡者生活」がこうして始まるのです。
同じ夜。一人の男が、移送車と列車の衝突現場に降り立ちます。彼の名は、サム・ジェラード。逃亡者を探す任務を負った連邦保安官です。そして、彼の後ろにはぴったりと4人の部下が従っています。現場に近づきながら、早々に1人の部下に、「おい、周囲の状況、調べて来い」と指令を出すジェラード。そして、現場に到着するや、移送官の嘘を暴き、マスコミや、調べの甘い地元の警察をいなし、大声で言います。
「あそことここに検問所を置け。逃亡者が隠れそうなガソリンスタンド、家、倉庫、鳥小屋、犬小屋に至るまで、徹底的に探せ!そしてキンブルを捕まえろ!」
有無をいわせぬ威圧感に、4人の部下はもちろん、他の関係者もクモの子を散らしたように動き出します。
その後も、ジェラードは矢のように命令を出し続けます。「ビッグス、これを調べろ!」「ニューマン、あっちをあたれ!」「コズモ、分析だ!」「プール、あれはどうなってる?」。傍にいる部下は、メモを取り続け、ジェラードが話し終わるや否や、駆け出していきます。
時には、「おい、盗聴だ。手配しろ」「えっ、それは無理ですよ」「判事に交渉しろ。やれ!」「何で俺ばっかり……。たまには俺の話しも聞いてくださいよ!」と、部下も反論しますが、けんもほろろ、取り付く島もありません。逃亡者追撃中で声を出せない場面でも、ジェラードは指の動きと目線だけで、次々に指令を出していきます。
キンブルを追い詰めながらも決死のダイブで逃げられた河のダムでは、「あの野郎。探せ、今すぐ水を止めろ!なんでできない!」「今やっているところです!」「なんとしても見つけ出せ!」とダミ声で叫びまくり、現地の保安官が「きっと死んでますよ、無駄ですよ。今頃魚のエサになっていますよ」と言えば、「だったら食ったその魚を探せ!」と、頑固親父のような応酬……。
それでも、部下達は、「サム、用意できました」「サム、こんなことがわかりました」「サム、情報がとれましたよ」と、生き生きと働き続けています。
これは一体、なぜなのでしょうか?
「もう、ちょっと、いい加減にしてよ、あの上司。高圧的だし、強引。いやだなあ」と思いたくもなる気もしますが、部下達にそんな様子は見られません。
ジェラードが上司で権威があるから、皆、当然のこととして従っているのでしょうか。権威ある上司の言うことを聞かないと罰を与えられるから、黙って言うことを聞いているのでしょうか。
そもそも、権威とは、何なのでしょうか?
権威とは何か
ここでちょっと、近代組織論の古典とも言うべき『経営者の役割』(ダイヤモンド社)の著者、チェスター・バーナードに、力を貸してもらいましょう。
『経営者の役割』は、1938年に、当時米国のニュージャージー・ベル電話会社の社長だったバーナードが書いた本です。いわゆる本業の学者ではなく、ビジネスの前線で経営者として活躍していたバーナードの著作が、その後何十年も経営学(経営組織論、経営管理論)の古典として読み継がれているというところが、何とも味わい深いですね。
要約すると、彼の主意は、「組織とは何かというと、2人以上の人々の、意識的に調整された活動や諸力のシステムのこと。そして、組織を成立させているのは、コミュニケーション、貢献意欲、共通の目的の3要素」ということになります。
もっとまるめて言うならば、複数の人が力を合わせて継続的に協働していくためには、「人と人との触れ合いの中で、それぞれの心に何が生じているか」に注目することが大事ということになります。
バーナードは、権威については、こう定義しています。
「権威とは、組織における、命令の性質のこと。メンバーが、その命令を組織において自分のすべきこと・せざるべきこと、と決定し、受容するもの」——ここまで聞くと、分かったような、分からないような。面白いのは、ここからです。
「もし、命令がメンバーに受け入れられるなら、命令を出した人の権威が確認されたことになる。命令への不服従は、彼に対する命令の権威を否定することになる。ゆえに、ひとつの命令が権威を持つかどうかの意思決定は、メンバーの側にあり、『権威者』すなわち発令者の側にあるのではない」
どうでしょう。これ、結構、コペルニクス的発想ではないでしょうか。上司の命令に権威があるのかどうか、つまり、上司が出した命令が聞いてもらえるかどうかという決定権は、実は部下の側に委ねられている、というのです。
こう聞くと、「いや、でも軍隊のような絶対的な命令系統のある組織では、そんなことはないのでは」と反論したくなりますよね。しかし、バーナードは更に元軍隊少将の言を引用し、たとえ軍隊が戦闘の極限状況にあっても、権威はやはり個人の受容ないし同意に基づいているのだ、と述べているのです。
たとえば、独裁的な専制国家があったとしても、その統治者が民意に反した運営を続けていれば、民衆はいずれ命令に従うことを止め、最終的には革命を起こし国家転覆に繋がることだってあります。嫌々上司の言うことを聞いていた部下たちも、「もう我慢できない」となれば、転職したり、異動願いを出したり、さらに上の上司に直訴することもあるでしょう。
上の立場になる人間は、自分が命令を聞いてほしい相手に対し、その「権威」を受容してもらえるように働きかけなければ駄目だということなのです。
権威受容のための条件とは
さて、権威の成立が、実は命令の受け手側に委ねられているということは分かりました。では、部下に、権威を認めてもらい、命令を受容してもらうためには、具体的にどんなことが必要なのでしょう。バーナードは、4つの条件を挙げています。
権威の受容のためには、受け手(部下)が
- 命令を理解でき、また実際に理解すること
- 意思決定するにあたり、命令が組織目的と矛盾しないと信ずること
- 意思決定するにあたり、命令が自己の個人的利害全体と両立しうると信ずること
- 精神的にも肉体的にも命令に従いうること
1は、上司の命令の伝え方の工夫により、かなり克服できるかも知れませんね。逆に4は、部下その人のコンディションによるので、上司としては如何ともし難いかもしれません。
問題は、2と3です。
文を読んでいて、何か気付いたことはありませんか。そう、文末が「信ずること」となっているところです。つまり、問題は、命令が組織目的や自己の個人的利害と整合するかどうかという「事実」ではなく、「そうだと信じられるか」「信用できるのか」というところなのです。
私達も、自分の経験を振り返ると、ふと思い当たることがあるのではないでしょうか。たとえば、最初上司に言われた命令がピンと来ず、「本当にこれをやっていいんだろうか」と思う。でも間もなく、「いや、信頼するあの人の言うことだから、今私が気付いていないだけで、きっと深い意味があるはずだ。よし、とにかくやってみよう」と、心が落ち着いてくる……。
こういうこと、ありますよね。
結局は、普段から周囲の人にどれだけ信頼されているか、「あの人の言うことだから乗ってみよう」と思ってもらえるかが、「権威」を受容してもらえるかを決める、ということなのでしょう。
さて、連邦保安官ジェラードはというと。キンブルと共に転落した移送車から逃走した受刑者を追い詰めた彼は、逆に自らの部下を人質に捕らえられてしまいます。「自分を逃がせ」と叫びながら部下を羽交い絞めにし、銃をつきつける受刑者。その瞬間、ジェラードの撃った銃弾が犯人を仕留めます。部下の肩越し、ぎりぎりの距離で。
命拾いをしながらも、ショックを受け、うつむく部下。「まさか撃つなんて。犯人と取引すべきだった。少しでも弾が外れていたら、僕は死んでいたのに」。そんな部下を静かに見守りながら、ジェラードは言います。「(爆音で)耳は大丈夫か?……俺はな、犯人と取引はしないんだよ。……いいな?」そして、黙ったままコートを部下の肩にかける。その時、言葉には出さないけれど、部下の表情にはこんな思いが浮かんでいるように見えました。
「このボス、強引だけど、何だか納得してしまう。この人はきっと、確信があってやっている。そして、僕が死んでいいなんて、これっぽっちも思っていない。もし何かあったら責められるのは本人だとわかっているんだ……。仕方ない、やっぱり僕はこの人を信頼してついて行こう」

2種類の権威
前述のバーナードは、権威を二つの種類に分けています。
一つ目は、職位の権威です。
「上位の職位から送られる命令が、その職位にふさわしい優れた視野と展望とにうまく一致しているならば、人々はこれらの命令に権威を認める」。また、「この権威はかなりの程度までその職位にある人の個人的能力とは別のものである」とされています。
そしてもう一つは、リーダーシップの権威です。
「明らかに、人によってはすぐれた能力をもっていることがあり、彼らの知識と理解力とは職位とは無関係に尊敬をかちうる。ただこれだけの理由で、人は組織において彼らの言葉に権威を認める。これがリーダーシップの権威である」とされています。
この職位の権威とリーダーシップの権威を一人の人が持つ場合、そこには大きな相乗効果が期待できます。たとえば、命令に従うというその行為自体が、部下にとって一つの心惹かれる要因となるのです。
シカゴに戻ったジェラードは、部下たちと一緒に、キンブルからかかってきた電話の音声を聞きます。集中して音を分析するジェラード。すると、声の後ろに、かすかに聞こえる何かの物音が。
「……これは、電車だ。……駅のアナウンスだ!あの野郎、このすぐ側まで戻って来たんだ。よし、皆、大至急追うぞ!」。鋭い推理で的確に逃亡者の居場所を特定するジェラードに、部下は冗談めかして、でも神妙な顔でこう言うのです。
「ボス、生まれ変わったらあんたになりたい」
「え、ハンサムになりたいって?」
勇んで捜査に出かける部下の顔には、「やれやれ、本当にあんたって人は……」と言いたげな、嬉しそうな笑顔が浮かんでいました。
信頼感が鍵となる
さあ、逃亡者と追跡者の攻防は、その後どうなったのでしょう。
キンブルを追い続けるうち、ジェラードの胸にはある想いが去来するようになっていきます。追われている立場なのに、たまたま居合わせた病院の急患を助けてみたり、逆探知を利用してわざと警官を妻殺しの真犯人と思しき人物の家におびきよせたりするキンブル。何より、あと一歩まで追い詰めたあのダムで、まっすぐ目を見て「私は妻を殺していない!」と叫んだ、あの時の表情。追跡が進むうち、想いは確信へと変わっていきます。キンブルは犯人ではない。そして、キンブルに対する不思議な感情も湧き始めていくのです。
ある夜、とうとうキンブルは真犯人を突き止めます。黒幕へ詰め寄るキンブル。そしてその2人を追うジェラード。高層ホテルでの息詰まる追撃で、キンブルを安全に確保したいジェラードはこう叫びます。「キンブル、出てくるんだ、君が無実なのは知っている!」。その瞬間、ジェラードを襲おうとした黒幕。しかし、その男はキンブルに倒されます。こうして、逃亡者キンブルと追跡者ジェラードの熱くて長い闘いは終結したのです。
未だ容疑者という立場であるキンブルは、手錠をかけられ、車へと誘導されます。でも、車に乗り込むとジェラードは隣に座り、すぐにポケットから何かを出します。鍵です。手錠をはずしながら、「はい、先生」と手をケアするものを渡すジェラードに、キンブルはこう言います。「思ったより優しいんだな」。
「みんなには内緒だぞ」。茶目っ気たっぷりに微笑むジェラード。
こんな、人間臭くて、仕事が出来て、憎めない、愛すべきボスの権威なら、受容してあげたくなりますよね。皆さんの周りには、権威を受容したくなる上司、いらっしゃいますか。もしかしたら、皆さん自身が、そんな上司なのかもしれませんね。
結局、国家、軍隊、企業、どんな組織であろうとも、上司やリーダーの指示に従うかどうかは、組織に属するメンバー一人ひとりの、その人に対する信頼、信任の情にかかっているということですね。人間は論理的に考えることも、もちろんできますが、「この人が上司としてのポジションに足る能力をもっていると、信じられるか」「尊敬や信頼に値する人物だと、信じられるか」という感情も、その人の行動を司るもうひとつの大きな要因です。
逆に、人の上に立つ、という機会を得た者は、その立場やパワーに安住・耽溺していてはならないということです。得られたと思ったそのパワーは、ある意味幻想でしかなく、立場に相応しい働きと自己を律する姿勢がなければいずれ霧のように消えてしまう。
だから、権威を持つことを許された者こそ、自分に厳しくなければならないということでしょう。
次回は、今も世界中で信奉者を持つチェ・ゲバラの青春時代を追った作品「モーターサイクル・ダイアリーズ」を題材に、キャリアを考えます。







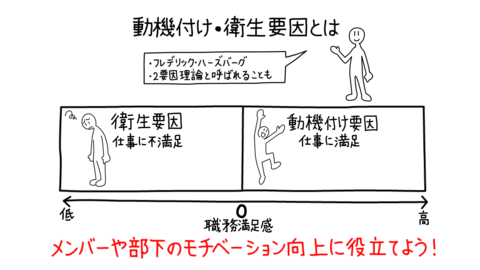



































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
