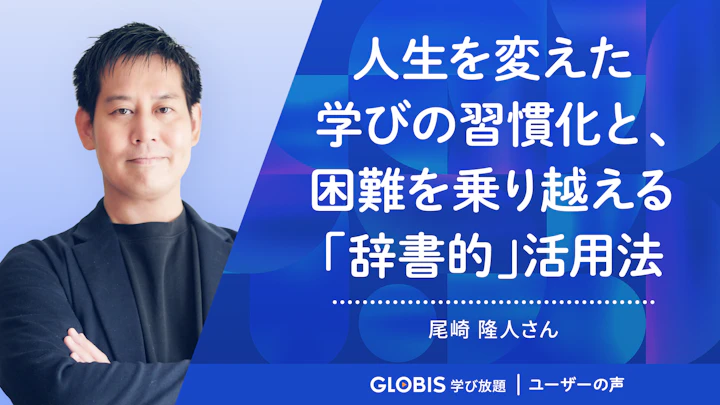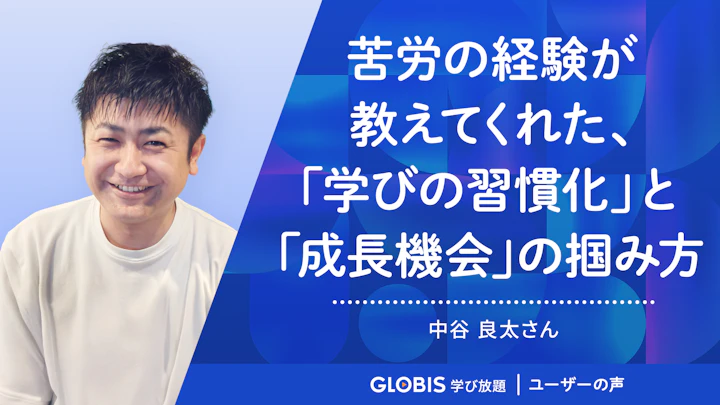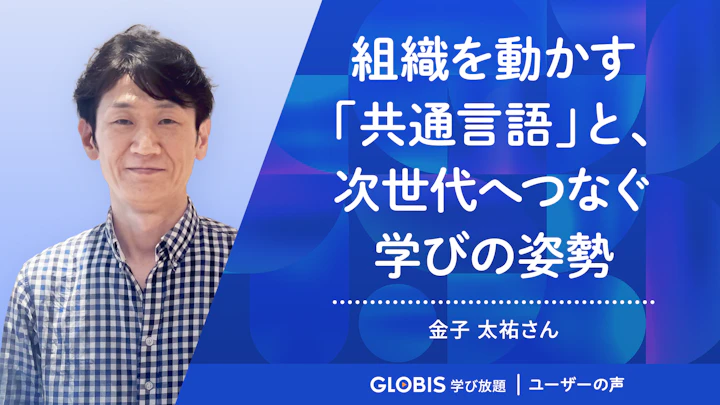市場が消える?!

「スコッチ(R)メンディングテープ」をご存じだろうか。粘着テープの表面につや消し加工が施され、貼り跡が目立たない。コピーをとってもほとんど影が映らず、テープの表面に文字も書けるという上質なテープのブランドである。
だが、「知っている」という人は圧倒的に40代以上の人が多いはずだ。ナゼなら、パソコンの普及と共に「切り貼り」の文化がなくなり、オフィスでの需要が大きく縮小したからである。バブル崩壊以降の不景気も追い打ちをかけている。単に貼るだけなら安価なテープで事足りる。ユーザーの認知は低下し、需要は細る。市場消失の危機が目の前にあったと言っても過言ではないだろう。
そこで同製品の再活性化のため、スリーエムが打ち出したのが、デザイナー文具への展開だった。このターゲットをどこに置くか。
「昨今、自分で使う道具を(企業や学校から)与えられたモノではなく、自ら買い揃えるという“こだわり”を持った人が増えているのです」。同社の石川由佳・ステーショナリー製品マーケティング部部長はユーザーの変化を指摘する。
市場縮小の中、ユーザーの変化は商機となる。ここで、「企業・学校などの中でこだわりを持った“組織内個人”」、「(将来にわたるユーザー育成を目的として広く)若年層」という2つの戦略ターゲットが設定された。そして、戦略実行の第1弾として10代女性をメインとした商品企画が行われた。
スリーエムがドーナツを売る?
商品はまず、2008年に台湾でデザインされた。テープを包み込む親しみやすいリング型でドーナツを模した形状のテープテープディスペンサーである。同国で爆発的な人気となっていたものを持ち込み、日本のマーケティングチームで、「スコッチ(R)メンディングテープドーナツ」(冒頭の写真左)という名称を決め、よりドーナツらしい色やパッケージにブラッシュアップして08年12月に上市したところ、たちまち店頭で在庫切れを起こす人気商品となった。
そこでさらに、2010年8月には「スコッチ(R)メンディングテープリングドーナツ」」(同写真右)として新しいシェイプのシリーズを展開した。こちらの商品は、「テープをはめる部分に溝を付け、住友スリーエム製の詰め替えテープしか使えないようにした。第1世代で95%だった詰め替え用での同社テープの利用を100%に引き上げる」(2010年10月1日付日経産業新聞「デザインここで勝負住友スリーエム」)
ドーナツといえば、“ミスド”(ミスタードーナツ)である。同店で大規模なコラボレーションの販促が行われた。店頭での陳列に加えて、景品としてサンプリングを行ったのである。また、「ドーナツデコレーションコンテスト」をネットで開催したり、「東京ガールズコレクション」でサンプリングするなど、同社としては異例の販促活動も多数展開。これによって、戦略ターゲット内の認知・使用率をアップさせることに成功した。「ドーナツ型容器の登場で、10〜20代の女性の認知度は発売直後の8%から09年9月で35%に向上した」(2010年10月1日付日経産業新聞「デザインここで勝負住友スリーエム」)という。
ドーナツ型からの学びは「エモーショナルなコミュニケーション」の重要性だった。そこで第2弾の商品を展開すべく、フィリップ・レフュアー氏が住友スリーエム初のデザインマネージャーとして担当に就いた「感性に訴える。使う楽しみ。UserExperienceというものをカタチにしたかったんだ」と同氏は語る。
2つの製品が企画された。1つはハート型(下写真、左)のテープディスペンサー。もう1つはボックス型(同写真、真ん中、右)のテープディスペンサーだ。ハート型は普遍的なデザインであるが、より若い女性に持ち歩いてもらう意図を込めて作った。「楽しさ」を強調したのである。ボックス型は「感性に訴える」デザインである。ビジネスデスクに馴染むスクエアな静かなデザインであるが、ひとたび開けばその開き方、手応え、開閉音などがクセになる。そのデザインが認められ、2012年3月にドイツの「レッドドット・デザイン賞」を受賞した。

デザインの力をマーケティングの基本セオリーで売りにつなげる

前々回「製品特性分析でノンワイヤーブラとカラオケについて考えてみた」で紹介したフィリップ・コトラー氏のフレームワーク「製品特性3層モデル」で考えてみよう。
製品を購入して実現したい「中核価値」はテープディスペンサーの場合、「テープが切れる」ことである。逆に言えば、今回スリーエムがフォーカスした「デザイン」は、中核価値とは直接関係のない「あればウレシイ」=「付随機能」だ。
一般に、製品のPLC(ProductLifeCycle)が進めば進むほど、求められる価値は「付随機能」へと移行していく。その意味で一連のデザインされたテープカッターは製品戦略の王道を歩んだと言える。
特筆すべきは、今回のテープディスペンサーは付随機能としてのデザインが優れているだけではない点にあろう。従来のカタツムリ型と比べて、テープを包み込む形状であることから、テープ自体にホコリが付いたり汚れたりしない。また、キレイにテープが切れて、テープ本体に巻き付くような状態にならないという切れ味を実現している。つまり、「中核価値」を実現するための欠かせない要素である「実体価値」=「切れ味」「テープの保護」も向上させているのだ。
もちろん商品というのは、優れたもの(Product)を作っただけで売れるというものではない。マーケティングの定番フレームワークである「4P」で考えれば、他の3つのP、価格(Price)・販売チャネル(Place)・販売促進(Promotion)との整合も求められる。
価格は商品の特性からして、「手に取って使われてこそ」だ。いくら優れたデザインであるからといって、手を出しにくい高価なものであってはいけない。そのため、294円と設定された。市場に広く行き渡ることを意図した「ペネトレーションプライシング(市場浸透価格設定)」である。
販売チャネルは一般の文具店だけでなく、LOFTや東急ハンズといった「こだわりのターゲット」が集うチャネルをおさえることに注力した。
プロモーションは商品力を活かし、POPなどで目立たせるという店頭訴求を行っている。
前述の通り、商品を再活性化するためのコツの1つは「商品力の強化」である。商品の価値構造を明確にして現在のPLCで求められる要素を的確に提供し、さらに価値を高める要素を補完していくということが欠かせない。そして、もう1つは「商品力を補完する要素を適切に展開する」ことだ。つまり、商品力だけに頼るのではなくそれを高めるべく、4Pをターゲットが魅力的に感じるようにミックスすることだ。
再活性化が求められる商品は市場に多数存在する。「スコッチ(R)メンディングテープ」のテープディスペンサーの事例は、マーケティングの基本セオリーを忠実に踏襲することの意義について、改めて考えさせてくれる。





































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)