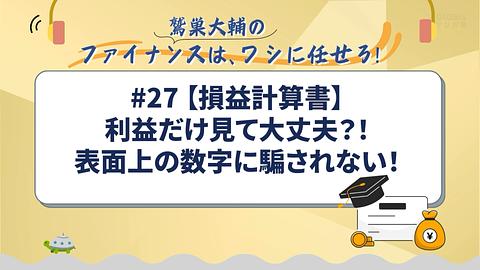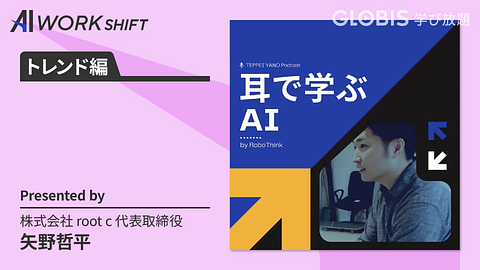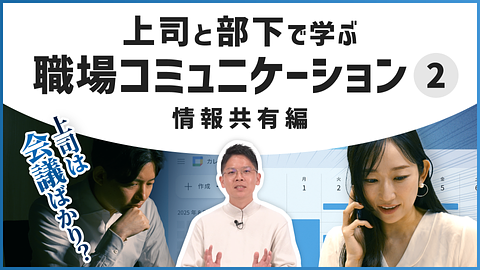社内金利制度とは
社内金利制度(Internal Interest)とは、各事業部が使用している資金の量に応じて金利負担を課すことで、より公正で正確な業績評価を行う管理会計の手法です。
従来の損益計算書だけでは見えなかった「資金の使用コスト」を明確にすることで、事業部の本当の収益力を測定できるようになります。この制度により、各事業部は資金をより効率的に活用し、会社全体の資本効率向上に貢献することが期待されます。
別名「社内資本金制度」とも呼ばれ、多くの企業が導入を検討している注目の評価システムです。
なぜ社内金利制度が重要なのか - 隠れたコストを見える化する必要性
現代のビジネス環境では、単純な売上や利益だけでは事業の真の価値を測ることが困難になっています。特に、資金を大量に使用する事業と少ない資金で運営できる事業を同じ基準で評価することは、公正性に欠けてしまいます。
①従来の評価方法の限界が明らかに
これまでの事業部評価では、売上高や営業利益といった損益計算書上の数字が重視されてきました。しかし、この方法では「どれだけの資金を使ってその利益を生み出したのか」という重要な視点が抜け落ちてしまいます。
例えば、A事業部が100億円の資産を使って10億円の利益を上げた場合と、B事業部が20億円の資産で8億円の利益を上げた場合を考えてみましょう。単純な利益額ではA事業部の方が優秀に見えますが、資金効率を考慮するとB事業部の方が優れているといえます。
②資本コストの概念を経営に取り入れる意義
社内金利制度の導入により、各事業部に「資本にはコストがかかる」という意識を植え付けることができます。これは株主や債権者から調達した資金には当然コストが発生するという、ファイナンスの基本原則を社内に浸透させる効果があります。
この意識変革により、事業部マネージャーは単純に売上を伸ばすだけでなく、資金をいかに効率的に使うかを常に考えるようになり、会社全体の資本効率向上につながります。
社内金利制度の詳しい解説 - 仕組みと運用のポイント
社内金利制度を効果的に運用するためには、適切な資金使用量の算定方法と金利設定が重要になります。制度設計には複数の選択肢があり、各企業の事業特性に応じて最適な方法を選択する必要があります。
①資金使用量の計算方法を理解する
社内金利制度における資金使用量は、一般的に以下の計算式で求められます:
資金使用量 = 総資産 - 借入金を除く流動負債
この計算式の背景には、事業部が実質的にコントロールできる資産の範囲を明確にするという考え方があります。借入金を除く流動負債(買掛金や未払金など)は、通常の営業活動に伴って自然に発生する無利息の資金調達源泉であるため、資金使用量から控除します。
具体例を示すと、ある事業部の総資産が50億円、買掛金や未払金などが15億円の場合、資金使用量は35億円となります。この35億円に対して社内金利を適用することになります。
②適切な金利設定の考え方
社内金利の設定方法には主に2つのアプローチがあります:
財務部の実効金利に合わせる方法は、自社の資金調達コストを基準とする考え方です。しかし、この方法では財務部の資金運用の巧拙が事業部の業績に直接影響してしまうため、事業部の真の実力を測定することが困難になります。
市中金利に合わせる方法は、客観的な市場金利を基準とする方法で、多くの企業で採用されています。この方法では、長期プライムレートやROE(株主資本利益率)の業界平均値などを参考に金利を設定します。
③簿価と時価の調整という重要な課題
資産の購入時期が古い場合、帳簿価額(簿価)と現在の市場価格(時価)の間に大きな差が生じることがあります。特に不動産や設備などの固定資産では、この差が事業部の評価に大きな影響を与える可能性があります。
理想的には時価ベースで資金使用量を算定することが望ましいですが、実務上の制約もあるため、重要な資産については定期的な時価評価を行い、必要に応じて調整を加えることが推奨されます。
社内金利制度を実務で活かす方法 - 導入から運用まで
社内金利制度の効果を最大化するためには、制度設計だけでなく、組織への浸透と継続的な改善が不可欠です。成功している企業の事例を参考に、実践的な活用方法を見ていきましょう。
①事業部評価システムとの連携で効果を最大化
社内金利制度を単独で運用するのではなく、既存の事業部評価システムと連携させることが重要です。例えば、ROA(総資産利益率)やROI(投資利益率)といった指標と組み合わせることで、より多面的な評価が可能になります。
具体的には、従来の営業利益に加えて「営業利益 - 社内金利負担額」という指標を導入し、これを「経済的利益」として事業部の真の収益力を測定します。この指標により、資金効率の良い事業部が正当に評価されるようになります。
また、事業部長の業績評価や報酬制度とも連動させることで、制度の実効性を高めることができます。単なる会計上の数字ではなく、実際のインセンティブと結び付けることが成功の鍵となります。
②継続的な制度改善とコミュニケーション
社内金利制度は一度導入すれば終わりではありません。市場環境の変化や事業構造の変化に応じて、金利水準や計算方法を見直す必要があります。
特に重要なのは、制度の目的と意義を組織全体に継続的に伝え続けることです。事業部のメンバーが制度を理解し、納得して活用できるよう、定期的な説明会や研修を実施することが推奨されます。
また、制度運用の過程で明らかになった課題や改善点については、積極的に制度に反映させることで、より実効性の高いシステムに進化させることができます。



























.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.png?fm=webp&fit=clip&w=720)