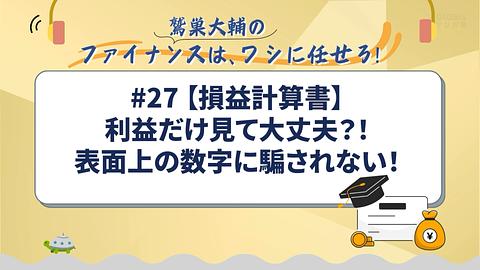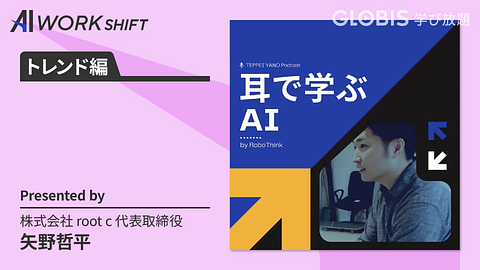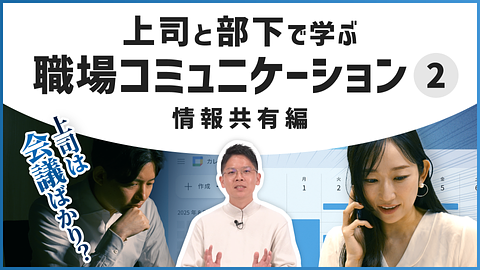本社共通費とは
本社共通費(コーポレートコスト)とは、全社の費用の中で、特定のグループや部門が使用したことが明確に特定できない費用のことです。
具体的には、本社社屋の修理費、社長をはじめとする本社役員の人件費、全社的な広告宣伝費、本社の総務や人事部門の運営費用などが該当します。これらの費用は、会社全体の運営に必要不可欠でありながら、どの事業部門がどの程度使用したかを正確に測ることが困難な性質を持っています。
一見すると単純な費用の分類に思えるかもしれませんが、実はこの本社共通費をどのように扱うかは、組織の業績評価制度や各部門のモチベーションに大きな影響を与える重要な経営判断なのです。
なぜ本社共通費の扱いが重要なのか - 組織の士気と公正性のバランス
企業が成長し、複数の事業部門を持つようになると、本社共通費の扱い方が経営上の重要な課題となります。その理由は、費用の配分方法が組織全体のパフォーマンスと各部門のやる気に直接的な影響を与えるからです。
①公正な業績評価の実現
各事業部門の業績を正しく評価するためには、その部門が実際にコントロールできる費用と、コントロールできない費用を適切に区別する必要があります。本社共通費を適切に処理しなければ、部門の真の収益性を把握することができず、間違った経営判断につながる可能性があります。
②組織全体の利益意識の向上
本社共通費の配賦方法によって、各事業部門が会社全体のコストを意識するかどうかが決まります。適切な配賦により、各部門が「会社全体の一員として利益を追求する」という意識を高めることができるのです。
本社共通費の詳しい解説 - 配賦するか、しないかの重要な選択
本社共通費の処理方法には、大きく分けて「配賦しない方法」と「配賦する方法」の2つのアプローチがあります。それぞれにメリットとデメリットがあり、企業の状況に応じて適切な選択をする必要があります。
①配賦しない方法のメリットとデメリット
配賦しない方法を採用する企業は、本社共通費を各事業部門の業績評価に含めず、全社レベルでのみ管理します。
この方法の最大のメリットは、業績評価の明確性です。各事業部門は自分たちが直接コントロールできる費用のみで評価されるため、評価結果に対する納得感が高くなります。また、恣意的な配賦基準によって業績が歪められる心配もありません。
しかし、この方法には重要なデメリットもあります。本社共通費が大きい企業では、各事業部門が会社全体のコストを意識しなくなり、利益追求に対するマインドが弱くなりがちです。「本社が勝手に使っている費用だから、自分たちには関係ない」という意識が生まれやすいのです。
②配賦する方法の効果と課題
一方、配賦する方法では、何らかの基準に基づいて本社共通費を各事業部門に割り振ります。
この方法の大きなメリットは、各事業部門の利益追求マインドの向上です。本社共通費も含めた上で利益を出さなければならないという意識が生まれ、より厳しい収益基準をクリアしようとする動機が高まります。また、各部門が最低限クリアすべきハードルが明確になるため、目標設定がしやすくなります。
ただし、配賦方法が不適切だと、かえって業績評価を混乱させる恐れがあります。特に、各部門の実際の使用量と関係のない基準で配賦すると、部門間の不公平感が生まれ、組織のモチベーション低下につながる可能性があります。
③具体的な配賦方法の種類
配賦する場合の具体的な方法としては、主に2つのアプローチがあります。
第一は、各部門が受けたサービスの程度に応じて配賦する方法です。例えば、購買部門の費用を各部門の発注件数に応じて配賦したり、人事部門の費用を各部門の従業員数に応じて配賦するといった方法があります。この方法は比較的公平性が高く、部門からの納得感も得やすいのが特徴です。
第二は、各事業部門の規模に応じて配賦する方法です。売上高、従業員数、人件費、総経費などを基準として、部門の大きさに比例して配賦します。この方法はシンプルで計算しやすい反面、実際のサービス利用量とは関係なく配賦されるため、部門からの理解を得るのが難しい場合があります。
本社共通費を実務で活かす方法 - 賢い配賦戦略で組織力を向上させる
本社共通費の適切な管理は、単なる会計処理を超えて、組織全体のパフォーマンス向上につながる重要な経営手法です。実務においては、以下のような場面で本社共通費の考え方を活用することができます。
①事業部制導入時の業績評価制度設計
多くの企業が成長段階で事業部制を導入しますが、その際に必ず直面するのが本社共通費の扱い方です。
効果的なアプローチは、段階的な配賦の実施です。まず、各事業部門との関連性が比較的明確な費用から配賦を始めます。例えば、特定の事業部門のみが利用するサービスの費用は、その部門に直接配賦します。次に、複数の部門が利用するサービスについては、利用実績に基づいて配賦します。
最後に、どうしても直接的な関連を見つけることができない費用については、売上高や従業員数などの客観的な基準で配賦します。このような段階的なアプローチにより、配賦の妥当性を高めながら、共通費の総額を最小化することができます。
②組織のモチベーション向上のための工夫
本社共通費の配賦を通じて、組織全体のコスト意識とモチベーションを向上させることも可能です
重要なのは、配賦基準の透明性と納得感です。各事業部門に対して、なぜその費用が配賦されるのか、どのような基準で配賦されるのかを明確に説明し、理解を得ることが大切です。また、配賦基準は定期的に見直し、事業環境の変化に応じて調整していく必要があります。
さらに、本社共通費の削減努力についても、各事業部門と情報を共有することが効果的です。本社部門が自らコスト削減に取り組む姿勢を示すことで、事業部門からの理解と協力を得やすくなります。
また、一部の企業では、本社共通費の一定割合を「社内サービス料」として位置づけ、本社部門が事業部門に対して提供するサービスの対価として明確化する取り組みも見られます。このような工夫により、本社と事業部門の関係をより建設的なものにすることができます。
本社共通費の適切な管理は、企業の成長とともにますます重要になる経営課題です。配賦方法の選択においては、組織の現状と目指す方向性を十分に考慮し、継続的に改善していく姿勢が求められます。



























.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.png?fm=webp&fit=clip&w=720)