サステナビリティが企業経営にとって避けては通れない課題となっています。しかし、大きなテーマであるが故に、日々の仕事と紐づけて捉えることが難しいテーマでもあります。本連載では、サステナビリティ経営を実践する推進者に焦点を当て、個人の志からSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の要諦を探ります。
第5回は、アサヒユウアス株式会社を取り上げます。アサヒグループホールディングスの新規事業会社である同社は、2022年設立とまだ立ち上がったばかりですが、廃棄プラカップを削減する「森のタンブラー」の開発、廃棄物を原料にしたクラフトビール製造やコーヒー副産物のアップサイクルなど、多岐に渡るプロジェクトを他企業や自治体との共創によって実現し、サステナビリティを推進しています。「森のタンブラー」の開発者でもある、アサヒユウアス株式会社(以下ユウアス) たのしさユニット ユニットリーダーの古原徹さんから、社外との接点を多く持ちながら、共創と協業でサステナビリティを推進する活動の様子を伺います(本コラム内の役職等は2024年4月のインタビュー当時のものです)。(聞き手・執筆:山臺尚子)
数々の共創によって価値をうむユウアス
古原徹さんは、2009年にアサヒビールに入社された後、アサヒ飲料に出向し、ペットボトルなどの容器包装開発を担当されてきました。2021年には、そのユニークさと味わいで話題となった「スーパードライ生ジョッキ缶」を開発。アサヒグループ内最多のグッドデザイン賞を3度受賞されています。
2022年にはユウアスの前代表取締役社長・高森志文さん(2024年当時アサヒグループ内のサステナビリティ推進本部部長も兼任)と共に新規事業会社のユウアスの創設にも関与しました。
そんなユウアスは、サステナビリティの楽しさを分かりやすく社内外に発信すること、そしてサステナビリティを目指す会社同士をつなぐ機能を持ち、グループ内外で存在感を増しています。現在では、街のパン屋さんから大企業、自治体や大学まで、約100社の団体、組織との共創プロジェクトを手掛けています。これまで共創した企業や自治体は約100社に上り、あるホテルチェーンでは140万本のペットボトル削減に貢献した例もあります。
.jpg?q=75&fm=webp)
中でも古原さんが開発された「森のタンブラー」は、パナソニック株式会社との共創によって誕生したエコタンブラーです。植物等有機資源を高濃度に活用できる技術を用い、これまで各企業、自治体で廃棄されていた素材をアップサイクルすることで、継続使用または販売が可能となっています。「使い捨てを無くしたい」「地域の未活用資源を活用したい」という想いから両社の共同開発がスタートし、ユウアスのフラッグシップ商品となっています。
ここからは古原さんに、こうした数々の共創のご経験から、共創と協業でサステナビリティを推進するためのポイントをお聞きします。
共創はどのようにつくられるのか?
――ユウアスでは、たくさんの団体、組織との共創プロジェクトを手掛けられています。社外の共創パートナーの方々とはどのように出会われるのでしょうか?
ありがたいことに最近では、講演やセミナーに呼んでいただける機会が多くなりました。そうしますと、1か月にいただく名刺は200枚くらいになります。また、土日や平日夜であっても、少しでも面白そうと思えば、イベントや企画にも頻繁に顔を出すようにしています。子どもも連れて行くこともあります。イベントに参加すると、すぐ10人くらいは知り合いになれます。半分趣味、半分仕事、みたいなものですね。とはいえ、自分でも、意識的に新しい仲間を広げるために頑張っている、というところもあります。
――たくさんの方との出会いが、どのように共創プロジェクトに繋がっていくのでしょうか?
新しく人と会う時は、常に「この人たちのために、何かいいことはできないだろうか」という気持ちでいます。例えば、とある企業と「こんなことがやってみたいな」というような、ふんわりとした雑談をしていたとします。そうしていると、私の中では「この企業と、この大学を結び付けて、こういうテーマの企画を組んだら、いけそうな気がする」というようなアイディアがぱっと頭に浮かんでくるのです。
そうしたアイディアがどんどんと膨らんでいく中で「じゃあ、一緒にやりましょう」と、新しいプロジェクトが決まり、始まることが多いです。そうすると、新しく出会ったその人も、その人に関わる別の人たちも、新しく自分たちのネットワークに加わります。そうやってプロジェクトが立ち上がり、仲間が増えてきたように思います。
――多くの人を引き付けるような共創のアイディアを発想する上で、心がけていることはありますか?
仕事に限らず、日常生活でも、困り事、課題は必ず発生しています。特に私は、自分自身の課題解決よりも、第三者の課題や仕事での課題を解決したい。何をやれば、その人にとって一番のメリットになるかを考えたい、という気持ちが常にベースにあります。
仕事上の課題を解決する場合、会社に勤めていれば、当然、自社のリソースやアセットで解決しようとするのが普通だと思います。ただ私には、社内か社外か、というこだわりがないことで、制約条件なく、手段を問わずに柔軟なアイディアを思いつくのではないでしょうか。
加えて、かなりたくさんの人たちと会っているので、「どこに誰がいて、どんなことを知っているか、何ができるか」という、引き出しも多いのだと思います。だから「この人の課題は、このアイディアやこういう人たちを上手く組み合わせたり、繋げたりすれば解決できる」という発想ができるのです。打ち合わせ中でも知り合いに電話をかけて、その場でどんどん新たな人たちを巻き込んで行くようなこともします。
――組織を超えてどんどんと人を巻き込んでいく過程では、ぶつかる壁も多いように思います。
通常、ラインの上司をすっ飛ばして、単独で仕事の話を進めるのはあり得ないことです。上司には部下の業務を把握していない、管理責任を果せていないような気持ちにさせてしまうと思います。ただ、「それでもいいや」と思えるようにならないと、社内外を意識しないような仕事の仕方はできないかもしれませんね。その点、ユウアスでの上司は高森だけですし、事後報告だけでいいのですごく楽です。
仕事への向き合い方を変えた、今につながる転換点
――他に古原さんが仕事をする上で意識していること、こだわりはありますか?
基本的に楽しくない仕事はやらないと決めています。だから、仕事は全てが楽しいです。特に、複数の会社が絡むプロジェクトで、皆で課題からソリューションを探し合う瞬間。お互いのアイディアを出しあいながら、それらを上手く組み合わせたり、繋げたりしている瞬間。「じゃあ、みんなでやろうね」と決める瞬間。スピーディーに進めて、いい成果が出た瞬間。そうした時間はとても楽しいし、自分でも得意なことをしているな、と思いながら進められています。
――「仕事は全てが楽しい」ということですが、入社当時からそうだったのでしょうか。
私は、容器や包装の仕事をしたくてアサヒビールに入社をしました。アサヒに入る人は、ビールや食品をやりたくて入社する人がほとんどなので、私はかなりの変わり者だったと思います。コンビニの棚に並ぶようなパッケージの仕事がしたかったのに、入社して数年は、思ったような仕事は全くといっていいほどできませんでした。
その代わり大事ではあるのですが、すごく地味な仕事をやり続けました。4~5年くらい。残業も多かったです。「お金がもらえているからそれでもいいや。会社から評価されようがされまいが、生きていける」。そんな気持ちで仕事をしていた時期でもあります。当時私はまだ独身で、大学時代からの友人も近くにたくさんいて、週末にサーフィンに行ったりしていました。週末には思いっきり遊んで全てをリセットできる。自分はこの休日のためだけに働く。今は修行期間を過ごしているのだ、と割り切ろうとしていました。
――転換点はありましたか?
入社して7年ほど経ったある時、当時の上司が「会社なんて自分が面白いと思う仕事するために使うものだから、自分で考えて、自分で作って、自分で売って、社会に喜ばれるような、そんな最高の仕事やろう」と飲み会の時に言い出したんですよね。
私は、その言葉をなぜだか、めちゃくちゃかっこいいな、と感じました。私は、素直というか、人から影響を受けやすいところもあって、自分もちょっと頑張ってみようかな、と思いました。ただ仕事を頑張る、というのではなく、自分がやりたい仕事ができるように頑張ってみよう、と思えるようになりました。
それからは、「上司に言われた仕事」としてやっていた仕事を、「自分がやりたい仕事にするためにはどうしたらいいか」という発想で考えるようになりました。すると仕事のスタンスが変わって、容器や包装開発部内に留まらず、マーケティング部に行って直接ディスカッションして、「こんなことやりましょう」と自分で提案して、ものづくりをするようになりました。
そのうち、マーケティング部と企画段階から一緒に仕事をするようになり、仕事を通じて出会う人も変わってきました。社外の人とも「売る・買う」という関係ではなく、一緒に仕事を作り上げるような関係になりました。社内でも、パッケージで何か新しいことをやりたくなったら、まず古原に相談してみよう、と声をかけ、相談してくれるようになりました。
この辺りから仕事がすごく楽しくなって、自分がやりたかったのはこれだ、これからはいろんな人と一緒にできる仕事をしていこう、と思うようになりました。
サステナビリティを仕事にしてこそ手に入れた、決してなくならない財産
――ソーシャルを仕事にするようになってご自身にどのような変化を感じますか?
一言で言うと「成長」でしょうか。サステナビリティの領域にいると、普通に会社で仕事をしているよりも1000倍くらいの成長実感が得られます。「ゴミ削減」のようなテーマに取り組むと、プラスチック関連の会社、廃棄物関連の会社などの方々が関わってくださる。新しい人と出会って、今まで知らなかったことを知り、できなかったことができるようになっていくことを実感します。知らないことを毎日勉強している実感があって、それは会社での成果や評価には代えがたい自己資産です。
会社での評価は会社がなくなってしまえばそれまでです。でも、こうした自己資産は決してなくならないのです。
様々な組織や団体と仕事をするようになって、ユウアスに「アサヒ」の冠がついている、ということが大きなアドバンテージであることを実感するようになりました。サステナビリティに向き合おうとする企業には伝統的な大企業も多い中、対外的には「アサヒ」の一部として見てもらえるところもあります。だからこそ、共創をする際にも社内で話を通しやすいのだと思います。「アサヒ」の冠を持っているけれど、ある意味、アサヒをアサヒとも思ってもないような私がスピーディーに動く。そういった連携が必要なのかもしれない、と思うようになりました。
――アサヒグループのお話が出てきましたが、ユウアスでやっていくこととの間での難しさはありますか?
ユウアスとしてやりたいことと、私がやりたいことは、ほぼ一致しています。ただ、アサヒグループから見たユウアスという観点では、個人と会社の考えの間の二律背反に悩むこともあります。
ユウアスは、アサヒビールやアサヒ飲料に対して、サステナビリティに関する新たなネットワークや示唆を与えたり、一緒にプロジェクトを企画したりして、売上が数千万、数千億規模になるような本業のサステナビリティ推進につながるきっかけを作っていくのが将来的な役割だと思っています。私のような働き方や動き方をやったことがない人も多いので、やっていることを理解してもらいたい、という気持ちもあります。
ただ、ユウアスをアサヒグループの新規事業として見た時、グループ内で売上規模の小さい会社に、自社の社員を出向させ続けたいと思うのか、と考えることはあります。私自身はアサヒビールで容器開発をした方がグループ全体の利益になる、という判断もあるかもしれない、とも思っています。
――古原さんにとって理想の働き方とはどのようなものなのでしょうか?
アサヒグループに所属しながら、他社の名刺も4~5枚持っていて、自分自身の成果にダイレクトに跳ね返ってくるような仕事を直接受けている、というのが理想です。自分視点かもしれませんが、そういう働き方を目指したいです。
サラリーマンでいると、会社のために自分がいる、という思考が強くなりますが、自分はそういうタイプではないと思っています。会社は好きです。だけど、会社のために自分がいる、という発想は全くありません。高森にもいつもそう言っていますし、高森は自分のそういう働き方を理解してくれているように思います。
サステナビリティやSDGsを意識するようになったきっかけと向き合い方
――古原さんは「ソーシャル・イントラプレナー」(注)のロールモデルとして取り上げられることも多いと思います。古原さんがサステナビリティやSDGsに関心を持つようになったきっかけは何だったのでしょうか?
私は、やりたい仕事をやり続けた上で、自分だけの唯一無二の武器を見つけたいと思っていました。いろんな人の話を聞いてみたり、勉強しながら探索をしたりしていたのですが、その中でサステナビリティやSDGsというテーマに出会いました。まだ誰も手をつけていなさそうな、サステナビリティやSDGsをキーワードに仕事を作ったら、他の人の100歩先を歩けるかな、と思ったのです。
周囲からは「古原はサステナビリティやSDGsの領域がめちゃくちゃ好き」と思われて、ボランティア的にやっているように見えているかもしれませんが、やってもメリットが見えないことはやりません。相手に「ギブ」をするにしても、「ギブ」するなりの理由を考えることから始めるようにしています。今日明日の短絡的な見返りを求めているわけではないですが、将来的に何らかの形で返ってくるかどうか、ということを考えています。
ですので、私は、自分自身がソーシャル・イントラプレナーのひとりとして取り上げてもらえることについては、とてもありがたいですが、少し違和感もあります。もちろん、サステナビリティやSDGsの仕事は好きですし、自分が仕事で関わっていくにつれどんどんソーシャル的な発想になっているところもあります。
でも、私は最初からソーシャルをやりたくてこの領域で仕事をするようになったわけではないのです。私自身の根っこにあるのは、「新しいことをやりたい」、「面白くて楽しいことをやりたい」です。新しくて、面白くて、楽しいことをやった結果として、誰かが喜んでくれたり、社会が今よりも少しだけでもいい方向になってくれたりすればいいな、とは思っています。
「世のため、人のため」というような言葉は、ビックワード過ぎて自分にはよく分かりません。自分が関わる仕事やプロジェクトが楽しくて、関わった人も楽しくて、みんなが楽しいと、仕事の後に飲む酒がうまい。アホみたいかもしれませんが、きっと、その方がサステナビリティの取り組みは長続きするように思います。
――古原さんが手がけるプロジェクトは、売上や利益にもこだわっていく、ということでしょうか?
売上や利益は、自分たちがやってきたことの社会的評価の表れです。だから、PLは良く見るようになったし、見るのも大好きです。メディアにユウアスが多く取り上げられているか、掲載されているか、ということも気にはしています。同時に、取り組んだことが継続的にお金を生み出すものであったかどうか、というところが、本質的に社会に対して良いことをやっているかどうか、の尺度になってくるのだと思っています。
趣味やプライベートであれば別ですが、利益度外視の仕事はやったことはありません。「プロジェクトに関わった皆さんにはこんなメリットが出せます。私もこういうメリットが得たいです。だから一緒にやりましょう」と打ち合わせでも言います。そうすると、お金の話は最初からちゃんとやらないとダメだと経験的に感じています。私も最初のうちはきちんとできていませんでした。「何かあったら一緒にやりましょうね」とふんわりとした話をしているうちは、結局、誰も何もしないし、何も動かないのです。
ソーシャル・イントラプレナーがリードするサステナビリティ推進
――企業がサステナビリティを推進していく上では、社内外を縦横無尽に動ける古原さんのようなソーシャル・イントラプレナーが機能することが大事だと思います。
自分自身で言うのもなんなのですが、「こいつにやらせたら、何かが起きるんじゃないか」と思えるような人材を、社内でしかるべき人がちゃんと見つけていく。そういう人たちにやりたいと思うことをやらせてみる、という動きが大事だと思います。
ただし、好きにやらせておけば、何でも誰でも上手くいく、ということでもありません。好きなこと・やりたいことがあって、「これがやれないなら、会社を辞めます」というくらいの人に任せていかないと無理だと思います。大企業の場合、社内で新たに何かを始めようとしても、管理職の全員が賛成しないと進まないことも多い。「そんな小さいことをやってどうなるの?」と言われることもあるでしょう。
そのような組織の中で、自分自身のやりたいことを何があってもやり抜く人は、ある意味、「人事評価や出世の道を捨てている」という言い方もできると思います。特に、本業ではないサステナビリティのような領域を頑張る、ということは、どれだけ頑張って成果を出したとしても、組織としての評価は最高点にはならないかもしれません。だけど、「それでもいい」と思えるような人、「自分の頑張ったことを会社から評価してもらわなくても構わない」と思えるような人でないと、「ソーシャル・イントラプレナー」として機能するのは難しいと思います。
――企業のサステナビリティ推進は、大義があっても解決するには時間がかかります。長期の時間の乗り越え方も課題のひとつだと思います。息切れせず継続するためのヒントはどこにあるのでしょうか。
確かにサステナビリティ関連の企画やイベントを開催するのは、準備も大変で、いつもどうしよう、と考えながらやっています。だから、長く続けていくには、自分自身の気持ちのコンディションをいつも前向きに保っておくことが大事だと思います。
例えば、外にできるだけ多く出てみて、一般の方々の行動がちょっとでも変わっていないかを探す機会に触れていけるといいのだと思います。飲食を伴うゴミゼロ化のイベントの会場で、ビールを飲みながら大いに酔っぱらっている人たちが、ちゃんとごみを捨ててくれている。今までとは違う行動を取っている。イベント全体ではゴミが大幅に減っている。
楽しい面白いイベントだけに終わらせない。プラスチックゴミの削減にもしっかりと貢献できている。小さくてもいいので、こういうつながりや変化を目の当たりにするような経験を積み重ねていくと、自分がやっていることの意義みたいなのは感じやすいと思います。皆がこうした変化に触れていけるようになると、サステナビリティ推進も、やってみよう、続けてみよう、という気持ちにもつながっていくのだと思います。
.jpg?q=75&fm=webp)
(次回に続く)
※注:ソーシャル・イントラプレナー:自身が所属する組織が持つ知名度、ブランド、社内リソース等を活かしながら、社外との協業を通じ社会課題解決に貢献する働き方、こうした働き方をしている人々


.jpg?fm=webp)

.jpg?fm=webp)




















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
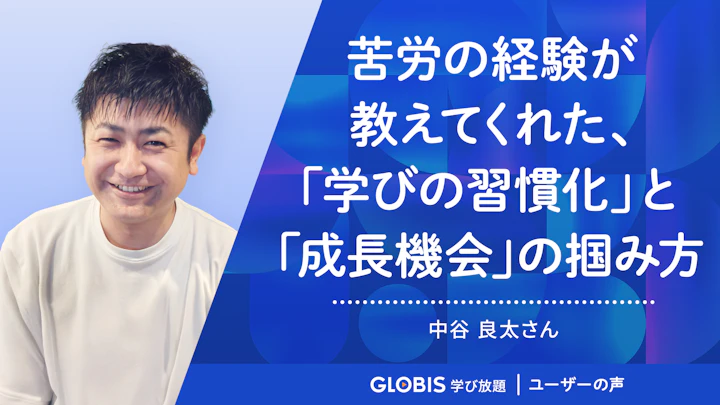
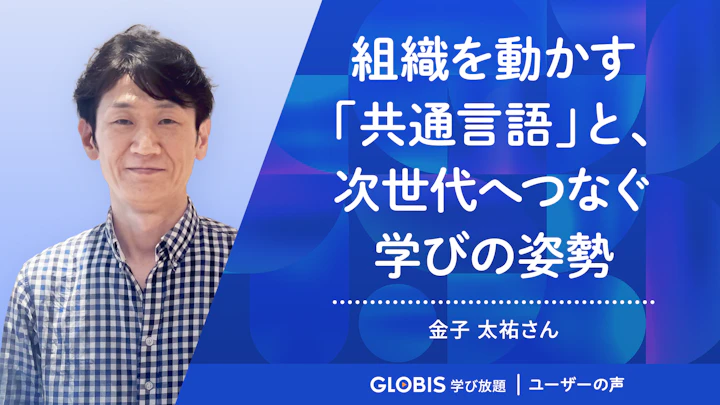
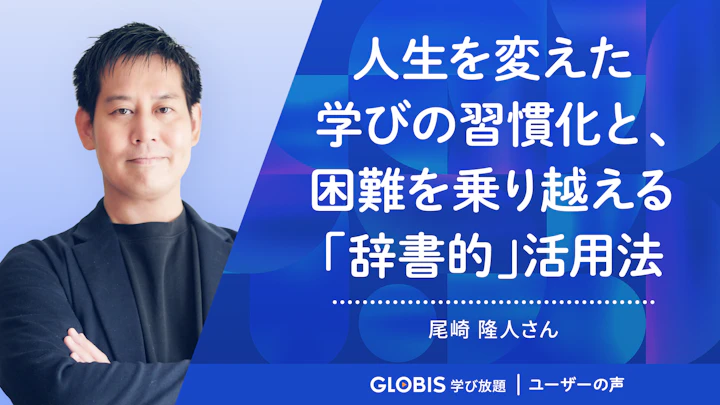

















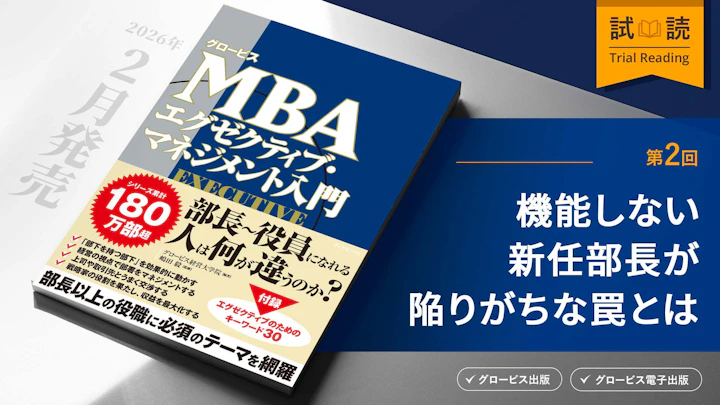




.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
