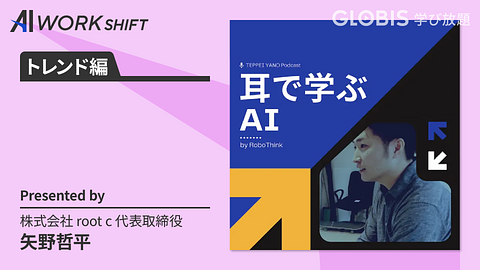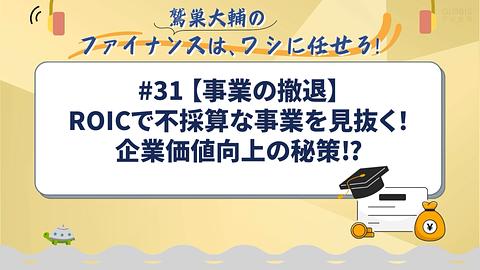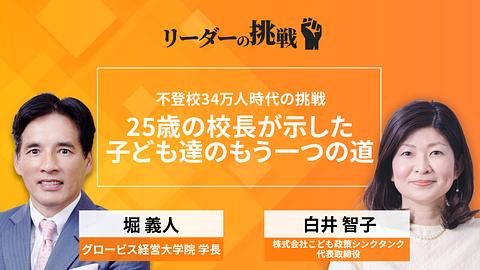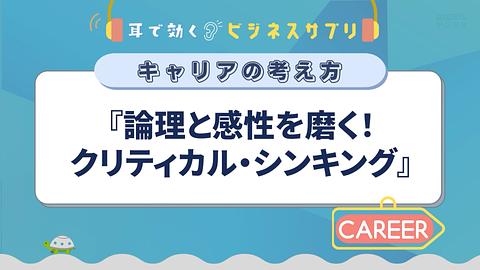共同化とは - 暗黙知を共有する組織の知恵
共同化(Socialization)とは、一人ひとりが持つ暗黙知を他の人と共有するプロセスのことです。
これは、一橋大学大学院の野中郁次郎名誉教授らが提唱したSECIモデルの最初の段階として位置づけられており、組織の知識創造において極めて重要な役割を果たします。
暗黙知とは、文書化されていない行動様式やその根底にある知恵、考え方の枠組み、視点などを指します。一方で、形式知は文書やマニュアル、方法論として可視化されたものです。共同化では、この見えない暗黙知を、共通の時間や空間を共有することで他者に伝えていくのです。
なぜ共同化が組織にとって欠かせないのか - 競争力の源泉を育てる仕組み
現代のビジネス環境では、知識こそが企業の競争優位の源泉となっています。しかし、組織の中には文書やデータには表れない貴重な知識が数多く存在しており、これらを活用できるかどうかが成功の鍵を握ります。
①組織の隠れた資産を可視化する力
多くの組織では、ベテラン社員が長年の経験で培った「コツ」や「勘」、新人が現場で身につけた「気づき」など、価値ある暗黙知が個人レベルに留まっています。共同化は、これらの見えない資産を組織全体で活用できる形にする重要な仕組みなのです。
②イノベーションを生み出す土壌を作る
共同化によって異なる背景を持つメンバーが暗黙知を共有することで、新しい発想や革新的なアイデアが生まれやすくなります。個人の枠を超えた知識の組み合わせから、予想もしなかった価値創造が起こる可能性が高まります。
共同化の詳しい解説 - 知識共有の具体的なメカニズム
共同化は単なる情報共有とは根本的に異なる、深いレベルでの知識伝達プロセスです。ここでは、そのメカニズムと実践方法について詳しく見ていきましょう。
①体験を通じた知識の伝達プロセス
共同化の最大の特徴は、五感を使った体験を通じて知識が伝わるという点にあります。
従来の徒弟制度では、弟子が親方の仕事ぶりを間近で観察し、同じ空間で作業を共にすることで、技術や心構えを身につけていきました。これは単に手順を覚えるのではなく、親方の判断基準や価値観、仕事への向き合い方まで含めて学ぶプロセスです。
現代の企業でも、OJT(On-the-Job Training)がこの共同化の典型例として機能しています。新入社員が先輩社員と一緒に営業先を回ったり、製造現場で作業を共にしたりすることで、マニュアルには書かれていない「生きた知識」を獲得していくのです。
②共感と没入による深い理解
共同化で重要なのは、表面的な観察ではなく、相手の立場に立って共感し、その場に没入することです。
思い込みや先入観を持ったまま現場を見ても、真の暗黙知を理解することはできません。一度自分の考えをリセットし、ありのままの現実を受け入れる姿勢が求められます。そして、現場と一体化し、共感できるレベルまで深く関わることで、初めて相手の暗黙知を自分のものにすることができるのです。
③小集団での密な相互作用
共同化は一般的に小さなグループでの活動を前提とします。これは、暗黙知の共有には密接な人間関係と頻繁なコミュニケーションが不可欠だからです。
大人数では一人ひとりとの深い関わりが困難になり、表面的な情報交換に留まってしまいがちです。少数のメンバーが継続的に時間と空間を共有することで、言葉では表現しきれない微妙なニュアンスや感覚的な部分まで伝わるようになります。
共同化を実務で活かす方法 - 実践的な取り組みのヒント
共同化の理論を理解したら、次は実際の職場でどのように活用するかが重要になります。ここでは、効果的な共同化を実現するための具体的なアプローチを紹介します。
①メンターシップ制度の充実
最も直接的な共同化の仕組みとして、体系的なメンターシップ制度の構築が挙げられます。
単に先輩と後輩をペアにするだけでなく、メンターが自分の暗黙知を意識的に伝える訓練を受けることが重要です。また、メンティー側も受動的に教わるのではなく、積極的に質問し、メンターの思考プロセスを理解しようとする姿勢が求められます。
定期的な振り返りの機会を設け、どのような暗黙知が共有されたかを言語化することで、共同化のプロセスをより効果的にできます。
②プロジェクトベースでの協働機会の創出
異なる部門や経験レベルのメンバーが共通のプロジェクトに取り組む機会を意図的に作ることも効果的です。
プロジェクトの過程で、各メンバーが持つ独自の視点やアプローチ方法が自然に共有されます。特に、問題解決の場面では、それぞれの暗黙知が表面化しやすくなります。プロジェクト終了後には、学んだことを整理し、他のチームにも共有する仕組みを作ることで、組織全体の知識レベルを向上させることができます。
③現場での実践を重視した研修設計
座学中心の研修ではなく、実際の業務現場での学習機会を増やすことが共同化には欠かせません。
例えば、営業研修では会議室での講義だけでなく、実際に顧客先への同行を重視します。製造業では、工場の現場でベテラン作業者と一緒に作業をする時間を確保します。こうした実践的な学習を通じて、教科書には載っていない「現場の知恵」を効果的に伝承できます。
また、異なる拠点や部門間での人材交流も、新たな暗黙知の獲得につながります。普段とは違う環境で仕事をすることで、これまで当たり前だと思っていたことを見直す機会にもなるのです。



























.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
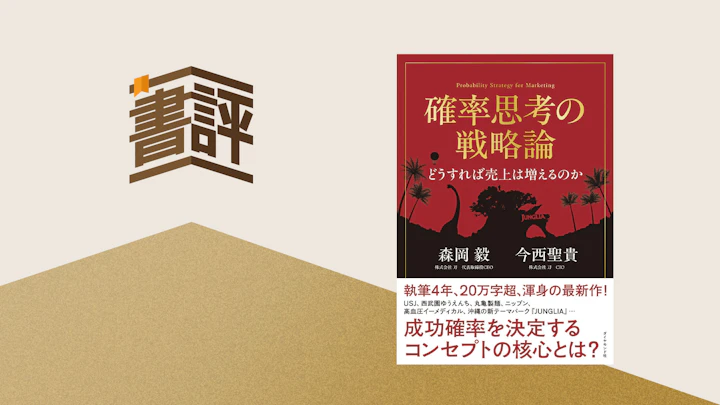
%20(2).png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.png?fm=webp&fit=clip&w=720)