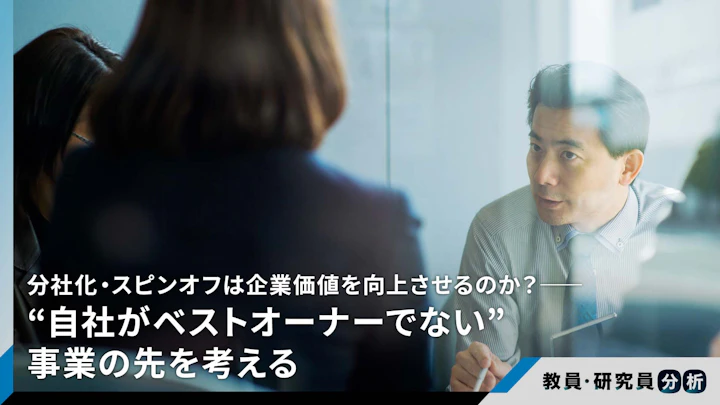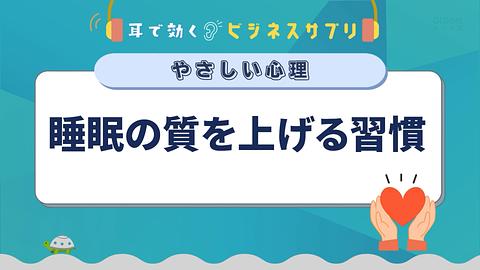ワークアウトとは
ワークアウト(Workout)とは、アメリカの大手総合電機メーカーGE(ゼネラル・エレクトリック)が開発した組織運営手法です。
1980年代末から全社規模で導入されたこの手法は、「境界のない企業」を実現するために生み出されました。
従来の日本企業のQCサークルが職場内の限られたグループで行われることが多いのに対し、ワークアウトは所属部署や役職にとらわれることなく、社内の様々な階層から数十名の従業員が集まって2~3日間にわたって開催される点が大きく異なります。
この手法の最大の特徴は、組織内外の「境界」を取り払い、全社員が一丸となって顧客満足という共通の目的に向かって力を合わせることができる環境を作り出すことにあります。
なぜワークアウトが重要なのか - 組織の活力を蘇らせる理由
現代の多くの企業が抱える課題の一つに、組織の硬直化があります。部署間の連携不足、過度な階層構造、形式的な手続きなど、これらの問題が企業の成長を妨げているケースは少なくありません。
ワークアウトが重要視される理由は、こうした組織の「境界」を取り払うことで、企業本来の力を引き出すことができるからです。
①組織の壁を壊す力がある
ワークアウトは、部署や役職の違いを超えて従業員が集まる仕組みです。
普段は接点の少ない異なる部署の人々が同じテーブルについて議論することで、新たな視点やアイデアが生まれやすくなります。
これにより、従来の「縦割り」的な発想から脱却し、会社全体の最適化を図ることが可能になります。
②現場の声を経営に活かせる
従来の企業運営では、現場の声が経営層に届きにくいという問題がありました。
ワークアウトでは、階層に関係なく様々な職位の従業員が参加するため、現場で実際に働く人々の生の声を直接聞くことができます。
これにより、机上の空論ではない、実践的で効果的な改善策を見つけ出すことが可能になります。
ワークアウトの詳しい解説 - 3つの段階で進む変革プロセス
ワークアウトは、段階的に進められる体系的なアプローチです。各段階には明確な目的があり、着実に組織改革を進めていくことができます。
①第一段階:官僚的な弊害を取り除く「タウンミーティング」
ワークアウトの出発点は、「タウンミーティング」と呼ばれる定期的な集まりです。
このミーティングには、各部署の様々な職位の従業員が参加し、まずは目に見える官僚体質の問題点を洗い出します。
具体的には、複数の承認が必要な手続き、不必要なペーパーワーク、過剰な報告書、意味のない慣例、単なる儀式といった、日々の業務を圧迫している要因を特定し、取り除いていきます。
最初のうちは、大勢の前で意見を述べることに抵抗を感じる従業員も多いですが、自分たちの提案が実際の行動に移されることを実感すると、積極的にアイデアを出すようになるといいます。
この段階では、比較的簡単に解決できる問題から取り組むことで、参加者の意欲を高め、変革への機運を醸成することが重要です。
②第二段階:業務プロセスの根本的な見直し
第二段階では、より深いレベルでの改善に取り組みます。
ここでは、仕事を複雑にしている無数のプロセスを詳しく検討し、本当に重要な問題だけを選び出します。
そして、より機敏に、より簡単に、より良い仕事ができる方法を発見することに集中します。
この段階では、単に表面的な問題を解決するのではなく、なぜそのプロセスが存在するのか、本当に必要なのかを根本から問い直します。
長年続いてきた慣習や手順であっても、現在の業務に適さないものは思い切って見直しを行います。
③第三段階:ベストプラクティスとの比較による水準向上
第三段階では、視野をさらに広げて改善の水準を高めていきます。
参加者は、自分たちが成し遂げた改善例をGE内部の他の部門や、世界の優良企業のベストプラクティスと比較します。
これにより、自分たちの改善がどの程度のレベルにあるのかを客観的に評価し、さらなる向上を目指します。
他社の成功事例から学び、自社の状況に合わせて応用することで、業界トップクラスの水準まで改善を進めることが可能になります。
この段階では、単に問題を解決するだけでなく、継続的な改善の文化を根付かせることが重要な目的となります。
ワークアウトを実務で活かす方法 - 現代企業への応用と成功のポイント
ワークアウトの考え方は、現代の日本企業においても十分に応用可能です。特にデジタル化が進む現代において、組織の柔軟性を高めることは競争力の源泉となります。
①部門横断プロジェクトでの活用方法
現代の企業では、新商品開発やDX推進など、部門を横断した取り組みが増えています。
こうしたプロジェクトにワークアウトの手法を応用することで、より効果的な成果を得ることができます。
例えば、営業、開発、製造、マーケティングなど異なる部門の担当者が集まって定期的にミーティングを開催し、それぞれの視点から課題を出し合い、解決策を検討します。
重要なのは、階層や部署の壁を取り払い、誰もが自由に発言できる環境を作ることです。
上司の顔色をうかがうのではなく、会社全体の最適化を目指して率直な意見交換を行うことが成功の鍵となります。
②継続的改善文化の構築ポイント
ワークアウトを成功させるためには、一時的なイベントで終わらせるのではなく、継続的な改善文化として根付かせることが重要です。
まず、経営層のコミットメントが不可欠です。従業員から出された提案を真摯に検討し、実行可能なものは速やかに実行に移すことで、参加者のモチベーションを維持できます。
また、改善の成果を定期的に共有し、成功事例を組織全体で学習することも大切です。
小さな改善であっても、それが積み重なることで大きな変化をもたらすことを組織全体で実感することで、継続的な改善への意欲を高めることができます。
さらに、失敗を恐れずにチャレンジする文化を醸成することも重要です。すべての提案が成功するわけではありませんが、失敗から学ぶことで、より良い解決策を見つけ出すことができます。



























%20(5).png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.png?fm=webp&fit=clip&w=720)