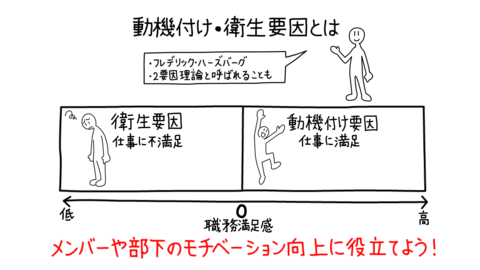■ピクサーの経営哲学
偉大なクリエイターを起用し、彼らに大きく賭ける。
ありったけの猶予と援助を提供し、監督が誰からも正直なフィードバックを得られる環境を提供する。
戦略の時代からマネジメントの時代へ
2000年代の最初の10年が終わった。振り返ってみると、これほど戦略というものに関して「大物」のコンセプトが出なかったディケイド(10年)は、経営学というものが体系化されるようになってきてから初めてかもしれない。「ブルーオーシャン」や「破壊的イノベーション」などのコンセプトなどは確かに出たが、かつてのPMSやPPM、あるいはポーターの一連の戦略フレームワークほどの汎用性や破壊力があるかと言えば疑問だ。最近のヒット曲ではないが、全般的に小粒なコンセプトが多かった印象は辞めない。
しかし、それは決して経営学者がサボっていたわけではない。単にフォーカスが変わってきたことを示すものと考えてよい。つまり、経営学者の関心が経営戦略そのものからは移ってきたということだ。では、その関心はどこに向かったのか。それはマネジメント、さらに言えば、マネジメントのイノベーションである。いかに生産性を高めるようなマネジメントを実現するかが、経営学者、そして経営者らの関心になってきたのである。
この点に関して言えば、ジム・コリンズやゲーリー・ハメルなどによる優れた仕事はあるものの、まだ決定的なフレームワークはまだ生まれておらず、発展途上といえよう。さまざまな経営学者が、帰納的アプローチ、演繹的アプローチの両面から決定打となるフレームワークを模索しているのが現状ではないだろうか。
ピクサーの歩み
そうした中で、1つのモルモット的な企業と考えられているのがピクサーだ。ピクサーは、よく知られているように、1986年に元アップル・コンピュータ社長であったスティーブ・ジョブズ(その後、アップルの社長に返り咲く)がジョージ・ルーカスの会社から1000万ドルでコンピュータ・アニメーションスタジオを買収し、独立会社としたのが企業としてのスタートである。
当初はコンピュータグラフィックス製作用の専用コンピュータなどを扱っていたが、顧客にディズニーがあったことから、徐々にCGの製作に軸足を移していく(結局、ディズニーは2006年にピクサーを買収する)。
ディズニーとの関係を深める中で最初のヒット作となったのが、95年に発表された『トイ・ストーリー』だ。同作は長編映画としては初のフルCGアニメーションによるもので、世界中で大ヒットとなった。監督のジョン・ラセターは、アカデミー特別業績賞も受賞している。
その後もピクサーの勢いはとどまることを知らず、最新作『カールじいさんの空飛ぶ家』に至るまで、1.5年に1本程度のペースで(大ヒットか中ヒットかの別こそあるが)ヒット作をコンスタントに生み出している。ディズニーという優れたパートナーに恵まれたとは言え、水物の映画ビジネスにおいて、毎回確実にヒット作を残すピクサーは、業界でも稀有な存在である。
ヒット作を生み出す鍵
なぜ、ピクサーはこのような稀有な成功を収め続けることができたのか。同社の前身も含めてピクサー創設時から実質的なトップを務めるエド・キャットマルは、著書『ピクサー流マネジメント術』(ランダムハウス講談社)で、その鍵は、ピクサー独特のマネジメントにあるとしている。そして、その基本理念を以下の四つとしており、これが社内に徹底しているからこそ、ピクサーの安定的な成功があるという。
1.真の才能を持った人間は非常にまれである
2.管理職の仕事はリスク回避ではなく、危機が発生したときに素早く回復させることである
3.どんなときにでも本音で話し合えなくてはならない
4.思い込みを常に見つめ直し、ピクサーの素晴らしい文化を壊しかねない欠点を探し続けなくてはならない
この中で、筆者が最も面白いと思ったのが3だ。1の人材の話や、4の企業文化の話は、ピクサーならずとも、さまざまな機会に語られてきた。2も、創造性を追及するからこそリスクが生まれることを考えれば妥当だ。それらと並んであえて3を挙げている点にピクサーのこだわりがあるように思われる。
冒頭に挙げた経営哲学の中でも、「監督が誰からも正直なフィードバックを得られる環境を提供する」とうたっていることから、ピクサーが、「本音」で「正直」なコミュニケーションを極めて重視しているのは間違いない。
ピクサーの試み
たとえば、ピクサーでは、「ラッシュ上映会」が毎日開かれており、あらゆる人々が参加し、自由に意見を言うことが強く奨励されている(ラッシュとは、映画の業界用語で、ネガから補正無しで起こされた制作途中のフィルムのこと)。これにより、さまざまな意見が交換され、インスピレーションが湧いてくる。また、他者の仕事を見ることで、競争心が掻き立てられ、よりクリエイティブになろうと考えるという。
また、ブレーン集団を招いて、正直なフィードバックを得るというプロセスも非常に重視されている。これにより、失敗作を世に出す前に、それを修正できるのだ。正直で本音のコミュニケーションがピクサーでは機能し、まさにクリエイティビティを刺激し、同時にリスク回避に寄与しているのである。
正直で本音のコミュニケーションが機能する前提
と書くと、非常に簡単なことのようだが、正直で本音のコミュニケーションはそれほど簡単なことではない。部下や上司に対して、言いにくいことをずばり指摘するのに苦労された経験は誰もが持っていることだろう。特に上司に対してはそうだ。いったん指摘する機会を逃すと、ますます指摘が難しくなり、結局は言えずじまいになってしまう、あるいは良くないタイミングになってしまうというのもありがちなパターンだ。
では、そうした壁を破るためには何が必要なのか。第一に必要なのは勇気だ。勇気のないところでは、どのような行動もできない。特に、対人コミュニケーションに関してやや奥ゆかしいタイプの多い日本人には、このポイントは重要かもしれない。
しかし、それ以上に重要なのは、相互の信頼である。逆に信頼さえあれば、必要以上に大きな勇気を奮うというストレスもなく、正直で本音のコミュニケーションができるはずだ。
では、相互の信頼はどこから生まれてくるのだろう?おそらくそれは相手の実力や実績だろう。実はここでチキン−エッグの議論が始まってしまう。「実力・実績があるから互いに信頼する」「相互信頼があるから実力を発揮し、実績を出しやすくなる」という議論である。
これに関しては、あらゆる組織に共通する明確な出発点があるわけではないように思われる。直感的には、まず実力・実績ありきという感もするが、それでは、若い人間などはなかなか信頼を得ることが難しい。実力や実績がまだ少ない段階でも、可能性を信じて信頼するというシーンも必要なのだ。
明確な出発点はないものの、このグッドサイクルを、先述した、優秀な人材の確保や、良き企業文化の維持などと複合させて回していくことが、強い組織には求められるのだろう。よく言われることであるが、グッドサイクルは最初が肝心である。初期にスパイラルが正の方向に向くか、負の方向に向くかで、未来が大きく変わってしまうし、一度回ったサイクルを止めるのは大変だからだ。そうしたグッドサイクルを、一般の企業がどのくらいの大きさで回せるか、どうすれば効果的に回せるかは、今後も経営学者の関心の的であり続けるだろう。
いずれにせよ、ピクサーの持続的な成功は、初期の段階からこのグッドサイクルを意識し、愚直に回してきたことが、その根底にあるのは間違いない。だからこそ、今日に至るまで、正直で本音のコミュニケーションが機能し、そのマネジメントの中核になってきたのだ。