地方創生を主動するリーダーの思考を詳らかにする本連載。前回は、地域活性化伝道師の松橋氏から外部と協働する際の姿勢やこれから求められる人材像について話を伺った。今回は、初音ミクを生んだクリプトン・フューチャー・メディア代表の伊藤博之氏のお話から、企業だからこそできる地域活性化の取り組みについて探っていく。
インターネットの可能性を考えれば北海道での起業は必然だった
 本田:
本田:北海道出身ということだが、札幌で会社を設立することへ強いこだわりがあった?
伊藤:「なぜ北海道なの?」とよく聞かれる。会社を作ったのは1995年で、ちょうどWindows95が出てインターネットが世の中に認知され始めた年。当時働いていた大学では、いち早くインターネットが導入され、メールやウェブページの基礎的なものが教員の間では普通に使われ始めていた。さらに、僕は趣味でコンピューターミュージックをやっていて、ヨーロッパの知人とセッションするためにこれまではデータを郵送していたけれど、インターネットを使うとそれが瞬時に届いて瞬時に返ってくるようになった。
インターネットはきっと世の中を変える――インターネットが広がる世界を想像すると、居ても立ってもいられなくなって、公務員を辞めて会社を作った。
その際に、東京に移ろうとは考えなかった。インターネットが広がる社会は、北海道にいながらにして日本、むしろ世界を相手にビジネスをできるはずだから、それをやってみようと。自分自身で実験してみた感じだ。
本田:公務員のキャリアを手放して会社を設立するのは、大きな決断だったと思う。
伊藤:もともと音楽だけでなく、デザインをするとか、文章を考えること含めて「つくる」ことが好きだった。コンピューターミュージックをするためにMacを購入したら、ちょうどPhotoshopやDTPができるツールが出てきて、自然とデザインをやり始めた。だから会社のチラシ作成などは全部自分でできたし、ウェブ上でしか宣伝・PRなどお客さんとのタッチポイントがないから、必然的にネットマーケティングにも詳しくなった。地域のハンディキャップは、コンピューターやインターネットが克服してくれると信じていた。
一方で、東京の方が様々な機会が多いのは確か。世の流れをいち早くキャッチするとか、教育や人材獲得では苦労することはある。
初音ミクが爆発的に普及した根底にあるコンセプト
本田:クリプトン・フューチャー・メディアから生まれた「初音ミク」は、二次創作を推奨したので、爆発的に世界中で普及したのだろうか。
伊藤:最初からオープンイノベーションにしようと思っていたわけではなく、やっていく中で都度判断していった結果だ。
もともと僕は趣味でサンプラーを使って音楽を作っていた。コンピューターで音楽を作ると音の素材が大量に生成されるので、他の人にも使ってもらえればという想いでアメリカの雑誌に個人広告を出してみた。そうしたら、「うちの持っている音を日本で売ってくれないか」というオファーが来るようになった。それで、他の人が作った音を日本のコンシューマーに売るというビジネスとして起業した。
我々が提供している素材のライセンスは、それを使って他の人が音楽を自由に作ってよいというもの。だから初音ミクという歌声を合成するソフトウェアを開発した。当然、そのライセンス範囲は自分で曲を作ることに自由に使ってよいとなる。キャラクターに関してもその考え方を適用して、自由に使ってよいことを前提に考えた。
本田:そこから派生したキャラクター「雪ミク」が、昨年の「北海道命名150年」事業にも登場した。
伊藤:およそ10年前、さっぽろ雪まつりで初音ミクの雪像を作ったのが雪ミク誕生のきっかけだ。雪でできた初音ミクなので、雪ミクとかSNOWMIKUと呼ばれて定着してきた。せっかくなので冬の北海道をさらに盛り上げようと、祭り期間中にイベントやライブコンサートを実施したりしてきた。
雪ミクは冬限定のキャラクターだが、国内外で人気が出てきたので、夏にも雪ミクが体験できる場所を空港に作ったり、よさこいソーラン祭りでコラボしたり、日本ハムファイターズの応援歌を歌ったり、北海道の色んなイベントや企業さんとコラボレーションしてきた。そうした流れの中で北海道庁から依頼を受けて、PRアンバサダーとしてキャラクターを使っていただいた。
「地方創生」から感じるイメージ
本田:「地方創生」という言葉に対する率直なイメージがあればお伺いしたい。
伊藤:地方に住んでいる者としては、「普段から地方創生をやっているよ」と感じる。地方という言葉自体が相対的なもので、北海道を見ると中心は札幌だけど、日本全体から見れば東京が中心で札幌は地方。どこの視点から見るかによって中央と地方は分かれるから、分けても意味がない。
とはいえ、一般的に地方の課題は中央に助けてもらって解決するものだった。例えば、北海道は国土の22%を占める広い土地があるから、道を作ったり橋を架けることが必要。加えて、歴史的に北方脅威への対応も必要だった。だから国策的に開発をする対象で開発局という専門の役所があり、そこに予算がついて国土整備が行われたという歴史がある。
そのため、北海道の経済圏は土建屋がすごく力を持っている。開発局の案件をゼネコンが請け負って、それを下請けの業者に発注して地域の産業を支えるという構造になっている。もう開発の期間は終わったが、「予算をください」という体質、発注元に依存する体質は建設業だけでなく、ITのような情報産業を始め色んなところに染み付いている。
それはある種、北海道の地方としてのキャラクターとも言える。中央から養ってもらわなければ地方はダメなんだという成り立ちだったものを、地方は地方で分権し、それぞれが独立して採算が取れるような体質にしていかないと日本も地方も衰退してしまうだろう。
北海道にはクリエイターが必要
 本田:
本田:札幌の強みとして、官・民・学が関係性を築いてプラットフォームとして機能していることは注目すべきと思う。その流れの1つに
No Mapsが位置付けられると思うが、今後どのような展望をお持ちか。
伊藤:No Mapsはもともとサウス・バイ・サウス・ウエスト(以下、SXSW)みたいなイベントとして、2000年に開催した。当時のSXSWは音楽フェスが中心、少しマルチメディアが加わったところで、面白いから札幌でもやろうと。ただ、早過ぎたのか、数回で終了してしまった。しかし、SXSWの認知度も高まっているし、もう1回やろうということで2016年に復活して今年で3回目になる。
音楽と映画に加え、メインはカンファレンス。例えば農業×AIのセッションでは、集めたデータを活用して何かいいことが出来ないかということを、研究者や農業従事者、企業関係者が入ってディスカッションする。北海道の中で何か新しいことに取り組むことで、産業を作っていくことを目指している。
北海道経済は決して悪くはないが、獲れた魚、収穫した野菜を何の付加価値もつけずに道外に出荷している場合も多い。付加価値を加える部分にはクリエイティブな発想が必要だから、北海道経済にはクリエイターが必要だということを僕は随分前から言っている。そういう人材を育成して、活用しながら、起業もどんどんしてもらい、それをみんなで応援していきたいという思いがこの根底にある。だからNo Mapsでは、スタートアップのピッチ大会や高校生向けのスタートアップの体験プログラムみたいなこともやっている。
さらに、実証実験にも取り組んでいる。例えば、自動走行車を町中で走行させたり、荷物を運ぶ自動トラクターをアーケード街で走らせたり。実証実験には、そのエリアのコンセンサスを取る必要があり、場合によっては警察の許可も必要だが、No Mapsは産官学で取り組んでいるから理解を得やすい。
本田: No Mapsの中で、Meet-upの位置づけは?
伊藤:Meet-upはお酒も出すから学生中心ではないけれど、平日のカンファレンス後に毎日開催している。真面目に話を聞いて「そうだ。その通りだ」と納得しても、そのまま帰ってしまっては面白くない。登壇した人と話を聞いていた側の人が交流をして「実際にどんなことやっているのか?」「じゃあこういうことしませんか?」みたいなことで意気投合すれば、次のステップに進みやすい。単に話を聞いて終わりじゃなくてその先に進められるようなイベントをやっている。
No Mapsは札幌で開催しているが、案外、東京や他の地方から参加される方も多い。だいたい半分は地元で、残り半分は外の地域から参加される。そういう方との出会いの場を提供することもNo Mapsの大きな意義と思っている。
本田:場を作り、人と人を意識的につないでいる。
伊藤:こういうイベントを開催していると、大学生に限らず高校生も訪ねてくる。「社会をこういう風にしたい」「世の中のこういうことがちょっとおかしい」と何かしら課題意識を持っている子に対して、行政の関係者とディスカッションの場を設定したりしている。
「自分の好きなことで人を喜ばせたい」「社会に貢献したい」という潜在的な意欲はどんな子でも持っている。そういう部分を引き上げて応援したい。自分の理想や実現したい願望に気づかせてあげると、そこから先に進むと思う。
シメパフェ誕生秘話
本田:シメパフェが大ブームだ。
伊藤:「つくる」を創る会社なので、お客様はクリエイター。そういった方々と接点を持つための場所を作ろうと考えたことが原点だ。コワーキングスペースやシェアオフィスのような形にしようかと思ったが、結局、人が入りやすい
カフェにした。とはいえカフェの運営経験もないし、出すものがない。悩んだ末、僕の地元の標茶(しべちゃ)町が酪農地帯なので、そこのミルクを使ったソフトクリームでパフェを作ったのが始まり。
ただ、ススキノにある夜遅くまでやっているお店でパフェを出しても、誰も食べてくれない。そこで、他にもパフェを出しているお店が何軒かあったから横で連携して「飲んだあとはパフェですよ」っていうブームを仕掛けた。チラシを作り、ホテルに置いてもらうと観光客の方も来てくれて、「シメパフェ」の名称でメディアに取り上げてもらった。結果、パフェ屋さんが増えて20店舗以上になり、新しい食文化として定着しつつある。
さらに、僕の地元の標茶高校には、授業の一環としてパフェづくりを取り入れてもらった。なぜパフェなのかというと、チーズやバターのような乳製品と違って、パフェは運べないから食べに来るしかない。だから、高校生が作った四季折々のパフェをカフェで展開すれば、観光資源になる。今はうちの会社と高校、標茶町とで連携し、町をあげてパフェの聖地としてブランディングに取り組んでいる。
その高校とはもう1つ連携している。生徒数は少ないけれど日本一敷地が広い高校なので、それを生かしてドローン教育を始めた。今は部活のような位置づけだが、ドローン操縦者・技能者の育成をしたいと思っている。そういったもので特色をつけると、ドローンを学びたくてその高校に入学したいという子も増えるのではないか。あるいはサマーキャンプ形式でドローンを2週間で体験し、ライセンスが取れるような仕組みがあれば日本中から学びたい子どもが集まってくるだろう。
潜在的な意欲が純粋な動機になる
本田:北海道大学や京都の大学院でも教壇に立たれているが、大学生や今の若者に期待したいことは。
伊藤:組織の中に入ると自分の意見を言いづらくなりがちだが、個にスポットライトを当てると、意外と色んな考え方や意見を持っている人が多い。もう少し個として自由になれるといいのかなと思う。
北海道の傾向として消極的、受け身体質という話もしたが、それは企業の体質に限らない。社会人もそうだし、その影響を子どもたちも少なからず受けている。だから積極的にお金を稼ぎに行こうという人は本当に少ないけれど、それはそれでいいと思う。ただ自分がやりたいと思っていることを形にして人に喜んでもらう、そういう内なる願望に目を向けたら純粋な動機が生まれ、出会いも広がると思う。そこから、北海道なりの新しい経済のあり方が生まれてくると期待したい。
まとめ
伊藤氏へのインタビューでは、北海道の地域活性化にはクリエイターが必要というお話が印象的だった。ビジネスの分野でもデザインシンキングやアートの感覚が重要視され始めているが、地方創生においてもクリエイティブな思考が必要という伊藤氏の考えは新鮮でもあり納得させられるものだった。また、大学・高等学校の教育機関と連携しながら地域をよりよくしていこうとする伊藤氏の姿勢は、地域に根差した企業活動を行う経営者としてのあるべき姿だと感じた。様々な取り組みを通し、次世代の北海道を担う人材を育てたいという伊藤氏の想いに触れられた時間だった。
 本田:北海道出身ということだが、札幌で会社を設立することへ強いこだわりがあった?
伊藤:「なぜ北海道なの?」とよく聞かれる。会社を作ったのは1995年で、ちょうどWindows95が出てインターネットが世の中に認知され始めた年。当時働いていた大学では、いち早くインターネットが導入され、メールやウェブページの基礎的なものが教員の間では普通に使われ始めていた。さらに、僕は趣味でコンピューターミュージックをやっていて、ヨーロッパの知人とセッションするためにこれまではデータを郵送していたけれど、インターネットを使うとそれが瞬時に届いて瞬時に返ってくるようになった。
インターネットはきっと世の中を変える――インターネットが広がる世界を想像すると、居ても立ってもいられなくなって、公務員を辞めて会社を作った。
その際に、東京に移ろうとは考えなかった。インターネットが広がる社会は、北海道にいながらにして日本、むしろ世界を相手にビジネスをできるはずだから、それをやってみようと。自分自身で実験してみた感じだ。
本田:公務員のキャリアを手放して会社を設立するのは、大きな決断だったと思う。
伊藤:もともと音楽だけでなく、デザインをするとか、文章を考えること含めて「つくる」ことが好きだった。コンピューターミュージックをするためにMacを購入したら、ちょうどPhotoshopやDTPができるツールが出てきて、自然とデザインをやり始めた。だから会社のチラシ作成などは全部自分でできたし、ウェブ上でしか宣伝・PRなどお客さんとのタッチポイントがないから、必然的にネットマーケティングにも詳しくなった。地域のハンディキャップは、コンピューターやインターネットが克服してくれると信じていた。
一方で、東京の方が様々な機会が多いのは確か。世の流れをいち早くキャッチするとか、教育や人材獲得では苦労することはある。
本田:北海道出身ということだが、札幌で会社を設立することへ強いこだわりがあった?
伊藤:「なぜ北海道なの?」とよく聞かれる。会社を作ったのは1995年で、ちょうどWindows95が出てインターネットが世の中に認知され始めた年。当時働いていた大学では、いち早くインターネットが導入され、メールやウェブページの基礎的なものが教員の間では普通に使われ始めていた。さらに、僕は趣味でコンピューターミュージックをやっていて、ヨーロッパの知人とセッションするためにこれまではデータを郵送していたけれど、インターネットを使うとそれが瞬時に届いて瞬時に返ってくるようになった。
インターネットはきっと世の中を変える――インターネットが広がる世界を想像すると、居ても立ってもいられなくなって、公務員を辞めて会社を作った。
その際に、東京に移ろうとは考えなかった。インターネットが広がる社会は、北海道にいながらにして日本、むしろ世界を相手にビジネスをできるはずだから、それをやってみようと。自分自身で実験してみた感じだ。
本田:公務員のキャリアを手放して会社を設立するのは、大きな決断だったと思う。
伊藤:もともと音楽だけでなく、デザインをするとか、文章を考えること含めて「つくる」ことが好きだった。コンピューターミュージックをするためにMacを購入したら、ちょうどPhotoshopやDTPができるツールが出てきて、自然とデザインをやり始めた。だから会社のチラシ作成などは全部自分でできたし、ウェブ上でしか宣伝・PRなどお客さんとのタッチポイントがないから、必然的にネットマーケティングにも詳しくなった。地域のハンディキャップは、コンピューターやインターネットが克服してくれると信じていた。
一方で、東京の方が様々な機会が多いのは確か。世の流れをいち早くキャッチするとか、教育や人材獲得では苦労することはある。
 本田:札幌の強みとして、官・民・学が関係性を築いてプラットフォームとして機能していることは注目すべきと思う。その流れの1つにNo Mapsが位置付けられると思うが、今後どのような展望をお持ちか。
伊藤:No Mapsはもともとサウス・バイ・サウス・ウエスト(以下、SXSW)みたいなイベントとして、2000年に開催した。当時のSXSWは音楽フェスが中心、少しマルチメディアが加わったところで、面白いから札幌でもやろうと。ただ、早過ぎたのか、数回で終了してしまった。しかし、SXSWの認知度も高まっているし、もう1回やろうということで2016年に復活して今年で3回目になる。
音楽と映画に加え、メインはカンファレンス。例えば農業×AIのセッションでは、集めたデータを活用して何かいいことが出来ないかということを、研究者や農業従事者、企業関係者が入ってディスカッションする。北海道の中で何か新しいことに取り組むことで、産業を作っていくことを目指している。
北海道経済は決して悪くはないが、獲れた魚、収穫した野菜を何の付加価値もつけずに道外に出荷している場合も多い。付加価値を加える部分にはクリエイティブな発想が必要だから、北海道経済にはクリエイターが必要だということを僕は随分前から言っている。そういう人材を育成して、活用しながら、起業もどんどんしてもらい、それをみんなで応援していきたいという思いがこの根底にある。だからNo Mapsでは、スタートアップのピッチ大会や高校生向けのスタートアップの体験プログラムみたいなこともやっている。
さらに、実証実験にも取り組んでいる。例えば、自動走行車を町中で走行させたり、荷物を運ぶ自動トラクターをアーケード街で走らせたり。実証実験には、そのエリアのコンセンサスを取る必要があり、場合によっては警察の許可も必要だが、No Mapsは産官学で取り組んでいるから理解を得やすい。
本田: No Mapsの中で、Meet-upの位置づけは?
伊藤:Meet-upはお酒も出すから学生中心ではないけれど、平日のカンファレンス後に毎日開催している。真面目に話を聞いて「そうだ。その通りだ」と納得しても、そのまま帰ってしまっては面白くない。登壇した人と話を聞いていた側の人が交流をして「実際にどんなことやっているのか?」「じゃあこういうことしませんか?」みたいなことで意気投合すれば、次のステップに進みやすい。単に話を聞いて終わりじゃなくてその先に進められるようなイベントをやっている。
No Mapsは札幌で開催しているが、案外、東京や他の地方から参加される方も多い。だいたい半分は地元で、残り半分は外の地域から参加される。そういう方との出会いの場を提供することもNo Mapsの大きな意義と思っている。
本田:場を作り、人と人を意識的につないでいる。
伊藤:こういうイベントを開催していると、大学生に限らず高校生も訪ねてくる。「社会をこういう風にしたい」「世の中のこういうことがちょっとおかしい」と何かしら課題意識を持っている子に対して、行政の関係者とディスカッションの場を設定したりしている。
「自分の好きなことで人を喜ばせたい」「社会に貢献したい」という潜在的な意欲はどんな子でも持っている。そういう部分を引き上げて応援したい。自分の理想や実現したい願望に気づかせてあげると、そこから先に進むと思う。
本田:札幌の強みとして、官・民・学が関係性を築いてプラットフォームとして機能していることは注目すべきと思う。その流れの1つにNo Mapsが位置付けられると思うが、今後どのような展望をお持ちか。
伊藤:No Mapsはもともとサウス・バイ・サウス・ウエスト(以下、SXSW)みたいなイベントとして、2000年に開催した。当時のSXSWは音楽フェスが中心、少しマルチメディアが加わったところで、面白いから札幌でもやろうと。ただ、早過ぎたのか、数回で終了してしまった。しかし、SXSWの認知度も高まっているし、もう1回やろうということで2016年に復活して今年で3回目になる。
音楽と映画に加え、メインはカンファレンス。例えば農業×AIのセッションでは、集めたデータを活用して何かいいことが出来ないかということを、研究者や農業従事者、企業関係者が入ってディスカッションする。北海道の中で何か新しいことに取り組むことで、産業を作っていくことを目指している。
北海道経済は決して悪くはないが、獲れた魚、収穫した野菜を何の付加価値もつけずに道外に出荷している場合も多い。付加価値を加える部分にはクリエイティブな発想が必要だから、北海道経済にはクリエイターが必要だということを僕は随分前から言っている。そういう人材を育成して、活用しながら、起業もどんどんしてもらい、それをみんなで応援していきたいという思いがこの根底にある。だからNo Mapsでは、スタートアップのピッチ大会や高校生向けのスタートアップの体験プログラムみたいなこともやっている。
さらに、実証実験にも取り組んでいる。例えば、自動走行車を町中で走行させたり、荷物を運ぶ自動トラクターをアーケード街で走らせたり。実証実験には、そのエリアのコンセンサスを取る必要があり、場合によっては警察の許可も必要だが、No Mapsは産官学で取り組んでいるから理解を得やすい。
本田: No Mapsの中で、Meet-upの位置づけは?
伊藤:Meet-upはお酒も出すから学生中心ではないけれど、平日のカンファレンス後に毎日開催している。真面目に話を聞いて「そうだ。その通りだ」と納得しても、そのまま帰ってしまっては面白くない。登壇した人と話を聞いていた側の人が交流をして「実際にどんなことやっているのか?」「じゃあこういうことしませんか?」みたいなことで意気投合すれば、次のステップに進みやすい。単に話を聞いて終わりじゃなくてその先に進められるようなイベントをやっている。
No Mapsは札幌で開催しているが、案外、東京や他の地方から参加される方も多い。だいたい半分は地元で、残り半分は外の地域から参加される。そういう方との出会いの場を提供することもNo Mapsの大きな意義と思っている。
本田:場を作り、人と人を意識的につないでいる。
伊藤:こういうイベントを開催していると、大学生に限らず高校生も訪ねてくる。「社会をこういう風にしたい」「世の中のこういうことがちょっとおかしい」と何かしら課題意識を持っている子に対して、行政の関係者とディスカッションの場を設定したりしている。
「自分の好きなことで人を喜ばせたい」「社会に貢献したい」という潜在的な意欲はどんな子でも持っている。そういう部分を引き上げて応援したい。自分の理想や実現したい願望に気づかせてあげると、そこから先に進むと思う。


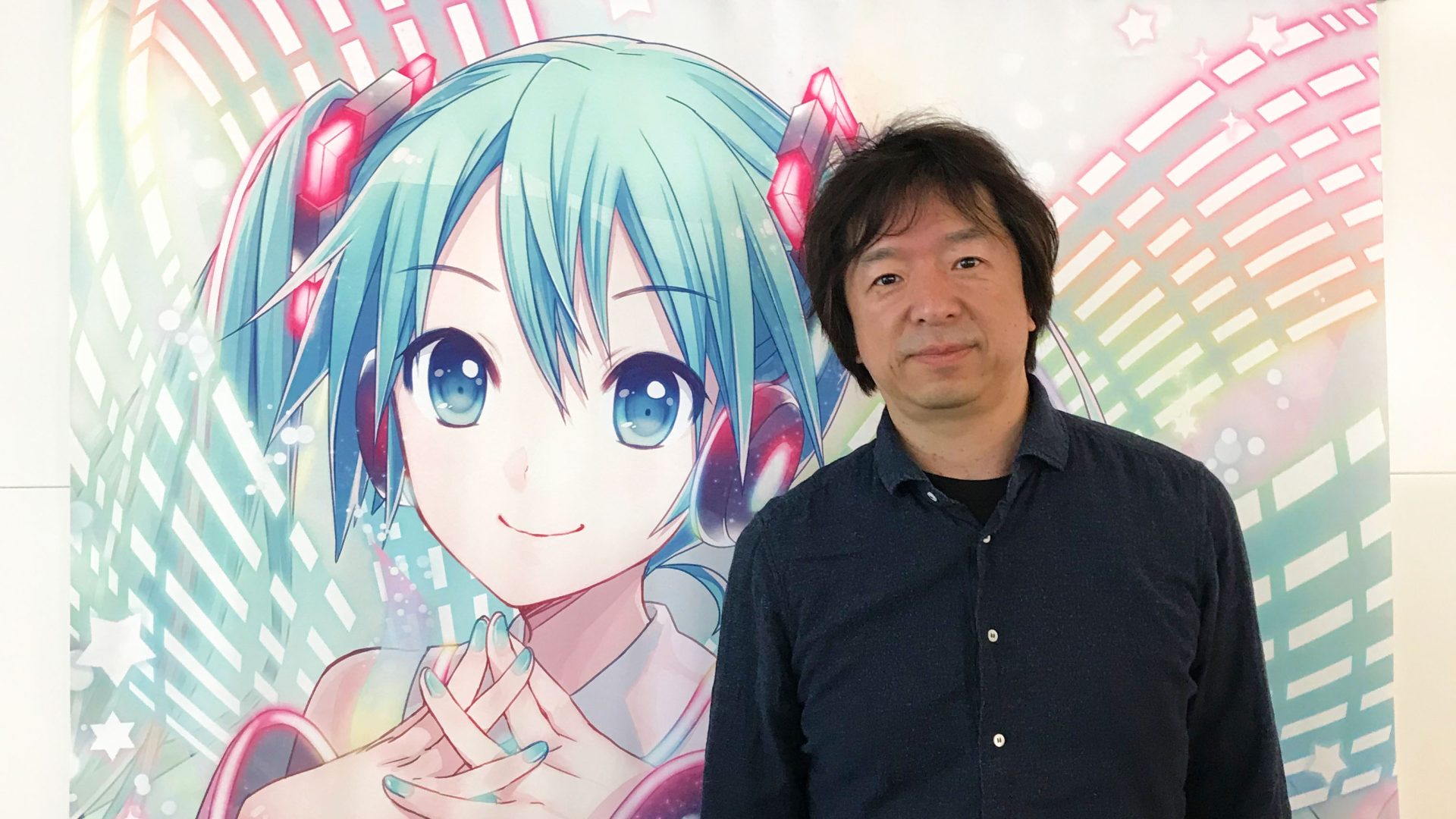





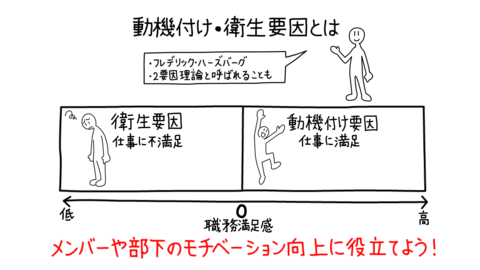






























.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




