 今回は、五輪の歴史を題材に、何かと積極活用が謳われている民間活力導入について考察します。
今回は、五輪の歴史を題材に、何かと積極活用が謳われている民間活力導入について考察します。
近代五輪は、1896年にアテネで第1回大会が開催されました。その後、大戦による中止なども何度かありましたが、基本的には4年に1度の祭典として開催され、スポーツ振興に大きな役割を果たしてきました。
昨今の五輪を語る上で避けて通れないのは、「商業五輪」色の強まりでしょう。そのきっかけとなったのは、1976年のモントリオール大会の10億ドルという巨額の赤字です。前回のミュンヘン大会でアラブ過激派によるテロ事件が起き、警備コストが跳ね上がったという事情もありましたが、「お役所仕事」で支出に歯止めがかからなかったことがその大きな原因です。この大赤字は、その後のモントリオール市やケベック州の経済に大きな影を落としてしまいました。
この大赤字に恐怖心を抱いた各国の大都市は、五輪招致に消極的になります。1984年のロサンゼルス大会は、実質、無投票当選でした。そのアメリカも、1976年開催予定であったデンバーでの冬季オリンピックを住民投票で返上したという過去があり、ロサンゼルス大会が無事に開かれるのか懸念する向きも少なくありませんでした。
そこで背に腹は代えられず、大々的に導入されたのが民間活力です。それまでの五輪も、テレビ放映料や公式スポンサーからの収入はあったものの、現在のレベルに比較すると微々たるものでした。また、先述したように、お役所仕事でいたずらに支出が増える傾向がありました。
ロサンゼルス大会では、元企業経営者で敏腕セールスマンでもあったピーター・ユベロス組織委員長が辣腕をふるい、徹底的なコストダウンを行いました。それ以上に重要だったのは、収入の増加です。テレビ放映権料を一気に増やし、スポンサーからの協賛金も激増させました。その結果、ロサンゼルスオリンピックは大黒字になったのです。
こうした収入はその後もうなぎ登りに上がり続け、今日に至っています。ちなみに、テレビ放映権料だけとってみても、モントリオール大会が3500万ドルだったのに対し、2020年の東京大会では概ね15億ドルです(そのうち半分が開催国の組織員会に配分されます)。「TOKYO 2020立候補ファイル」によれば、東京五輪の収入は3400億円を見込んでおり、その半分をIOCからのテレビ放映権負担金と、ローカルスポンサーシップで賄う予定です。
商業五輪の功罪について言えばいろいろなものがあります。まず「功」について言えば、
・スポンサーの関心、市場性が高まった結果、優秀なアスリートが五輪を目指すようになり、競技の質が向上した
・予算が潤沢になった結果、世界中にスポーツ文化を広めやすくなった
これらは、スポーツ振興の立場からすれば好ましい話です。一方で「罪」としては、
・資金の出し手の発言力が著しく強くなった(その代表はアメリカのテレビ局です。たとえば東京五輪は、気候を考えれば前回同様10月頃の開催が適切なはずですが、アメフットシーズンやMLBのプレーオフと重ならないようにした結果、猛暑の7月、8月に行われます)
・ビジネスとして巨大化したため、開催地の選考過程などにおいて不適切な行為が行われるようになった
端的に言えば、ビジネスの手法を持ち込んだ結果、五輪そのものの収益性や成長性は上がったものの、「もの言う顧客」の発言力が強まった結果、本来あるべき姿を曲げてでも、商業的な側面が重視されるようになったのです。
これは他の分野でも、公的セクターの仕事を民営化した時に少なからず生じる話です。交通インフラで、トータルとしては赤字は減ったものの、不採算路線の運行本数が減り、一部住民が多大な不便を受けるなどは洋の東西を問わず生じている話です。
話を五輪に戻すと、もう1つ面倒な話があります。先のロサンゼルス大会は、既存の施設を使うなどして極力コストを下げました。ユべロス組織委員長にとっては、赤字を出さないことが至上命題だったのです。
しかし、それ以外の国では、五輪はインフラを作る機会として捉えられがちです。特に日本では「箱モノ」にかかる費用はばかになりません。すでに2020年東京五輪の予算は、当初の予定の数倍の2兆円になるとも3兆円になるとも言われています。
これは、五輪そのものの収支ではなく、「経済効果」という大義名分のもとに予算が膨れ上がりやすい体制や仕組みに問題がありそうです。1998年の長野冬季五輪でもその点は指摘されましたが、その教訓が生かされたかというと疑問です。
官に任せていては赤字に歯止めがかからない分野に、民間の力を活用するのは筆者としては基本的に賛成です。しかし、やるならやるで、透明化も含め徹底しないと、極めて中途半端になってしまいますし、なまじ巨額のマネーが動くだけに、健全ではない状況が生じてしまいます。
また、民間の力が強くなったがゆえに生じる「もの言う顧客」からのプレッシャーにどれだけバランス良く対応するのかも重要な問題です。これらをクリアできないと、かえって大きな禍根を残すでしょう。
今回の学びは以下のようになるでしょう。
・民間活力の導入にあたってはそのデメリットやリスクを最小化する仕掛けが必用。また、ステークホルダーの影響力のバランスを適切にとる必要がある
・中途半端に「公」の力が入り、また透明化されないと、予算は必ず肥大化し、費用対効果は見合わなくなる
・日本人のハコもの好きは一朝一夕には変わらない






















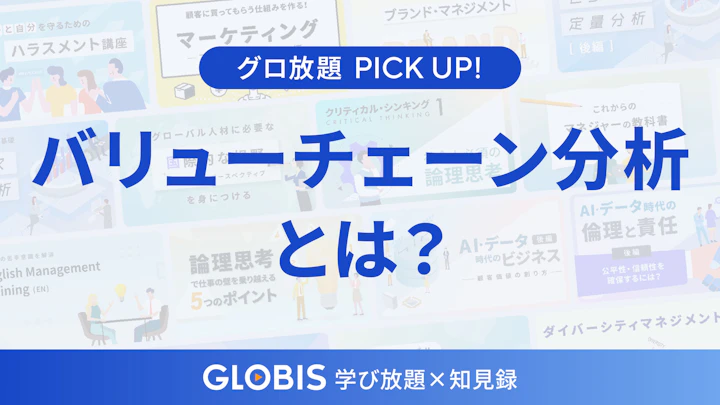















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

