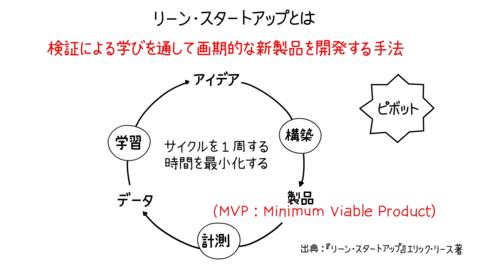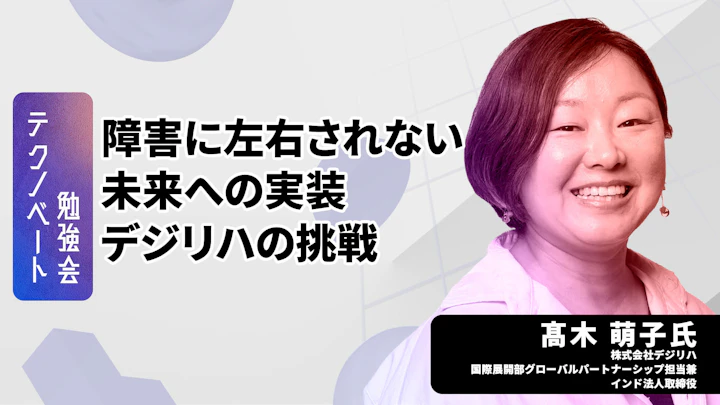前回の連載では、ベンチャー企業にやがて訪れる「成長の踊り場」からどのようにして脱出し、飛躍すべきかを、グロービス・キャピタル・パートナーズ(GCP)プリンシパルである今野穣氏に、経験を踏まえて聞いた。
今回は今野氏と、同氏が担当する投資先であるインタラクティブブレインズ(IB)取締役副社長の中村達郎氏の2人に登場してもらい、成長の岐路に立たされたベンチャー企業がいかにして成長の踊り場からの飛躍に至ったかを語ってもらった。
ベンチャーキャピタルという存在の意義
‐‐GCPの投資の分野や戦略の特徴については前回の連載で伺いましたが、今野さんが担当されている分野について教えてください。
今野:今、GCP全体だと半分以上がIT関連への投資です。今のように景気が落ち込んだり、ストック市場が低調になると、箱物的な施設型の事業で利回りを図るのは厳しい。そこで、ある一定の期間内に一定の規模までに成長を達成するとなると、IT分野へのレバレッジが必要なんです。
私自身は、特にIT・モバイル関連の企業への投資を中心に担当しています。ひとことでITと言っても、コアテクノロジーからハードウェア、ミドルウェア、アプリケーション、サービスまでさまざまです。
またIT以外では、オンラインに特化した生命保険会社であるライフネット生命保険も担当しています。一般的に、生命保険の保険料の約半分は人件費が占めるといいます。ライフネット生命保険は、店舗を持たずにオンラインで提供することで、保障の内容は同じでありながら保険料を従来の半額程度に抑えるというシンプルな手法で業界に対してチャレンジを続けている企業です。不景気が追い風となり、極めて順調に成長を続けています。
‐‐IBについて紹介してください。
中村:IBは、2001年にゲーム会社のナムコ(当時)の研究者が中心となって立ち上げた会社です。設立以降、おもに携帯電話用のゲームアプリの受託開発をしたり、大手企業と共同でゲームを制作・展開したりということをやっていました。しかし今からちょうど1年半ほど前に我々のビジネスを見直していこうと議論しまして、“インタラクティブエンターテインメントプロバイダー”として世界一を目指す、とビジョンを仕切り直しました。我々は、携帯電話のゲームアプリ開発に留まらず、ゲームやそのほかのエンターテインメントを“人と人とが一緒に楽しむための媒体”として提供するように事業を転換しました。
--IBの技術的な強みや開発手法の特徴はどういったものでしょう?
中村:弊社の創業メンバーの中心人物は、世界最先端の3Dゲームの開発者で、特に最近はクラウドをつかった3D描画技術を強みにしています。具体的な例で言うと、3Dアバターを携帯電話上で表示する場合に、アバターを端末のアプリ上で処理するといった従来のやり方ではなく、ハードウェアアクセラレーション技術によって、能力を最大限に引き出したサーバハードウェアで高速レンダリングし、結果を携帯電話端末に配信するということなどをやっています。これによって、サーバ台数をソフトウェアレンダリングとの比較での約10分の1から20分の1程度に抑えることができたという実績もあります。
携帯電話のアプリ開発で高い技術力がある会社、また、サーバソフト開発で高い技術力がある会社は多数ありますが、サーバのハードウェア、ソフトウェアから携帯電話側のアプリまでトータルでベストチューニングできる会社は珍しいと自負しています。
--GCPでは2006年12月にIBに対して3億円に投資をしています。それぞれ投資に至るまでの経緯や最初の印象教えてください。
今野:まず市場という観点から言うと、当時まだグリーやDeNAの姿はなくても、モバイルコンテンツ市場は今後全体的に伸びるというのは容易に想像できました。その中で、どういうかたちでもいいから「トップになり得る会社」を我々は探していました。その点においては、IBは3Dモバイル、ゲームディベロッパーとして突出していました。
ただし、技術力はある一方で、ビジネスで中核となる人物がいないというのが第一印象でした。しかし、IBに限らず、エンジニアしかいないから悪いという考え方ではなく、これからビジネスに強い人に入ってもらえる器があればいい、と判断しました。そういう意味では、(エンジニアとして)非常に勤勉で謙虚な人たちがそろっていているので、ビジネスの部分は投資後に伸ばしていければいいと思いました。
中村:私はGCPの投資が決まった時点でIBに入社したのですが、私が聞いたところでは、GCP以外にももう1社、別のベンチャーキャピタルからも投資のお話をいただいていたそうです。両社とも金額は同じでしたが、その他の条件についてはGCPのほうが厳しい内容でした。しかし、経営支援力にひかれてGCPに決めたそうです。
その投資実行とほぼ同時期に、経営企画的な機能が必要ということで人材の募集があり、そこで私が採用されました。私は前職では携帯電話会社でマーケティングを担当していたのですが、同時にグロービスの経営大学院に通い、「成長の痛み」に苦むベンチャー企業を拡大、成長させていくマネジメント手法などを学んでいたので、GCPがハンズオンで入るというのは、IBに転職する大きな後押しになりました。
成長の踊り場をタッグで乗り越える
‐‐IBにとって“成長の踊り場”を迎えたのはいつごろだったのでしょう?
今野:そもそも出資の目的が、事業的にも組織的にも踊り場からの脱却でした。当時のIBは、技術はあるのにほぼ受託しかやっていない状態でした。これでは企業の資産の切り売りをしているだけで会社にとっての継続的収入やアセットを蓄積することにはならない。それから、トップがキーマンとなり、1対多で人を動かす規模も組織として限界に来ていました。
中村:当時は、売上を伸ばすための受注は好調だったのですが、一方で組織ができていないという状態でした。なので、受注しても計画以上に開発期間がかかってしまい、想定以上のコストが発生して赤字が出るわけなです。でも、売上は求めなければいけないからさらに受注を増やしてという悪循環。数字のつじつまは合わなくなるし、体制は立て直らないし—というベンチャー企業の成長の痛みの教科書どおりのことが目の前でまさに起きていました。
--その成長の踊り場にいたIBに対して、VCとしてどのような支援をされたのでしょうか?
今野:まずは資金と人材を入れて、ビジネスを1人のキーマンがワンマンで動かすやり方ではなく、経営を考えたキャッシュフローを考えて回していく仕組みづくりをしました。それこそ会議で使う資料も一から作り直して、事業別やプロジェクト別の収益性、案件進ちょく、稟議規定などかなり細かいところまでです。
中村:組織として利益を上げるための役割分担を徐々に整理して明確にしていきました。しかし、悪循環が来るところまできて、2007年秋ぐらいにいったん、案件受注を全部ストップしました。今野さんに「こんなことやってちゃだめでしょ」と言われて、本当に収益率が高い、その当時の体制でも絶対つくり切れる案件だけに絞って、体制を立て直すことに集中しました。
今野:黒字でも赤字でも続く会社は続くのですが、もっとも続かない理由はキャッシュがなくなってファイナンスが続かなくなることです。実は、開発期間中のベンチャーはキャッシュフローがもっとも大事な指標ですけど、キャッシュを消化している段階では、次のファイナンスを意識しながら事業判断をすることも肝要なのです。
具体的には、キャパシティー以上に売上を追求するなど、闇雲に頑張ってキャッシュフローを痛めるよりも、メッセージ性の強いプロジェクトや収益性・継続性の高いプロジェクトをしっかりこなしていけるよう体制を整理しました。実はそのときのプロジェクトが今の事業転換の軸にもなっています。研究開発費を投じるのではなく、案件ベースで市場のニーズを探ってうまく展開できたと思います。
--中村さんがGCPとの付き合いを通して感じた、ベンチャー企業から見たVCの理想的なあり方というのはどういうものでしょうか?
中村:一般的に、VCというのは、投資に対するリターンをとにかく早く出すことを強く求められるものだと思うんです。でもベンチャー企業からしたら、それだけを追いかけると事業を壊しかねない。短期、中期、長期での視点をそれぞれ考慮した上で、トータルでの企業価値を上げることを親身になって考えてくれる存在になってもらうことはベンチャー企業にとっては本当にありがたいです。VCが投資先の人間と話すときに、自分たちと投資先の企業とをあわせて「我々」と言ってくれる、一緒になって考えてくれるというのはベンチャー企業にとっては大変ありがたいですね。
--逆に、今野さんから見たベンチャー投資のあり方とはどういったものですか?
今野:VCである以上、我々は投資家から預かった資金を最大化してそれをお返しするというのが第一義的なミッションです。もちろん個人として新しい産業にチャレンジしている人・会社を支援したいと常に思っていますが、資本主義の生態系の中での職業人としては、ベンチャーに投資するのは、リターン最大化のための手段とも言えるわけです。
ただ、その手段を達成するために投資先の人たちに我々ファンドのロジックを過度に、またはそれを正面からぶつけてもいいことはまったくと言ってよいほど良いことはないと感じています。だからと言って、それを外したから我々の経営陣と対立するというわけでもないんです。本質はシンプルで、ファンドが入っていようが、成長のためにやるべきことはあまり変わらないと思います。