メンタル不調がもたらす経済的損失

1兆数千億円――さて、これはいったい何の数字だと思われますか。実はこの数字、複数のシンクタンクが、メンタル不調による休職や、さらにそれらに関連する就業規則上の問題などにより発生する生産性低下の経済的インパクトを見積もったものです。
厚生労働省の「働く人々の健康状況調査」によれば「職場で強い不安や心配、ストレスを感じる」と回答した人々の割合は82年50.1%、87年55.0%、92年67.3%、97年62.8%、02年61.5%と回を追うごとに増加し、高い状態で推移しています。また精神障害による労働災害件数と訴訟事件による企業への損害賠償請求も増大しています*1。
従来、うつ病による自傷他害行為などは労働災害の認定対象としては認められていなかったのですが、近年は労働災害に認定されるようになり、認定を請求する件数も、認定された件数も、ともに増加し、06年度は過去最高になりました*2。また、勤務先企業に損害賠償を求める民事訴訟では、企業側が「安全配慮義務違反」等で敗訴することが多くなっています。
カナダ・ストレス研究所の報告によれば、ハイパー・チェンジによって社員の疲労、うつ状態、感情障害は増加し、経済的損失(仕事離れや長期休職者の増加など)を引き起こします。M&Aなどが盛んに行われた80年代のアメリカでは、ストレスによる経済的損失は連邦政府の財政赤字に匹敵する1500億ドル(約19兆円)であると報じられました*3。
メンタルヘルスの低下がもたらす経済的損失を測定するメジャーとしては、(1)労働損失日数 (2)医療費 (3)訴訟費用 (4)職場における対策費用、などがあります。
労働損失日数、休職、欠勤の増加による経済的損失を例にとると、ある大企業(従業員5000人規模)では、この五年間、精神障害による休職者が増加し(なかでも「うつ病」による長期休業は日数の増加要因となっています)、労働損失日数が約2000日から8000日へと4倍になりました。仮に1人・1日当たりの遺失利益を2万円とすると、その経済的損失は、4000万円から1億6000万円へと増えたことになります。当事者のそうした遺失利益に加え、職場の上司・同僚の負担増に伴う事故やミスの増加、モラールダウン、CSR(企業の社会的責任)への影響、さらには機密書類の漏洩、転職、インターネットへの書き込み、顧客へのサービスの低下によるトラブルの頻発、新しいアイデアを企画する力の低下等の間接的損失まで入れて計算すると大変な金額となるでしょう。カナダ・ストレス研究所は、ストレス対策を怠ることに伴う最大の経済的損失は企業の成長力低下であると指摘しています。
わが国におけるメンタルヘルスケアの歴史
今や各企業・職場における重要な課題になってきているといっても過言ではないメンタルヘルスの問題ですが、もともと、メンタル不調が生産性に影響を与えることは古くから問題視され、さまざまな施策がなされてきました。その歴史を簡単に振り返っておきましょう。
60〜70年代までの取り組み
60年代までは、統合失調症等、いわゆる精神病への精神医学的、社会福祉的対応が中心でした。産業界においても、疾病に対する治療、管理、職場復帰援助が健康管理の主な内容でした。
70年代には、「欠勤」「アルコールによる怠業」「災害」を3悪*4とみなし、これを低下させることに企業は励みました。その具体的な施策が、安全衛生と健康管理の充実強化です*5。
筆者が勤務していた日本鋼管(現・JFEスチール)のメンタルヘルスケアへの取り組みは早く、経営者の先進的思想によって、健康管理から分離した形で産業心理学的なメンタルヘルスへのアプローチを取り入れました。当時、60年代に「金の卵」といわれた中卒労働者が、社内での技能教育を受けて一人前となった後に、2、3年で退社してしまうケースが増加していたのですが、経営陣は、「心の問題」「ストレスの問題」が原因の一つであり、働きやすく生きがいを持てる職場づくりが若年労働者の定着率の向上につながると考えたのです。
こうした先進的な取り組みがいくつかあったものの、当時はメンタルヘルス(精神保健=Mental health)はまだ精神衛生(Mental hygiene)と呼ばれ、現代ほど大きな社会的テーマとはなっていませんでした*6。
80年代以降の取り組み
80年代以降は、IT化が産業界全般に普及し、多くの産業で生産性が向上しました。その一方で、合理化の下に人員削減が増加し、また頭脳労働に従事する者が増加するにつれ、変化に対応できない職場不適応が顕在化してきました。精神的ストレッサー(ストレスを発生させる要因)が増加し、誰もがストレス性疾患のリスクにさらされるようになってきたためです。
メンタルヘルスケアの必要性は、バブル経済下の繁忙期、バブル崩壊後の不況期を通じて一貫して高まっていきました。誰でもストレスによってメンタル不調になる可能性があることから、健康な社員のメンタルヘルス施策の必要性も強く叫ばれるようになりました。
こうしたなか、社内に産業医を常駐させる企業が増えました。また、国の健康管理上の施策も変化しました。いわゆる「精神病」に対する取り組みだけでなく、それ以外の社員に対するメンタルヘルス施策もとられるようになってきたのです。86年には「企業におけるストレス対策のための指針」が労働省、中央労働災害防止協会によって定められ、88年には「心とからだの健康づくり」によるTHP(トータル・ヘルスプロモーション・プラン:労働者の健康保持増進のための措置)の展開がありました。87年に精神衛生法が精神保健法(現・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に改正され、92年には労働安全衛生法改正に伴う「快適職場形成」指針が策定されました。
そして21世紀を迎え、メンタルヘルスを導入することにより休職日数や件数を減少させることで、経済的損失の低減を図ろうとする企業も増えています。10年間にわたる取り組みにより、ストレス性疾患の減少という効果をあげる企業も出てきました。06年には、労働安全衛生法により、過重労働による健康障害の防止が強化されました*7。
しかし、ここで一つ疑問が湧いてきます。企業ははたして、メンタルヘルスを正しく理解しているでしょうか。たとえば、メンタル不調が起こる原因を正しく理解したり、メンタル不調の症状を正しく整理できたりしているでしょうか。これができていなければ、結局は対症療法となり、いつまでたってもいたちごっこです。そして多くの企業は、残念ながらメンタルヘルスを正しく理解しているとはいえないのです。
ハイパー・チェンジ・エイジのメンタル不調
どのようなメンタルヘルス施策が適切かを考える前に、近年、特にメンタル不調が増えている原因、あるいは重視されるようになった要因について再確認しておきましょう。
高まりゆくストレス
グローバル化の進展、ITの発達など、我が国の産業は大きな変革の時期にあります。この変革は、日本のみならず世界的な潮流であり、ストレス研究で名高い、カナダ・ストレス研究所所長のアール博士は、これを、超高速変化の時代、ハイパー・チェンジ・エイジと名づけています。
ハイパー・チェンジとは、予測しがたく、これまでの経験に照らして対処方法を考えがたい未経験の変化を指すものです。これは、単なる変化のスピードではなく、変化の「目新しさ」と「予測不能性」に注目した概念です。どうなるのか予測できず、備えられないことが不安材料となり、しばしば強いストレスを引き起こすと考えます。私たちは、目先の職場で体験する事象に目を奪われがちですが、背景には大きなハイパー・チェンジがあるのです*8。組織と個人の両者において、この超高速の変化がもたらすストレスに適応しなくてはならないのですが、それは一朝一夕にできることではありません。
経済のソフト化
経済はモノづくりからソフトへとその重心を移しています。そうした時代には、ホワイトカラーの創造性や企画力などがものを言うわけですが、これらはメンタルヘルスが不健全な状況ではなかなか高まりません。
ちなみに近年の研究では、欠勤(アブセンティズム)よりもむしろ「プレゼンティズム」が生産性との関係で問題になることがわかってきました。出社はしているものの、ちょっとした体の不調や花粉症のような慢性アレルギー、飲みすぎによる頭痛等がむしろ生産性低下をもたらすとの指摘です。この傾向は、ホワイトカラーほど当てはまることといえるでしょう。
リスクの増大
企業を取り巻くリスクは拡大・増加しています。PL(製造物責任)に絡む訴訟リスクや、ネットなどでの評判リスク、知的財産の漏洩リスクなどは、かつてはそれほど注目されませんでしたが、今や避けて通れない問題です。そして、メンタル不調は、往々にしてこれらのリスクを高めてしまうことにつながります。競争が激しく、否応なくストレッチしなくてはならない現代、さまざまな問題に関する許容範囲が狭まっているという事実を強く意識する必要があります。
こうした状況の変化に加え、企業がメンタルヘルスを正しく理解していないことが、多くの問題を招いています。
では、多くの企業が犯している間違いとは何でしょうか。メンタル不調に気づいても上司が見て見ぬふりをする、あるいは、メンタル不調からの回復をすべて個人の自助努力にゆだねるといったやり方は論外ですが、産業医などを積極的に導入している比較的先進的な企業でも、望ましい総合的なアプローチは必ずしもとれていません。
そうした企業が犯している過ちは、ひと言で言えば、あらゆるメンタル不調を医学の領域に押し込め、医学的に対応しようとしているということです。もちろん、医学的な対応を適切に行うことは重要なのですが、そうした対応だけではメンタルヘルスの問題には対処しきれないという理解が不足しているのです。
では、メンタル不調を防ぐためには、どのような捉え方をしたうえで対応すればいいのでしょうか。その鍵が、「適応アプローチ」の理解です。
次回は「適応アプローチとは何か」について、ご紹介します。
*1 「労働者健康状況調査の概況」厚生労働省大臣官房統計情報部回
*2 「精神障害者労災補償状況」厚生労働省補償課
*3 ""Newsweek"" 1988.4.28
*4 Alcoholism, Absenteeism, Accidentを指して「産業の3A」と呼ぶ。
*5 当時は、労働者の楽しみは、帰宅時の飲酒が多く、鉄鋼業などの交代勤務制度の職場では「アルコール依存も含めた飲酒問題」による間接的生産性の低下がクローズアップされていた。また、ヒューマンエラーを含めた労働災害の撲滅が企業の重要問題とされていた。
*6 こうした時代に、メンタルヘルスが大きく社会の人々の関心事になった事件として、82年2月9日の日本航空機の羽田沖墜落事故がある。これは、「心身症の機長による事故」として大きく報道された(後に、心身症ではなく統合失調症であることが判明)。
*7 改正労働安全衛生法第七〇条の2に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(06年3月31日発表)は、衛生委員会等の活用、メンタルヘルス推進担当者の選任、個人情報保護などについて述べている。
*8 (1)リチャード・アール「科学シンポジウム サピエンス:第10回『ストレスの科学』プレゼンテーション:「ストレス科学の第3の波」1996年 (2)リチャード・アール:カナダ・ストレス研究所所長、職場の“超”変化によって起こる「フューチャーショック・トラウマ」を乗り越える Scientific Live/ SAPIENS (3)リチャード・アール「IT革命時代の経営戦略─北米最新ストレスサイエンスからの提言」、国際ストレス科学シンポジウム資料、1-67,2000
本稿の著作権は著者に帰属しています。内容の無断転載、無断コピーなどはおやめください。また、私的利用の範囲を超えるご使用の場合は、グロービスおよび出版社の承諾書と使用料が必要な場合があります。
『ビジネススクールで教えるメンタルヘルスマネジメント入門』について
『ビジネススクールで教えるメンタルヘルスマネジメント入門―適応アプローチで個人と組織の活力を引き出す』(佐藤隆・著、グロービス経営研究所・監修)から、著者による「まえがき」と、「本書の構成と特徴」について、以下に再掲載する。
■まえがき
メンタル不調*1者の増加は続き、厚生労働省への相談件数も、精神障害による労働災害と認定された件数も、訴訟事件による企業への損害賠償請求も、過去最高となっています。07年10月には、わが国で初めて上司のパワー・ハラスメントによる自殺事件が労災認定されました。なぜ、多くの企業の努力にもかかわらず、問題は解決されないのでしょうか。
臨床心理士や精神科医は活躍しています。勉強熱心な管理職ならば「パキシル」や「トレドミン」といった抗うつ剤の名前も知っているかもしれません。カウンセリング・ルームの設置やストレス診断テストの導入も、一般的になりました。職場のリーダーやビジネス・パーソンもこの問題には決して無関心ではありません。にもかかわらず、メンタル不調で苦しむ人々は増加しつづけています。
メンタル不調が増えている大きな原因となっているのが、世界的な大競争時代の進展に伴うストレスの増加です。カナダ・ストレス研究所長のリチャード・アール博士*2は、現代を、人類が経験したことのない「超高速変化の時代=ハイパー・チェンジ・エイジ」と名づけました。こうした変化の時代は、能力ややる気のある個人にはチャンスである一方、彼らを含め、あらゆる従業員が常にストレスにさらされることになり、心身の健康と活力保持が重要な課題となってきます。
組織と個人は、こうした変化に対する適応力を高めなくてはなりません。今起きている変化の波を知り、あらかじめ備えて対処することが必要なのです。しかし、それができないことが、メンタル不調の増加につながっています。
経営学とメンタルヘルスの融合が求められている
では、どうすればいいのでしょうか。メンタルヘルスの問題を解決するためには、まず、メンタルヘルスの考え方を正しく理解し、そのうえで総合的なアプローチをとることです。
「正しく理解する」第一歩は、ストレスに対する理解を深めるとともに、メンタルヘルスを「疾病とその治療」という狭い枠のなかで考えるのではなく、職場の対応も含めて改善を図る、「適応アプローチ」という、より包括的な考え方で理解することです。本書でも、この適応アプローチの説明に多くのページを割いています。
「総合的なアプローチ」というのは、経営学とメンタルヘルスを融合させ、その両面からメンタル不調(訳もなく意欲がなくなった、急に将来を悲観的に感じるようになった等)の予防策、対応策(ソリューション)を講じることです。これも適応アプローチに基づく考え方です。これまでのメンタルヘルスを扱った類書と、本書の大きな差異はそこにあります。
筆者は、企業や病院、大学でメンタルヘルスの臨床、教育、研究に携わったあと、06年にグロービス経営大学院が文部科学省認可の経営大学院としてスタートするにあたり、教授として招聘されました。そして、グロービスの経営学の知識と経験に触れ、「人を生かす経営やマネジメント」「人の気持ちを考え、部下を生き生きとさせて生産性を向上させるマネジメント」の実際を目の当たりにして、ますます適応アプローチをベースとしたメンタルヘルスの考え方を世に問わなければならないと思うようになりました。
本書は、筆者の35年の臨床経験・調査研究と、グロービスの経営学が融合してできたものです。ここで述べていることは単なる仮説ではありません。多くの企業における実践で実証されたことです。本書で提示するアプローチが、個人と組織双方のメンタルヘルスと生産性の向上に寄与することを願ってやみません。
このアプローチを構成するにあたっては、カナダ・ストレス研究所のリチャード・アール博士に多くのご指導をいただきました。この場をお借りして、厚く感謝いたします。
また、メンタルヘルスに関する活動内容を、本書に掲載することに快く応じていただき、本書の実践性に厚みを持たせてくださった企業の皆様に感謝申し上げます。
そして、本書の出版にあたり真摯な議論をいただいたグロービス・メディア事業推進室の嶋田毅氏と有園香苗氏、グロービス経営研究所の荒木博行氏、植村ルミ氏、グロービス・グループ広報室長の野田史恵氏、株式会社オトムメディアの栗原雅氏、そして本書の出版にご高配いただいたダイヤモンド社書籍編集局の石田哲哉編集長に心より感謝いたします。
グロービス経営大学院教授 佐藤隆
■本書の構成と特徴
第1部 基礎編:メンタルヘルスの基礎知識
その第一歩は、メンタルヘルスの知識を正しくつけることです。メンタルヘルスとは、心の健康を守ることです。精神的に健康であることで、意欲的に職務に取り組み、仕事のパフォーマンスを上げることが可能となります。
本書では、まず第1部で、現在起こっているメンタルヘルスに関する問題を正しく把握します。そして、メンタルヘルスの全体像と、重要な概念について解説します。そして、専門の医療従事者が予防、治療、復帰を行う「医療依存アプローチ」に頼り切るのではなく、経営者や人事部、管理職の努力を要する「適応アプローチ」を実施することが効果的であることを提案します。
なお、適応アプローチと医療依存アプローチの違いは本文で述べますが、本書では特に適応アプローチについて深掘りをしていきます。
第2部 状況把握編:自己のストレス状況・特性/職場のストレス状況を把握する
第2部では、個人と組織のストレスを正しく測定し、発生している問題と原因を見極める方法について説明します。やみくもにイベント的に(単発的に、一過性の)メンタルヘルス施策を計画する企業がありますが、それでは成功しません。いくつかの重要ポイントをきちんと押さえていく必要があります。企業でメンタルヘルスの対策を行う目的を明確にしたうえで、組織やスタッフ、会社のメンタルヘルスの実態(メンタル不調者の人数、どの職場に何人いるか、産業平均値と比較して多いかどうか、欠勤、遅刻、健康管理上の休業日数等)を把握しなければなりません。
第2部1章ではまず、簡単にできる個人向けメンタルヘルスチェックとして、「簡易版THQストレス診断(個人のストレスを測定するテスト)」を紹介します。これにより、ストレスに対する個々人の受け止め方の違いがわかり、コーピング(対処法)のヒントが得られます。読者の皆さんもぜひトライしてみてください。
第2部2章では、職場のメンタルヘルスチェックとして正式版THQストレス診断についても紹介します。この診断ツールは筆者が中心となって開発したものであり、さまざまな企業でその有効性が確かめられています。
第3部 ソリューション編:セルフケア/リーダーシップ/人的資源管理によるソリューション
第3部1章ではまず、メンタル不調を引き起こすストレスに対する個々人の受け止め方の違いに合わせたコーピングの仕方を説明します。自分自身の特性に合わせた対応はセルフケアと呼ばれており、メンタルヘルス対策の重要な部分です。
第3部2章と3章では、メンタル不調改善のソリューションを、組織行動学(対人リーダーシップ。OBHあるいはOBともいう)、人的資源管理(人事施策。HRM:ヒューマン・リソース・マネジメントともいう)の面から、実証的事例も含めて説明します。メンタルヘルスの重鎮である、イギリスのT・M・リングは「産業メンタルヘルスの目的は、個人のストレスを最小にし、共同の成果を最大にすることである*3」としています。しかし、職場の実態を見ると管理職はハイパー・チェンジの変化についていくのがやっとで、部下の状態を把握しきれていないのが現状でしょう。あるいは、採用や配置、育成、評価・報奨といった人事施策もなかなかメンタルヘルスにまで手が回っていないのが実情です。
まず第3部2章では、管理職が日常留意すべき対人的なケア(これをラインケアといいます)について説明し、リーダーにとって重要な心がけについても紹介します。なお、こうしたリーダーシップのあり方は、何も目新しいものではなく、実は既存のリーダーシップ理論の延長線上にあるものです。
第3部3章では、人的資源管理、すなわち採用、配置、評価・報奨などに関連した施策を提示します。これらは既存のメンタルヘルス本では取り上げられていなかった領域であり、本書が他の書籍と最も異なっている箇所でもあります。ここでは、メンタル不調を減らすというネガティブかつ限定された側面だけでなく、社員の活性化という観点でこうした問題を考えていくことが、強い組織を生み出すことを説明します。第3部2章で紹介するリーダーや個人の働きかけと合わせ、それをどうミックスすることが、メンタル不調を減らすのか、ひいては活き活きと働けるよい組織の条件となるか、考えるきっかけとしてください。
なお、本書では、適応アプローチがないために発生したトラブルを多数紹介しています。個人のストレスを最小にし、共同の成果を最大にするためには、個人や管理職の努力のみでは限界があります。企業も、医療依存アプローチに頼るだけではメンタル不調の減少につながらないことに気づきはじめてきました。筆者がメンタルヘルスでお手伝いした企業は280社に及びますが、適応アプローチを取り入れている企業が顕著な効果をあげている事実が、その有効性を物語っています。
*1 メンタル不調とは、不安、緊張、イライラ、不適応、意欲の低下、作業能率の低下や、労務の不完全な提供、良好な勤務状態の低下、対人関係から生じるトラブルの増加等を指す。職場、個人、緩衝要因を包括して考える。本書で述べる「メンタル不調」とは、精神疾患や自殺といったことだけでなく、幅広いものである。参考文献:(1)『産業精神保健ハンドブック2 産業精神保健の実際』日本産業精神保健学会・編、中山書店、1998年 (2)『ストレスの事典』河野友信、石川俊男・編、朝倉書店、2005年 (3)『メンタルヘルス事典』上里一郎、末松弘行、田畑治、西村良二、丹羽真一・監修、角川書店、2001年
*2 リチャード・アール(Richard C.B. Earle, Ph.D):1945年生まれ、トロント大学大学院組織心理学専攻博士課程修了。モントリオール大学実験医学研究所でストレス心身生理学を研究。「ストレス学の父」ハンス・セリエ博士とともにカナダ・ストレス研究所を設立、1982年所長就任。産業疲労、職業ストレス病を研究中。
*3 『職場の精神衛生と人間関係』T・M・リング・編、笠松章、坪上宏・訳編、誠信書房、1968年
本稿の著作権は著者に帰属しています。内容の無断転載、無断コピーなどはおやめください。また、私的利用の範囲を超えるご使用の場合は、グロービスおよび出版社の承諾書と使用料が必要な場合があります。








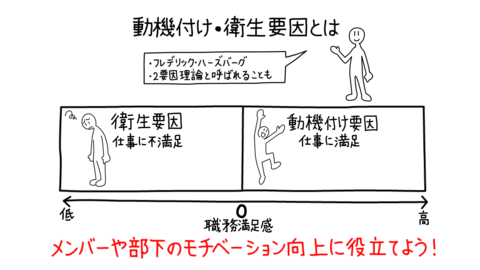



































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
