技術は絶対条件。そこに、自分の「心」を重ね合わせてはじめてプロの仕事になる――。グロービス経営大学院で講師を務める松林博文が、「世界の車窓から」、「鳥になる日」などのテーマ音楽で知られる作曲家・チェリスト、溝口肇氏に聞いた(本稿は、2006年6月30日にグロービス東京校で行われた、USEN「ビジネス・ステーション」(I-26チャンネル)「ビジネス・セミナー」公開収録の内容を再録したものです)。
場の持つエネルギーが音と共鳴する

松林:本日のゲストは、テレビ朝日「世界の車窓から」やフジテレビ「鳥になる日」のテーマ音楽などで知られる作曲家で、日本を代表するチェロ演奏家でもある溝口肇さんにお越しいただきました。早速ですが、ご自身のウェブサイトで、エルサレムを「特別な地」と表現していらっしゃるのが目に留まりました。既に二度ほど行かれているそうですね。
溝口:一度目は、オーケストラのレコーディングのためにイスラエルに行きました。あちらは金曜日の夕方から土曜日の夕方までが安息日で、日曜日にはアラブ系の方々が休むので、金土日は仕事ができなくなります。金曜日の2時ぐらいになるとオーケストラの人たちが帰ってしまうため、僕たちはやることがなく、エルサレム市街を観に行きました。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教といった異なる宗教を信じる人々が同じ所に隣り合わせに入り乱れ、戦いながらも共存している土地です。実際に行って「土地の力」のようなものも感じました。本当に特別な場所ですね。
松林:ごく狭い範囲に何百という宗教が列を成しているわけですからね。本当に不思議な場所だと思います。溝口さんは、寺社や美術館で演奏されることも多いそうですが、土地や場の持つ力というのは音にも反映されるのでしょうか。しかも、京都の寺院などでは和服で弾かれることもあるのですよね。和服を着てチェロを弾くというのは、やはり趣があるものですか。
溝口:「和服では弾きにくいのでは」と、よく聞かれます。先日は和服で袴を履いて演奏したのですが、和服は非常に合理的にできていますから、チェロを弾くには全く問題がないのです。
京都では岩倉実相院と平安神宮で、また先日は東京都美術館「プラド美術館展」で、絵の前で演奏しました。こうした音響を全く考えていない場所で弾く場合と、コンサート会場で弾く場合では、やはり差異はあります。寺社や美術館というのは音楽用の建物ではないので、コンサート会場で弾くより音はよくないとは思うのですが、場所の特殊性が演奏に及ぼす影響というのは大きいのです。
絵が飾ってあるか否かでも場の空気感は大きく変わります。これはプラド美術館展で演奏してみて分かったことなのですが、絵の内容からイメージを受けるというより、絵そのものに存在感があるのです。お客様を前にして弾いているので僕自身は絵を見ることができないにも関わらず、背後や側面に飾られた絵から、ある種のエネルギーのようなものが感じられて、それが演奏の場所を作り上げている。見えない力ですが、それによって演奏が色々な方向に広がるのです。コンサート会場で演奏する場合と違い、ものすごく影響がありますね。
松林:「(パブロ・ピカソがスペインの内戦を描いた)『ゲルニカ』は、あまりにも多くの人に見られて、最近、疲れているのではないか」と、話されていましたね。絵も疲れるものなのですか。
溝口:そう思います。僕は写真が好きで、毎年パリに行っては写真を撮っていたのですが、20年前のパリと今のパリとはかなり違うのです。以前にいい写真が撮れた場所に行って同じように撮影するのですが、何かが違うと感じる。ある写真家が「写真を撮られ続けた街というのは疲れてしまう」と書いていて、その内容にとても共感したのですが、同じ絵、同じ風景なのに見え方が異なる理由は、見る側だけにあるのではなく、見られる側にもあるのではないか、見られる側も疲れてくるのではないか、と考えています。
松林:ある神職の方から、「有名になりすぎた神社は、皆がお祈りに行くので疲れている」と聞いたことがあります。人は自分に都合のいいことばかりを願いますよね。そこに神様がいるとしたら、神様は「もう疲れた」と、片田舎の寂れた所に行ってしまうそうなのです。人が自分のためにだけ祈る場というは、その場所が疲れていくみたいですね。
溝口:僕自身、神社には何かをもらいに行こうとしますから、その話は、よく分かります。逆に、良い演奏のされた会場、ステージというのは、良いエネルギーが蓄積しています。初めて演奏するコンサート会場であっても、それは瞬時に分かりますよ。そこで音楽家が放ったエネルギーと聴衆が心を打たれたエネルギーとが、少しずつ蓄積していくのです。駄目なホールは本当に駄目ですね。ホールのせいにしてはいけないのですが、どんなに良い演奏をしようとしてもエネルギーを吸い取られてしまいます。
松林:皆さん、お聞きになりたいと思うのですが、この場所(グロービスの教室)は、どんな感じですか。
溝口:僕が感じるのは、全くの「ニュートラル」だということです。ニュートラルというのは、とても良いことだと思います。エネルギーがどちらの方向にも動いていきますから。
過去を破壊することから新たな創造は始まる
松林:マーケティングのコンサルタントをしている友人が、「大事なことは頭の中をニュートラルにすること」と言っていました。新しいことを始める際、以前にしたことの残像や記憶が頭を覆っていると、同じようなアウトプットに結びつきがちなので、人によっては気持ちを切り換えるために瞑想をしたり、運動をしたりしますよね。溝口さんは作曲をする際、そうしたことを意識されますか。
溝口:ものをつくる立場からすると、過去のものはすべて忘れて壊していきたいと思っています。例えばドラマの音楽をつくる場合。つくるのがクラシックテイストの曲でしたら、それはそれで懸命に取り組みます。自分の引き出しは全部開けて、何もかもを出し尽くして生み落とす。すると、つくり終えた時点では飽きがきているわけで、次にいただく仕事は異なるものを志向します。例えばロックテイストにするとか。つくる側としてはそういう気分転換を望むものです。では、(依頼されてつくる曲ではなく)ごく個人的なソロアルバムはどうかというと、自分が主体的にしてきたことをすべて壊すわけですが、さらに大きなエネルギーが必要になり、言うほど簡単にはいきません。
これに関して、僕が敬服しているのがピカソです。彼は自分の描きたいものが従来の画風ではもうこれ以上は表現できないとなると、ガラリと違う画風に移行しますよね。それはアーティストの側から見ると大変な冒険です。例えば「青の時代」から「バラ色の時代」に移るその瞬間というのは、新しいものを創造する何十倍ものエネルギーと情熱を、従来からのものを壊すことに注いだのだと思います。なかなか真似のできないことです。僕が気分転換で新たな試みをするのは、あくまで仕事として依頼がある場合です。それは技術とかスタイルでカバーできる範囲のことです。ところが、ピカソは自己の作品、言い換えれば自分自身をすべて破壊してしまう。いつ見ても凄い。それを思うと、僕も頑張らねばと励まされるのです。
僕が仕事を依頼されるときにいつも直面する課題は、依頼者が何を望んでいるのかということです。僕の場合は、プレゼンして売り込んで仕事を依頼されるというやり方ではありません。もらった仕事に全力を注いで、その結果がCMやドラマの挿入曲、CDなどとして残る。それを聴いてくれた方が何年か後に、「あの時のあの音楽がすごく良かったから、今回の作品に合うだろう」と仕事を依頼してくださる。ところが、僕はもうそこから何年もたって違うことをやり始めている。そういうことの繰り返しなのです。自分としては過去の作品はもちろん大切にしたいですし、スタイルとしては守りたいところですが、時代とともにそれにプラスアルファしていきたいと思っています。今の自分と過去の自分のギャップをいかに埋めて、より良いものをつくるか、期待に応えるかというところでいつも苦心しています。
松林:村上春樹さんも「昔の小説を書いてほしい」とよく言われるそうです。彼はその度に、「もう書けない、あのときだったから書けたのだ」と答えるのだそうです。作者自身の年齢だけではなく、時代背景など環境も変化するわけですからね。
溝口:音楽もまさにそうです。15年前にかいたものともう一度と言われても、かけるものではありません。たまに、昔のスコア(オーケストラ全部のパートを書いた楽譜)を引っ張り出すと、自分でも驚きます。作曲にしてもアレンジにしても今よりは技術がない。自分でもそれを分かっていますから、足りない力を補おうと、かなりの情熱と時間を注ぎ込んでいます。譜面づらはすごく下手で、恥ずかしいものですが、それを見ると僕は愕然としてしまいます。今ではできない時間のかけ方、想いの入れ方などが見えてしまうからです。音楽業界も予算削減が進む一方、作品のクオリティーは以前と同じかそれ以上を求められるので、コンピュータを使うなど、色々工夫をしています。若い頃に技術がなくて情熱だけでかいていたものは、その当時にしかできなかったものだとつくづく思いますね。
松林:「料理をおいしくするのは技術か愛情か」と、お友達と議論をした際、「やっぱり料理は技術ではない。愛情の入っていない料理はまずい」と言われたとか。この考え方は音楽にも共通しますか。
溝口:プロとしては、まず技術が絶対に必要です。何が何でも技術です。それプラス「自分」を出せることが必要です。僕の場合は、曲をつくる技術、チェロを弾く技術、アレンジをする技術、色々な技術に加えて、その技術を維持するための努力もしています。そうして初めてプロとしてお金がもらえるわけです。ただ、それだけではなく、さらにプラスアルファ、自分自身を乗せたいと思います。大げさな言葉ですが、愛情とか自分の心とかをいかに乗せられるかが最終的には肝ですね。料理においてもしかり。アマチュアの段階では愛情だけでいいと思います。
人から人へと幸せが伝播する音楽を届けたい

松林:現代美術家である村上隆さんの著書に、「芸術家はもっとマーケティングをしなければならない」という言葉がありました。お金がないと芸術活動もできないという側面もあると思いますが、村上さんの言葉には、もう少し深い意味があるようです。
聞くところによると、アメリカではマッキンゼーのような戦略コンサルティングファームで、MFA(Master of Fine Arts、美術学修士号)取得者のような、芸術を専攻している人たちを積極的に採用するようになってきているそうです。MBA(Master of Business Administration、経営管理学修士号)取得者一本槍ではなく、ビジネスと芸術というような異なる視点を融合させて、それを差異化につなげていこうとしているのだと思います。村上さんが言いたいのは、それと逆の話。ビジネスサイドが芸術家を採って、その幅を広げようとするように、「芸術家は、もっと勉強をして、新たな地平を見出しなさい」ということでしょう。自分の専門外のことも勉強しないと、本当の意味で生き残ってはいけないということですね。
溝口:そうですね。芸術家にも色々な人がいていいと思います。ピカソにも裕福ではない時代がありました。隣人から石を投げられたりするほど変な人だと言われても、彼は自分が信じるスタイルの絵を描いていたかったからそれで通しました。
僕の場合は、芸術面も含めた仕事に関して言うと、自分のソロアルバムは、できれば多くの人に聴いてもらいたいし、もっとCDが売れてほしいので、音楽をつくるときは、そういうことと、自分自身のつくりたいものがどのようなものであるかということの双方を考えます。一方、TVドラマの挿入曲などをつくる際は、自分自身の個性はあまり際立たせてはならないと思っています。ドラマの主人公がいて、脚本があって、映像があって、そのストーリーにいかに感情の起伏を持たせることができるか。どんな音楽が流れたら、観る人にもっと悲しさが伝わるか。楽しさが伝わるのか。そのあたりを中心に据えて考えます。直接、お金にはつながりませんが、これはマーケティングに近いのではないでしょうか。
僕は今、46歳(講演時)で、村上ファンド(M&Aコンサルティング)の村上(世彰)さんと同い年です。彼が記者会見で「お金を儲けることの何が悪いか」と言ったとき、色々なコメンテーターが「儲け方次第だろうな」と発言していましたが、テレビのこちら側で、僕も同じ思いで観ていました。
僕はもちろん音楽は芸術だと言っていますが、暮らしていくことを考えるとお金を儲けなければなりません。音楽それ自体は、人が生存するために直接的には必要のないものです。命の危険にさらされていたり、日々の食べるものにも困るような環境下で、音楽は必要とされません。そういう性質のものに対し、僕はお金をもらっているのです。ですから、根本的にはサービス業ですね。
例えば、ドキュメンタリー番組の一部で僕の音楽が流れても、聴いた人は溝口肇の音楽だとは分かりません。分からなくとも、その音楽をたまたま耳にしたときに「いいな」と思って貰えることが、僕自身にとって、すべてにつながっていくのではないかと思うのです。
コンサートのときに思うのは、「いかに人の心を動かすか」ということです。コンサート会場のドアを閉じた瞬間に、世の中とはまた違う時間軸で演奏会が動きはじめます。自分が演奏している音楽と聴衆がいて、その雰囲気の中では、ドアを隔てた外界と時間や世界観が少しずれる。そのずれた空間の中で、人の心を動かしたい。聴いてくださった人の心をうれしいとか幸せだとかいう気持ちで満たしたい。
そして、コンサートが終わると、ドアが開いて、聴いてくださった人たちが街に散っていきます。そのときに、いい気持ちでいてほしいのです。そうして帰りの電車に乗れば、そのいい気持ちは、きっと、隣の知らない人にも自然と伝播していく。僕はいつもそれを願ってチェロを演奏しています。
これはサービス業全般に通じることではないでしょうか。例えば、タクシーの運転手一人、そのブレーキのかけ方一つで、乗客のその日の気持ちが大きく違ってくる。そして、その気持ちはおのずと人から人につながっていきます。目の前で起きる結果だけではなく、派生するもの、影響を広くイメージすることが大切と思っています。
答えは用意されている、僕たちはそれをただ掘り起こすだけ

松林:ただ体を維持し、命をつなぐために音楽は必要ないかもしれません。けれど、心の部分で必要なのではないでしょうか。例えば、何か音楽を聴いたことで死ぬのを踏み留まった人は絶対にいると思います。明日、明後日の話ではなく、人が長く生きるために音楽は不可欠のものと、僕は信じます。以前に聴いた音楽を、改めて聴くだけで、記憶がフラッシュバックしたり、鳥肌が立ったり、心だけでなく体も反応する。音楽はとても不思議な力を持っていると思います。
溝口:そうですね。もう一つ思うのは、音楽を聴いた感動や心の動きは、聴いたその瞬間が最も大きいということ。もちろん記憶の中にも残りますが、本物の音楽を聴くとのとでは差は歴然です。だから僕たち音楽家、芸術家はずっと存在できるのです。生演奏をしたり、曲をつくり続けることによって、同じ感動を次々ともたらすことができる。そして、ご飯を食べておなかいっぱいになっても、もう一生、食べなくていいということではないのと同じに、聴き手も音楽や絵画などを、ずっと求め続けるように何かプログラムされているように感じます。
松林:古い手帳や日記を見ると、昔の自分がまるで他人のように思えることがあって、人は変わり続けていることがよく分かります。人って面白いと思いますね。
溝口:こういう機会にお招きいただいて、何をお話しすべきか迷いました。僕は仕事を一生懸命に取るというよりも、来た仕事から自分の仕事を広げているという部分がすごく大きいので、皆さんにとって何のチャンスにもヒントにもならないのではないかと思います。
ついこの間も、「和民」を展開する、渡邉美樹・ワタミ社長のドキュメンタリー番組を見ました。本当に自分と真逆で、彼は手帳に将来やりたいことを連ねてすべて達成しています。それを見た瞬間に自分はこれでいいのかなと自問しました。僕は将来、何をしようというものは一切なく、いただいた仕事をとにかく今の自分の最大限の力でどういいものにしていくかだけなのです。
松林:吉本ばななさんの『キッチン』を読んで書いたファンレターに、返事をもらったことがあるそうですね。
溝口:『キッチン』の発表と、僕のデビューがちょうど同じ頃でした。彼女も新人として出たときで、それもあってファンレターを出したら、直筆のハガキが一枚届いて、今も宝物としてとってあります。
『キッチン』は自分の心の奥にあるものを思い出させてくれました。芸術や音楽はすべてそうだと思いますが、「1+1」の答えが「2」であるように、「答え」は既に存在していて、僕たちの仕事はただ、それを見つけ出すだけなのです。コンサートで人の心を揺り動かしたい、幸せにしたいというのも同じです。聴いてくださる方々の心の中には既に、あらゆるもの、あらゆる感情が存在しています。楽しいという気持ちがどういうところから来るのかは、生きてきた過程によって異なっても、音楽で心を揺り動かしてその感情を引き出す助けになりたい。『キッチン』を読んだときも、心の奥深いところですごく共感できるものがありました。
質疑応答 ―当たり前の日常にも発見はある
会場:感覚の使い方に非常に興味があります。曲をつくるときは、聴覚的なハーモニーやリズム感でつくるのでしょうか。それとも、イメージや体の感覚など他の感覚を使いながら曲をつくるのでしょうか。
溝口:若い頃は、情熱でいくらでも曲をつくれました。1日10曲でも。ある程度つくるとストックがなくなります。そうすると、絞り出すのですが、乾いた雑巾をいくら絞っても水は出てきません。心を潤わせるために、自分の引き出しに色々なものを入れていきます。旅行をするとか、特別なことをするのではなく、99%は日常生活からイメージを膨らませます。何かを見たり、聞いたり、人としゃべったり。僕は人としゃべるのが一番好きですね。
例えば、パリを旅してきた人が、僕の知らない風景について話したとします。何度もパリに行っているのにその風景を知らないと思うと、自分の中にイメージができます。知っているものは、自分の中で制約ができてしまいますが、知らないからこそパッとイメージが広がる。その瞬間をストックしておきます。その時にメロディーが出てくることもあります。例えば、ドラマの映像に対する曲をつくる場合は、映像を見たときに、そういえば引き出しの中にあの話があった、今回はそのイメージでつくってみようかと、大体そういうことをします。
会場:日常の生活でリズムやハーモニーなど何か感じるということはありますか。楽譜がパッと出てくるのでしょうか、それともリズムが出てくるのですか。
溝口:リズムより、まずメロディーです。メロディーとコード(和音)の二つを重ねてつくることが多いですね。曲をつくる手法はいくらでもあります。今ここで何かをつくるとしたら、メロディーを何にしようかと考えます。例えば最初の音をラの音で始めよう、ラの次は何の音にしようかと…。半分技術、半分イメージでつくっていくことができます。
「イメージはどこからくるのか」という質問はすごく多いのです。繰り返しになってしまいますが、僕の場合は日常生活からです。日常生活が一番面白い。例えば、同じ道を歩いたり、運転していて目に入るものが、いつもと違うと感じる。そんなことが頻繁にあります。それは、朝起きた時の自分の感覚がどういう状況かで左右されたりするのです。何か悲しいことがあると、それだけで街を歩く時も違う面が見えてきます。例えば、「こんなところに紫色の花がある」と花の色に反応していることもあります。その日の状況ですべての感覚が違ってくると思うので、毎日同じものを見ていても違うのだと思います。
会場:芸術家の方は、調子のよく出る時と出ない時があると思います。溝口さんの中で、すごく乗るようなやり方、調子の出るようなやり方はあるのでしょうか。
溝口:それがあったら僕も本当に知りたいです(笑)。コンサート会場でも、リハーサルの時は調子がいいのに、お客さんが入ると会場の響きが全く変わることがあります。舞台に出て、1音目を弾いた瞬間に、「うわっ、違う」というのはいくらでもあるのです。それが、「全然違う、音が届かない、この辺で音が留まっている」と思う時は一番苦しいですね。それでも1時間半から2時間演奏しなければならない。もちろん自分が考えていることはお客さんには分かりませんが、一生懸命、修正していきます。どういう音の出し方をすればもっと遠くに音が飛ぶだろうかとか、弾いている瞬間、瞬間に修正するのです。F1ドライバーなどと一緒ではないでしょうか。同じカーブでも、路面状況によって1周目と2周目の通過速度が違ってきます。例えばタイヤのカスが路面に付着したり、雨が降ったりが影響するでしょう。僕の楽器も雨が降れば全く状況が変わります。もう本当に、その瞬間、瞬間で変えていきます。
僕もプロとしてお金をもらっています。プロというのは自分に100%の力があるとすると、必ずその80%は出さなければならない。それは自分の中の絶対条件です。風邪を引いていても、何があろうとも80%出せるというのがプロです。もちろん人間ですから、色々な条件がよくて120%になるときもあります。これが自分の力だろうかと思う時もあります。それは神様のプレゼントとしてとっておきますが、基本は、80%は出せるということですね。
会場:「歳を取るにつれて、経験を重ねるにつれて技術は上がっていく。それでもやっぱり心は必要だ」というお話を先ほどされました。ここにいらっしゃる方は皆さん、経営に関する技術を取得するためにこういう学校に来ていらっしゃると思います。技術を身につけながら、最初に持っていた情熱、荒削りな心の部分を、どのようにして失わないようにしていくかを考えていらっしゃると思います。心を失くさないために何か工夫をされていることがあれば教えてください。
溝口:それは僕も習いたいですね。僕の演奏に関していうと、実は技術は学生の時代と比べ、今のほうが下がっています。指が回って、何時間も弾いていられるという意味では、20歳代が一番強いのです。そこからどんどん落ちています。それは体育会系の人間と一緒でしょう。短距離走者に100メートルの最高記録を出すことのできる年齢的なピークがあるのと同じで、チェロを弾くにも肉体が必要です。一日ずっと練習をしていても絶対に落ちてきます。
ただ、技術とか体力とかは落ちますが、それを補うものがついてきます。何十年も弾いてそう思うのです。それはどちらかというと感情や心の部分で、自分が表現したかったものが表現できるようになりますね。例えばその表現方法は、技術を持ってできるかと言えば、できなかった。逆に言うと、僕はそんなにテクニックがある方ではないのですが、「テクニックがあるがために見せられない」こともあったのではないかと思っています。
ですから、僕が今もっと指が回って、速い曲がガンガンに弾けるのであれば、多分その曲を弾いていると思います。そういう曲が弾けなくなってきた時に、もうちょっとスローな曲を弾く。そのゆっくりとした曲を弾いている中に、必然的に自分の心を出したいと思う。それで音に乗りやすくなるのです。この先、テクニックや体力はもっと落ちていくはずですが、プラスマイナスゼロなのかなという考え方をしています。これが答えになるでしょうか。これが経営にどう関わるかというのは、ちょっと僕も分からないのですけれども…。
松林:今日は本当に楽しかったです。どうもありがとうございました。








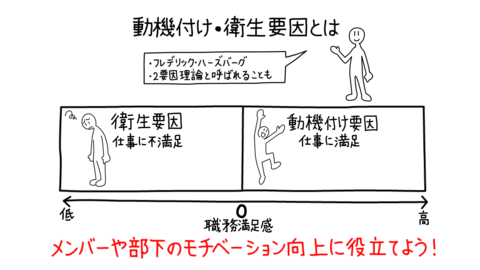






























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
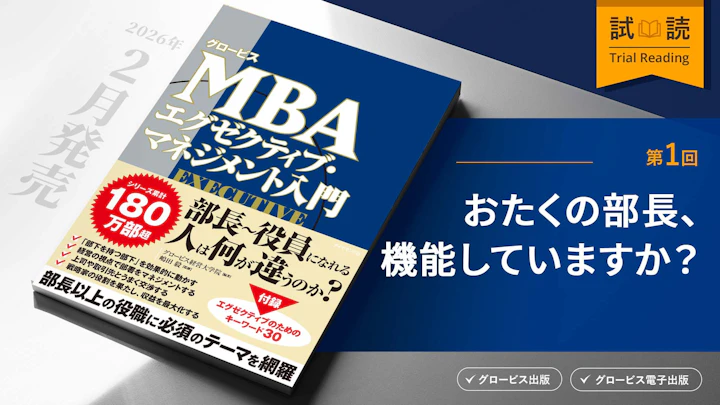
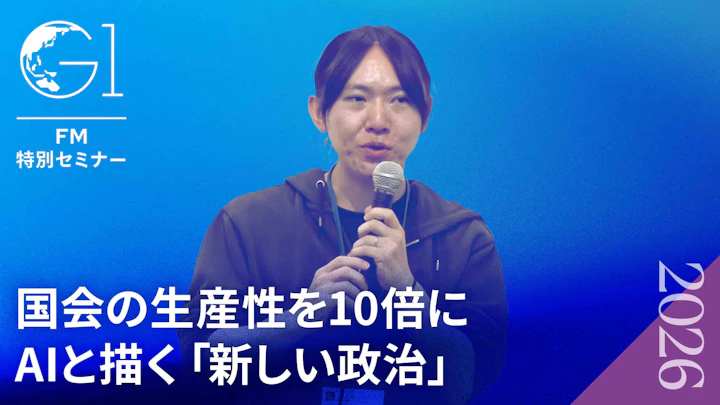


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
