日本が欧米列強の仲間入りを果たしつつあった大正年間、財閥系商社を凌駕する業容を誇る、日の出の勢いの新興商社があった。神戸を地元とする鈴木商店である。同社は、第一次大戦時には「スエズ運河を通る船の10に1つは鈴木の船」といわれるほど大々的に事業を展開する。そのロンドン支店長として辣腕を振るい、同社を「世界のスズキ」として急成長させた中心人物が高畑誠一である。
鈴木商店自体は、関東大震災の影響などもあって1927年に倒産してしまうが、翌年、高畑は仲間と共に日商(日商岩井を経て、現・双日)を設立する。わが国の商社の歴史は彼抜きには語れない。
桁外れの取扱量「日本で初めて」の数々
高畑は神戸高等商業学校(現・神戸大学)を卒業後、当時、中堅商社だった鈴木商店に入社、直ちに頭角を現す。その名を広く知られるようになったのは1912年、25歳のときにロンドン支店に赴任してからだ。
当時はロンドンが世界の商業の中心であり、世界中の精鋭がロンドンに集っていたが、その中でも高畑の活躍は群を抜いていた。第一次大戦が勃発したと見るや食料や鋼材を大量に買い付け、ヨーロッパの列強に売りつけた。ライバルの大手商社が二の足を踏む中、彼等とは一桁も二桁も異なる量を扱い、現在の価値で数百億円にも及ぶ取引を次々と成立させていった。
この活躍が認められ、高畑は4年後の1916年、20歳代の若さでロンドン支店長に就任する。その時には既に、つい数年前には「無名」に近かった鈴木商店は売上高日本一の商社になっていた。
高畑には数多くの「日本人で始めて」の冠がつく。たとえば、本国を介さない三国間貿易を日本人で初めて行ったのは高畑である。当時は、積荷を降ろした船は、そのまま積荷を積まずに元の港に帰っていた。高畑はそこに目をつけ、積荷を降ろした船に新しい積荷を載せた。しかも、元の港に戻すのではなく、別の目的地に向かわせるというアイデアを発案、実践した。これにより、取引量は急増する。
また時には、出航時点では目的地を決めず、航海中に売り先を探すという芸当もやってのけた。積荷に加え、船まで売却してしまうという荒業を演じたことも一度や二度ではない。
これは高畑という人物の、枠にとらわれない思考の柔軟性、好機と見るや果敢にリスクをとる大胆さ、抜群の行動力の賜物と言えよう。
没落の始まり挫折、そして再起へ
瞬く間にわが国を代表する商社へと伸し上がっていった鈴木商店であるが、その没落も早かった。もともと戦中の投機的事業が急成長の源だったため、戦時の好況が過ぎてしまうと、商いは急激に縮小する。また、合理的な経営ではなく、山師的な個々人の才覚に頼っていたツケが一気に噴出した。
鈴木商店は、規模こそ三井や三菱を凌いでいたが、経営のありようは文字通り「個人商店」の面影を引きずっていた。帳簿の仕組みは完備しておらず、意思決定の仕組みも秘密主義の中にあった。また、数千人の従業員を抱え、旺盛な資金需要があったにもかかわらず、経営陣は株式の公開に抵抗し、合名会社であることにこだわっていた。
こうした状況を憂いた高畑は、鈴木商店の経営近代化を唱える急先鋒となる。また、株式を公開することで資金調達するとともに経営の透明化を行うよう、経営陣に強く迫る。
これに抵抗した守旧勢力の代表格が鈴木商店の大番頭、金子直吉だ。「これまでこのやり方で成長できたのだから、これからも株式公開などは必要ない。急激な経営合理化も不必要」と彼は考えていた。世界の潮流や時代の変化が見えていなかったのだ。
改革派と守旧派の攻防が一進一退を繰り返す中、業績は着実に悪化していく。最後のダメージとなったのは1925年の関東大震災だった。2年後の1927年、震災手形の処理をめぐって主力銀行の台湾銀行が貸付金を引き揚げる。資金調達を銀行融資に頼っていた鈴木商店はなすすべなく、その劇的な興隆の歴史に幕を下ろした。
鈴木再建では大きな挫折を味わった高畑であるが、しかし、彼の「貿易立国日本」にかける思いはいささかも衰えなかった。
「資源のない日本が世界に伍していくためには、工業と貿易の興隆が必要不可欠。それは日本にとっても海外諸国にとってもメリットがある」というのが彼の揺ぎない信念だった。
彼は何人かの元・同僚と共に翌年「日商」を設立する。そして10数年後には再び大手商社の仲間入りを果たし、新たなステージへと踏み出していった。
硬直化した組織を変革する困難
高畑の生涯を概観して著者が感じるのは、硬直化した組織、過去の成功体験に縛られた組織を変えることの難しさだ。高畑ほどの実績と社内での発言力をもってしても、旧態然とした鈴木商店を変えることはできず、再生のために倒産という代償と契機を必要とした。見方を変えれば、鈴木商店の再建プロセスがもっと長引いて倒産が遅れていたら、その後の日商の歴史はなかったかもしれない。
近年、わが国でもMBO(マネジメント・バイアウト)など、「衰退する企業に有能な人材を道連れにする」ことを避ける道筋が増えてきたものの、実際にそこまで踏み切れるケースはまだ多くはない。もちろん、企業の変革は重要なテーマであり、有能な人材が取り組む価値は高いが、見極めを誤ると、時間とエネルギーと才能を浪費するだけに終わってしまう。
人材不足が叫ばれるいま、高畑のような人材を狭い枠に「死蔵」せず、いかに社会全体として活用するかが切に問われている。
参考文献)
・桂芳男『総合商社の源流 鈴木商店』 日本経済新聞社、1977年
・城山三郎『鼠―鈴木商店焼打ち事件―』文藝春秋、1975年




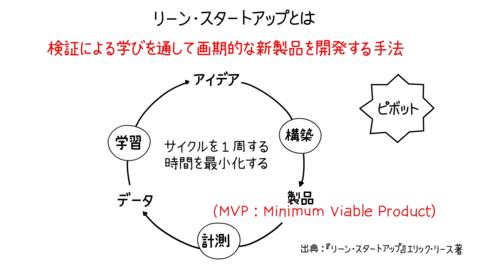































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)





