「わが国の近代史を概観して『事業創造』における第一人者を挙げよ」と問われたとき、最も多くの人が挙げる人物は誰だろうか。
本田技研工業の本田宗一郎やソニーの井深大、盛田昭夫らと並んで多数の支持を集めるであろう人物の一人が、明治から大正、昭和にかけて日本の産業勃興をリードした渋沢栄一だ。
渋沢の業績を見て圧倒されるのは、立ち上げに関与した企業数と、その多種多様さである。渋沢はその生涯にわたり、数十の産業分野で、500社とも600社とも言われる企業や組織の設立、運営に関わった。
実名を挙げれば、1873年の第一国立銀行(後の第一銀行。現在は統合を経てみずほ銀行)を皮切りに、王子製紙(製紙)、日本郵船(海運)、新日本製鉄(製鉄)、サッポロビール(食品)、帝国ホテル(ホテル)、東洋紡績(紡績)、清水建設(建設)など、枚挙にいとまがない。(注:順不同。企業名は現在のもの)
なお、最初の第一国立銀行は、「国立」という文字から誤解されがちだが、いわゆる国営企業ではなく、日本初の本格的株式会社組織で、かつ最初の銀行であった。
特筆されるのは、渋沢が財閥の傘の下に子会社や孫会社、関連会社を展開して一大コンツェルンを築いたのではなく、多くの場合、それぞれの企業を別個に立ち上げていることである。これは、先に挙げた企業群が現在、必ずしも同じグループに属して強い紐帯を維持しているわけではないことからも理解されよう。
渋沢は、ある産業が「日本にとって必要であるにもかかわらず、未開あるいは貧弱」と見るや、資金と人材を投入して企業を興した。その際には、自分がマジョリティを握るのではなく、広く資本を募り、経営はしかるべき人材を選定し、委譲している。
さらに、土地や設備などの所有を追求することなく、あくまでプロデューサーに徹したことも大きな特徴である。このような渋沢の行動を支えた哲学や信念については、後で触れる。
激動の渦中にあった青年期
渋沢は1840年、現在の埼玉県深谷市に富農の家の嫡男として生まれた。そして青年期を、徳川幕府の崩壊、明治国家の建設という激動の中で過ごした。
当初は攘夷派として活動した渋沢であったが、紆余曲折を経て幕臣となり、徳川慶喜の知遇を得る。1867年、慶喜の命でフランスヘの視察に参加したことが、彼の運命を大きく左右することになった。
渋沢はヨーロッパで約2年間を過ごし、世界の最先端を行く自由主義・資本主義社会に触れ、さまざまなものを吸収した。
彼の地で渋沢が衝撃を受けたのは、総じて貴賎の差が小さく、商人の地位が高いこと、出自によらず本人の才覚次第で出世しうること、「ぜひうちの国から輸入してください」と国王自らが自国製品を売り込む姿を目の当たりにしたことなどである。
士農工商の身分制度と世襲、「武士たる者が金儲けの話など…」という文化で育ってきた渋沢にとって、万事が驚きであったことは想像に難くない。
渋沢は帰国後まもなく、明治新政府の要職にあった大隈重信の紹介で大蔵省に奉職し、井上馨の右腕として活躍する。30歳そこそこにして省内屈指の実力者となり、その気になれば政府高官として洋々たる前途が開けていた。
しかし数年後、渋沢は井上馨とともに大蔵省を離れる。その背景には、明治政府の巨頭・大久保利通との確執などがあったようだが、当時の感覚からすれば、政府の高官を辞して野に下ることは、いまの数十倍も「破天荒」で「もったいない」ことであった。
退官後、渋沢はただちに第一国立銀行を設立する。33歳のときのことだ。そしてこれが実業家・渋沢栄一のスタートとなったのである。
未来志向の意思決定と先進的な事業哲学
渋沢の業績からは、彼が常人離れしたエネルギー、バイタリティを持っていたことがわかる。さらに、思考と処世の柔軟さ、先見性の高さ、そして信念の強さも、よく指摘される特徴である。
渋沢の柔軟な思考や時代を見る目の確かさは、攘夷の志士→幕臣→明治政府高官という経歴からもうかがえよう。人によってはこれを変節、豹変ととる向きもあるが、筆者はそうは思わない。
情報収集が困難であった激動の時代に良質の情報を得てその意味合いを探り、未来を洞察し、「何をすれば自分を生かしつつ、世のため人のためになるのか」を考え抜いたうえで、渋沢は意思決定をしていたと考えられるからだ。
当時、先行きのことなどまったく考えない人間、考えても保身から決断できない人間が圧倒的多数を占めるなかで、渋沢ははるかに勇気ある行動をとった。
渋沢が自らの行動原理とし、率先垂範した信念は、驚くほど先進性に富んでいた。その中で、いまの日本人にも参考になるものをいくつか挙げてみよう。
・民間から活発に(ベンチャー)事業が興らなければ、国の繁栄はない
・大資本による独占は産業の発展を阻害し、結局は国益を損なう
・一人の才覚に頼るのではなく、多くの人間の英知を動員してこそ事業は伸びる
・社会に利益をもたらさないような事業には価値がない
・実業家たる者、あるいは銀行家たる者にモラルは不可欠である
こうした信念が生まれた背景には、幼少時より親しんできた「論語」の素養、欧米での見聞、あるいは宿敵、三菱財閥の岩崎弥太郎に対するアンチテーゼなどがあったという。
これらは相反する要素も併せ持っている。とりわけ、論語の精神と、プロテスタンティズムをバックボーンとする欧米貢本主義には、対立する点も多い。しかし、そうした矛盾を自分なりに消化して日本に移植しようとしたところに、渋沢の真骨頂がある。
今日の日本に必要な渋沢の精神
100年前に渋沢が提唱・実践していたことが、いまなお声高に叫ばれる日本の資本主義経済とは何なのだろうか。
たしかに、明治や大正に比べれば多くの有能な人材が民間企業で活躍するようになった。GDPの額を見ても、日本の産業が世界経済に占める比重は大きい。その一方で、「寄らば大樹の陰」というような大組織依存型の考え方も根強く存在する。「ベンチャーブーム」は幾度か起こったものの、それが結果を伴って継続したことはいまだかつてない。
乱暴な言い方をすれば、たしかに日本経済は大きくなったものの、それは渋沢の考える(日本的)資本主義の精神が根づいたからではなく、勤勉かつ知的レベルの高い国民性、地政学的・人口動態学的アドバンテージ、国際政治上の偶然など、いくつかの幸運が重なった結果にすぎないのかもしれない。
しかし、もはや幸運だけに頼ってはいられなくなったのが、バブル以降の日本である。明治維新、戦後に匹敵する第三の危機的状況を迎えているいまこそ、渋沢の精神をより広く啓蒙し、実現できる人材を育てたいものだ。
最後に付言しておきたいのは、渋沢が社会活動家としても後世の範となっていることである。特に晩年期において、渋沢は企業活動以外にも、教育や医療・福祉の充実、国際交流の発展に尽力した。ここでも渋沢はプロデューサー的役割に徹しながら、多額の私財を投じている。
関東大震災のときには、83歳の老体に鞭打ち、パニックに陥った群集の中で身の危険を顧みず、被災者支援に走りまわったという。こうした点も、ややもすると小市民的な蓄財や私欲に走りがちな今日の企業経営者や上級公務員にはぜひ学んでいただきたいものだ。
渋沢が「私」より「公」を優先させたことはしばしば言及されるが、筆者はそれに加え、「未来への贈り物」を真剣に考えていた生き方に、強い共感と畏敬の念を抱くのである。




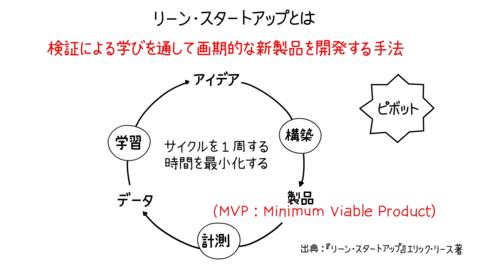




























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)





.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


