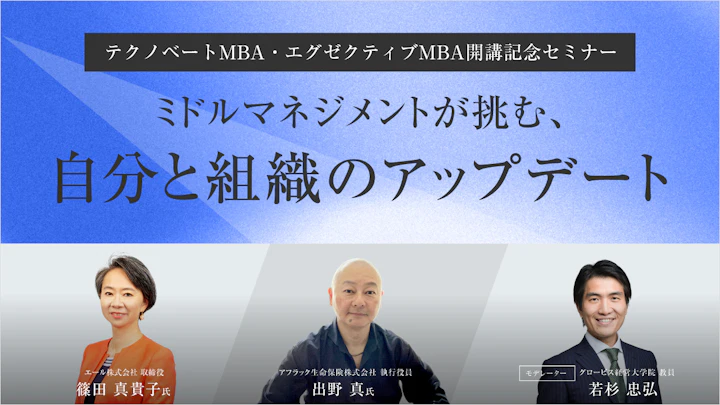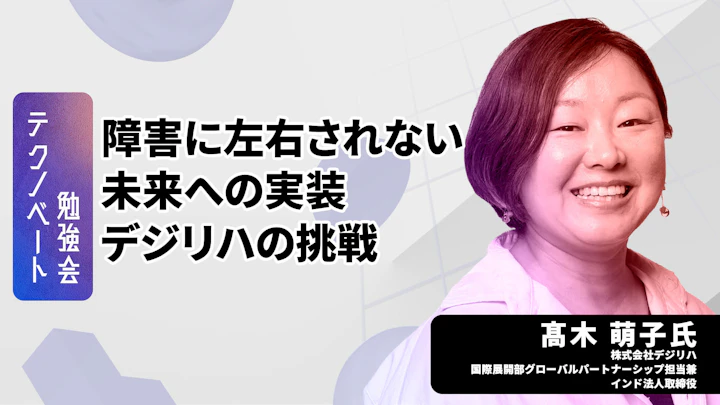160万台売れたクッション型マッサージ機
「顧客はドリルが欲しいのではない、穴が空けたいのだ」。
消費者が真に必要としている「ニーズ」と、それを実現するためのモノである「ウォンツ」の関係を最も端的に表した言葉である。「○○をください!」と言われたら、「ハイどうぞ!」とモノを売るのではなく、真のニーズを探り当てて最適なモノを提供しなければならないということを説明する時に用いられる。
2011年2月4日付日経MJコラム「着眼着想」にも取り上げられた、大ヒット商品の「ルルドマッサージクッション」。
日経MJの記事によれば、「使用場所を選ばないクッション型」には「本格的なもみ心地」が秘められている。「通常のクッションとしても使える」だけでなく、「寝そべっても座っても身体に合う形」を求めて「試行錯誤を繰り返して現在のピラミッド型にたどり着いた」という。また、「ちょうどマッサージしてくれる人の手の温度」のヒーター内蔵のもみ玉を装備しているという。
う〜ん、36センチ四方のその小さな商品には、何ともうれしい機能が満載だ。
もう少しその魅力を細かく分解して価値構造を明らかにしていこう。
消費者がマッサージ機という「ウォンツ」に求める「ニーズ」は「カラダを楽にしたい」ということだろう。つまり、「やさしいマッサージ」が商品の「中核価値」だ。それを実現する「実体」は、場所を取らずにカラダにフィットする形状と、温かなもみ玉。さらに商品の魅力を高める「付随機能」が、通常のクッションとしても使えることだ。
「2009年9月の発売から累計160万台を売る大ヒット商品に」「昨年12月のクリスマスシーズンには出荷数が30万台を超え」というから、とんでもないヒット商品に化けたわけだが、商品化までは大変な道のりであったという。
その開発ドラマを、2011年1月8日付大阪読売新聞の記事「[ONタイム・仕事師たち]ルルドマッサージクッション」が詳細にレポートしている。
常識にとらわれるオトコと顧客の「ほしい」に耳を傾けるオンナ
記事を要約すると、開発や企画を推し進めたのは、女性チーム。ベテラン営業マンの「売れるわけがない」という強い反対に遭い、家電量販店からは「ひと目でマッサージ器とわかるものを」と一蹴される。
社内の男性社員からは「パッと見たとき用途が不明」「電源の位置がわからない」などの声も寄せられた。
それでも、「買い物の権利の決定権の7割は女性にある」と、女性視点からの商品開発にこだわった。
最終的には同社の会長がゴーサインを出し、本格的な商品化が決まったという。
まず思いを致すのが、男と女の深い溝。かくも、男と女の間には黒くて深い川がある如く、わかり合えないものなのか。女性開発担当者は、エンヤコラと川を渡る船を出してRowandRowと漕いだりはしなかった。
(ちなみに黒くて深い川の話がピンとこないお若い方は、直木賞作・「火垂るの墓」、童謡「おもちゃのチャチャチャ」作詞の野坂昭如をググってほしい。「黒の舟歌」という曲だ!)
「カラダが楽になりたい」というニーズには男女差はない。また、フィリップ・コトラーの「製品特性3層モデル」で分解して考えた「価値構造」で考えても、受入れがたい価値の差異はないはずだ。しかし、決定的に違っているのは、オトコは「パッと見て効果・効能がわかりやすい」という「機能美」を求め、オンナは「マッサージ機にすがっているんじゃないわよ」的な「らしくなさ」を求めていたのだ。
そしてまた、インプリメンテーション(実行)のフェーズがいかに大切か、思い知らされる事例でもある。マーケティングや商品開発の職場は“花形”と思われ、学生から人気の高い職種の一つではあるが、実はひたすら社内調整に追われることも多い。
いくら頭の中で素晴らしい戦略が描けても、素晴らしい商品を思いついても、それを社内政治の中で実行まで移すことがいかに難しいか。R&Dを説得し、営業に納得してもらい、流通を口説き落とす…。その過程の中で、エッジが削られ、小さくまとまった商品になってしまうことも少なくない。もちろんエビデンスも用意はするが、そんなもの解釈次第でいかようにでも反論されてしまう。
リーマンショック以降MBA教育が見直される中で、「実行する能力」が問われなおされている。頭の中で描いたものを、実行のフェーズまで移すある種の政治力がないと、結局変革やイノベーションは起こせないからだ。
今回のデザイン開発コンセプトが「かわいいけれど甘すぎない」マッサージ機であったというが、社内の男性陣の意見を振り切った結果、商品は大ヒットした。発売から1年以上が経過した今でも売れ行きに衰えがないというから、担当者の慧眼、実行力には脱帽だ。
「仕事の合間に独自に開発を始めた」という、あらゆる反発にあってもめげない、信念を貫き通すオンナの胆力や執着心。草食化した男子も、学びたいものである。