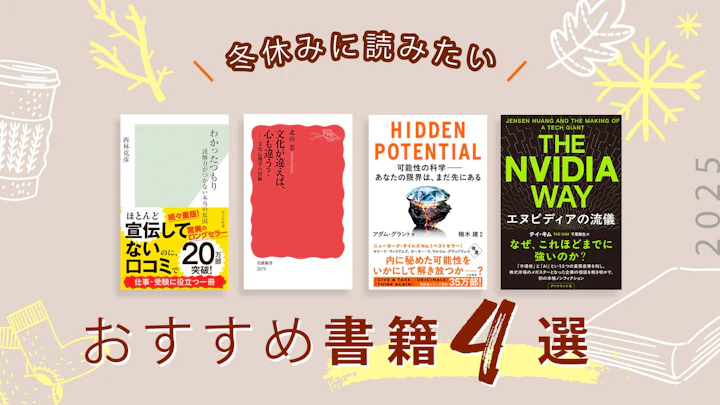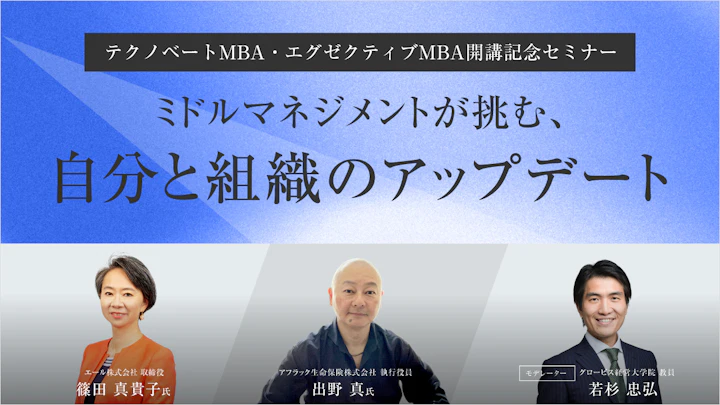前回のコラムでは、さまざまな業界で、市場の成熟化にともない、商品の寿命が短命化、成功率が低下するという“コンテンツ産業症候群”に巻き込まれていること、また、新商品や新企画に対する経営陣のリスク感度が上がったことによって、現場から商品企画を出しにくくなっているという話を述べました。
今回は、そうしたジレンマの背後にある深刻な問題について、少し考えてみたいと思います。それは、企業における「商品開発」という営みに対する、経営陣と現場のあいだにある認識ギャップです。
 経営者の企画介入はヒット商品を生まない?
経営者の企画介入はヒット商品を生まない?
前回も述べたように、経営者から見たときの「新商品開発」というのは、失敗するリスクが非常に高く、ファイナンス的な投資価値は限りなくゼロに近いわけです。そうすると、経営者としてはそのリスク察知能力を生かすためにも、また投資家への説明の必要性からも、商品開発のプロセスに関与して、その成功率を少しでも上げようと試みるものです。
商品開発のリスクを少しでも下げようというこうした努力そのものは、あながち問題とも言えません。実際、私が取材したことのある範囲でも、経営陣が新商品に関してまったく注意を払わなかったために、現場が暴走して企業全体のブランドイメージからずれた商品を作って発売したり、とてもその事業規模に見合わないような投資計画を作って大損を出したりといった失敗は、枚挙に暇がありませんでした。
しかし、経営者が良かれと思って口出しした場合でも、実際にその介入に直面した商品企画担当者たちの現場レベルの声を聞くと、むしろ「ヒット商品を生み出す」とは逆の効果があると受け取られていることが多いようです。
著名なヒット商品を開発した企画担当者に商品化までの経緯をうかがうと、たいてい『社長には「こんなもん、売れるわけがない」と猛烈に反対されたが、押し通した』「経営トップから製品の細かい仕様に口を出されたが、すべて断った」といった武勇談?のようなものがこぼれ出てきます。
中には、『経営者の意見を聞いて修正を加えた商品は必ずといって良いほど売れない。売れる商品は、担当者が自信をもって「こうでなければだめだ」と言いながら作ったものだけだ』と言い切るマーケターの方もいます。これらの話を聞くと、どうも経営者の企画介入は「ヒット商品を生まない」方向に作用することが多いのではないかとさえ思えてきます。
しかし、考えようによってはこうした介入も「経営者の反対という壁を乗り越えられるほど強い意志で作られた企画でない限り発売させない」というかたちで、消極的な意味ではありますが企画失敗のリスクを低減させているのかもしれません。その点は評価できなくもありません。
ヒット企画を「手柄」にしたがる経営者の重大な誤り
それよりももっと深刻な問題だと思うのは、「成功させたい」という経営者の思いが行き過ぎて、あるいはもっと別の政治的な理由から、現場が一生懸命作ってヒットさせた商品を「あれは私がアイデアを出してやらせた企画だ」などと自分の手柄にしようとする経営者が時々いることです。
現場が一生懸命ひねり出したアイデアに、会議でちょっとアドバイスしたり、「やってみろ」とゴーサインを出しただけなのに、さも自分がすごく重要な決断をしたかのように勘違いしてしまう。たとえ実際に自分がアイデアを出して、それがヒットを実現したとしても、こういう発言をする経営者は、もはや“経営者失格”のレベルと言っても良いだろうと思います。
新商品の開発とマーケティングを成功させるためには、アイデアを出したり企画を立てたりする段階の知恵だけでなく、実行段階の現場の努力が不可欠です。その中には例えば、社内外のボトルネックとなる部分を見つけてそれを乗り越えるために関係者を必死で説得したり、事業計画を製造から営業までの現場のオペレーションにきっちり落とし込んで実行させるために汗を流したり、部門間の激しい利害のぶつかり合いにも「顧客にこの商品を届けたいから」という気持ちで耐え忍んだりといった、日の当たらない行動や見返りのない協力などが含まれます。
したがい、新商品の成功の賞賛はまず一義的に、実行に汗を流したすべての現場の人間に対してなされるべきですし、そうした賞賛を得られることにより、クリエーターや技術者や営業マンといったすべての人々が「成功のためにはチーム全員が力を合わせることが大事だ」ということを学習し、成長していくのです。この学習、成長がなければ、いかなる組織も連続して成功・成長を遂げることなどできません。
つまり、新商品開発というのは、現場レベルで見ればその成功・失敗という「結果」だけでなく、人材と組織が成長していく「プロセス」としての重要性が非常に重いということが言えます。挑戦→格闘→達成→賞賛→さらなる挑戦…と続く成長のサイクルの「賞賛」だけを横取りしようとする経営者は、その意味では新商品開発に伴う経営リスクを気にしすぎるあまり、本来その営みによって達成すべきものを取り違え、かえって現場の組織力を衰弱させているとすら言えるのではないかと思うのです。
新商品開発や企画というもののマネジメントがうまく回らない根本的な原因に、経営者と現場の間にその意義をどこに見出すかという視点の違いがあるということを述べました。
次回は、こうした問題の所在から示唆されるジレンマの脱出方法について、少し考えてみたいと思います。(つづく)
▼「マーケティングの泉」とは
毎日手に取る商品から、新しいサービス、気づかず消費者が誘導される購買行動まで、グロービス経営研究所研究員川上慎市郎が新しい視点でコメントする。
▼「グロービス経営研究所コラム」とは
グロービス経営研究所の研究員がその知見や日々の活動を発信するブログ。「変革ファシリテーション道場」「組織学習とイノベーションなど専門分野に特化した内容や、「知的好奇心・大阪通信」「当世研究員気質」などのコラムがある。


































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)