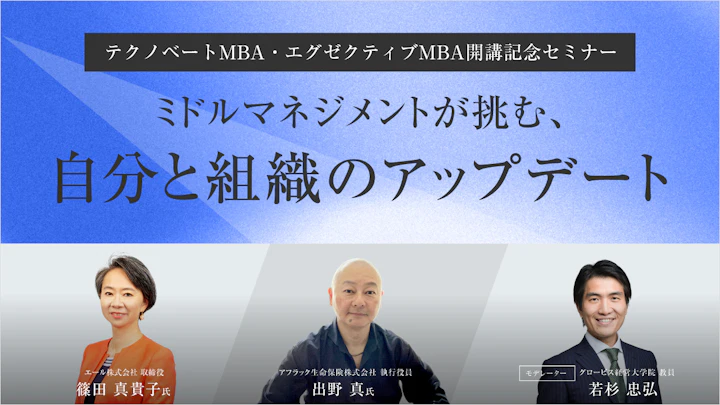今回は、100年に1度の金融・経済危機の“犯人”として、MBA教育を挙げる論調について分析、また次代の企業経営の在り方についても考える。
MBA教育の何が問題だったのか
昨年(2008年)12月に、米国ビジネスウィーク誌のネット上で、米国のMBA教育界を巻き込んだ「100年に1度の金融・経済危機」の犯人探しが行われた。この時の議論を踏まえ、以下に筆者なりの意見を交えながらその論点をまとめるとともに、企業とは何か、そして企業経営者はいかに対応すべきかを考察してみる。
(1) 経営者のモラルの欠如
株主は株主総会を通じて経営を委任する取締役を選任するが、株主と取締役の利害は必ずしも一致しないので、それが一致するような仕組みを構築する必要がある(エージェンシー理論)。この仕組みの一つとして、業績連動報酬制度が導入された。経営陣の報酬を業績に連動させることによって、経営陣に対し、業績を上げ、株価も上がるよう経営するようインセンティブをあたえたわけである。
また、社会的にも、株価を上げることが経営の目的であるといった「株主価値(株価)至上主義」の風潮が蔓延した。この結果、金融界を筆頭に経営陣は、株価を上げ、その成果として多額の報酬を手にするために、いかに短期的な利益を捻出するかに知恵を絞るようになった。経営陣は株主のために業績を向上させ株価を上げるとの「美名」のもとで、次から次へと生み出された色々な(ハイリスクでハイリターンな)金融商品を使って短期的な業績作りに邁進し、“素晴らしい業績・株価”に連動して多額の報酬・退職金を懐に早々に退任してしまった。そして、今回、そのほころびが表面化したということである。株価至上主義を主導し、カリスマ的なリーダー経営者作りを促進したのが米国の経営大学院であり、反省せねばならないという自戒の念である。
(2) 時代にそぐわない経営理論
ファイナンスの世界では、リターンは正規分布し、そのリスクの大きさ(リターンの標準偏差)は測定可能であることから、ポートフォリオを組むことによってリスクをコントロールできるとされている。この観点からは、自然科学である物理学や数学の法則が社会科学であるファイナンス理論でも例外なく通用する(つまりリスクは統計学的手法で管理可能)と過信したことが、今回の金融危機の原因となったといえる。
しかしながら、現実のビジネス界ではリターンは正規分布ではなく、一方に裾野の広いベキ分布の形態をとっていることから、統計学的なリスク管理手法は通常の範囲内では有効であっても、非常時には有効とは限らない。金融界に移籍した数学界や物理学界の俊秀が、自然界の法則を創った神の手を自分たちも持っていると過信し、その理論を金融界に持ち込み、そして数学をよく理解していない投資銀行家が自己の利益のために、これらのクオンツが作り出す金融商品を次々と世の中に送り出していったことから、今回の危機は発生したのではないか。投資銀行家が、どこまで高度な数学・統計理論を理解していたか、またその理論がどこまで金融界に適用可能かを把握していたのか、大いに疑問が湧くところである。
モダン・ポートフォリオ理論に立脚したファイナンス理論が時代にそぐわなくなっているのであるから、時代にマッチした経営理論を開発していく必要があるという反省の弁である。『ブラック・スワン』(ダイヤモンド社)という書籍において、著者のナシーム・ニコラス・タレブマサチューセッツ大学教授は、「確率分布の裾野に位置するような滅多に起こらないが、起こると甚大な損害をもたらす予期されていない危険」に言及しており、この書籍は今回の危機が顕在化するタイミングで出版され話題となったことは記憶に新しい*1。
(3) 更に混乱に輪をかけたデリバティブの存在
本来、本体である原資産のキャッシュフローのバラツキを軽減するために開発されたデリバティブが本体に成り代わり、結果的に尻尾が本体を振り回し、混乱を更に大きくした。「この世の中にローリスク・ハイリターンはありえない」、「何らかの競争優位性を持っていない限り勝ち続けることは不可能である」という極めて当たり前の原則を人々は忘れてしまっていたのではないか。デ゙リバティブは高度の金融理論モデルに立脚した複雑な数式で構成されており、パラメータをすこしいじるだけでその価値は大きく変化してしまう。本来デリバティブ取引はゼロサムゲームでありながら、パラメータをすこしいじるだけで取引の双方とも利益が出ると誤認させることが可能である。デ゙リバティブはリスク軽減のために有効な手段であるが、このツールをどう使うかという点で使い手の品格が問われる。
(4) 他人任せのリスク評価
複雑にサブプライムローンが組み込まれた証券のリスク評価は難しいが、十分な分析を行わずに安易な格付けを行った格付け機関、そしてその格付けを鵜呑みにし、リスクをとらずにリターンがとれるという幻想に踊った投資家。すべての資産がパニック的に売却されその実勢価格が同時にかつ急激に下落するという状況は、分散投資の効用を説く現代ポートフォリオ理論の想定外の出来事であり、格付けが機能不全に陥ってしまった。
「社会的企業価値」を定義する
ここで根源的な問いに立ち返りたい。経営者の使命とは何であろうか?そして、そもそも「会社」とは誰のもので、また何のために存在するのであろうか?
法律的に解釈すれば会社は株主のものである。株主は株主総会を通じて選任した取締役陣に会社の経営を委任する。委任された経営者は株主に代わって会社を経営する。したがって、経営陣は株主に代わって株主の利益を最大化する義務を負っている。
ところが、株主の利害と経営者の利害は必ずしも一致しない。株主と経営者の利害を一致させるために編み出されたのが、先にも触れた「業績(株価)連動型報酬制度」である。業績が向上して株価が上がれば経営者の報酬も上がる。このメカニズムを通じて株主と経営者の利害を一致させようとするものである。株主も経営者も企業の長期的な成長とその結果である株価の継続的な上昇を志向していれば問題はないが、株主そして経営者とも短期の株価志向になると、この制度は大きな問題を引き起こす。株主は株価の短期的な上昇率によって経営者を評価し、経営者もこの株主の短期的な要求に応えることによって自己の報酬を積み増そうと行動することになる。
しかし、短期的に無理して上げた割高な株価は早晩崩壊することになる。米国でも短期的な値上がり益を追及するファンド投資家そして業績連動型報酬制度に踊らされた経営者の間で「株価至上主義」、「利益至上主義」がもてはやされ、また、マスコミも企業の利益にばかり注目することによって、そのような風潮を煽ってしまった。MBA教育の現場でも、「右肩上がりの時代、ビジネススクールでは緻密さよりも経営会議で同僚を説得するカリスマ性が重視」され、「企業がボロボロになっても、経営者が何百万ドルもの退職金を持ち去る文化が何故生まれたのか、そのような人材を供給したビジネススクールの責任」(米国ビジネスウィーク誌、2008年12月6日付け日本経済新聞より)を反省する声が聞かれる。
企業の経営者は、株主だけでなく債権者(有利子負債の提供者)からも資金を預かり、その資金を投資し適正なリターンを返還する責任を持つことから、経営者は資本提供者(株主および有利子負債の提供者)から預かった資金を効率的に運営し、その価値を最大化する義務を負っているというのがファイナンス理論の基本的な考え方である。このため、経営者は投資家から預かった資金を実物資産(事業)に投資し、適切な事業運営を通じてそこから得られるキャッシュフローを最大化するとともに、キャッシュフローのリスクの大きさを把握しながら上手にこれをコントロールすることによって、キャッシュフローの現在価値を最大化していく。これが企業経営者に与えられた使命であると考える(企業価値=Σフリーキャシュフローn/(1+WACC)^n)。
この考え方にたてば、株主価値は企業価値から有利子負債の提供者に返還される価値(元本および事前に設定された金利)を控除した後の残額であり、企業価値が最大化されれば株主価値も最大化されることになる。この場合、経営者が責任をもつのは、株主そして有利子負債の提供者といった資本提供者である。このモデルの問題点は資本効率追及のあまり財務レバレッジが高くなっていく傾向を助長することである。過度のレバレッジは今回の金融・経済危機の原因の一つであり、一旦、危機が発生すると企業の存続性に大きな負のインパクトをあたえることになる。
企業には株主や有利子負債の提供者以外に広範な利害関係者(ステークホルダー)が存在し、それらステークホルダーを継続的に満足させられなければ企業は永年にわたって存続することはできない。企業は、経営者や従業員、商品やサービスを購入してくれえるユーザー、商品を製造するために必要な部品や原材料を納入してくれるベンダー群、企業や工場を取り巻く地域社会、そして民間企業では提供できないインフラを提供する政府・国家、これらのステークホルダーに対して企業として適正なリターンを継続的に返還していく必要がある。このように考えていくと、本来的な「企業の価値」とは、単に事業や資産が生み出すフリーキャッシュフローの現在価値(いわゆるファイナンス理論でいうところの企業価値)ではなく、ステークホルダー全員に返還することのできるキャッシュフローの現在価値ということになろう。
このように定義された「企業価値」とは、ファイナンス理論でいうところの「経済的企業価値」に対して、「社会的企業価値」とでも定義されるものではなかろうか。このような社会的価値を継続的に増加していける企業のみが長期的に生き残っていけるのである。最近MBA教育界や経営界では企業存続の鍵を握るものとして「サステイナビリティ(持続可能性)」という言葉が脚光を浴びているが、まさに「社会的企業価値」を継続的に向上していける企業こそが「サステイナビリティ」を持った企業といえよう。
「社会的企業価値」とは以下のような付加価値の総和として定義できよう(PV:現在価値)
(1) 付加価値@社会・環境=環境破壊の最小化もしくは環境改善価値
(2) 付加価値@顧客=PV(消費者余剰)*2
(3) 付加価値@ベンダー=PV(利益@ベンダー)
(4) 付加価値@従業員=PV(給与)+PV(企業に帰属することの精神的効用)
(5) 付加価値@経営者=PV(報酬)+PV(企業を経営することの精神的効用)
(6) 付加価値@有利子負債の提供者=PV(有利子負債の提供者へのリターン)
(7) 付加価値@株主=PV(株主へのリターン)
企業としては以上の付加価値の総和を長期的に最大化するよう経営していけばよいわけである。また、政府・国家は以上の付加価値の総和から得られる税収からインフラの提供コストを差し引いた余剰を最大化していくことになる。
経営とは当たり前のことを当たり前に正しく実行して行くことではないだろうか。鱒の記憶は30分といわれており、実際に筆者の経験でも1回釣られた鱒は川に戻して30分もすればまた釣り上げることができる(但し、何回も釣り上げられているとそのうちに学習して用心深くなり、中々釣り上げることが難しくなっていく)。人間の反省と記憶もせいぜい10年程度しか持続せず、更に鱒と違ってあまり学習していないのかもしれない。このため、経済・金融危機は10年に1度程度と比較的頻繁に発生することになる。
正しい経営理論を通じて記憶をもっと長続きするものにしていく、これが本当のMBA教育の姿ではないだろうか(グロービス経営大学院では、正しい経営理論を身につけ、志をもって実践していくことのできる経営者・起業家である“創造と変革の志士”を育成し、社会に貢献していくことをその教育理念としている)。
*1 ファイナンス理論ではリターンは正規分布していると想定している。2008年3月までの過去5年間におけるTOPIX大型株の年間の投資収益率は9.42%、その標準偏差(σ)は4.31%であった。リターンが正規分布している場合、平均値から2.33σ以下のリターン(=9.42-4.31*2.33=-0.62%)が発生する確率は1%(つまり100年に1回)以下となる。一方、2009年3月までの30カ月のリターンは―26.71%と、この数値を大幅に下回る。100年に1度の金融・経済危機と称された所以である。しかしながら、この程度の危機(「この程度の」の定義にもよるが)は、過去100年間に少なくとも数回は起きている。その理由は、リターンは必ずしも正規分布していないという現実にある。現実の世界ではリターンは一方方向に裾野が長く広がる「ベキ分布」(「ベイシアン分布」)の形態をとっている。リスクは正確に定義すると、「狭義のリスク」(リターンのバラツキであり、リターンの標準偏差で表され、通常「ボラティリティ」と称されている)と「不確実性」(わからないこと)の2種類が含まれる。長い間、ファイナンス理論は、統計的に把握でき、したがってコントロール可能な「狭義のリスク」をコントロールすることに集中し、コントロールできない「不確実性」は理論化が難しいことから片目をつぶってきていたといえる。
*2 右肩下がりの需要曲線と右肩上がりの供給曲線の交わった点が均衡価格(Pe)と均衡供給(販売)量(Qe)となる。この状況下での売上高(=消費者の支払額)はPe*Qeとなる。しかしながら右肩下がりの需要曲線は、均衡価格以上の価格であっても消費者として支払う意志があることを示している。この需要曲線のPeと需給曲線の交点を結ぶ線より上のエリアを「消費者余剰」という。つまり消費者全体としてはPe*Qeにこの消費者余剰を加えた金額まで支払う用意があることを示している。

































.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)