サステナビリティが企業経営にとって避けては通れない課題となっています。しかし、大きなテーマであるが故に、日々の仕事と紐づけて捉えることが難しいテーマでもあります。本連載では、サステナビリティ経営を実践する推進者に焦点を当て、個人の志からSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)の要諦を探ります。
第5回も、前回に続きアサヒユウアス株式会社から、2024年8月まで代表取締役社長を務められていた高森志文さん(現アサヒロジ株式会社常務取締役)にお話を伺います。会社設立の経緯やサステナビリティ推進者に求められる要件などを伺いながら、サステナビリティ推進におけるリーダーシップの在り方について掘り下げていきます。
本コラムは、2024年4月時点でアサヒユウアス株式会社の代表取締役を務められていた高森志文さんのインタビューを基に執筆しています(役職等は2024年4月当時のものです)。(聞き手・執筆:山臺尚子)
ユウアス設立に生かされた、転職、再入社、新規事業の経験
――アサヒユウアス(以下ユウアス)の設立の経緯は非常にユニークだと聞いています。きっかけは何だったのでしょうか?
発起人は古原徹さんです。古原さんとの出会いは、10年くらい前に遡ります。
私がアサヒ飲料で仕事をしていた頃、容器の技術者が必要になって探していたことがあります。その頃のペットボトルの形というのは、どの商品、どのメーカーも同じで、あまり面白くない形をしていました。ところが古原さんは商品に合わせてペットボトルの膨らませ方などで形を変えたり、デザインを変えたりして容器を作っていました。
美味しいビールや料理を作りたい、という人がアサヒビールやアサヒ飲料にはたくさんいます。ただ、「容器をやりたい」という人は全くいない。そんな時に古原さんを知ることになって、「こういう人をアサヒ飲料に入れないといけない」と思いました。それが最初の出会いです。
その後、私が3年ほど前にアサヒホールディングスに異動になり、サステナビリティ推進の仕事をすることになったタイミングで、古原さんから「森のタンブラー(前編リンク付与)は、アサヒビールの中では大きくなりません。外に出さないと潰れてしまいます。高森さん、なんとかしてください」と懇願されたのです。私は古原さんに「じゃあ、会社にでもしちゃう?」と返事をしていました。
今でこそ、アサヒグループ内には新規事業を束ねる部署があり、新規事業創出もたくさんやっています。上市のジャッジや継続を判断する仕組みもあります。ただ、当時はそんな状況ではありませんでした。
――当時のアサヒグループ全体は、まだこうしたチャレンジを後押しするような雰囲気ではなかった。
アサヒビールもアサヒ飲料も大量生産、大量販売。日本国内、隅々まで安い商品を届けていくことが仕事です。新規事業をやってみよう、という雰囲気ではなかったと思います。
私は、一度アサヒを辞めています。新卒でアサヒビールに入社してビールの営業を担当した後、人事の仕事をしました。32歳の時に退職して、リクルートで、新規事業の仕事を7年ほどやりました。再度アサヒに入社したのは42歳の時ですが、私にとって、このリクルートでの7年間はとても大きかったです。
アサヒは、新卒で入ったら99%が定年まで勤め上げる会社。一方のリクルートは当時、定年退職者がまだ2人しか出ておらず、人もどんどん辞めていました。真逆の文化だったのです。
リクルートには「Ring」という、会社従業員を対象にした新規事業提案制度があります。私がリクルートに在籍する間に接した人たちは、何か新しい面白いこと、アイディアが出てくると、「Ringに出して新規事業をやろうよ」というような会話を常にしています。そしてうまく事業になったら、自分が社長になって社外へ出ていく。この経験があったからこそ「会社にしてみよう」という発想ができたのだと思います。
――ユウアスを新たに立ち上げることについて、周囲の反響はどのようなものでしたか?
上司に相談すると、当時の組織体制からすれば意外だったのですが非常に応援してくれました。実はこの上司は、何か変えないと会社が変わらない、とずっと考えていた人だったんです。だから「やってみたら」と後押しをしてくれたのだと思います。会社設立のための準備プロジェクトも半年ほどやりましたが、周囲も協力的でした。
「本業の商売と比べると随分小さい商売だけど本当にやるの?」という雰囲気がなかったわけではありません。しかし同時に、「このままビールや飲料だけ売っていていいのだろうか」とも、皆どこかで思っていたのではないでしょうか。
日本の人口が減っていく中で、同じことをやり続けるだけがアサヒの文化でいいのか、何か新しいことをしなくてもいいのだろうか。そんな閉塞感、そして、この閉塞感を打破したい、という機運がアサヒビールにも、アサヒ飲料にもあったのだと思います。
サステナビリティ推進に「地球防衛軍」はいらない 大事なのは柔軟性とバランス
――高森さん、古原さん以外のユウアスの立ち上げメンバーは、公募で募ったと伺いました。人選にも関わられたと思いますが、選抜の基準はどのようなものだったのでしょうか?
私は、能力やスキルはあまり当てにしていません。経験や学歴も全く重視しません。一番大事なのは、働く上での「スタンス」です。
スタンスというのは、例えば、柔軟性が高い人、人への向き合い方が寛容的である人、そういった人にある資質です。柔軟さ、寛容さがある人は、新しいことをどんどん学び、吸収していきます。一方、仕事をする上でスキルや能力が大事だと思っている人は、どうしても知識に頼りがちで、知識を盾のように考えてしまう。そうなると、新規事業のような仕事は難しいと思います。そこでとにかく、このスタンスをしっかり見ました。
――ユウアスとして手掛けようとしている、社会課題や社会的価値への関心や意欲の強さは問われないのでしょうか?
確かにサステナビリティをやりたい、社会課題解決をやりたい、という人がたくさんいましたが、この点もあまり重視していません。私は、サステナビリティ志向だけで考えているような人を「地球防衛軍」だと考えます。しかし実際のところ、「地球防衛軍」ではバランスが悪く、ユウアスがやりたいことはこれではないのです。
とはいえ、あまりにもビジネス志向が強いと、これはこれでサステナビリティやSDGsの世界観が分からない。自分たちだけが儲ければいい、というような考え方も困る。
地球が持続可能な状態になるために、社会課題もいろいろと解決しながら、ビジネスを創っていく、くらいのバランスが必要なのです。
――高森さんから見た古原さんは、「地球防衛軍」ではなくバランスの取れた方だった?
古原さんは、生ジョッキ缶のように、自分が生み出した面白い技術で世の中を変えたいと思っている人です。ただ、研究所に閉じこもって研究だけやるようなタイプでは全くありません。人と関わることが大好きで、会社を超えた人脈もすごくたくさん持っていました。
人と直接関わっていくことを通して、新たな技術のアイディアが湧き出るという経験をたくさん持っている人だと思います。初めて会った頃から古原さんは天才だと。この人だったら、いつか何かやるだろうと思っていました。
ユウアスが社内と社外で果たす役割――新規と既存の二律背反をどう乗り越えるか
――高森さんの日頃の時間の使い方について教えてください。
私の仕事は大きく2つに分かれています。ユウアスの運営と、アサヒグループホールディングスのサステナビリティ推進です。それぞれの業務には時間をほぼ半々で割り振っています。
ユウアスでは、新規事業ならではの柔軟性や視野の広さが求められます。しかし、アサヒグループ出身の従業員は大企業特有の役割分担が明確な文化で育った人が多く、環境の違いに戸惑うこともあります。特に、工場出身者は品質や安全を最優先に考え、厳密な規則を守る文化に慣れているため、新規事業の曖昧な環境にストレスを感じがちです。このため、チーム内での衝突や調整が頻発します。
また、手順が整備されていない中でメンバーが試行錯誤しながら進めるため、成果は上がるものの、様々な局面で負担がかかる場面も少なくありません。その一方で、こうした挑戦が新規事業を推進するエネルギーにもなっています。
私のユウアスでの役割は、そんな組織やメンバーが既存事業の論理に葛藤したり、矛盾を感じたりすることなく、サステナビリティや新規事業に没頭してまい進できるような調整や環境整備をして、組織としての安定を作っていくことだと思っています。サステナ推進の仕事では、調達から物流まで、アサヒグループ全体のバリューチェーンで環境や人権の持続可能性を高める取り組みを進めています。
――サステナ推進部長とユウアス社長のどちらが楽しいですか?また、両方の仕事に関わることのメリットは何でしょうか?
どちらも甲乙つけがたく、両方にやりがいがあります。
ユウアスではスピード感を持って面白い事業を展開し、それが売り上げにも繋がっています。サステナ推進の仕事では、アサヒグループの大規模な事業に持続可能性を組み込み、変革を促すことが醍醐味です。ユウアスでの実験的な取り組みが、グループ全体のビジネスに良い影響を与えています。
ユウアスの機動性を活かして実験的な挑戦を行い、その成果をアサヒグループの本業に反映させることができています。逆に、本業で得た知見をユウアスにフィードバックすることで、さらに新しい挑戦が可能になります。この双方向の循環があることがメリットであり、魅力ではないでしょうか。
社外から社内と社会をサステナビリティに巻き込む 経済的・社会的インパクトにこだわる理由
――ユウアスとしての今後のチャレンジは何でしょうか。
アサヒには新規事業が多数存在し、研究所でも多くのビジネスの種が育っています。その中で「なぜ、ユウアスに資源を投下し続けるべきか」を示し続ける必要があると考えます。
優秀な人材は新規事業よりも既存事業に行った方がよいのでは、という見られ方をされることがあります。ユウアスのビジネスの評価によっては、重要な人材たちを他の新規事業や既存の大規模事業に配置した方が良い、と会社が判断することもあり得ます。だからこそ、ユウアスはアサヒグループにとって重要で、ここに優秀な人材を置き続けるべきだということを経済的・社会的インパクトの両面で証明し続ける必要があります。
――経済的・社会的インパクトというと具体的にはどのようなものでしょうか。
経済的インパクトとしては、まずビジネスとして設立させることです。これはユウアスとして特に重視していることですが、私自身、過去にCSR事業が収益化できず、最終的に中止や縮小を余儀なくされるのを目の当たりにしてきました。なのでまず、「3年目単黒(単年での黒字化)」を達成することを最優先にしています。
ユウアスは、常に社会にポジティブな影響を与える存在であり続けることが最も重要だと考えています。ただ、ユウアスの意義が既存のビジネス規模の大きさと比較され、アサヒビールやアサヒ飲料のようなビジネスや売り上げの大きさが求められる場合には、必要に応じて外部に切り出すという覚悟も必要だと思っています。
社会的インパクトとしては、例えば環境省の補助金の獲得、グッドデザイン賞の受賞、というような外部からの評価を得ることです。これによって、ユウアスが独自の価値を持つ存在であることを示すことができます。アサヒグループ内での地位を強化するだけでなく、消費者や社会全体への信頼にもつながります。
ユウアスは「簡単で楽しく、分かりやすい」取り組みを通じて、世の中にサステナビリティの可能性を示す存在です。例えば「森のタンブラー」が直接的にCO2削減を実現するわけではありませんが、分かりやすいサステナビリティの進め方を具体例で提示できたことで、多くの共感や注目、共創のご依頼の声を集めてきました。
ありがたいことに、いわゆる「モテる」この状況は大きな強みだと思っています。これに加え、外部からの評価を得ることで、ユウアスの活動は外部から後押しされ、さらなる共創の機会が生まれますし、積み重なれば「おいそれとは潰されない存在」となるはず。これが目標です。社内での評価だけではなく、社会全体からの支持を得ることは、ユウアスの未来を切り開くカギだと考えています。
――最後に、サステナビリティ経営はどうしたらうまくいくと思いますか。サステナビリティ推進のコツがあれば、是非伺ってみたいです。
最終的には、全ての部門、全ての人が「自分ごと」としてサステナビリティを推進できる文化を作ることが重要です。自分の領域で何ができるかを考え、行動できるように、評価制度にサステナビリティ目標を組み込む、PDCAを徹底する、といった方法はあります。
しかしより重要なのは、消費者の意識が変わるタイミングを見据えて、予め準備を進めることだと思います。消費者はサステナブルな選択を強く意識しないように見えても、例えばマイバッグの普及の時のように、ある時点で大きな意識転換が訪れる可能性が今後もあります。
その時に備えて、試験的な取り組みを行うことが必要だと感じます。例えば消費者が自然にカーボンフリー商品や人権に配慮されたフェアトレード商品を選べるようにする。そんな環境を予め整えておくようなことが重要です。
私自身の役割は「そろそろタイミングが来るぞ」という警笛を鳴らし、組織や消費者が準備を進められるようサポートすることだと思っています。そして、「やらされ感」や「義務」ではなく、「これができたら面白し、楽しい」という共感を多くの人が感じられるサステナビリティが、自然に取り入れられるような社会を目指したいと考えています。
.jpg?q=75&fm=webp)
アサヒユウアスのSX推進のポイント
前回の社内と社外を繋ぎながら縦横無尽に活躍する古原さん、そして、今回の新規事業と既存事業の間の橋渡しを担う高森さんが推進する、ユウアスのサステナビリティ経営には、以下のような3つの特徴が見られました。
1 社外との共創に集中できる組織構造を作る
ユウアスは、アサヒグループ内の一部門ではなく、社会価値の実現を徹底的に追求することができる組織として別会社化されています。これにより既存事業の論理に翻弄されたり、ジレンマに悩むことなく、社外との共創を本業に据え、社外の接点を開拓することだけに集中できる環境が整っていました。
2 社外から社内にサステナビリティ推進の輪を広げていく
本業ではないサステナビリティ推進の場合、取り組みたくても何からどう着手していいのか分からないことも多いようです。「アサヒの中にあってアサヒにはない動きができる」ユウアスの躍進を目の当たりにすることによって、「自分たちでもやってみよう」という社内向けの着火剤の役割もユウアスは果たしているようです。
3 楽しさ、面白さがなければ続かない
古原さんにとって、「サステナビリティ」は「自分自身のやりたい仕事をやりたいようにやる」ための手段の一つではありましたが、社内では得られないような強烈な成長実感や目に見える成果、感謝を目の当たりする中で、ご自身なりの取り組みの意義や意味を見出すようになりました。また、高森さんもサステナビリティ一辺倒の「地球防衛軍」ではなくビジネス感覚が重要、「やらされ感では続かない」と仰っています。お2人方とも、使命感、義務感や取り組む規模の大小ではなく、それぞれにとっての「面白さ」、「楽しさ」、「共感」を活動の中に見出し、自然に取り組める状態にしていくことの大事さを伝えていました。
最後に
サステナビリティ推進は、分かりやすい結果が見えづらい中、短期ではなく長く継続していく営みです。営みの性質上、本業かサステナか、短期か長期か、等々、様々な矛盾や葛藤に対峙しやすいテーマでもあるため、どうしてもこうした矛盾や葛藤をどう乗り越えるか、そのためにどうするか、に意識が強く向きがちです。
しかし、きっかけや入口はどうあれ、携わる上での自分なりの居心地の良さ、手触り感のある手ごたえをいかに各自、各社で見出して、小さな一歩をいかに早く踏み出せるか。こちらに発想と舵を切り替えられるかどうか。SX推進の壁を乗り越えられるかどうかは、実はこうした発想の転換にあるのではないでしょうか。


.jpg?fm=webp)

.jpg?fm=webp)




















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
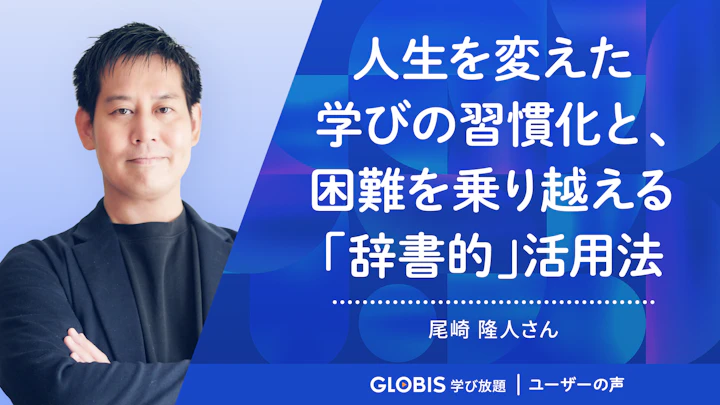
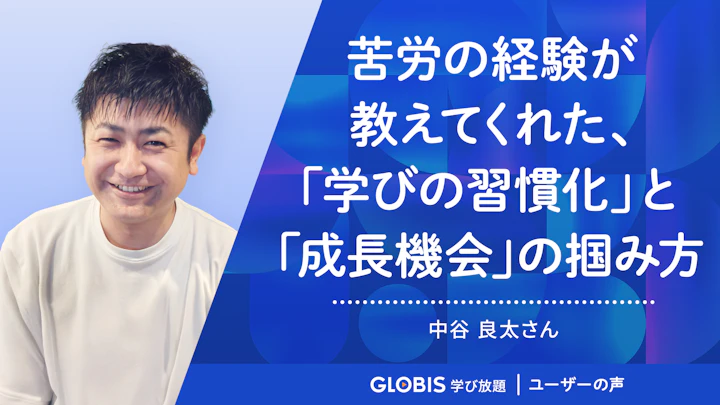
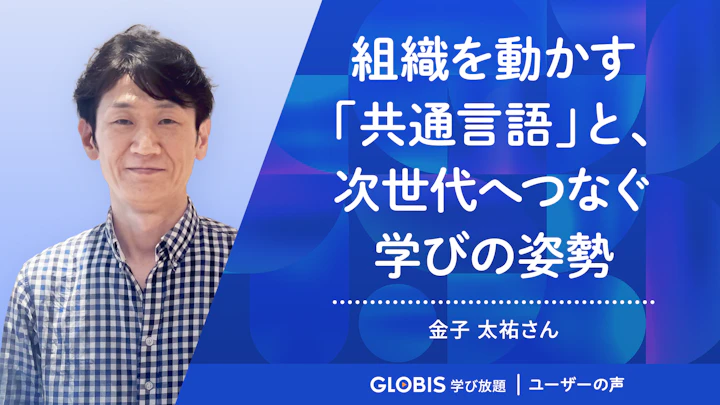


















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

