
問い: アルムナイ・アワードの受賞おめでとうございます。まずは感想を伺いたい。
青柳: 過去のあすか会議では蒼々たる方々がアルムナイ・アワードを受賞されていたので、まさか自分が受賞するとは思わず、本当に驚いた。私が頂いた賞というより、チーム、支援先で一緒に活動している皆さんを代表して、一代表というか右代表として頂いたものだと思っている。
問い: 今回のアワード受賞に至るまでの青柳さんの歴史について聞きたい。青柳さんは1991年に当時の日本船舶振興会に入られたが、なぜ日本船舶振興会を仕事の舞台として選んだのか。
青柳: 私が学生の頃はバブルの終わりぐらいで、企業訪問すればすぐ内定をくれたような時代だ。法学部だったので本来は公務員か弁護士を志望する者が多いと思いきや、多くの友人が給料の高い金融系などに走った時代だった。当時の私には、金融が社会的に果たす本当の意義が分かっていなくて、あまり興味がなかったし、向いていないと思っていた。
亡くなった父親の影響も大きいと思う。父は千葉の田舎でずっと地方公務員をやっていたので、地域のために働く姿を高校卒業まですぐ横で見ていた。それもあって、お金とか利益のために働くのではなく、世の中のために働きたいと思うようになったし、それでご飯が食べられる仕事につきたいなと思っていた。普通は公務員を思い浮かべるのだが、入った途端に全部レールを引かれてしまう感じもあった。当時は電話帳のような分厚い就職情報誌がリクルートから送られて来ていた時代。そこに出ていたのが日本船舶振興会と国際協力機構(JICA)だった。
就職活動を始める前、大学3年の夏休みに1人でエジプトを3週間、バックパックで旅行した。観光地の表側はきらびやかだが、少し裏側に入ると過酷な現実があった。小さな子どもが物売りして働いている。アルバイトでお金を貯めて気軽に海外旅行に出られる自分との格差を体感し、世界をもう少し良くするために働きたいと思った。そして就職先を探し始めた時に、就職情報誌で船舶振興会を見つけたというわけだ。
当時の職員は70人ぐらいだったが、予算はフローで入ってくるお金が年間700億円ぐらい。ボート(競艇)の売り上げの一部だ。700億円ものお金を、たった70人の人間が、世の中のために使うという仕事だ。ある友人が、「官庁の外郭団体と違って、プロパーで入っても仕事を任せてもらえるのではないか」とアドバイスしてくれた。なるほどと思い、採用試験を受けたら、最終面接まで進み内定をいただいた。
問い: ちなみに青柳さんのご出身は?
青柳: 千葉県の小見川町というところ。今は合併して香取市になっている。香取神宮という大きな神社があり、隣が佐原市というところで、どちらのまちも昭和の初めごろまでは利根川流域の水郷地帯の商都として栄えた。

問い: お父さんは?
青柳: 小見川町の町役場の職員だった。平成の大合併で香取市となったが、その小見川町はその昔の昭和の大合併で小見川町となった。小見川町の前身の良文村の最後の村長が私の曽祖父だと聞いている。就職の時に父親に相談したことを覚えている。日本船舶振興会のほかに、地方公務員の内定ももらっていたので、父親は「公務員がいい」と言うに違いないと思っていたのだが、意外にも「好きな方にしろ」と。父親のその一言で、船舶振興会に決めた。獣道に見えたが(笑)。
問い: 最初はどんな仕事をしていたのか?
青柳: 入ってすぐ研修が始まった。ボートレース選手の学校に入り、ほとんど休みのない生活を1年間続けた。この養成学校では、半年に1回、50~60人が選手の卵として入ってくる。1年間の選手養成コースを経て、半分くらいの人数が途中で脱落せずにプロテストに合格し、レース場(全国に24カ所)にデビューする。その一方で、レースを運営したり、管理監督したりする人を養成するコースもある。ボートの検査をしたり、審判をやったり、資格が必要な職業で、大学出の人たちが専門職として育成される。私はそこに入れられたわけだが、要はレース場で生み出されたお金をいただいて使わせてもらう立場なので、その源泉をきちんと見て、体験して来いということだった。
丸坊主の海軍形式。朝6時から夜10時の消灯までスケジュールがびっしり。それを365日やった。最初の3カ月は外出もできない。6月末の日曜日に初めて外出許可が下りたが日中だけ。お盆休みと年末年始をそれぞれ10日ぐらい。1ヵ月に1回ぐらいは日曜日に出られる。選手養成のコースの自衛隊出身の人が、「メンタル的には自衛隊よりもきつい」と言っていた(笑)。
この1年をなんとか乗り切って、その後の4年間は笹川良一氏の秘書をやった。日本船舶振興会の創業者。いろいろな評判があったが、身近にいると「優しいおじいちゃん」という感じ。いろいろな人に細かく気を遣う、優しい人だった。
問い: 最初の1年は、その後の青柳さんにとってどんな意味があったのだろうか。
青柳: 自分が意識していたのは、「入社前の志」を忘れないようにすることだった。この1年間を乗り越えないと、やりたかった仕事に就けない。ここでリタイアしたら何の意味もないので、絶対に忘れないようにしていた。軍隊のような生活はきついけれども、逆に、決められたことだけができれば良い。そうすると、ルーティンをこなすことだけを優先し、創造的なことを考えなくなってしまう。このままでは、学校を出てから財団で使い物にならなくなってしまうと直感していた。教官の厳しい指導でも「間違っている」と思ったことには意見もしていたが、やるべきことをやっていないと全く聞いてもらえない。だから、やるべきことは絶対100点を取る。その上で言うべきことを言う。そこを学んだ。おかげで、「志」が鍛えられた。今、何をやっても、何をされてもへっちゃらだ。

問い: 大局の中で、自分はどこにいて、何ができるのか、何をすべきかを知った?
青柳: すごく客観的になれる自分を発見した。例えば、5分間でエンジンのキャブレターを分解して、終わったら、また組み立てるという作業がある。「スタート!」の合図でバッとバラして、バッと組み立て直す。ネジが1個余った。「何やってんだぁ!」と教官からバカンとやられる。そんなことを何度も繰り返していると、意味を問うことが無意味に思えてくる。「禅」の境地というか、組み立てている自分を客観的に見ている自分がいることに気づく。キャブレターを5分で分解して組み立てる作業は、ほかの仕事には役に立たないけれど、それを繰り替えしているうちに何かを突き抜けてしまった。
問い: それを見越して、仕組まれたプログラムだったらすごい。
青柳: たぶん、そんなことはない(笑)。
問い: その後、笹川さんの秘書をやられた数年間があって、いよいよ事業部に配属された。
青柳: 阪神淡路大震災が起きたのが1995年。事業部に配属されたのは、その翌年のことだ。27~28歳ぐらいのときだ。そのときの上司にとても鍛えていただいた。「とにかく現場に足を運んで、そこで起きていることをきちんと見極めろ」と言い続ける、そんなタイプの方だった。
日本財団という組織は、「助成」と呼ばれる仕事をするためにある。「助けるに成る」と書く。何らかのプロジェクトを実施したい方々が現場にいて、これだけお金が必要という企画書をもらう。我々は、そのプロジェクトが世の中の1つのモデル、起爆剤になって広がっていくかなど、いろいろな視点から検討してお金を出すかどうかを決める。このシードマネーを出すという点が助成財団の社会的な役割だ。
私はというと、そのシードはどこにあるかをリサーチしたり、それをもっと大きく膨らますための企画を練ったりということを現場の方々と一緒にやっていた。向こう側から来たものを審査するだけでなく、向こう側に何があるのか当たりをつけて、助成して変化を起こした先の社会の姿のところまで自分で見つけにいく。待っていても「これだ!」というものは来ない。だから良い案件を探しにいって、それを本当に良いプロジェクトにしていくための企画を一生懸命に考えるということをやっていた。
お世話になったその上司に教わったのは、助成財団としてコミットしつつも、少し引いた冷静な立場で物事を見ることを忘れるなということだ。面の視野から点を見るということ。全体の構造を面的に把握して、その構造を変えていくためには、どういう点、つまり事業を生み出すべきなのかを考えろ、と。そういうメッセージを、背中で見せる上司だった。
現場のパートナーと3年なら3年、しっかりやり抜けと言われるだけ。しかし、甘いことをやっていると雷が落ちた。仕事に対するスタンスや何が大事なのかということを、その方から教わった。
問い: 何という事業部だったのか。
青柳: ボランティア支援部だ。NPO法が施行される前からあった事業部だ。配属の前年に阪神大震災があり、多くのボランティアが活躍した。「ボランティア元年」と言われ、個人レベルの貢献から、組織化して活動する時代に入っていた。そういう流れの中で、法的な後ろ盾も必要だということで特定非営利活動推進法(通称:NPO法)がその後にできる。そういう時代の流れに正面から取り組む事業部だった。
問い: だが、仕事の対象が大きすぎて、手を打ったとしてもすぐに効き目が実感できないのではないか。「自分は何をやっているのだろう」などと悩まれたことはなかったのか。
青柳: それはあった。だが、性格的に割り切りが早い。財団の助成によって日本社会を変えるようなことは簡単にはできない。具体的なゴール設定をして、それに向けては頑張ったとしても、できないこともある。こちらに原因があることもあるし、相手に原因があることもある。そもそも外部環境が全く変わってしまうということもある。うまくいかない原因を分析して手を打つが、駄目だったら駄目で撤退する判断も結構早い。良くも悪くもそこは割り切っている。
事業部を約7年やってから総務部企画課に異動、組織機構の改編などのプロジェクトをやった。きちんとした経営企画部門と、その中に人事部門を作りたいと組織再編のときに提案して認められ、それがきっかけで人事部門の責任者を任された。2002~2004年頃のことだ。その後、経営企画部門の責任者も任せていただいた。
それからは、ボートレースの小さな場外売り場を街中に作る企画があり、関連団体で出向して営業も経験した。市町村などの自治体周りだ。
2年間で100カ所ぐらい回ったが、ものになったのは2~3カ所だけ。街にギャンブル場ができるイメージだから、各自治体の首長は本音では財政の足しになってくるので「欲しい」と思うが、住民の反応を考えると実際には難しい。政治的な判断になり、首長のリーダーシップだけでは決まらない。非常に複雑な世界を見た。その後、日本財団に戻り、海洋グループという事業部に再配属された。主に造船の技術開発に助成する責任者になった。船舶振興会のまさにコア事業だ。
そこでの3年目が終わるぐらいのときに東日本大震災が起き、復興支援タスクフォースの責任者を拝命して今に至る。
問い: 東日本大震災への対応はどのように進めたのか。
青柳: 3月11日の2日後の日曜日、朝8時ぐらいに役員全員、管理職全員、現場の若手数名を含めて30人ぐらいが緊急会議に招集された。まずは初動の支援として人や物、お金がどんどん東北に向かい始めるだろうが、先ほど「面」と「点」と言ったように、我々は中長期的に見てどんなニーズが発生し、それに対して何をどう準備をしていくべきかという中長期の視点で考えていた。創業者の三男である笹川陽平会長が、会議をリードした。僕も含めて、被災地支援の現場経験があった何人かがアイデアを出して議論を重ねた。
その中で、3年下の後輩が「3月11日の夜8時に、ネット募金を立ち上げた」と事後報告を上げてきた。募金はどんどん集まっていた。それとは別に阪神淡路大震災を経験したNPOたちが街頭募金を始めて、そのお金を日本財団に送ってくれていた。「多くの人の善意を無駄にしないように、しっかりやらなければいけない」と思い、会議の後に役員にメールを書いた。当面必要となる役割・機能・仕組み、横断的なチーム・組織について提案し、先手を打って作っておくべきだ、と。「俺が、俺が」とシャシャリ出るつもりは全く無かったのだが、専任担当として指名を受けることになった。
問い: その時期と、グロービス経営大学院に通い始めた時期は重なっている。
青柳: 2011年4月に本科生として入学した。前年秋に入試を受けて合格していた。東日本大震災が起きたので休学しようかと迷ったが、せっかく「学ぼう!」と思っていた勢いが削がれてしまうので、出られる授業だけでも出ようと思い直した。
問い: その決断についてもっと詳しく聞きたい。震災復興支援の新しい仕組みを作る仕事と、MBAの大学院へ通うことを両立させることは、容易なことではなかったと思う。そこから青柳さんは何を学んだのか。それは2011年の「あの時」でなければならなかったのか。
青柳: 「同時に両方やれ」と、何かに突き動かされた。仕事の現場で迷ったり困ったりした時、自分自身の経験、人から聞いた話、読んだ本から得た知見で考えたり、話したりできるが、全く体系化されていないことに不安を抱いていた。30代後半まで、なんとか仕事をこなしてきたが、抜けモレがあることに気付いていた。知ったようなことを言ったり、書いたりしていたが、「本当は、そうじゃないんだよな…」ということをいつも感じていた。組織の機構改革や人事を手がけ始めたのが35~37歳ぐらい。その頃、「しっかり学び直さなければならない」と確信した。通いやすかったからグロービスを選んだのだが、なかなか踏ん切りが付かなくて30代後半では行けなかった。ところが、そうこうするうちに自分の体に癌が見つかった。幸い早期発見だったので手術することで、現在は完治している。41歳の時だった。そんなこともあり、残りの人生はあと半分しかないし、やりたいと思うならやっぱりやっておかなければ駄目だと思い、ようやく踏ん切れ。だから、震災はあったけれども、自分の中での「決意」を途切れさせたくなかった。
問い: 極限的な状況で仕事と学びの二兎を追った経験から、青柳さんが得たものは何か?
青柳: 「やれば何とかなる」ということだ。グロービスのクラスで学んだことは、だいたいすぐに現場で使えた。だから、無理してでもクラスに出席した。事前の予習は、ほかの成績優秀者の方に比べると浅かったかもしれない。だが、クラスでは「実践できること」を1つでも掴み取って帰るよう最大限集中して臨んだ。持ち帰ったものが、自分自身のまるで「火事場」のような現場ですぐに使えたことが何度もあった。だから、続けられた。
問い: グロービス経営大学院では、学生に提供するものの1つとして「生涯にわたって切磋琢磨していける人的ネットワーク構築の場」を掲げている。そうした面で実効的な効果はあっただろうか。
青柳: 私のような職種の学生は、グロービスではものすごく少ない。200人ぐらいいる同級生のうち、「財団」に勤めているのはほかにたぶん1人。公的な仕事で飯を食っている人も少ないので超マイノリティーだ。仕事の会話は合わなかった。だが、東日本大震災の復興支援の担当として、企業との連携を加速させるための施策を考えたりしていたので、同級生からいろいろなことを教えてもらったりもした。グロービスの卒業生がGRA(http://www.gra-npo.jp/)を立ち上げたりしていたので、グロービスに来るたびにモチベーションが高まるようなところがあった。今振り返ると、特定の問題意識を持った方々と深く、長くつながるタイプの人的ネットワークを構築していた。

問い: そして今の青柳さんがいる。今の立場は日本財団そのものの活動領域を拡大していく経営視点に近いところに踏み込んでいる。この3年ぐらいを振り返って、ここが転換点あるいは自身の成長の瞬間だったというものを1つ挙げるとしたら、どこだろうか。
青柳: グロービスでMBAを学んでいたおかげで、東北の支援をしたいという企業とやりとりする中で、「企業とはどういうコミュニケーションを取るべきか」「企業にとってのメリットは何か」という視点を持てるようになった。そうしたプロトコルで企業と会話できるようになったことこそが私の転換点だった。2011年秋ぐらいにはそう感じていた。その前と後では天地ほどの差がある。
問い: 青柳さんの頭の中のマッピングというか、関係性の地図ができていると気付いた瞬間があったということだろうか。「視座」が上がったということか。
青柳: そう言えると思う。企業が復興支援をしようという時、当たり前の話だが、お金が無駄な使われ方をされたくない。100万円の寄付金が、200万円、300万円の価値を生み出していくように使ってほしいわけだ。当然のことだが、復興支援といえども、企業はマーケティング的な意図をそこに織り込む場合もある。そうした企業の思考法や論理は、ずっと財団の中にいて財団の発想で仕事をしていると、本当に一部しか理解できなくなってしまう。グロービスでは、マーケティングひとつとっても「全体」を学ばせてもらえる。こちら側だけでなく、向こう側の立場からも見るトレーニングを重ねさせてもらった。プロジェクトを進めていくための図面を引きつつ、全体を俯瞰して、関係者の利害得失を考えながら、「一番の肝はここだ」というところに当たりをつけ、実際にそういう会話が成り立ち始めたのが2011年秋ぐらいだったのだ。
問い: ある瞬間に、ふっと気付いたのだろうか?
青柳: 「振り返るとそうだった」という感じだ。話がうまく噛み合って、具体的なプロジェクトになっていくということが、その時期に急に増えた。グロービス経営大学院仙台校への奨学金(「ダイムラー・日本財団イノベーティブリーダー基金」)、の件は、もともとダイムラー社から「ぜひ有効に使ってほしい」と資金だけはいただいていた。東北復興支援に積極的に取り組んでいたグロービスから、それを生業としている僕に対して、「何か一緒にできないだろうか」と話が持ち込まれた時、奨学プログラムを思いつき、「これだ!」と思ってつながせてもらった。
問い: 最後に、青柳さんにとって「学ぶ」とはどういうことなのか。そして、今後の展望、夢について聞きたい。
青柳: 観念的な話だが、「学ぶ」とは自分の成長だ。自分の成長は何のために必要かというと、世の中に何かしらの「還元」「貢献」「良い関わり」をするためだ。世の中に対して良い関わりをするために、私はもっと成長したいと思った。グロービスに入って、ますますそう思うようになった。そのために自分は学ぶのだということが、すべての前提にある。
今後は、今取り組ませていただいている「ソーシャルイノベーション」のハブになっていきたい。非営利か営利か、という分け方がずっとされてきたが、昨今は、むしろそういう分け方ではない世の中に少しずつ遷移していきていると思う。その遷移スピードをもっと速め、社会的な課題に企業が向き合うことをごく普通のことにしていきたい。ビジネスで解決できる課題はどんどん解決してもらい、ビジネスにならないものは我々のようなところがしっかり支える。お互いをもっと深く知り合って連携の可能性を広げ、そうした協力が、互いに肩肘張らず、普通に成り立つ世の中にしたい。
問い: 日本財団そのものも変わる必要があるのか。
青柳: もちろんある。財団という機能は主にアメリカからきている。古いところだとロックフェラー財団やカーネギー財団といったところ。大型の助成財団として歴史がある。最近では、ビル・ゲイツさんがつくったビル&メリンダ・ゲイツ財団は資産が1兆円以上ある。社会への影響力が違う。エイズ撲滅とか、積極的に仕掛けている。社会起業家を育成しようということで、社会起業家の卵たちにお金を出しているアショカ財団もある。
日本財団は、日本代表、いや世界代表になりたいと思う。カーネギーやロックフェラーに比べて機能的に遜色はないと思う。だが、アショカのようなところと先端的な取り組みで勝負できているかというと、まだまだだ。今、そういう議論をしている。名刺にあるソーシャルイノベーション推進チームというのは、財団の中期計画などのビジョンを作り直しつつ、日本財団が考えるソーシャルイノベーションはこういうものだというビジョンを示したうえで、世界的な流れの中の1つのハブ機能になりたい。この6月から取り組みを始め、今年度中には大きな絵を描き切る。
問い: 青柳さんの理想をどのぐらいのタイムスパンで実現するのか。
青柳: 10年以内にやり遂げたい。今後5年ぐらいで企業の社会貢献に対する考え方はかなり変わっていく。この5年でどれだけ加速できるかが勝負だと思っている。引っ張って、尻を叩いて、伴走して、非営利と営利がお互いに一緒にやれると確信できるようにするまでに5年。2020年のオリンピックの年までというのが、1つの目標だ。企業も個人も、魅力的なこの日本を世界へ発信したいと思うはずだ。東北復興はもちろんだが、「世界の中の日本」という文脈がますます大切になってくる。
良い話をポジティブに明るく発信していく。そして、少子高齢化や老人介護といった社会の大きな課題を解決するための新たな行動を巻き起こしていく。そうした活動を通して、日本という国をしっかり作っていきたい。そうしなければ、世界中からお客様をお迎えするのに恥ずかしい。負の課題からも逃げない日本を、きちんと伝えていく。日本は先進国の中でも一番に進んだ国として、他国をリードするような気概で前に進むべきだと思っている。そのために微力を尽くしたい。
「グロービス アルムナイ・アワード」は、ベンチャーの起業や新規事業の立ち上げなどの「創造」と、既存組織の再生といった「変革」を率いたビジネスリーダーを、グロービス経営大学院 (日本語MBAプログラムならびに英語MBAプログラム)、グロービスのオリジナルMBAプログラムGDBA(Graduate Diploma in Business Administration)、グロービス・レスターMBAジョイントプログラムによる英国国立レスター大学MBAの卒業生の中から選出・授与するものです。選出にあたっては、創造や変革に寄与したか、その成功が社会価値の向上に資するものであるか、またそのリーダーが高い人間的魅力を備えているかといった点を重視しています。詳しくは、こちら→「グロービス、第10回「グロービス アルムナイ・アワード」を授与、ロット・武山和裕氏、ペー・ジェー・セー・デー・ジャパン・野田泰平氏、日本財団・青柳光昌氏、三菱商事・松本有史氏の4氏」




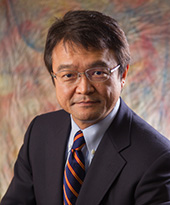




















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)








