シェアとは - 「所有から共有」へのパラダイムシフト
シェア(Share)とは、モノやサービスを一人で所有するのではなく、複数の人で共有することを基盤とした ビジネスモデルです。コラボ消費とも呼ばれるこの概念は、従来の「所有することこそが豊かさの象徴」 という価値観を覆し、「必要な時に必要なだけ使える」という新しいライフスタイルを提案しています。
レイチェル・ボッツマンとルー・ロジャースが著書『シェア〈共有〉からビジネスを生みだす新戦略』で 紹介したことで一般に広まったシェアビジネスは、カーシェアリングや民泊、コワーキングスペースなど、 私たちの身の回りに急速に浸透しています。実は図書館なども広義のシェアビジネスであり、 このコンセプト自体は古くから存在していましたが、現代のテクノロジーと社会情勢が その可能性を大きく押し広げているのです。
なぜシェアが重要なのか - 現代社会が求める新しい価値観
シェアビジネスが注目を集めるようになったのは、単なる流行ではありません。 現代社会が抱える様々な課題に対する合理的な解決策として機能しているからです。
①環境問題への意識の高まり
所有することが資源や金銭の浪費を生み、地球環境に大きな負荷をかけているという反省から、 シェアビジネスは注目されています。例えば、一台の車を複数人で共有することで、 製造に必要な資源の消費量を大幅に減らすことができます。また、使用頻度の低い アイテムを個人で所有せず共有することで、無駄な生産を抑制し、 持続可能な社会の実現に貢献できるのです。
②経済合理性の追求
リーマンショック後の経済状況や、市場の成熟により購買力が低下したことも、 シェアビジネス普及の大きな要因です。高額な商品を個人で所有するよりも、 必要な時だけシェアする方が経済的に合理的だという認識が広がりました。 特に若い世代にとって、「賢い消費」という観点からシェアは魅力的な 選択肢として映っています。
シェアの詳しい解説 - 成功する条件とメカニズム
シェアビジネスが成功するためには、特定の条件が揃う必要があります。 ボッツマンらが提唱した4つの原則を理解することで、シェアビジネスの本質が見えてきます。
①クリティカルマスの存在
シェアビジネスが機能するためには、一定数以上のユーザーが必要です。 参加者が少なすぎると、共有する意味がなくなってしまいます。例えば、 カーシェアリングサービスでは、利用したい時に車が利用可能でなければ サービスとして成り立ちません。十分な数のユーザーと車両があることで、 利便性が確保され、サービスの価値が生まれるのです。
②余剰キャパシティの活用
個人で所有するより共有した方が合理的である状況が必要です。 使用頻度が低く、維持コストが高いものほどシェアに適しています。 例えば、一般的な自家用車は95%の時間は使われずに駐車されています。 この「余剰キャパシティ」を活用することで、所有者は収入を得られ、 利用者はコストを抑えて必要な時だけサービスを享受できます。
③共有資源(コモンズ)の尊重
シェアされる資源を大切に扱うという意識が参加者に必要です。 自分だけのものではないからこそ、より丁寧に扱い、次の利用者のことを 考える姿勢が求められます。この意識が欠如すると、シェアビジネス全体の 品質低下につながり、サービスの持続性が損なわれてしまいます。
④他者との信頼関係
シェアビジネスで最も重要とされるのが、参加者同士の信頼関係です。 見知らぬ他人と資源を共有するわけですから、お互いを信頼できる 仕組みが不可欠です。例えば、カーシェアリングで荒い運転をする ユーザーがいると、車両の消耗が早まり、そのコストは最終的に すべてのユーザーに転嫁されます。評価システムや身元確認など、 信頼を担保する仕組みがシェアビジネスの成功を左右します。
シェアを実務で活かす方法 - ビジネス機会と戦略的視点
シェアビジネスは、新しいビジネス機会を創出する一方で、 既存企業にとっては競合となる可能性もあります。
①新規ビジネスとしての活用シーン
スタートアップ企業にとって、シェアビジネスは魅力的な事業領域です。 インターネットやモバイル環境の発達により、情報仲介のコストが 劇的に低下したことで、小規模な投資でもシェアプラットフォームを 構築できるようになりました。民泊サービスのAirbnbや 配車サービスのUberなどは、その代表例です。
また、既存企業も自社の遊休資産をシェアビジネスに活用することができます。 オフィスの空きスペースをコワーキングスペースとして提供したり、 社用車を業務時間外にカーシェアに活用したりすることで、 新たな収益源を創出できます。
②競合分析と戦略的対応のポイント
既存企業にとってシェアビジネスは潜在的な競合となりえます。 自社の事業領域にシェアビジネスが参入してくる可能性を常に 監視し、対策を講じることが重要です。
競合対策としては、自社でもシェアビジネスに参入する、 既存サービスの付加価値を高める、シェアビジネス企業と 提携するなどの選択肢があります。重要なのは、 「所有から共有へ」という消費者の価値観の変化を理解し、 それに適応した戦略を構築することです。
シェアビジネスの台頭により、企業は「所有価値」ではなく 「体験価値」や「アクセス価値」を提供することが 求められるようになってきています。この変化を機会として 捉え、新しいビジネスモデルを構築していくことが、 今後の企業戦略において重要な要素となるでしょう。
























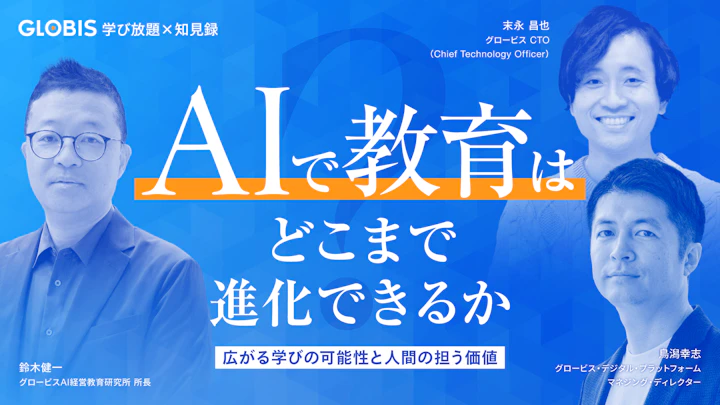
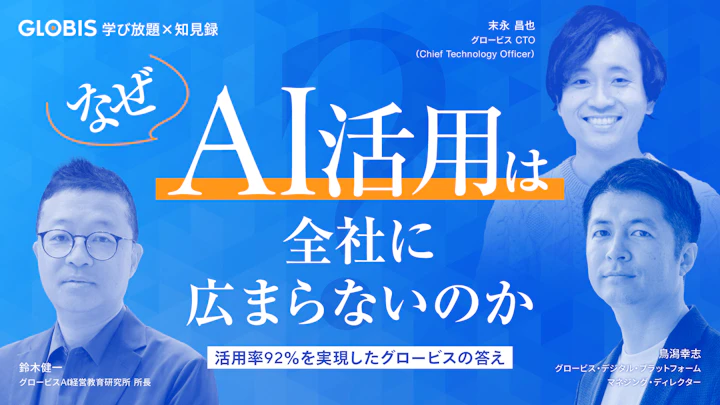
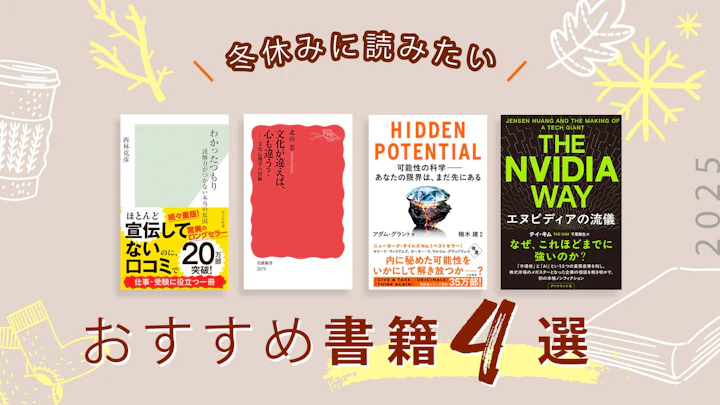
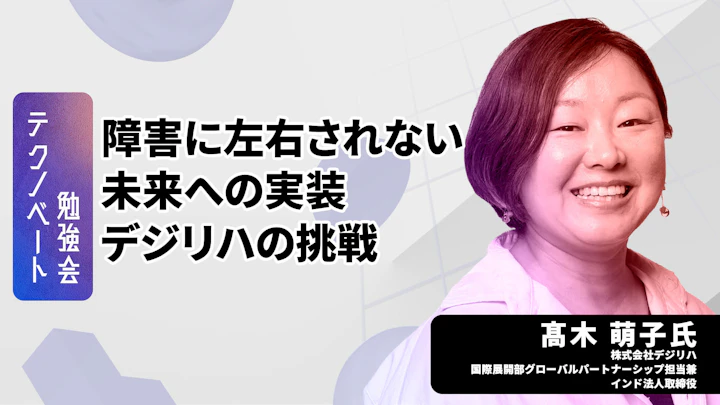













.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)




