本記事は、G-STARTUPセミナー「産業変革に向けて指数関数的な成長を続ける戦略構築」の内容を書き起こしたものです。(全2回 後編)
今野穣氏(以下、敬称略):なるほど。一方、ラクスルの良さに関して言うと、CFOである永見世央氏(ラクスル 取締役CFO)の存在もすごく大きいと考えています。彼はどうやって獲得したんですか?
1トップ状態で会社が疲弊、CxO採用へ
松本恭攝氏(以下、敬称略):永見さんの採用はシリーズBが見えたタイミングです。13年10月ぐらいに動き出して11月頃には何社かコミットしてくれるところが出てきたので、「あ、これはきちんと調達できるな」と思えたタイミングですね。
当時の私が持っていた課題感は、1トップの状態でチームが結構疲弊していた点です。私がトップで、かつマーケティング、カスタマーサポート、ウェブディレクション等々、各部門の責任者もすべて私が兼ねていました。「私とメンバーたち」という状態です。それで、当時は必死にやっていたので当たりも比較的強く、組織がだいぶ傷んだ状態になっていました。事業は急成長しているけれども組織が追いつかず傷んでいくという。それで、「これは1人でやるのは限界があるな」と。かなり早い段階で能力的にも精神的にも限界を迎えると思い、リーダーシップチームをつくらないといけないと考えました。
そのタイミングでCクラスを、CFO、COO、CMO、そしてCTOと、ポジションを分けて採用しようと考えました。それで、ビズリーチを使って、自分よりもキャリアがはるかに上で、かつマネジメントできる方を採用する方向に舵を切りました。そうして、ちょうど1月に永見さんとビズリーチで会うことができ、4月に加わっていただいた形になります。
今野:B直前まで松本さん以外にCxOはいなかったということですか?
松本:COOはいましたが、当時のディシジョンメイキングはほぼ1人でやっていました。
今野:あるところまでは1トップで引っ張る会社は結構多いですよね。逆に、早いタイミングでCxOを乱発すると良くないこともあったりしませんか?良い肩書きの人が来たりして。
松本:それは強く思います。バランス感覚の話として、私はトップがすべての仕事について一定の解像度を持つ必要があると思っています。言語化できる必要はないと思いますが、すべての情報が集まったところで最初の一周はトップが回すというところまでやらないと、トップの意思決定が解像度のないものになって間違いを起こしやすくなると感じています。
今野:たしかに。私は資金調達もAまでは社長がやるべきだと思うんです。それをCFOとか、ましてや外の人がやってしまうと、その大変さやプロトコルや期待値調整がすべてズレてしまう。Bぐらいまでは1トップですべて引っ張るほうがいいんですかね。
松本:本当にそう思います。私は結果的に、WEBづくりのディレクション経験、Google Adwords(現グーグル広告)のダッシュボードを触って数字をまとめる経験、テレビCMですべて設計して回す経験、あるいは組織の報酬体系から評価制度まで決める経験等、すべて自分で行ってきました。高度なことはやっていませんが、プリミティブな部分を自分の頭で考えて取り組んでいました。そうした経験を通して、結果的にはどの領域を見てもだいたい理解できるようになったと思っています。
たとえばデータベースの設計も最初の最初はやっていたので、何を話しているかは分かりますし、そうした経験で土台ができると分からない領域が減っていきます。でも、分からない領域が1つでも出たときにトップが「任せる」になってしまうと、それでうまくいけばいいのですが、うまくいっているか否かの判断ができなくなってしまう。ですから、チーム化をするタイミングで「強いチーム」をつくるのは当然重要ですが、その手前の段階で「強い個人」であるために、幅広い経験をしていくのはとても大切なことだと、今振り返ってみると感じます。
今野:現在のラクスルさんは物流事業の「ハコベル」と広告事業の「ノバセル」も手掛けています。比較メディアからECに入り、そこから物流をやってテレビCMということで、もう4つの大きな事業体をつくっている、と。そうしたコングロマリット化というか、新しいビジネスをつくるのも上手だなと思うのですが、その辺はどんなタイミングで何を考えて参入しているのでしょうか。
「次は何をやるか」と常に探し続ける
松本:2009年9月1日に会社を設立して最初の仕事はビジョンをつくることでした。どのタイミングでビジョンやミッションをつくるのかという議論はよくあると思いますが、ラクスルの場合は、私自身が「産業の非効率性を改善する必要があるし、それができると世の中が良くなる」と信じてスタートした会社です。それで、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」というビジョンでスタートしました。その意味では印刷業界の仕組みを変えるだけでラクスルという会社を終わらせたくなかったし、常に「次は何をやるか」ということを探し続けています。
ただ、「ハコベル」と「ノバセル」は少しスタートが違っています。ハコベルは2014年末、シリーズCが決まるかどうかぐらいのタイミングで取締役会にかけて、ほぼ全員に反対されましたが、それでも「やりたいからやる」と言って、2015年から本格的にスタートした事業です。きっかけは物流業界が印刷業界と同じような多重下請けの業界構造だったこと。大きな産業で、大手数社が寡占していて、下請けは数万社におよんでいて、かつ生産性が非常に低い産業というのはないか、と。そういう視点でいろいろな産業を見ていたのですが、物流業界はまさにそれでした。
物流業界は14兆円の市場で大手10社がマーケットの半分を持っています。一方で、6万3,000の運送会社があり、下請けは5レイヤーから7レイヤーぐらい。まさに、「これを解決すると業界が大きく変わるのでは?」と思えるような状態でした。また、一方で海外を調べてみると、その領域でベンチマークになるような企業が出はじめていたタイミングだったということで、「あ、これはいける」と。そう思ってはじめたのが「ハコベル」ということで、コンセプトからのトップダウンになります。
今野:アナロジーの水平展開ですね。
松本:そうです。一方で、「ノバセル」はまったく逆のアプローチでした。2016年の話です。当社はそれまでコールセンター業務を大手コールセンター会社に委託していたのですが、「内製化しないと良い人材が採れないね」と。それで、自分の足で全国9都市を廻ってマーケットリサーチをしていた時期があります。たまたま大分でトランスコスモスさんにお話を聞いていたとき、「今、大手携帯電話会社から受注を請けていて、2ヶ月で300人、大分市でスタッフを雇わなければいけないんです」という話を伺いました。で、そのための広告予算は500万円ということで、「ラクスルさんの新聞折込サービス、いいですね。使わせていただけませんか?」とおっしゃるわけです。
ただ、我々は当時すでに自社のテレビCMを数多く打っていて、大分のGRP(Gross Rating Points)単価も頭のなかにあったものですから、「500万円あるのであればテレビCMを制作して放送したほうがいいですよ」と提案したんです。そのときCM事業をやっていたわけではないのですが。すると、「え?テレビCMってそんなに安く打てるんですか?」と驚かれて。500万円あれば、ほぼ全員に携帯電話会社の求人があることを知らせることができる。ところが、東証一部上場企業の本社で経営企画をやっていた方々にはその事実が知られていないわけです。そういうことに衝撃を受けました。
それで、「あ、この業界、実は価格が不透明で、ほとんどのユーザーがテレビCMは高いと思っているのでは?」と考えました。でも、実際の売値はものすごく安くて、そこにギャップがある。「それなら、テレビCMの価格を透明化してコマースで販売したりすることで、テレビCM業界を変えることができるのではないか」というアイディアが浮かびました。それで社内のメンバーに投げかけたところ、今ノバセル事業の責任者をしている田部正樹(ラクスル 取締役CMO)だけが、「あ、それいいですね」と反応してくれて。そこからスタートしたという形で、こちらはボトムアップですね。
今野:テレビCMも代理店からすると都市と地方でバンドルしていて、ごちゃ混ぜになっていますから。地方だけなら、もっと安くできるところはたくさんあるわけで。
松本:そうですね。とにかく、拡張したいという気持ちはもともとありました。そのうえで、トップダウンのアプローチとボトムアップのアプローチの両方があるわけですけれども、テレビCMサービスに関して言えば今はお客さんの7割が印刷サービスも使ってくださっています。クロスセルからスタートして、2年目にはクォーターで7~8億円、年間で30億円ぐらいのサイズ感になってきました。ですから、顧客ベースを拡大できると、ブランドの拡大でレバレッジが効くという意味では非常に強い事業だなと思っています。
「プレイングマネージャー」から「経営者」に転換し、最悪な時期を乗り越えた
今野:ここまで聞いた会場の皆さんは、松本さんがあまりにも理路整然とお話をなさるので「苦労はしてないのでは?」と、いい意味で感じているかもしれませんが、今までで1番大変だったのはどんなときでしたか?
松本:大変だった経験はたくさんありますけれども、一番大変だったのは第1章から第2章への移行ですね。事業はすごくうまくいっていました。良いときはMoMで100%でした。
今野:月で倍々という。
松本:ただ、そういうときに組織が最も傷んでいました。マネジメントがいない中で自分がすべての意思決定をして、完全にキャパオーバーを起こしていたんです。自分自身が事業マネジメントでキャパオーバーとなっているうえに、ピープルマネジメントも決して得意ではなかったので。24歳で起業して部下を持ったことがなくピープルマネジメントの経験がなかったのに、当時は突然20~30人、カスタマーサポートを含めると50人ぐらいの部下ができていたわけですね。それで、皆のモチベーションをしっかり高めて目標設定をして、権限移譲をしていくということができませんでした。すべてにおいて必死だったので。それで組織が大崩壊して、当時の離職率は40%に達していました。
今野:Bの前ぐらいですよね。そのことで1度ご相談いただいた記憶があります。
松本:A前とB前で2回あって、そのときが一番辛い経験でした。原因は自分にあって、自分を変えないとどうしようもない状況だった、と。ただ、そこで自分の性格やスタイルを変えるのか、自分とメンバーとの関係性や組織のあり方を変えるのか。私は自分の性格やスタイルは変えることはできないと思っているし、これはエゴですけれども、変えないほうがいいと考えています。変えると良さが失われると思っていて。ですから、社長室をつくって皆と会わないようにしました。たったの30~40人のフェーズで。そのうえで、それぞれの領域で自分より優秀な人を採用して、その人たちに全権を委譲する形にしました。
その結果、たとえばCMOが来たときは、私が3年かけて関係性を築きあげてきた広告代理店のチームとの取引を辞め、別の代理店に移すなんていうこともありました。でも、そういうことも含めて、信じた仲間や優秀な人が働きやすい環境、形にしよう、と。任せたうえで口出ししないという風に変えました。会社との距離が変わったというか。それまでは最前線にてすべて自分で決めていたので。
今野:プレイングマネージャーから経営者になったような感じですか?
松本:そうですね。そういう風に変化して最悪な時期は乗り切ったと感じています。
今野:素晴らしい。続いて、IPOについてはどのように考えていて、どんな風に進めていたのでしょうか。ラクスルさんのIPOは割と大きなニュースにもなりましたが。
「IPO」は1合目
松本:IPOはすごく自然に、まさに黒字化を迎えたタイミングで行いました。50億の赤字を掘ったうえで、売上にして80億ぐらいが見えたタイミングで、「黒字化するなら」と。赤字のときは未上場のベネフィットを最大限受けることができると思いますが、逆に黒字化するなら上場したほうが資金調達の流動性もフレキシブルになります。実際、我々は上場したあとに100億円を調達しているし、未上場のときより簡単に調達できるようになりました。このときは79億円をVCの方々に出資していただきましたが、そうした流動性を供給するタイミングも必要だったということでIPOを実施しています。
今野:資金調達の柔軟性と、株主の入れ替え、流動性の供給あたりが決め手だった、と。
松本:はい。一番大きいのは黒字化ですね。
今野:そのときの工夫について、何かお話しできることがあれば。
松本:当時は、まずIPOをどのように位置づけるかという議論がありました。「IPOというのは1合目だ」と、私はチームによく言っていて、実際のIPOでも「ようやく1合目まで来ることができました」とコメントしています。上場タイミングでは、たとえばエムスリーさんは400億ぐらい、モノタロウさんは200億ぐらい、GMO Payment Gatewayさんは200億ぐらいでした。ただ、それらの会社に今どれだけの価値があるかというと、2兆円とか。IPOをしてから100倍になったりします。ですから、IPOというのは企業価値を高めるためにすごく良いツールだと思っています。
では、企業価値はどのように高めていくのか。企業価値を高め事業価値をつくりだし、社会のインフラになる事業をどのようにつくり出していくのか。投資家に応援されることで我々は未上場でもいい事業をつくることができましたし、そのなかで投資家との良い関係性をつくってきたのはすごく良かったと思っています。上場してからもそれは一緒です。ただ、上場後はそれまでのVCがパブリックインベスターになるわけですが、多くの会社はパブリックインベスターが入りづらい。
我々は機関投資家に株を持って欲しかった。特に、VCと同様、長期視点で「何に投資すると事業価値がどのように高まるか」という部分に理解があり、それをディスカッションしながら決めていくことのできる投資家に入って欲しいと思っていました。たとえば、アマゾンが上場した直後から投資し続けていたり、アリババのIPOタイミングからずっと見ていたり、ユニコーン企業にプライベートラウンドから入って、上場後もずっと株と持っていたりするような投資家ですね。そういう事例をたくさん見てきた投資家を巻き込んで、我々の株主になっていただいて、そのナレッジを貸していただきたい、と。また、それをすることで、たとえば利益が出なかったとしても企業価値が高まる点を評価してくれる投資家に入って欲しいと考えていました。
ですから、いわゆる“マザーズの壁”、“死の谷”を乗り越えるため、VCの方々に全株式を売り出していただきました。その代わり、機関投資家、特に海外の機関投資家の方々に上場タイミングで数百億規模の買い入れをしていただいています。いわば、バトンタッチですね。プライベートラウンドを支えていただいた投資家から、パブリックラウンドを支えてくれる投資家にバトンをうまく渡すための場づくりということをしました。
ただ、これには良い点も悪い点もあったと思います。我々にとっては良かったのですが、あたかも「これが答えだ」みたいになってしまって。それで今は多くのスタートアップが同じことをしようとしています。でも、これはしたほうがいい会社としないほうがいい会社があると思います。期待値ではなく事業をベースとした企業の価値がしっかりあって、一定程度のサイズがあり、かつマネジメントが海外の機関投資家ときちんとコミュニケーションできる体制になっている会社はいいと思います。でも、そうでないために、むしろ皆が不幸になるケースも何件かあったと聞いていて、その辺はちょっと功罪があったかなと思っています。
今野:ご存知ない方のためにご説明すると、ラクスルさんは上場時に(取引所の規則として売却不可の株式を除いて)流動株をすべて売却に出しました。当然、VCからすれば「もっと上がるのでは?」と思うわけですが、松本さんがそれを“場づくり”と言ったのは、上場時、高めに設定したということですよね。その状態で入ってくるのは「入るのなら大きなサイズで長期間持ちたい」と考える投資家なので、彼らとのマッチングを、上場を通じて行ったわけです。ただ、その後数社が同じような手法を取ったのですが、それほど事業性がなかったりしてサイズのある投資家がつかなかったケースもあります。その瞬間、上場時に目論んでいた値段ががくんと落ちてしまったという。
松本:売出しが大きくなって個人投資家しか付かなくなるとどうなるか。個人投資家の方々は本当に強烈です。我々を買った投資家の方々の、1ヶ月後の回転率は200%台。全員2周していました。一瞬は付きますが、すぐに投げ売られる、と。ですから、「この会社の価値が本質的にいくらなのか」ということを自分の頭で考えることのできる投資家がいないと、永遠に下がっていくわけです。
今野:そうですね。さらに言うと、上場時に目論見書に書いてあった値段からだいぶ落ちてしまった会社もありましたよね。投資家によるプレゼン評価の見込み違いで下がってしまうと、マーケットに対してすごく大きなメッセージが出てしまう。「これは人気がないですよ」と。ですから、“ラクスルモデル”が通じる会社とそうでない会社があるとは思います。
松本:結局、それも自分の頭できちんと考えたほうがいいのではないかなと思っています。ベンチマークとして参考にしていただくのはいいのですが、決してこれだけが答えではないですし、すべてはケースバイケースですから。
目標を常にアップデートし続ける
今野:分かりました。最後に1つだけ。松本さんはどのようにご自身を成長させていますか?自分の成長について何か心がけていることがあれば。
松本:基本的に、私は必要とされるケイパビリティに今の自分が届いていないという状態がずっと続いています。目標を常にアップデートし続けているからです。それがすごく重要なのかな、と。そのうえで、目標をアップデートしたとき、それを実際に達成したことがある人を調べて、その人に会いに行くなりして、アドバイザーになってもらったりしています。たとえば、先般はオリックスの宮内義彦氏(同社シニア・チェアマン)に当社の社外取締役として入っていただきました。
今野:それもすごいですよね。
松本:宮内さんは、ほぼゼロから4兆円企業を一代でつくりあげられた方ですから。今は複数の事業ポートフォリオで企業を経営していくにあたり、どのような投資やガバナンスであれば個別の事業を成長させることができ、かつコーポレート全体で価値を最大化できるかというチャレンジをされています。そんなわけで、今はたとえばGEの人事制度を参考にしたり、ポートフォリオや予算策定における考え方についてゼロから伸ばすということをなさってきた方にメンターとして入っていただいたりしています。ベンチマークにしている企業と当社が置かれている状況との差分を見て、それを埋めていくという作業を続けています。
今野:お題の設定がすごく適切だと感じますし、逆に言うとウルトラCをしているわけでもないというか、原理原則に則っているということですよね。
松本:そうですね。「すべては皆が1度通った道だ」と思っています。過去に起きたことはまた必ず起きる、と。ですから、過去に何が起きて、さらには「そのタイミングで成長してきた会社が何をしてきたか」といったアナロジーを調べて、自分との差分を見つけていくというのが、僕なりの自分を成長させる方法になります。
<前編はこちら>























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
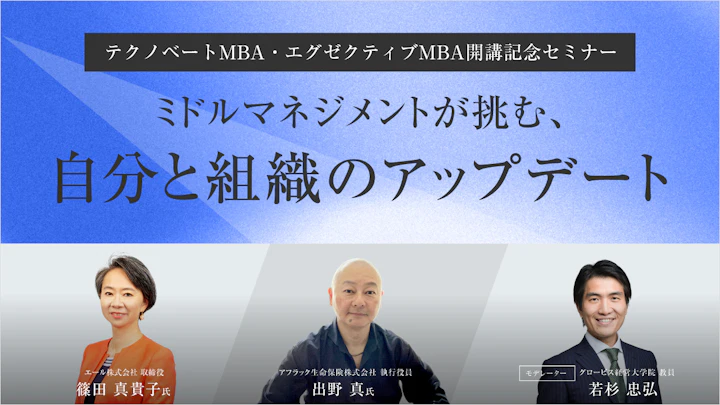
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

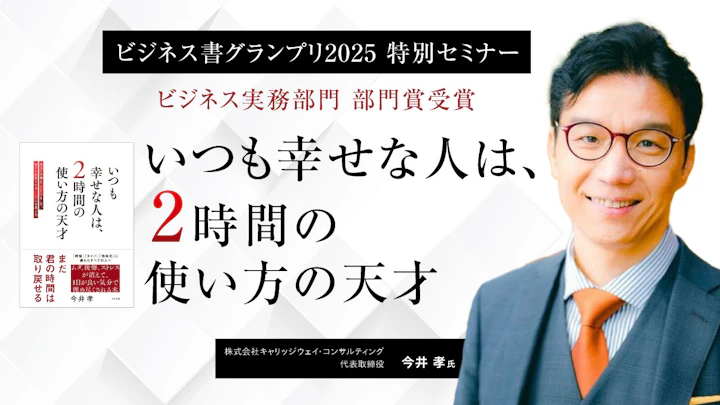
















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

