企業が事業変革や構造改革を行っていくためには、もはやDXが欠かせない。そんな変化の中、2018年に「IT小売業宣言」を掲げた株式会社カインズは、ゼロから新たなデジタル体制を整備し、施策を実行。高成長を続けてきた。 このカインズのデジタル戦略の仕掛け人、執行役員CDO兼CIO兼デジタル戦略本部長兼イノベーション推進本部長の池照直樹氏へのインタビュー。今回は、ゼロから成し遂げたデジタルチームの内製化や、「リテールでのDX」だからこそ意識した点などについて伺う(Vol.1はこちら)。聞き手は引き続きグロービス マネジング・ディレクターの板倉 義彦。
デジタルチームの内製化を導入し、約20億円の人件費を削減
板倉 前回までのお話を通じ、デジタル用語をあえて使わずに、デジタルマーケティングのわかりやすい説明をすること、そして次に従業員のDNAに刺さる戦略に落とし込むことがデジタルイノベーションでポイントになると理解できました。その他に、ポイントはありますか。
池照 デジタルをやり始めると、新しい仕事が増えてきます。認知コントロール上は、同じ仕事を同じようにやる方が、計画しやすいわけです。でもデジタルによって、業務が増えてしまうと、「どうしよう、何か業務を減らさなきゃ」となるので、そのまま放置しておくと、業務に取り組めないわけです。
そこで、それまで開発はSIerに任せていたところ、社内にエンジニアを雇用し、アプリケーション開発を内製化しました。販売の現場などに必要なアプリを投入して、効率的に作業を行えるようにしたのです。
板倉 それによって、コストなども削減できたのでしょうか。
池照 アプリを投入したことで、数十億円レベルで業務が減りました。このアプリ投入にあたっては、社内のエンジニアには要件定義禁止令を出し、ユーザーである現場(販売)から「何がやりたいのか」を直接聞いて、「簡易に作ってくれ」と指示しました。
ローコードでいいので、打ち合わせで聞いたことをもとに、まず作って、1週間ぐらいでリリースします。そして、リリースしたものに対してユーザーの評価を聞いて、修正していく。開発したプロトタイプをベースに、要件定義を行っていく感じです。だから、「パーフェクトなシステムを作ってはダメ」「8割でリリースしなさい」ということを、エンジニアには何度も話しました。
板倉 ということは、どんどん機能追加していくわけですか?
池照 機能追加しか行いません。プロトタイプを、打ち合わせをしながらプロダクトへと仕上げていくイメージです。こうすると、徐々にエンジニアは持ち帰らずにその場で直していくようになるので、スピードがどんどん速くなって、効率化していきます。
板倉 非常に斬新な発想ですが、この考えに至ったのはどこからなのでしょうか?
池照 過去立ち上げたシステム開発会社での経験からです。私は昔、マイクロソフトのDynamicsCRMというCRMツールを、ローコードで開発するシステム開発会社を立ち上げました(ケイ・ピー・アイ・ファクトリー)。
当時はクライアントに聞いた要件について、打ち合わせの場でエンジニアとディスカッションしながらソフトウェアを作っていました。そうすると、わざわざ要件定義をしなくても開発ができるので、ユーザー(クライアント)とエンジニアとの間で信頼関係が醸成されていきます。
これを外部のSIerにお願いすると、お互いビジネスだから、仕事の範囲(要件定義)を決めなければなりません。そうしないと、次のフェーズにも入れない。なるべく効率的にプロジェクトをやっていかないとSIerも商売にならないですから。外部のSIerに頼むと、そういうビジネスモデル上の課題が発生します。
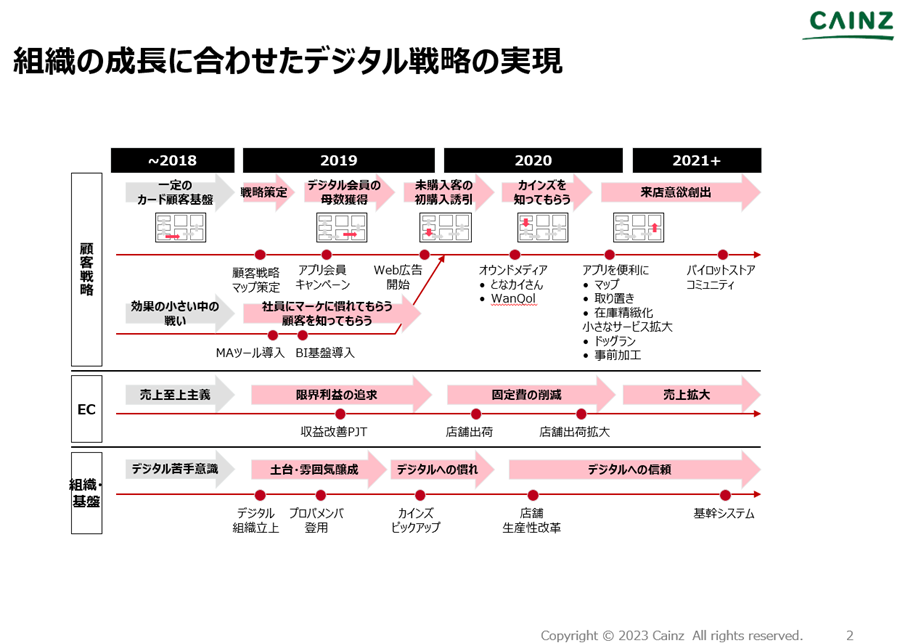
板倉 それでアプリ開発の内製化を導入したわけですね。
池照 そうです。発注する側からすれば、厳密に要件定義を行わなくてすみますし、それでいて1週間後にはアプリができ上がってくるので安心感があります。内容に変更が発生しても、SIerだと要件定義をし直して、再見積もりを行って、再スタートとなってしまいますが、自社内開発なら、それもありません。
シーケンス(手順、仕様)自体が無駄を作ってしまうので、とにかく発注依頼(修正)をぐるぐる回せるようなモデルにするために、シーケンスを省き、デジタルチームの内製化を導入したわけです。
リテールの人たちが苦手とする、中長期視点でのストーリーづくりのスキルを徹底的に鍛えた
板倉 新たにエンジニアを雇用して開発組織を内製化したとなると、現場の人たちもエンジニアと対話しながら仕事をする文化は元々なかったわけですね。そこはどうやって定着させていったんですか。
池照 現場から3人、積極的な人材を引っ張ってきました。現場とエンジニアの間に立つ、翻訳者のようなポジションになってもらい、アプリケーションを開発していくプロセスをゼロから一緒に作り上げていったんです。
板倉 この3人にどのような業務を任せていたか、もう少し具体的に教えてください。
池照 まずは「プランニング」です。何を実現するためにアプリを開発するのか。目的に対する評価を、徹底的にしかも大量に経験してもらうようにしました。その昔、私がミスミの三枝さん(ミスミグループ本社 名誉会長:三枝 匡氏)から学んだやり方を、下の世代に伝えていました。
そこで重視したのは、現場の人たちに不足していた、中長期視点での思考と実行です。とにかく、中長期視点でストーリーを作ることが重要です。何かを変えていく(直していく)腰を据えた取り組みは、リテールの人たちは、非常に苦手です。しかし、中長期視点でストーリーを作っていかないと課題も見えないし、今後の変化にも対応できません。
板倉 基本的にリテールは日銭を稼ぐビジネスなので、そうした思考になってしまいがちかもしれませんね。
池照 カインズには、現社長の高家が副社長時代に導入したアクティビティベースドコスティング(ABC、Activity-Based Costing:活動基準原価計算)があり、これで「生産性改革」のストーリーを作ることができました。
<参考動画>ABC (活動基準原価計算)~正確な原価計算を行う手法~|GLOBIS 学び放題
板倉 ABCを用いると、どんな業務に、どのぐらいの時間を要するのかが分かりますね。そして一つひとつの工数(時間)削減などを、ディスカッションを繰り返して、練り上げていったと。
池照 3人はエンジニアとのディスカッション、やりとりが初めてだったので、まず私が手本を見せながら、エンジニアと現場それぞれの要望を分かりやすい、一般的な言葉に置き換え、齟齬がおきないように、進めていきました。
そのうちに彼らが翻訳者を担うようになって、次第に翻訳がなくても、現場とエンジニアで会話ができるようになっていきました。いまではこのプロセスも定着したので、その人たちは現場に戻り、現場での生産性改革やイノベーションのリーダーとして、指揮や後進育成に取り組んでもらっています。
(次回につづく)

















































.png?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

