デカコーン企業とは、ユニコーン企業の10倍となる100億ドル以上の企業評価額が付いたスタートアップ・ベンチャーを指す。TikTok運営のByteDance、イーロン・マスク氏が立ち上げた航空宇宙企業SpaceXなどが該当するが、日本には未だ存在していない。
グロービスはこの度、テクノベート経営研究所、通称:TechMaRI(テクマリ)を設立した。
ミッションを「テクノベート(Technology×Innovation)時代の産業創生・企業育成を研究し、大学院のカリキュラムに反映させると共に、日本発のデカコーン創出に寄与する」と定めたこの新組織は、グロービス経営大学院とグロービス・キャピタル・パートナーズ(GCP)との共同で運営される。
TechMaRIとはどんな組織であり、日本のスタートアップエコシステムにどのように貢献しようとしているのか。
今回はGCP共同創業パートナーであり、TechMaRI初代所長を務める仮屋薗 聡一と、同じく副所長を務め、グロービス経営大学院で創造系(ベンチャー関連)科目をリードしてきた髙原 康次の対談をお届けする。
100のユニコーンより、10のデカコーン?
髙原:昨年、政府によってスタートアップ5ヵ年計画が発表されました。この中では「100社のユニコーン企業を生み出す」という目標が掲げられるなど、日本のスタートアップは盛り上がっているなと感じます。
仮屋薗:「100社のユニコーン」というと意欲的で大胆な目標だなと思いつつ、数値に重要な意義があるかというと、そんなことはないと思っています。重要なのはこの背景にある思想です。それは「新産業におけるリーダー企業、もしくはグローバルにスケールしていく企業を日本から輩出する」、そんな社会的インパクトを国家レベルでうみだそうという思想です。
そういう意味ではもしかしたら、100のユニコーンという以上に、10のデカコーンを作るということが重要な観点になるかもしれません。
髙原:テクノベート経営研究所、通称TechMaRI(Technovate Management Research Institute)は「日本発のデカコーン創出に寄与する」というミッションを掲げ設立されたシンクタンクです。
われわれでこの巨大なミッションに立ち向かうにあたりさっそくですが、仮屋薗さんは日本のスタートアップにとって何がポイントになるとお考えですか。
日本でユニコーン/デカコーン企業を創出するために
仮屋薗:重要なポイントとしては、まずやはり市場選定です。そもそもしっかりとスケールする可能性のある市場を選定することが大切です。また、グローバルで競争優位性を持つために日本が世界に通用する特定領域や技術を持っている領域であるかどうかも鍵になってきます。
次に2つ目は、技術を活かす環境が整っているかです。技術を持っていたとしても、それを使いこなせる人材が必要です。また経営人材も必要ですし、その領域における適切なエコシステムが揃っているかどうかも重要な観点です。
そして3つ目のポイントとして、しっかりと資金を中心とした資源を投下できるかです。これは起業家や各社の経営資源と共に、社会・国としての資源投下の必要があります。
ではこの資源投下ができるようになるには何が重要か。それは、国全体でパッションやストーリーを持って取り組める領域なのかどうかです。例えば、日本は世界でも特に高齢化が進んでいますが、ここに先進的なソリューションを提供すると、世界的なリーダーシップを発揮できると思います。このように、自然に人々が関心を持つような領域やストーリーのある領域を探索していくことが重要なポイントになると思います。
髙原:TechMaRIはこの資源投下という観点について、グロービスが蓄積してきた「ヒト」「カネ」「チエ」の経営資源を統合的に社会還元していく役割を担っています。
ここで、この「グロービスが蓄積してきた経営資源」や、日本のスタートアップエコシステムへの見解について改めてお話していきたいと思います。
GCPが見てきた日本のスタートアップの変化
仮屋薗:そもそもグロービスが創業された90年代は、それまで日本が世界経済をリードしていたところからバブル崩壊へと、スタートアップの創業環境としてはまったくのゼロベースと言える環境でした。そもそも、「スタートアップ」という言葉も一般的ではありませんでしたし、マザーズなどの出口も存在しませんでした。
そんな中、1996年に設立されたのがGCPです。日本のベンチャー・キャピタルとしては初めて本格的なハンズオン型をとり、経営者と共に成長しながら、資金、人脈やノウハウ、そしてIPO準備を含めた価値を提供してきました。
アーリーステージからの支援に注力しており、これまでユニコーンとなったメルカリやスマートニュースなどへの投資実績があります。
髙原:こう聞くと、スタートアップの出口戦略や社会的影響力には当時と比べて大きな変化が生じていますね。近頃は、1件あたりの投資金額も増え、資金の出し手もかなり多様化してきています。
仮屋薗:この10年、特に2010年代に大きく変化したと思います。リーマンショック後の落ち込みから、昨年は8000億円規模の調達が行われるなど、日本のスタートアップの年間調達額は10年かけておよそ10倍規模にも達しています。
そして機関投資家のような巨大な資金投下を行う存在、あるいは成功した企業家が後輩を育てる、いわゆるエンジェル投資家が日本でも広がってきました。金銭的なリターンを求める投資以外に、社会へのインパクトでリターンの大きさを測るインパクト投資も一般化しつつあります。
アメリカや中国などの大国に比べるとまだまだ差がありますが、日本のスタートアップエコシステムは様々な局面で着実な進化の途上にある、というのが今なのではないでしょうか。
イノベーションは今や普遍的になった
髙原:資金面以外ですと、スタートアップにはどのような変化が起きているとお感じですか。
仮屋薗:2010年代を通じて、スタートアップは人々の身近な存在になり、興味を持たれやすくなってきたと感じます。テクノロジーが進化したこと、またより大きな社会全体の枠組みでイノベーションが捉えられるようになりました。その結果、スタートアップやイノベーションが、以前は局所的なものであったところ、今や普遍的な社会の基盤をアップデートする活動となってきたのだと思います。
特にスタートアップの主要部分を占めるIT産業からは、多様なイノベーションが生まれています。
髙原:確かに、中小企業のバックオフィス業務に対してソリューションを提供するマネーフォワードやフリー、SmartHR、ダイレクトリクルーティングを普及させたビジョナル、印刷や物流に取り組むラクスル、近頃は製造業向けのキャディなど、着実にスタートアップの影響が広まっていますね。
仮屋薗:DXの重要性が高まったほか、ライフサイエンス分野や地球環境に対する意識も人々の間で高まり、テクノロジーを活用したソリューションが求められています。
髙原:ライフサイエンスだと、創薬プラットフォームのペプチドリームが有名ですね。地球環境ですと、再生可能エネルギー事業に挑むレノバがあります。スタートアップが様々な形で社会に貢献している姿は、心強く思います。
仮屋薗:また、「起業家である」こと自体も、大企業のサラリーマンより成功した時のインパクトも大きく、資産面でも有利な魅力あるキャリアの選択肢として認識されるようになってきました。スタートアップで働く人の平均給与が大企業を超えてきているという報告もありますし、ここでも社会が変わりつつあることを感じますね。
こうした変化に応じて、起業家自身の姿勢も変わってきましたし、経営者やビジネスパーソンに求められるスキルも大きく変化しました。
(次回に続く)







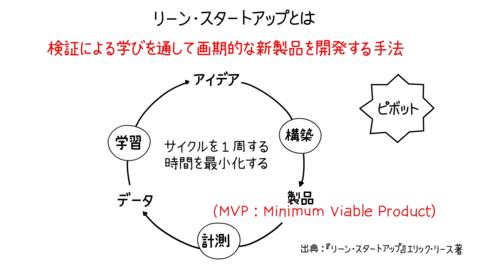





























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

