「イニシェリン島の精霊」は欧米では2022年、日本では2023年に公開された映画作品。1923年のアイルランドの孤島を舞台に、アラフィフの年齢と思しき素朴な島民のおじさん二人の諍(いさか)いを描いた作品だ。はじめは単なる口喧嘩と思われた争いは、やがて過激な方向へと発展していく。本作は2023年の第95回アカデミー賞に8部門でノミネートされるなど、特に批評家筋から高い評価を得た。
劇作家出身で、シニカルで知的な作品づくりで知られるマーティン・マクドナー監督がオリジナル脚本を書き監督も務めている。興行収入狙いのエンターテイメント作品ではなく、監督が作り込んだ「作家性」が表現される作品、と意識したうえで見るべきだろう。
分からない、しかし、考えが止まらない
ストーリーはシンプルだ。登場人物は少ない。会話量も多くない。にもかかわらず、最初に見終わった後には「とにかく、わけがわからない」「こんな話をなぜわざわざ映画にしたのだろう」との感想をもった。にもかかわらず、その後数日間、この映画が頭から離れない。人々の感想や分析、WebやPodcastを漁るなか、自分の身の回りにもこの映画の主題がある、と気がついたときには、この作品の深さに魅了されていた。
閉鎖空間での人間関係の対立がもたらすもの

この映画には、時代も、地域も、仕事もまるで違う日本で生きる私たちにも、問いかけるテーマがある。それは、人間と人間との「対立」、特に閉鎖的な状況での対立はどのように始まり、どのようにエスカレートしていくのか、ということだ。
本作の舞台は、とても小さな島だ。1923年の設定で、島には自動車すらない。道を歩いているだけで、顔見知りの島民同士が何度もすれ違うような濃い人間関係がある。島の対岸には本土が見えるが、行き来には定期船が必要になっている。物理的にも簡単に脱出できるような環境ではない。このような島で、主人公パードリックとコルムは仲たがいを始める。二人の関係について「これまでは親友だった」とパードリックは語る。コルムがどう思っていたのかは、ハッキリは説明されない。
これらが何を暗喩しているのか、読み取り方は観客次第だ。たとえば、家族のなかでの親子や夫婦の関係になぞらえられるだろう。メンバーシップ型で転職が不自由な日本企業内の人間関係とみてもよいかもしれない。二人の不毛すぎるやりとりは、インターネットのSNS上での「クソリプ」合戦もほうふつとさせる。私たちの身の回りにも、閉鎖的で簡単には離れがたい人間関係があり、また、そういう中で突然の争いが始まることも、決して珍しくはない。
コルムとパードリックには人物としての嗜好に微妙な違いがある。パードリックは本当に素朴で天然。コルムはやや文化人的な側面を持つと描かれている。しかし、すこし突き放して見るならば、しょせんは「島民」「同年代の男性」であり、似たもの同士にすぎない。しかし、一度始まった争いは、妙にエスカレートする。私たちは、なんとなく、争いというものは文化や思想が異なる者の間でこそエスカレートする、と思いがちである。しかし、「似たもの同士」の争いこそがこの映画のように本当にとんでもない状態になるのだ。今の世界の実際の争いもそうではないだろうか。
ポリコレ映画の多勢に安易に乗らない
また、監督は現代世界の抱える問題について、ここ10年主流となってきた、ポリティカル・コレクトネス映画たちとは少し違う角度で問いを投げかけているように思われる。ここ10年の欧米映画の主流は、少数派・弱者の目線をストーリーやキャスティングに導入し、従来型の無自覚な強者に気づきや反省を促す作品たちである。
ここで少数派・弱者として多く導入されたのが、女性、有色人種、性的指向における少数派、身体障がい者などであり、強者の象徴は、「白人男性」である。この流れは、この連載でも多数紹介してきた通り、2020年代の今も基本的には続いていると言えるだろう。
対して本作は「今風の文明が全くない、昔の田舎の白人男性同士」の話をひたすら描いており、これだけでも「最近の映画では珍しい」立ち位置と言える。白人男性ではあるものの、お金も、知識も、将来展望も無い二人だ。「退屈な島での時間潰し」というセリフが何度も出てくる。島全体が「弱者」といえるのかもしれない。この二人の争いを見る(おそらく都会人や教養人が多いであろう)観客は上から目線で「別世界の話だ」と笑えるのか、との無言の問いかけを感じる。
そして、二人以外の第三の登場人物としてパードリックの妹のシボーンの存在が重要だ。彼女は本が好きで、島ではいちばん「学」があり、目ざすキャリアゴールも持っている。おそらく、今の「ポリティカル・コレクトネス」を進める人々を、彼女のキャラクターに託して表現しているのだろう。性別を抜きに、一番、この(文芸的な)映画を見ている現代の「観客」に近いと思われる存在だ。彼女がこの島の人間関係や闘争のなかでどう振る舞うのか、監督は緻密に表現している。おそらく、物語の舞台の100年後となる現代の社会にもシヴォーンのような人物は大勢いる、と監督は意識して話を作っている。
分断はどう止むのか
映画が「対立や分断」を扱うことそのものは決して珍しくはない。ただし、日本では相対的に意識されづらいが、欧米経済社会内では、ブレグジット[1]、トランプ現象、BLM運動[2]など政治的対立の先鋭化が大きなイシューになっているのが、この10年間である。
本作の製作動機や受けている高い評価には、そうした現実社会が投影されていると想定し、解釈をしていくのが「グローバル感覚を持った人材」としては自然だろう。逆に、そういう現実社会の投影を意識しないと、本当に「単なる田舎のおじさんの喧嘩」にしか見えなくもある。
そして、作品内では分かりやすい処方箋は示されていない。教訓すら簡単には得られない。「現実社会も同じだろう、エンターテイメントが分かりやすい答えを示すならそれは嘘だろう。きれいな理想論で世の中が片付くかい?」そんな作家の信念を感じる作品だ。いったい、「分断」はどう止むのだろうか。作品を見てから自分の頭で考えるしかない。
[1] 国民投票によるイギリスのEUからの離脱
[2] Black Lives Matter 運動


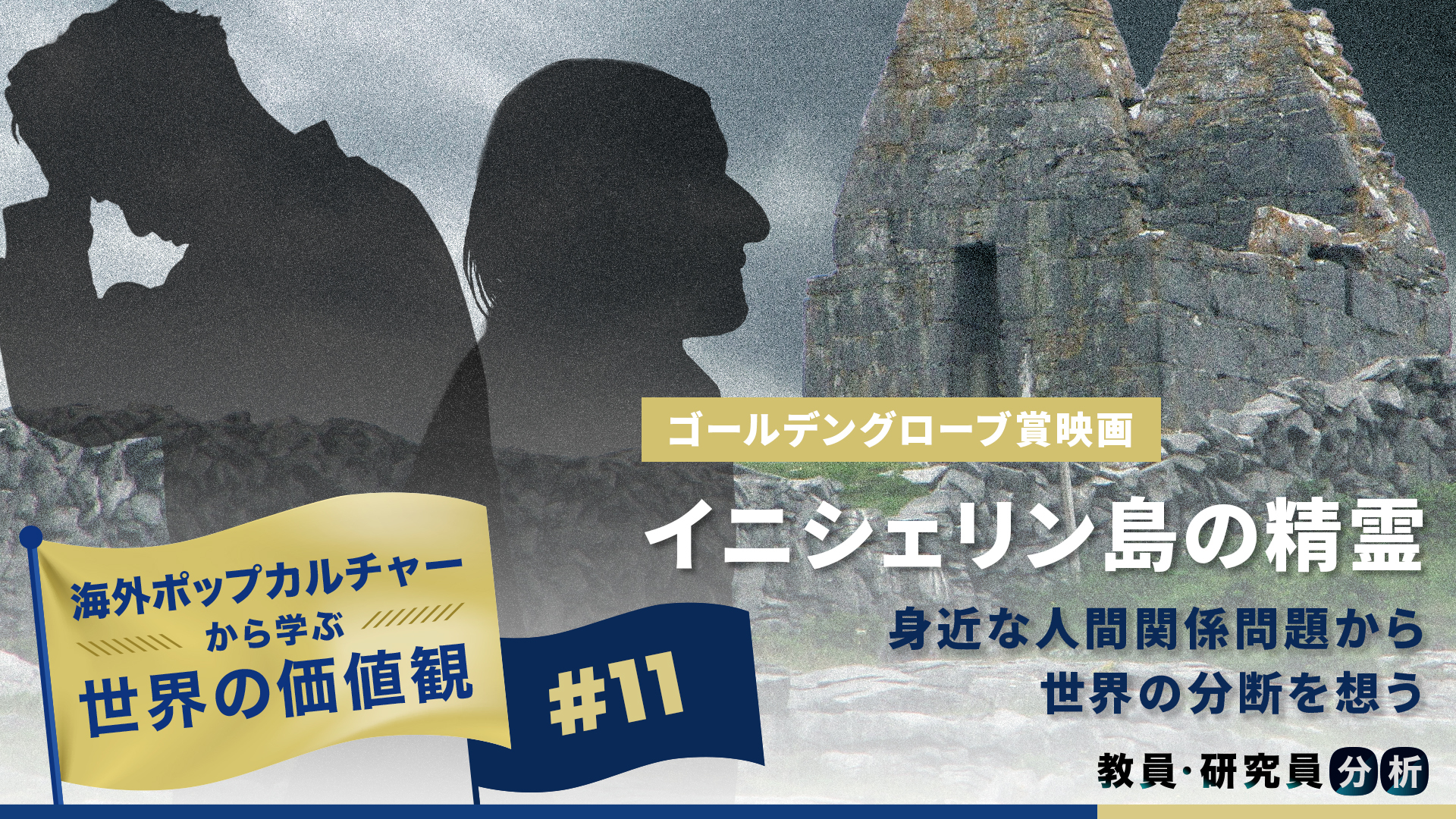






















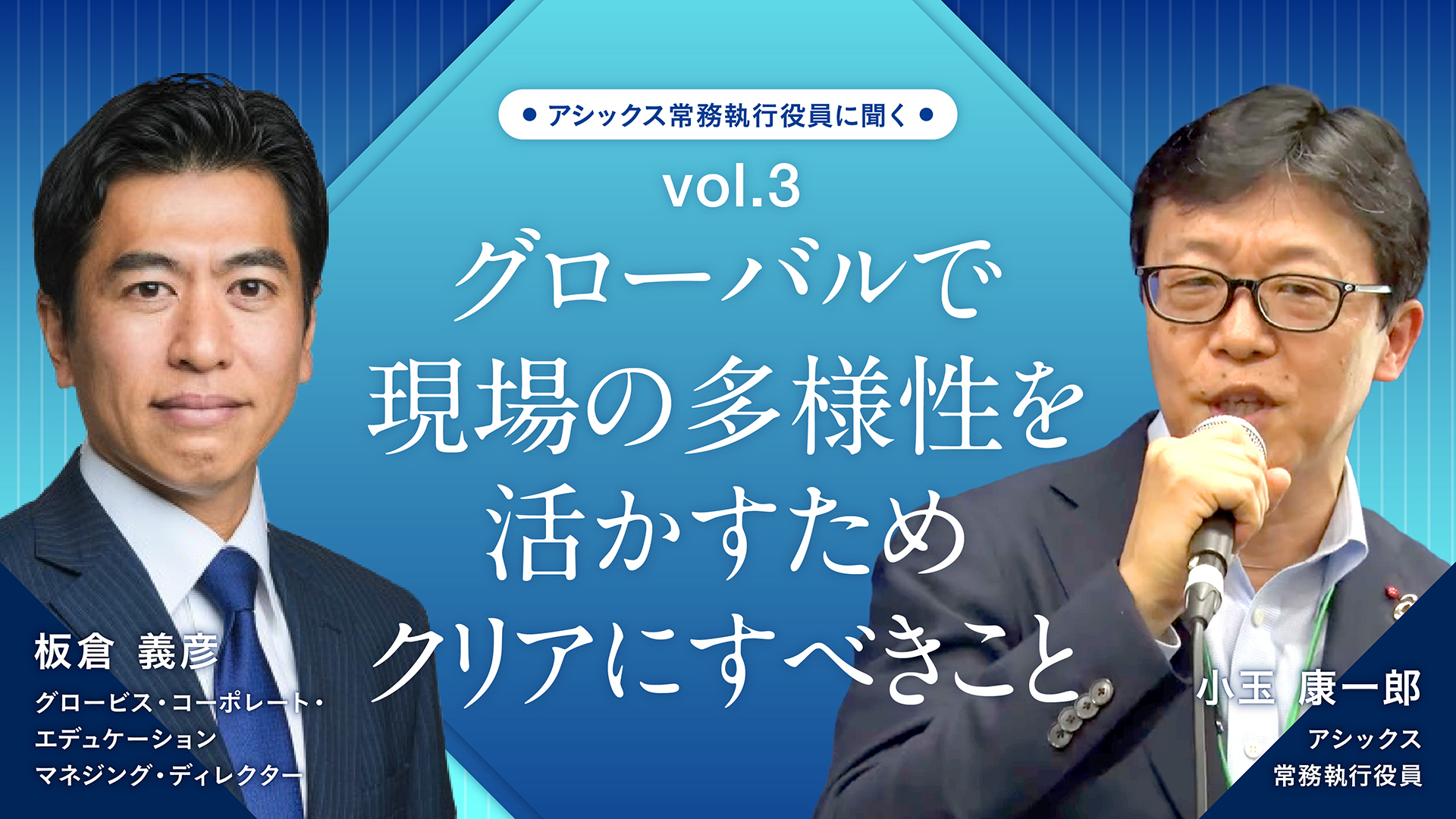











.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)


