チームワークの名の下に埋没する「個人主義」
 仕事を進めていく上で、仲間とコラボレーションしていくことはとても重要だし、チームワークもある程度取れている方だと思う。しかし、その結果として、どうも周囲に依存してしまう傾向があり、個人としての強さが育っていないのではないかという危機意識がある――そういう方は多いのではないでしょうか。
仕事を進めていく上で、仲間とコラボレーションしていくことはとても重要だし、チームワークもある程度取れている方だと思う。しかし、その結果として、どうも周囲に依存してしまう傾向があり、個人としての強さが育っていないのではないかという危機意識がある――そういう方は多いのではないでしょうか。
「戦略を実行していく上で、組織マネジメントにどのような課題を感じていますか?」という問いを投げかけた時、多くの方から聞こえてきたのが、「個の自立」とも言うべき課題意識です。チームワークの重要性は語るまでもありませんが、行き過ぎたチームワークは時として「他人への依存状態」を生み出し、結果的に「リーダーシップ不足」という課題を生みかねません。
では、そのさじ加減はどうすればいいのでしょうか?そのヒントとして、今回は味の素の食品事業における「チームワークと個人主義」のバランスの取り方をベースに考えを深めていきたいと思います。
味の素の食品事業を牽引する「マーケター」
食品メーカーは、新商品の企画開発力、商品化するための高い技術力、営業力(棚取り)といった各機能の全てにおいて、しのぎを削った戦いをしています。時代の変遷と共に変わる顧客ニーズを捉え、ヒット商品を生み出し続けることが、競争優位に繋がるからです。中でも、味の素の食品事業は、「味の素」「ほんだし」「Cook Do」などのロングセラーブランドに始まり、最近では「鍋キューブ」「トスサラ」など、さまざまなヒット商品を生み出し続けています。
味の素の食品事業の戦略において特筆すべきは「マーケター」という存在です。「マーケター」という言葉を聞くと、マーケティング担当者のような認識を持ちがちですが、味の素の場合はそうではありません。新商品開発において、企画から商品化、営業、そしてマーケティングまで全ての権限と予算を持つ、言ってみれば「プロダクトの統括責任者」、オーケストラの指揮者の様な立場になります。味の素の食品事業において、マーケターに任命されることは栄誉であると共に、多くの責任を抱えるということにもなります。それぞれ専門家が存在する研究組織や営業組織に対して指示を出し統合していく立場なので、当然といえば当然です。
そして、そのマーケターに任命されるのは、必ずしも「十分な経験を積んできたリーダー層」ではありません。むしろ、30代前半といった組織内の若手を含めて、早期にそのような重要なポジションに抜擢されていきます。プロダクトによっては、予算数十億円単位の権限にもなります。もちろん、選ばれた人材には、荷が重すぎるケースも発生します。そのため、マーケター経験者である諸先輩にどうしたらいいかを尋ねる機会も出てきます。しかし、そこで常に返されるのは、「お前はどうしたいのか?」「とことんまで考え抜いたか?」という問いです。マーケターに任命された以上は、諸先輩や上長に確認しつつも、最終的にはマーケター本人の意思決定が尊重される仕組みであり、運用になっているのです。
もちろん、一人の意思決定が尊重されるとはいえ、「独断」というわけではありません。徹底した現場主義に基づく「組織の知恵の集約」が励行されます。マーケターには、上下関係なく、「それは本当に見たのか?」「誰がそう言ったのか?」という問いが頻繁に入ります。その問いに常に答えられるよう、マーケターは、研究の現場、商品開発の現場、実際の販売の現場など全ての現場に足を運び、関係する人に意見を聞いて回ります。視点の漏れがある場合も「ここの部分、抜けてないか?ちゃんと考え抜いたのか?」といった指摘を受けます。組織全体の意見を拾い上げつつ、それぞれを統合して「自分の意志」を持って「自分一人で決める」。こうしたマーケターという立場の元で「一人の責任者が徹底的に考え抜いた」内容が反映される意思決定構造が成立しているのが味の素の特徴です。
「衆知を集めて一人で決める」という原則が守られているか?
さて、この「組織の知恵を集めてリーダーが決める」という味の素のマーケターの仕組みを聞きながら、私たちが思い出したことがあります。それは、スコラコンサルタントの柴田昌治氏が書かれた『なぜ会社は変われないのか』(日本経済新聞社)の一節です。その書籍において、同氏はこのことを「衆知を集めて一人で決める」と表現されています。
責任を本気で感じるには「他の誰の責任でもなく、自分の責任」であることをはっきりさせることだろう。「自らの頭で考え、自らの責任で判断する」というのが、責任を持って仕事をするときの前提である。だとすると、自律的に動くための基本ルールの候補として、合議に頼らず「自らの責任で一人で決める」というやり方が考えられる。話し合いはするけど合議では決めない、「衆知を集めて一人で決める」と言った方がより的確だろう。
ここで語られているのは、「すべて自分で決める」というような過度な個人主義ではありません。そして、よくありがちな「チーム全員で集まって、チーム全員で決める」というような責任分散、つまり、ややもすると無責任体制になりがちなマネジメントでもありません。大事なことは、組織のノウハウ、ナレッジを最大限生かしつつも、個人が決め切るという仕組みを作るということなのです。
私たちはインタビューを行いながら、この仕組みの奥深さを思い知ると共に、こういったことを実現させている味の素の運用における徹底度合いについて理解することができました。「任せると言ったら、中途半端なことはしない。徹底的に任せる。しかし協力はいつでも惜しまない」。こういった仕組みを作ることが、チームワークと個人主義をバランスさせるためのあるべき方向なのではないでしょうか。
【今回の学びのポイント】
(1) 組織において、チームワークが全てではない。チームワークは行き過ぎると、互いに「依存しすぎて」「責任が分散」し、結果、何もできなくなる
(2) リーダーは、組織の知恵を総動員して、自分の意志を持って「1人で決める」と腹を括る覚悟が必要
(3) しかし、決める際には「衆知」の存在が不可欠。リーダーが偏りなく重要な情報を得ることができるよう、周囲が協力する仕組み作りが大事である
次回はこちら
https://globis.jp/article/4826





























.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)
.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

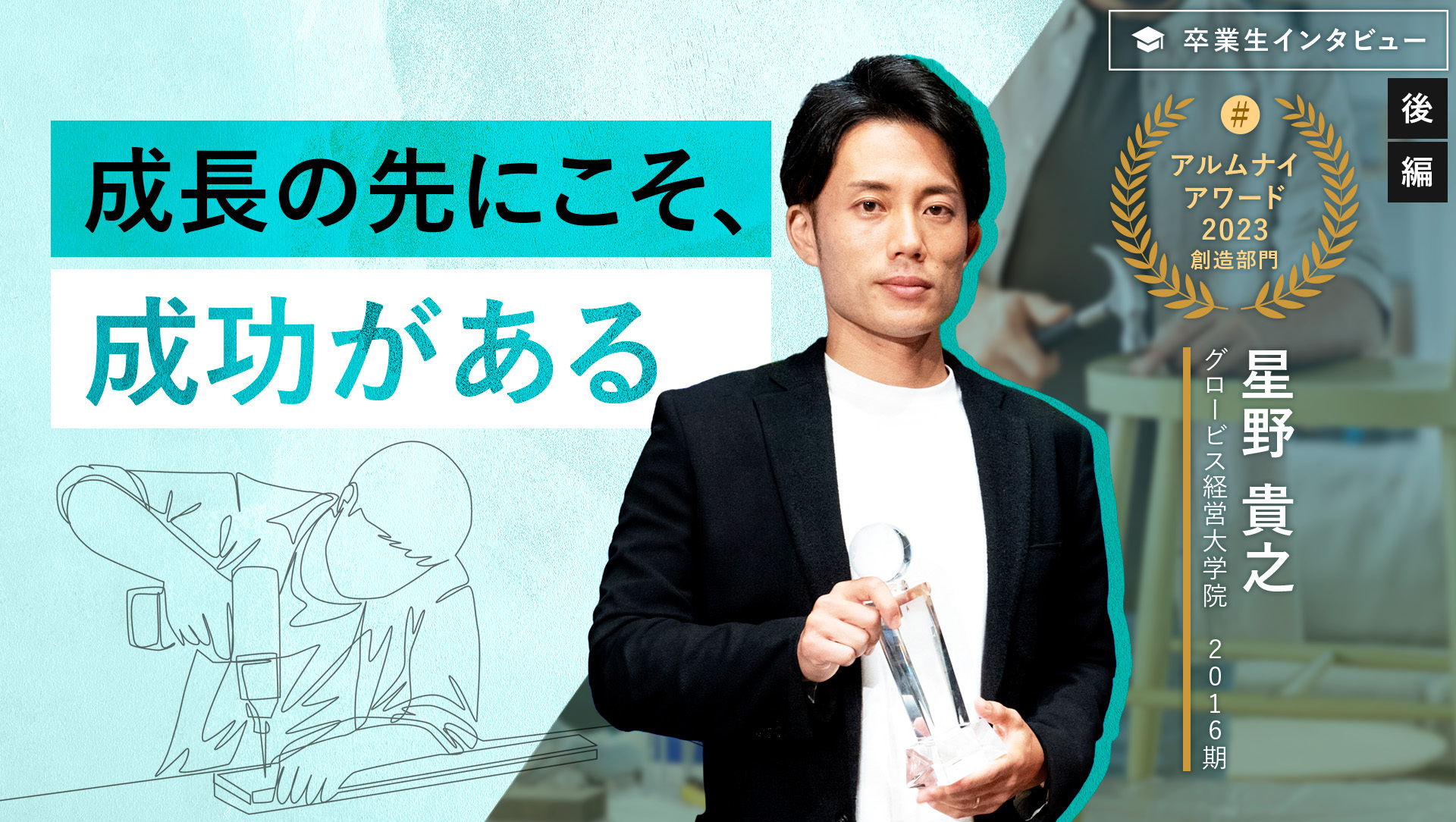













.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)



.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)

