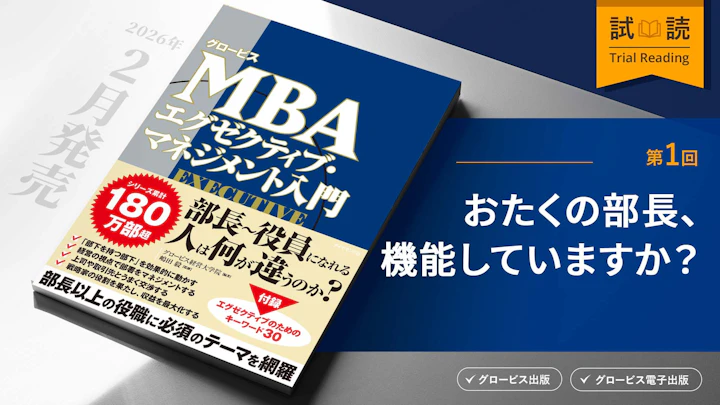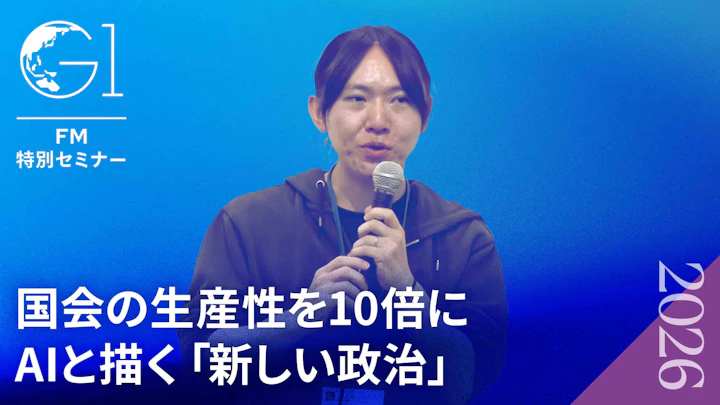ちょっと気になるこだわりの店を方々で出店しつづけるSoup Stock Tokyo とカフェ・カンパニー。人気を誇る、オリジナリティ溢れる魅力的な店舗の源は何なのだろうか。
Soup Stock Tokyoの遠山氏は、意義深く想いが詰まったビジネスあれば、始める時は少し不況なぐらいでちょうどいいぐらいだと言う。求める理想が決まっていれば、たとえ最初はうまく行かなくても解決策はあとからついてくるというのだ。
一方、カフェ・カンパニーの楠本氏は、ピュアに、皆に伝えたいと思うことを自分の中に満ちあふれさせることが最も大切であり、自分の役割を心から感じることができさえすれば、儲けはともかくやり続けることが肝心だと説く。
二人の献身的な仕事術の底辺には、自分の仕事へのこだわりと熱い想いがある。どうすれば、その想いを見つけ、育て、生涯の仕事としていけるのか。二人が気さくに語る決して平坦ではなかったこれまでの道のりや常識にとらわれない発想法は、私達が自分の天職を見出すヒントに溢れている。
日本版「サード・プレイス」をつくりたくて(楠本)
松林:皆さんおはようございます。本日は来てくださってどうもありがとうございます。このセッションでは、まず楠本さんと遠山さんのお二方にそれぞれプレゼンテーションを行っていただきます。そして、僕も含めて3名で対談後、ポストイットに書かれたみなさんの質問の中から、お二人に直観で数枚選んでいただいてそれらに応えるという3部編成にしたいと思います。ではさっそく楠本さんから、カフェ・カンパニーの成り立ちやどのような会社かといったことについてお話しいただきたいと思います。楠本さんよろしくお願いいたします。
楠本:皆さんおはようございます。私がカフェ・カンパニーという会社を設立したのは2001年のことです。飲食店自体をはじめたのは1995年でした。渋谷と原宿のあいだに「キャットストリート」という一角があるのですが、そこにいろいろなカフェをつくって場所の力を上げて、地域の活性化をしようとしていたのがそもそものはじまりです。他にも当時、東急東横線高架下の渋谷3丁目地区の地域活性化プランとしてカフェを提案していました。そうこうしているうちに、「実際にやってみろ」ということになりまして、自分で運営をしているうちに現在の事業を手掛けるまでになりました。カフェ・カンパニーという社名の“カフェCAFE”は、ここでは「Community Access For Everyone」を指します。単なるコーヒーショップではなく、人が集まるところ、つまり “格好良い街の食堂”をつくろうとしたのが原点になっています。
弊社のカフェ直営店事業というのは、“コミュニティ”を企画・運営すること、つまり地域コミュニティをつくっていく仕事です。ですからカフェ事業を中心にしながらも、音楽事業や土地開発のコンサルティング、プロデュース事業も手掛けています。オフィスやマンションを設計して、そこをカフェ化、つまりコミュニティ化しているのです。最近では他社さんとのコラボレーションによるカフェも増えてきました。
「街の風景をつくって感性豊かなライフスタイルを創造し、みずみずしい情緒感あふれる地域社会を実現していく」。弊社の経営理念は、いわば“カフェのある風景”をつくろうというものです。僕がこの会社を創業した1997〜1998年頃は、どちらかといえばインターネット上のコミュニティが増えていた時期でした。でも僕はへそ曲がりなので、「現実の場所が“ワイヤレス”でいいのだろうか?」という気持ちを持ちつづけていました。ネット上のコミュニティが普及すればするほど、リアルな場所としてのコミュニティが必要になってくるだろうと考えていたのです。それこそがカフェであり、そこは“ワイヤレス”ではなく“ワイアード”なのだと。こうしてリアルな“つながり”を形成するような事業を展開していくことになりました。
自分自身で読むのは恥ずかしいのですが(笑)、「しあわせな人生の真ん中にCAFE がある。」というコンセプトを掲げて取り組んでいます。一生続ける仕事ですから、なにかこう、「自分という人間はこうだ」と自然に思えるようなものにしたかった。つまり、あえて「自分が、自分が」と言うまでもなく、自分自身がおのずと滲みでていると感じられるようなことを仕事にしたかったのです。そう思ってつくったのが、このコンセプトです。
弊社ではまた「サード・プレイス」という言葉をキーワードにしています。レイ・オールデンバーグという社会学者が提唱した考え方で、家でもない職場でもない「第3の場所」という意味です。たとえばロンドンではパブ、パリではカフェ、イタリアではバールといったように、成熟した社会は「サード・プレイス」を必要とします。スターバックスの創業者・ハワード・シュルツが、「アメリカにはサード・プレイスがないから“アメリカ版サード・プレイスをつくる”」と言ってスターバックスを創業したのは有名な話です。
その日本版と大きく構えるまではいきませんが、僕も日本らしいサード・プレイスをつくりたかった。ただ、自分としては「家でもなく職場でもない」ではなく、「家でもあり職場でもある」場所をつくりたいと思いました。
「カフェは縁側なんです」。これは、日本版サード・プレイスを考えた時の自分なりの答えであり解釈です。僕は昭和39年生まれですから、どうしてもサザエさんの風景、タラちゃんがいてサザエさんがいて、という昭和的縁側の風景のような、人と人との出合い、交流の場を思い浮かべてしまうのです(笑)。つまり、真正面で向かい合って名刺交換しながら挨拶するのとは異なる、もっと自然発生的なあいまいな出会いの場をつくりたいと思ったのです。
事業を行うにあたっては、「感性」を大切にしています。社員にはいつも「世界の流れを感じ取ろう。ライフスタイルを“想像”して“創造”しよう」と言っています。空想できなければ、本当の創造はできないからです。具体的に細かいところをイメージできるかどうか、その「感性」が非常に重要だということです。日頃から街や人に目を凝らしているか、商品や設計、BGMなどの細かい部分にまで気がついているか。それがお客様の気持ちを感じ取る仕事にもつながります。たとえばお客様に手をあげさせることなくオーダーをとる、そんなことにも通じるのです。
もちろん事業ですから、「感性」とともに「科学」が両輪のひとつになっていることが重要です。ここでいう「科学」とは、言い替えればフレームワークのことです。つまり経営理念を具体的な戦略に展開する力、現状を分析する力、日や週単位でのアクションを計画的に立案する力、そういったもの、つまり感性を育てていくためのしくみです。
生活、文化、暮らしと連動しライフスタイルを紡ぐのが「カフェ」(楠本)
楠本:事業の具体的な事例もいくつかご紹介しましょう。弊社のカフェは地域に根差した形でブランドをつくり、カスタマイズしていくというスタンスですから、店舗自体はあまり目立ちません。まず、東急東横線の高架下ではじめたのが、「SUS(Shibuya Underpass Society)」というカフェです。高架下なのでアンダーパス。3年半の限定プロジェクトでしたので今は別の場所に移っています。移転時に高架下ではなくなるので「アンダーパス」という名称をどうしようかと考えたのですが、勝手に「では今度は頭文字が同じUの“Universal”でいこう」ということで(笑)、今は「SUS(Shibuya Universal Society)」。SUSでは1階が食に関するコミュニティ型の本屋さん「COOKCOOP」、2階は「RESPEKT」というカフェ、地下1階には「SECO」という音楽やファッションイベントを発信するバー空間にしています。
このほか、「WIRED CAFE」は渋谷を中心に20店舗ほど展開しています。青山には「246CAFE<>BOOK」という店もつくりました。店をつくるうえでは“土地の記憶”という要素がとても重要だと考えているので、青山という土地のキャラクターを生かそうと思って名づけたものです。青山は国道246号線の起点なので、旅やドライブをテーマにしたカフェと本屋が隣り合わせになっています。それから豊洲では「OCEANS BURGER INN」という店もやっています。海の隣なのでロマンチックにしてみました(笑)。あとは「A971」。この店は東京ミッドタウンにあります。ミッドタウンはもともと、戦後にGHQから防衛庁へと所有者が変わっていった土地で、言ってみれば戦後日本史の中心となった場所。そのため日本を強く感じる要素を体現したお店になりました。ちなみにA971というのは赤坂9丁目7-1という旧防衛庁の住所です(笑)。
直営店は現在44店舗ありますが、最近ではプロデュースやコラボレーションによる出店も増えています。たとえば面白法人カヤックというネット事業でお馴染みの会社とは、「なにか面白いことやろう」ということで、彼らの本社がある鎌倉のビルで「DONBURI CAFE DINING bowls」というカフェを一緒につくりました。どんぶり料理を出すカフェなのですが、ここでは「どんぶり勘定制度」というシステムが目玉です(笑)。どんぶり勘定制度というのは、ぜんぶ食べ終わったときにボウルの底に「当たり」や「ハズレ」が見えて、「当たり」だと安くなるというものです(笑)。
また、サントリーさんとは「伊右衛門」のブランドをパワーアップする目的で、京都で「IYEMON SALON KYOTO」というお店を一緒にはじめました。世界におけるお茶のブランド化を目指したコラボレーションです。僕たちは、日本のお茶は世界中でもっと飲まれるべきだと考えているので、海外の方が来たときにハンバーグとスパゲッティを食べながら、「緑茶って合うじゃない」と食中茶として認知してもらえるような場所にしていこうとしています。メニューは和洋折衷ですが、建物の設計は数寄屋造や京都にある町家造りをモチーフにしています。このほかにも漫画とアートが融合したカフェや、音楽プロデューサーの小林武史さんと一緒にエコや自然をテーマにしたカフェなどもプロデュースしています。
僕はカフェというのは、生活文化、暮らし、健康、そして農業や生産者と連動していくべきものだと思っているんですね。それらのつながりの真ん中にカフェがあって、さまざまなライフスタイルを紡いでいく。それこそがカフェの役割だと思っています。
松林:ありがとうございました。それでは遠山さん、お願いいたします。
「もの」って書き出しておくと、実際にそうなるものです(遠山)
遠山:おはようございます。私の経歴について簡単にお話ししますと、1985年に三菱商事へ入社して、10年ほどサラリーマンをしていました。ですが、自分はサラリーマンとしての仕事の延長では満足できないということだけは、当時はっきりわかっていまして、「何かやらなくては」といつも考えていました。それであるとき、手はじめに絵の個展を開きました。「どうしてそこで絵の個展なのですか?」と聞かれても、よくわかりませんが(笑)。ですが、アーティストというものは、自分でアーティストと言えば成り立つものですので(笑)。その経験は、とても良いきっかけとなったと思います。個展を開くために友人にいろいろと手伝ってもらっていたのですが、私が「これで自分の夢が実現したよ」と言ったところ、「そんな小さな夢になど付き合っていられないよ。ここからが大切なんだろう」というように諭されまして、「そうだよね」と(笑)。そこから、「何かしなくては」とますます強く思うようになったのです。
当時の私は三菱商事で情報産業のグループにいたのですが、自分がその後に関わる事業は“手触り感”があるものにしたいと思っていました。たとえば、食べ物や小売業などです。それで当時かなり無理を言いまして、ケンタッキーフライドチキンに出向させてもらいました。情報産業の背番号をつけたまま、「通信衛星の『スーパーバード』を使って1000店舗に情報配信します」というような理由をつけて出向させてもらったのです。そこで「Soup Stock Tokyo(スープ・ストック・トーキョー)」の企画書をつくり、じきに1号店が生まれることになりました。
三菱商事に戻ってからSoup Stock Tokyoの会社をつくることになりまして、私も一部の株式を持たせていただきました。会社が出来た2000年当時はITベンチャーやIPOというものが流行っていましたから、ストックオプションが全盛でした。ですが私自身は株式公開するつもりがなかったので、ストックオプションでは意味がなく、どうしても自分を入れたいということでキャッシュを入れさせてもらいました。それが後々効いて、一昨年、三菱商事からMBO(経営陣による自社買収)で全株式を取得しました。株主だったからこそそういう土俵にもつけたのかな、と思っています。Soup Stock Tokyoは現在52店舗ございます。10年前に書いた企画書には10年で50店という「ものがたり」が書いてありましたから、「ものって書いておくと、本当にそういう風になるものだな」と、今では実感しています。
サラリーマンを元気にするネクタイ、イケてるリサイクルショップまで(遠山)
遠山:今回のテーマはクリエイティビティですので、デザインのことにも少し触れておきましょう。Soup Stock Tokyoのデザインでは、もともとスープに彩りがあるから、他に余計な色は使わないというのが基本にあります。ロゴも一色です。店舗デザインも、木、モルタル、ガラス、ステンレスといった素材の色はありますが、意味のない着色はしていません。リーフレットなども同様で、すべて素材の色です。先日、各種スープを並べる場所に「分かりやすくなるよう、野菜類のスープは緑、肉は赤、シーフードに水色の点を付けようか」という話がクリエイティブ部門から出てきました。しかしわれわれは水色なんていう色をこの10年間使ったことがないわけです。素材に水色なんてありませんから。その小さな粒をつけるかどうかで大きな議論になりました。別のときにはクリエイティブのメンバーにずいぶん時間をとられて、「ホームページで1行だけイタリックにしたい」と説明を受けまして、「うーん、イタリックかぁ…」って(笑)。結局、ボリューム感をつけるために1行だけイタリックにしようということになったのですが、そんな感じでデザインにはこだわりを持っております。
Soup Stock TokyoではJALとのコラボレーション企画で「ON THE SHIP(オン・ザ・シップ)」という機内食ブランドもつくりました。3年ぐらい前にJALさんへ行ったとき、「昔書いた企画書にJALさんとコラボをすると書いたので、一度プレゼンさせていただけないでしょうか」とお願いしたのがきっかけです(笑)。先方はコンソメスープなんかが出てくるだけじゃないかと思われていたようですが、われわれは機内食全体をプロデュースするというプレゼンを行いました。映像もつくったりして。おかげさまでプレゼンはうまく行き、最終的に新ブランドの立ちあげに至りました。今はハワイ便にこの機内食が使われていて、今度はパリ便にも乗る予定です。
スマイルズではこのほかにも、「giraffe(ジラフ)」というネクタイ専門のブランドも持っています。今から15〜16年ぐらい前でしょうか、三菱商事のサラリーマンだった頃、上司に「ネクタイ屋やりたいんですが」と(笑)、いきなり意味のわからないことを言ってみたのが事業のはじまりです。なぜそのようなことを言ったのかというと、サラリーマンが格好悪いからなんですよね。場合によっては自虐的な感じすらしますし。だけれども、たとえばここにある水だって、建物の植木だって、サラリーマンである誰かの仕事によって存在しているわけですよ。サラリーマンがいなければ日本は前へ進まないのに、なんだか元気がなさ過ぎませんか。それで「まずは首元から」、せめて格好の良いビジネスマンと言われるようにできればと思ったのです。
また、去年は「PASS THE BATON」という新しいリサイクルショップもはじめました。昨年9月に丸の内ブリックスクエアに第1号店、今年の4月末に表参道ヒルズに第2号店を出店しています。そのあたりのお話ものちほど改めてさせていただこうと思います。
松林:ありがとうございました。それでは今から私のほうから質問をしながら、お話を続けていきたいと思います。
楠本:ちなみにご質問については、外食というジャンルで区切って考えるのではなく、もう少し広く、生活文化という切り口で考えていただいたほうがよいかと思います。たとえば弊社は先日、音楽事業に加えて農業の事業もはじめています。農家を元気にするとか、働く人たちを元気にするというような取り組みです。ですから今日は外食というより、もう少し広く捉えていただければと思います。
頭の中にあったのは、ビジネスプランというより「ものがたり」(遠山)
松林:まずお二人のお話を伺って感じたのは、ロマンチストだなと。お二人とも照れると思ったのでそう表現したというのもありますが、実は私を含めて、三人とも意外とシャイなんではないでしょうか(笑)。
それと、お二人ともいわゆる「常識」が好きではないですよね。遠山さんのお話にありましたが、私もサラリーマンが苦手でした。もちろんいろいろな人がいるわけで一所懸命やっている人もいますけれど、一方で少し疲れて元気のない人もいます。そういうものに対してお二人は反抗している、と言いますか、それを変えていきたいという想いがあるのかなと感じました。ちなみに、手がけられた事業への想いというのは学生の頃からの延長だったのでしょうか。もしくは、たとえば遠山さんであれば、事業の着想は、「スープのあるものがたりが“降ってきた”」というたぐいのものだったのでしょうか。ビジネスプランというよりもむしろ、ものがたりを書き出そうとしたと言ったほうがよろしいのでしょうか。
遠山:ビジネスプランという要素はほとんどないですね。まず学生時代の延長ということでいうと、最初にやってみた飲食店は、会社に入って3年目ぐらいに青山ではじめた屋台のおでん屋です。当時、青山に「ゴールド」という有名なクラブがありまして、その入り口で「おでんゴールデン」というのをやっていました(笑)。
松林:(笑)それは流行ったんですか?
遠山:流行りました。青山でやっていたときにはユーミンさんが来てくれたり、かなりいい感じでした。半年ぐらいで譲ってしまいましたが。
松林:そのおでん屋さんというのは、普通のおでん屋さんと比べて、遠山さん的ひねりはあったのでしょうか?
遠山:ありません(笑)。どちらかというとコミュニケーションの場でしたね。
松林:楠本さんはいかがでしょう。学生の頃の延長ですとか、おでんではなくとも、何か「ものがたりが降りてきた」といったエピソードはありましたか?
楠本:そうですね…、少し恥ずかしいですが昔の話をすると、僕は米軍住宅の隣で育ちました。子どもの頃はお隣の米軍住宅に匍匐(ほふく)前進で侵入したりして…、そこが僕のいわばサード・プレイスでした。そんな風に過ごしているときの、夕陽が差し込んでくる風景のようなものが僕のロマンだったといえばいいでしょうか。学生の時はショーパブをやったり(笑)、レゲエのライブハウスで働いて音楽に触れたり、いろいろなイベントを仕掛けたり、そんな体験がベースにあります。
そんな学生時代を過ごして、何か場づくりがしたいと思って不動産屋に入りました。不動産屋ならば、きっと場所の価値を盛り上げるような仕事が出来るのではないかと思ったためです。しかし時代はバブルの頃でしたので、「安く買って高く売れ」というような世界(笑)。しかも、僕は旧リクルートコスモスに入ったので、広報室に入って少しして、リクルート事件が起こり、社長秘書になって、東京地検特捜部に呼ばれて…と、だんだんとクリエイティブではない方向に向かっていったのです(笑)。そんなことを5年ぐらい続けていました。
いつでも“辞表”を出せる気持ちで仕事をしてきました(楠本)
松林:たとえば遠山さんは、情報産業部門にいらしたのに「食べ物がやりたい」と思われたわけですよね。普通の人であれば、「やりたい!」思うことはあっても、実際にはやらなかったり、できなかったりするのではないでしょうか。やりたいけれども、それを言ったらおかしいと思われるのではないか、そういった気持ちはありませんでしたか?
遠山:当時の上司だった部長がすごく優秀でチャーミングな人でした。仕事の出来る人でしたから、僕自身がほんとうにやりたいことを話しても理解してくれるのではないか、というイメージがありました。で、実際に話してみたところ、「面白いじゃないか」と賛同してくれて、「まあ、言いたいことはわかる」という風になりました。でも、「それで終わり」、みたいな感じになりました(笑)。その後、4年ほど前になりますが三菱商事で外食部門の親分にもう一度プレゼンしたことがあるのですが、その時は全くダメでした。それで、最終的に私個人でやることにしたのです。三菱商事では兼業禁止という決まりが一応ありましたので、うちのかみさんに社長をやってもらいまして。
松林:人をウォッチしていて、うまくいくかということの判断基準にもなるんですね。この人だったら通じ合えそうであるとか。
楠本:今ならばそういう面もありますけれど、当時はそこまでは考慮していなかったように思います。僕はリクルート事件が終わったあとに、“場”をつくりたいと思って社長に自分のプランを直談判しました。ところが「は?」って言われて、「いいからお前は営業に行け」と言い渡されました。その頃の僕はずっと、直接トップに言って当たって砕けろという感じで、実際本当に砕けていました(笑)。当たってすぐに砕けて、「じゃあ次のことを考えよう」ということの繰り返し。ですからどちらかというと、企業の中で頑張るというよりも、「自分のしたいことができないのなら辞めるしかないな」というタイプなのだと思います。常に“辞表”を持って仕事をしている感じといえばよいでしょうか。
「あれ持ってきて」で通じる人間関係をまずつくる(楠本)
松林:なるほど。ではそろそろ質問を回収していきましょう。お二人の仕事を拝見していると、やはり「ものがたりが降りてきた」であるとか、「当たって砕けろ」であるとか、常識にとらわれない部分がありますよね。ですが多くの会社では、何か面白い仕事や創造的な仕事、あるいは面白い発想を生むための状況が、阻害される場合が往々にしてあるのではないでしょうか。面白い発想が出てきそうなのに、会議室で部長が偉そうにしているから言えなくなってしまうなど。常識にとらわれずクリエイティブな発想が生まれやすい環境づくりにお二人はどのようにして取り組んでおられるのか、お聞かせいただけないでしょうか。
楠本:答えになるかどうかわかりませんが、うちは “アレアレ経営”と呼んでいるものを実践しています。コンセプトや細かいところは社長がいろいろと喋っても伝わらないんですよ。「伝える」ということと、「伝わる」というのは違いますから。ですからその想いをつなげていくには、あちこちに連れていくしかないのです。たとえば弊社では、カフェの設計やメインの開発は全て社内でやることにしています。それが最重要課題と信じて、同じ価値観を共有する仲間をどれだけ増すかということに僕はずっと取り組んできたからです。
だからこそ、いろいろなところに連れていって、ものを見せたり一緒にご飯を食べたりしています。人はこんな風に生活しているんだよねと、一緒に見て歩くのです。それをずっと続けているとどうなるか。「あ、ちょっと林くん、あのときのアレ持ってきて」と言えるような間柄になります(笑)。もちろんはじめのうちは「え? アレってどれですか?」と言っているのですが、そのうちに、なんとなくサッカーでいうアイコンタクトのようなものが生まれてきます。「アレ持ってきて」でも、必要なものがサっと出てくるようになる。そうなってくると僕としては「しめしめ」と思うわけです。
松林:一歩間違えるとただのおじいちゃんのような(笑)。「あれだよあれ」だけですべてわかりあえるような。
楠本:そうなっていくのが理想ですね。
松林:遠山さんはいかがでしょうか。
不景気だからこそ、チャンスが転がっている(遠山)
遠山:上司や会社に理解してもらうというのはなかなか大変ですよね。かくいう私も「PASS THE BATON」の企画当初は、社長が私で株主も100%私なのに、会社に説明することができませんでした。せっかくですので、ここで少しPASS THE BATONの話をまとめさせてください。これは2008年10月に三菱地所さんからご提案いただいたお話で、当時はリーマン・ショックの真っただ中でした。Soup Stock Tokyoも売上が落ち、その対応に追われていた時期でした。ですが、お話をいただいた私個人としては、場所が20年間通った丸の内だったということと、ゆくゆくはネクタイの事業で丸の内へ出店したいという想いが重なって、やってみたいという気持ちになっていました。ただ、会社になかなか言い出せませんでした。そのため結局、経営会議にかけることができず、「giraffe」の仲間とほぼ2〜3人で潜伏して進めるような感じになってしまいました。
実は私としては、PASS THE BATONの立ち上げ時期が不況と重なっていたのは、よかったと思っています。まず、丸の内や表参道ヒルズという場所を店舗として確保できたのは不況のおかげです。さらに不況であると、モノを集めるコストも安くなります。当時はメディアもほかに景気の良い話題がないものですから、われわれのことを集中してとりあげてくれました。一方で肝心の売るほうはどうかといえば、たしかにしんどい部分はありました。しかしそれならば、景気が良ければ商売はいつも順調なのかというと、必ずしもそんなことはないですよね。ビジネスはいつだって大変なのではないでしょうか。景気が良ければ競合他社も増えるわけで、お客様は散ってしまうものです。何より、不景気のあいだはお客様の財布も紐が堅いので、一所懸命考えて、われわれとコミュニケーションして、納得したうえで商品を買おうとされます。つまりきちんとした商品を提供出来るのであれば、実は不景気なぐらいが都合がよい、と私は考えています。
ですから私としては、とにかく不景気のうちにはじめなければならないと思っていました。1号店のオープンが去年9月、2号店は今年4月末でしたから、かなり早いペースでした。それは私が「早く仕込まなくては」と焦っていたためです。新聞に「景気回復」なんて書いてあると、「これはまずい!」と(笑)。たしかに不安はありました。それまで物販をやったことはなかったですし、ましてやリサイクルなんて経験がありませんでしたから。そのため「オープンしても、しばらくはうまくいかないかな」というくらいを前提として考えておりました。3年ぐらい踏ん張って、それでやっと頭を出せるかなという程度に構えていたのです。
行き先が見えていれば、手段はあとからついてくる(遠山)
遠山:ただし、このような状況下では、意義のある事業でないと社内でも話を通すことができません。つまり事業は「意義」がないと踏ん張るのは難しいということです。Soup Stock Tokyoも「世の中の体温をあげる」という想いがあってはじめて踏ん張ることができているのです。もしPASS THE BATONがうまくいかなければ、「スープで稼いだ僅かなお金をこっちでジャブジャブ使って…、社長、何ですかこれ?」と言われてしまうでしょう。そこで「だって、格好良いじゃないか」と言ったところで、全く理由にはならないのです。そうしてこの事業の意義を強く考えているうちに、一気に「リサイクル」というコンセプトへ舵を振り切るようになりました。すると、「他にイケてるリサイクルショップってないな」と、何かを発見したような気になって、さらに早くやらなくてはならないと思うようになったのです。
私は今後、事業を「世界規模」でやっていきたいと思っています。昨年のG1サミットに出席させていただいた時、帰りに自分が電車の中で書いたメモを見るとそう書かれていたのですが(笑)、現在、PASS THE BATONのコーポレートカラーはピンクになっています。もし、モノが集まるところが赤く光る地球儀があったとしたら、恐らく東京が地球上で最も赤く光っているでしょう。その赤を薄く延ばしていくイメージだからピンクなのです。しかも東京は単なる赤ではなくて良いモノが集まる赤ですから、なおさら東京から全世界に事業を広げていく意義があると思っています。もちろんPASS THE BATONを立ち上げるうえで、それはもう不安でしたよ。ヒリヒリするような不安がたしかにありました。でもその一方で、今お話ししたような高い理想や意義といったもので不安を打ち消していたのです。
求める理想が決まっていれば、最初はうまくいかなくても解決策はあとからついてきます。たとえば山の頂上に行こうと決めているなら、ある道が塞がれていれば別の道を探したりしますし、もしかしたらヘリコプターをチャーターしたりするかもしれません。結局、行き先さえ見えていれば手段は後からついてくると思っています。ただし、その「行きたい心」があまりにも弱いと、踏ん張ることはできないですよ。当然リスクはあるけれども、リスクを冒してまで行くならば、それだけの価値がなければいけない。ですから私は理念や理想といったもののハードルを常に高めています。そうしてハードルを上げて夢を語っていると、周りが協力してくれるようになるのです。表参道ヒルズに出店できたこともその一例です。ですから今は、「自分はワールドワイドでやりたい」と口にしています。これがたしかな形になる時が来るはずなのです。こうして理想のレベルをあげて、吹き飛ばすのです。
松林:ありがとうございます。お二人とも私の質問に答えていただいているような、いただいていないような(笑)。皆さんも相手に質問されたら、とりあえず質問内容は置いておき、「俺はこれをやりたいんだ」と話すことが創造性の第一歩なのかもしれません。
空間づくりの前にその場所に必要な「磁力」を考える(楠本)
松林:それでは質問が出揃ってきましたので、まずは遠山さんに“ビビッ”ときたものを一つ選んでいただきましょう。そのあいだ、楠本さんにはクリエイティビティというテーマを掘りさげた質問をさせてください。
私は以前、お二人のオフィスにお邪魔させていただいたことがありますが、そこはいわゆる大手企業のオフィスとはまったく違っていました。ソファがあって、音楽が流れていて、観葉植物があって、そして本棚がある。マンションの一室かカフェか、という印象でしたが、それはやはり居心地の良い空間が創造性をサポートしているということなのでしょうか。
楠本:そうですね。先ほどは“アレアレ経営”に触れましたが、オフィスについては少し今風に表現すると、“アナログ版クラウドコンピューティング型オフィス”ということになります(笑)。情報を集約するクラウドサーバのようなオフィスです。これはどういうことかといいますと、一口に情報と言ってもさまざまな切り口がありますよね。雰囲気、感情、経験、あるいはフィーリング。僕はそれらをすべてオフィスに溜めていくことが大切だと思っています。オフィスという場所のレイアウトはデザインのためのデザインではなく、「どんな場にしたいか」「そこにどんな磁力を持たせたいか」と考えれば、必然的に決まるものです。
弊社のオフィスでは生産現場の人たちと営業の人たちを向き合うような形にして、真ん中にカフェをつくりました。そこでコーヒーブレイクしつつ、「最近どう?」と問いかけて、それに「いや〜…」と返す。そこでさらに「だよね〜」と(笑)。そういう他愛のないやりとりがとても重要だと思っています。「だよね」「でしょ?」という会話が減っている現代だからこそ、社員をつなぎあわせたかった。その結果として“アナログ版クラウドコンピューティング型オフィス”が生まれたのです。
松林:なるほど。皆さん、明日からオフィスで「だよね〜」を、1日10回ぐらい使ってみてください(笑)。それではこのあたりで遠山さんにお伺いしてみましょう。ひとつ質問をお読みいただけますか?
お風呂と布団の中がアイデアの量産空間(遠山)
遠山:では数名の方にいただいた同じ質問で、かつ答えやすいものを選ばせていただきます。「ひらめく時間と場所は?」というご質問です。
私はたいてい、お風呂と寝ている時です。布団の中に入っていても、何かアイデアが浮かぶと楽しくなって眠れなくなってしまいます。たとえばPASS THE BATONでは、あるとき陶器の古いそばちょこをプレゼントにできないかと思っていろいろと考えた末に、夜中の2時頃に「お菓子を合わせたら面白いかもしれない」と思いついたんですね。それで、起き出して近くのコンビニに行ってみたんですが、イケてるお菓子がないのです。仕方がないのでさらに遠いコンビニへ足を延ばしてチョコレートを買いました。それをそばちょこに詰めてパッケージングして、翌日、会社へ持って行って皆に「どうかな」って見せました。ついこのあいだもお風呂に入っているとき、あるアイデアが浮かんだものですから、お風呂からあがって小躍りしたりしていました(笑)。
松林:小躍りですか(笑)。では、次は楠本さんのほうからもひとつ。
コミュニティづくりは未来へ向かうためのもの(楠本)
楠本:カフェと農業に関するご質問をいくつかいただいていますね。少しお話ししそびれていましたので、改めてここで農業についてご説明させてください。
まず個人的には、コミュニティをつくる仕事というのはブームをつくる仕事とは正反対のことであると思っています。つまり僕は全く逆のことをやりたい。学生時代にいろいろと企画を手掛けていくなかで、盛り上がっていた時期もありました。でも一方で、これがどんな風に将来へつながっていくのだろうか、という気持ちも生まれていました。そして次第に、「コミュニティはサステナビリティ(持続可能性)。息の長い関係を続けていくべきなんだ」と考えるようになったのです。コミュニティづくりは未来へ向かうためのものです。先ほど、「街の歴史や土地の記憶が重要」と言ったのは、PASS THE BATONさんもそうだと思いますが、つまり未来へ向かうために過去に戻っているということになります。
それからもう一つ。コミュニティにしても、ビジネスにならないといけませんよね。最近、「コミュニティ」という言葉があちこちで使われていますが、ビジネス化についてはあまり語られていないのではないか、という気持ちがあります。飲食店においては、コミュニティが深くなるとお客さんが1日に3〜4回同じ店に来ます。一方で一過性のブームでは、お店が出来た当初は人が大勢来ますが、あとはパタッと来なくなる。そんなブームにはまったく興味がありません。コミュニティを創り、一人ひとりのお客さんと厚い関係をつくっていく仕事をずっと続けていきたいと思っています。原宿や渋谷の店舗で行っている音楽とカフェのつながりはそういう意味で継続していきますし、これからもっと広がっていくと思います。同様にインテリアとカフェ、スポーツとカフェも今後ますます広がっていくと考えています。
このことが農業の話にもつながっていきます。弊社は現在、食糧自給率が1%しかない東京都を出発点にした「TOKYO 100 MILE CAFE」というプロジェクトを立ち上げています。東京を中心に100マイルという広さで考えますと、ちょうど日本を道州制とした場合の一州の規模と同じくらいになります。それを一つの生活文化圏として、ライフスタイルを紡いでいきたいと考えています。何を言いたいかというと、この圏内で食べ物の作り手の農家と生活者の間をつないでいこうとしているのです。
生産者と消費者には未だ本当のコミュニティが出来ていません。コミュニティが士農工商の時代からずっと分断されている。近代になっても生産者と消費者のあいだには常に中間が存在し続けています。生活者、あるいは消費者から見て「生産者の顔が見えない」とはよく言われることですよね。近頃ではスーパーマーケットに行くと、商品に「『私がつくりました』(農家の加藤さん)」なんていう紙が貼ってあったりします。しかしながら生産者からはまだ、生活者や消費者の顔が見えていません。このことも問題です。僕は社内で「消費者」という表現を禁止しているのですが、生産者と“費やす人”ではなく、あくまで生産者と“生活者”であるべきです。その両者をつなげるのが最終的なカフェの役割ではないかと思っています。
そうして「地域にカフェをつくろう」という取り組みをはじめて、まずは千葉の館山で漁業の方々とカフェをつくりました。ここまでですと、地産地消型のレストランということになりますが、それだけでは本当のつながりにはなりません。そこでさらにスポーツや音楽をからめたりしています。暮らし方が同じ文化圏になってくれば、そこで初めていきいきとしたコミュニティが生まれてくるはずです。そういう意味で、僕は生産者と生活者をつなげる仕事をしたいと思っています。ブームとしての農業をする気持ちはまったくないんですね。
松林:ありがとうございます。今おっしゃっていただいたことは遠山さんのPASS THE BATONにおけるモデル…、売る人と買う人の顔が互いに見えるというマッチングの概念にも通じる思想があるのかなと思いました。
何より現場との交わりが楽しいと思っています(遠山)
松林:それではここで、皆さんにご覧いただきたい映像があります。長さは5分ぐらい。遠山さんにご用意いただいたものです。
遠山:申し訳ないのですが、この映像は…、オチとか、ありません(笑)。Soup Stock Tokyoでのおもてなしを考えるワークショップのような場で見せているものです。3〜4年前、あるメディアの方に「社員さんの笑顔が映っている写真を貸してほしい」と言われまして、探してみて愕然とした経験がありました。笑顔の写真が一枚もないんですよ。真剣な表情はあったのですが、笑顔がなかった。そもそもSoup Stock Tokyoはファーストフードに対するアンチテーゼのようなものからはじまりましたから、笑顔の練習とか、そういうものを私は忌み嫌っていたんですね。ですから笑顔の練習なんて一切やってこなかった。
けれどよく考えてみると、われわれはニューヨーカーでもなければ、ハグしてしまうようなイタリアンでもないわけです。弊社で働く社員には、地方から東京に出て一人暮らしをしながら、一所懸命生きている若い女の子だっているわけです。そういう人がいきなり自然なスマイルなんてできないですよね。そんな社員に対して「それぞれの個性に任せる」なんて、聞こえは良いですけれども、実はただの放置をしているだけだったのだと思いました。
それからは、一番嫌いだった笑顔の練習をするようにしました。鏡で自分を見て、「ひきつった笑顔でもいいじゃん」と。むしろ東京らしいひきつった笑顔で「いらっしゃいませ」と言ってくれたら、「ああ、この子も頑張っているんだな」と思ってもらえます。この映像は、このようなことを考えながら、笑顔の練習をはじめた頃につくったものです。こわばった笑顔の中から、少しずつ本当の笑顔が出てきたというストーリーですね。
(〜映像〜)
今日は少々格好良いことも言いましたが、結局はこんな風にチームで働けるのが好きだから、私は仕事をしているのだと思います。会議室で少しばかり頭の良さそうなことを言って仕事をした気になっていますと、そういう大切な気持ちを忘れてしまいがちになります。私はだから、本当に現場との交わりが楽しいと思っています。なぜ仕事をしているのかといえば、こんないい仲間やいいお客さんに出会えることが嬉しいからなのだということを、強く感じています(会場:拍手)。
松林:本当にありがとうございます。それではお二方にそれぞれ最後に、「この質問に答えていないな」ですとか、何かお話があれば伺いたいと思っています。
感性を生むのはノウハウではなく、意思であり、気持ちです(楠本)
楠本:では最後にひとつ、「感性をどのように磨いていますか」といったご質問がいくつかありましたので、それについてお話をさせてください。
僕は今日、「過去が大事」と、重ねてお話をさせていただきました。これは「IYEMON SALON KYOTO」をつくったときに感じたことですが、「おもてなし」というのは、500年前から続いていることです。おもてなしの心が生まれるのは、「この出会いが最初で最後になるかもしれない」という一期一会の精神があるからでもあります。そんな心を、僕らは今一度日本人の価値としてしっかり引き継いでいかないといけないと思いますし、それが今、少し壊れてきていると思っています。うちのカフェなんて、実際下手なこともあります。レストランに素晴らしいシェフがいるわけでもないですし。ですが、本当にその地域が好きで、お客様が好きで、自分のお店が好きという人たちの集まりではあります。最終的にはそういう想いが場所のエネルギーを生むのだと僕は信じています。こうしたエネルギーを生むことができるのも日本人の力だと思います。ですから感性を養うのはノウハウではありません。それは意思であり、気持ちであり、そしてその連続性ではないかと思うのです。
松林:以前私は発想法や創造性を養うツールにトライしたことがあるのですが、今のお話を伺って、結局はその人の心持ち次第だという想いを改めて強くしました。学校で教わる「ある種の賢さ」ではなく、どれだけピュアでいられるかということが、もしかしたら一番大事なのかもしれないですね。ツールやコンセプトに逃げてしまう人はとても多いものですが、それよりも子供の頃に持っていた純粋さを持ち続けていられるか。お二人を見ていますと、年齢は50近くでも、言っていることや立ち振る舞いがまるで小学生のようです(笑)。周りからは社長と言われているわけですが、なにかこう、やんちゃな子供二人がここで悪だくみをし合っているような情景が浮かびます。
僕自身は人と長く付き合おうとするとき、その人の中にある子供の一面を発見できるとすごく安心することがあります。あと、表情に喜怒哀楽がある人にも。たいていの人間は大人になるにしたがって、しだいに能面みたいな表情になっていくではないですか。喜怒哀楽を隠しているうちに、本当に喜怒哀楽がなくなってしまう人は特に都会に多いと思うのです。それは怖いことですよね。僕にとっては、その人が賢いかどうかということよりも、きちんと表情を出しているかどうかということのほうが大切な場合もあります。
5年あれば、何かしら変えられる(遠山)
遠山:人の話を聞くときも同じようなことが言えますよね。私はその人自身の「ものがたり」を聞きたいと思います。よく朝礼で、どこかで聞いてきたような、本で読んできたような立派な話をする人がいますが、あれはもう本当に勘弁してほしいですね(笑)。そんな話をするくらいなら、今日の朝体験したこととか、昨日お店であったことを話してくれるほうがずっとずっとリアルでいいです。たとえオチなんてなくても。
松林:それで今、思い出したのですが、今日、ここに来る前に電車の中で食べるお寿司を買ったんです。そうしたら何と、お箸が付いていなかったんです、ちらし寿司なのに(笑)。仕方がないからそのまま手で食べるべきかどうかとか、いろいろ考えているうちにペンを2本見つけて、結局それを使って食べました。食べにくかったですが。もちろん、ちゃんと洗ったのが…、今持っている このペンです(笑)。そういえば今思い出しました。
遠山:まさにそういう話です。しかもその話がショボければショボいほどいいんです(笑)。
松林:あのときは、「なぜ箸を入れないんだ?」と思いましたが、今考えるとペンも意外と役に立つということが勉強できました(笑)。さて、そろそろお時間ですので、あとは何でも結構です。質問に対するお答えでも良いので、それぞれ何か一言お願いしたいと思っています。
遠山:私がSoup Stock Tokyoをはじめた10年前、三菱商事で企画書を配っていたとき、それを読んだ仲間の女の子が一人、その後結婚して海外で暮らすようになりました。彼女は最近になって数年ぶりに帰国したのですが、日本でものすごく驚いたことがあったというのです。「あのときの企画書が実現している!」と(笑)。すごく喜んでくれました。なんだか浦島太郎みたいな話ですよね。でも、これはよく考えると「あ、そうか。5年あれば何かしら変えられるんだ」という教訓でもあるような気がしています。私は今45歳ということで、あと3つぐらいは何か仕込めるのではないかと思っています。そのぶん今30代前半の人が本当にうらやましいです。5年あれば本当に実現できますよ。だからぜひ頑張ってください(会場:拍手)。
感性を磨くより、“ドン・キホーテ”になれ(楠本)
楠本:カフェというと、何かお洒落なことをしているように聞こえるかもしれません。しかし僕自身は、「昔からずっと変わらない価値って何だろう」「それが伝わっていないところってないだろうか」といったことばかりを考えています。
実は先日、沖縄の友人が6月23日の慰霊の日、ある芝居をやるというので観に行きました。その芝居は、戦争に駆り出されて死んでいった少年たちや残されていった老人たちのものがたりです。沖縄にはそんな人々がたくさんいますが、あまり語られていません。おじいさんたちも自分だけが生き延びてしまった恥ずかしさであるとか、さまざまな感情をお持ちと思うのですが、とにかく今の世代にはあまり伝わっていませんでした。それを僕の友人は3年かけて沖縄じゅうで話を聞いてまわり、舞台にしたのです。
一夜限りの公演でしたが、もう涙が止まりませんでした。何を申しあげたいかというと、僕としてはビジネスのために感性を磨くより、“ドン・キホーテ”になったほうがよいと思っている、ということです。大切なのは、「俺の役割ってこうなんじゃないか」と心から感じること、一所懸命、天真爛漫に、ピュアに、皆に伝えたいと思い続けられるようなことを、一体どれだけ持つことができるかということです。さらにそれは数ではなくて想いの強さとして、です。そうしたものが己の中に満ち溢れてきたら、あとははじめのうちは儲かるかどうかは別にして、とにかくやり続けることが重要なのだと思います。
僕にとってのそうした想いは、昔から伝わる価値をつないだり、この国にあるさまざまな価値を皆で伝えあったりする交差点としてのカフェをつくることでした。ですから皆さんも、そういったことを毎日自分なりに発見していくといいますか、探して、感じていただきたいと願っています。今日のセッションがそうしたことの何らかのきっかけになりましたらとても嬉しく思います(会場:拍手)。
松林:本当にありがとうございました。皆さん、最後にお二人へもう一度盛大な拍手をお願いいたします(会場:拍手)。


























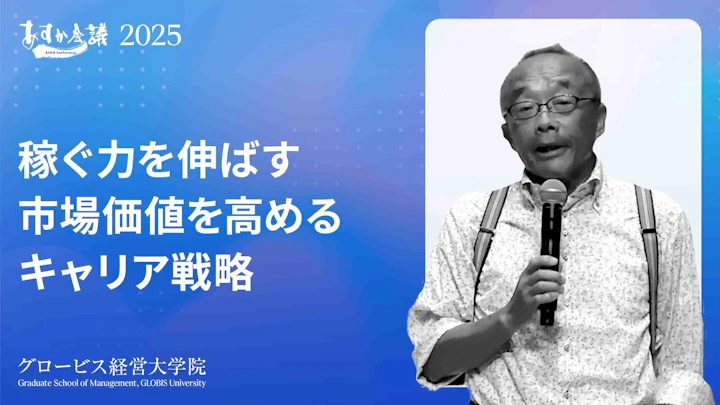

















.jpg?fm=webp&fit=clip&w=720)