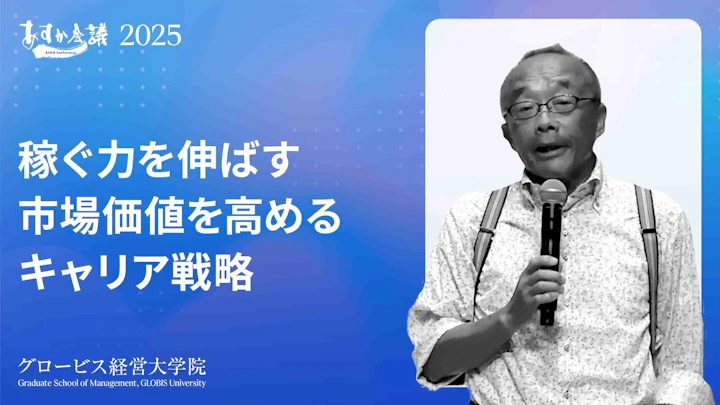真綿で首を絞められるように息苦しい平成ニッポンに、誰もが閉塞感を感じている。なぜ日本は変われないのか。企業が変わるためにどうすればいいのか。企業再生に長年携わってきたプロフェッショナル4人の答えはシンプルだ。「破綻」か「クーデター」。
変革の必要性を強く訴えるのは、リゾート再生請負人と言われる星野リゾート・星野佳路社長。明治維新や太平洋戦争後の復興を例に挙げたうえで、「今日本は大企業病にかかっている。しかも既得権益を持っているのが国民だから改革が遅々として進まない」と指摘、「安保闘争の時のエネルギーを考えれば、企業の変革だってできる」と奮起を促した。
外資系投資銀行出身で、地方企業の再生ファンドとして存在感を増すジェイ・ウィル・パートナーズを率いる佐藤雅典氏は「大都市圏に集中した人材を地方に分散させることが、日本活性化の鍵」と話す。「日本を活性化するためには色々な既成概念や反対論にチャレンジしていかないといけない」と説いた。
弁護士として多くの企業再生案件を手掛けてきた永沢徹氏は「ひと昔前と違って、企業破綻に対する抵抗感が薄まってきている」ことを指摘。「本来潰れるべき会社が、無理に支えられて、生ける屍になるのは、好ましくない。潰すべきものは潰す政策判断が必要」と訴え、「まっとうなことをできない。その阻害要因を外すために、破綻処理が非常に有効な場合もある」と強調した。
ダイエーの企業再生に取り組み、エーエム・ピーエム・ジャパン元社長の相澤利彦氏は言う。「自分の力では変えられないと大企業を辞めていく人はすごく多い。でもこのままだと大企業がだめになってしまう。中で残ってクーデターを起こす人がいないと、良くなっていかない」。
上が変わらないなら、ミドルから変革を起こせ——。再生の修羅場をくぐりぬけてきた体験に裏打ちされた言葉には、重みがある。
企業再生に挑む4人の志士たち
相澤:ここに登壇しているメンバーは、ほとんど同じ世代なんです。1980年代中盤ぐらいに社会に出て、いま、40代後半ぐらいになります。実は企業の再生に携わっている人が、この世代には多くいます。
社会人生活があと15年、20年というタイミングで、日本がおかしくなってきた、あるいは会社がおかしくなってきた。「俺たちがなんとかしないといけない」という意識を持った世代なんですね。それもロングスパンで見たときの、大きな変革の必要性に迫られた世代です。平均年齢としては、今日のあすか会議の聴衆の皆さんは、もう少し若いでしょうから、なおのことロングタームで変えていかなければならない。そういう意味では、是非このメンバーの再生セッションの話を参考にしていただきたいと思います。
3人のパネリストは、みなさん日常的に再生を行っています。再生の現場は私も経験しましたけれども、通常の仕事をルーチンワークでやるよりは、はるかに大変なことをやっています。まず、過去を否定しないといけない。これは改善でもなければ、改革でもない。破壊なんです。そのうえで、新しいものを創らないといけない。この2つを同時にやらなくてはならない。再生は決してかっこいいものではありません。パネリストの方々にとっては日常なので、サラッとお話されるかもしれませんが、現場はドロドロしています。
佐藤:地方の中堅企業、中小企業を中心とした再生を行っています。再生の定義は必ずしも一様ではありませんが、こう考えていただきたいと思います。すべての会社は、何らかの問題を抱えている。我々がお手伝いしているのは、普通の会社よりも、割と大きな問題を抱えている会社です。
会社を再生する際にやっていることは、基本的に2つに限定しています。まずは、帳簿、会計を全部見直してみる。実はこれをやるだけで、混乱している企業はかなり落ち着きを取り戻すというとても重要な効果があります。伝票1枚をきっちり付けるだけで、落ち着き始めます。
それから、中堅企業、あるいは地方企業が多いものですから、組織がうまく機能していない。大半が俗にいう文鎮型組織です。絶対的なオーナーがいて、オーナーがすべてを管理しようとしている。これをごくごく普通に意思伝達ができる“普通の組織”に変える。
極論するとこの2つをやるだけで、問題のある会社が普通の会社のところまで戻っていく。我々は投資家からお金を預かっているので、リスクを取って、普通の会社に戻ったら、「ウチの救急病棟から出ていってください」というようなことを、基本方針としています。この方針は投資家だけではなく、経営者や従業員にそれを伝えています。この2つのポイントが我々の再生であり、一番難しい要因でもあります。
永沢:救急病棟から出すのが再生の仕事だという佐藤さんのお話がありましたが、まさに私は破産した会社のいわば臨床医という立場です。管財人としてメスを執る場合もあるし、内科医のような立場で、アドバイザーとして再生に携わることもあります。
私が破綻した会社の仕事をするときに、「落ちてくるナイフは掴むな。落ちてしまったナイフは拾え」と申し上げます。落ちてくるナイフを掴もうとすると怪我をしますが、落ちたナイフを拾うときには怪我をしなくて済む。そういう意味では、破綻した会社の再生という仕事はやりがいがあります。元々期待値が高くありません。サッカーのワールドカップで1勝もできないと思っていたのがベスト16に進むと、万々歳になりますね。「勇気をもらった」というような話になるわけです(会場笑)。
我々の場合は「単黒」というのですが、単年度の業績が黒字化しただけでだけで社員全員が盛り上がってくることが、非常にありがたい。何十年も増収増益を続けている会社では、こういった思いは味わえないでしょう。そういう意味では、日々の再生の案件は非常にやりがいのある仕事です。
実はこの場所(山梨県小淵沢にあるリゾートホテル「リゾナーレ」)は、再生の手本のような場所です。マイカルという会社がリゾートとしてかなりのお金を費やして造ったところを、「再生請負人」の星野さんが手を掛けて仕上げると、ここまで立派なリゾート施設になるわけです。こういった場所で星野さんとお話ができるのは、とても嬉しいことです。
星野:リゾート・旅館の運営会社を経営しています。開発・所有にこだわらず、運営サービスだけを提供する仕事です。この時代の背景の中で、再生がポイントになってきました。リゾート・旅館の再生屋と呼ばれますが、あまりいいイメージではないですね。「星野さんのところのリゾートは、全部再生ですよね」と言われることは、「全部破綻した経験があるんですよね」というニュアンスを含んでいるので、できるだけ「再生」という言葉から、「運営をお任せいただく会社」というイメージにしていきたいと思っています。
佐藤さんからお話があったように、経理・会計は大事ですし、私たちも組織をがらりと変えますが、同時にリゾートの観光事業というのは、まだまだ産業全体が成熟していないところが多くあります。スケールメリットも効いてないし、仕組みもできてないし、運営ノウハウがプリミティブ(原始的)なレベルにいる業界です。
私たちは、経理・財務・組織だけではなく、運営の仕組みそのものを提供することが専門分野だと思っています。したがって、私たちの仕組みを完全に理解していて、創るべき組織文化に精通している総支配人を送り込んで、現地のスタッフ全員の仕事の仕方を変えていく。一人ひとりのスキルを上げていく。3年ぐらいの間に集客と収益を上げていくのが、私たちの会社です。
再生を専門にされている佐藤さんとかなり違うところは、我々は運営会社なので、再生し終えて収益が出始めた後も、ずっと長く私たちが運営したいと思っています。一緒に仕事をさせていただいている投資家の皆さんは、イグジットとして「再生終了」ということに価値を見出そうとします。これは当然のことなんですけれども、私たちは継続して運営に携わっていきたい。それが私たちの仕事だと思っています。
相澤:再生していく上で「人」が大切なのは言うまでもないのですが、3年前のあすか会議で、「再生に携わるリーダーに必要な3つの条件」という偉そうなことを言いました。今日は懺悔したいんです(会場笑)。3年前に何を言ったかというと、まず売上、利益など現物のメリットを上げること。2つ目は夢を与えること。将来のビジョンを示さなければならない。3つめは、誠実な人格。信用できないリーダーはだめだと思っている。この3つを言いました。
今日なぜ懺悔かというと、現実に自分でやってみて、リーダー一人が頑張っても仕方がなくて、社員一人ひとりのみなさん、それから株主や金融機関などすべてのステークホルダーが「その気になる」ということがすごく重要だと思い知らされました。リーダーの視点だけでは再生はできない。今日はどうやって現場をやる気にさせたかも聞いていきたいと思います。また、3年前に産業再生機構が解散して、再生に関して世の中のトレンドが変わってきた気がしています。最近ご自分が取り組んでいる案件でもいいですが、何かお話をしていただければと思います。
「パンドラの箱が開けられた」(永沢)
佐藤:トレンドという観点からお話します。再生が語られるようになって恐らく10年ぐらいになるでしょう。最近では、「再生」という文字がニュースに上らない日はないと思います。私がこの世界に入ったのは10数年前で、まだ再生という言葉が世の中に認知されていませんでした。再生が単なる不良債権処理だと思われていた時代が10年ほど前。2003年に産業再生機構ができました。竹中平蔵さんによって、不良債権処理の方針が随分変わったのが7〜8年前です。それ以降、再生しなければならない会社がどんどん増えてきました。
ここ数年はさらに変化が加速しています。従来のルールや商慣行が劇的に変わってきている。当然多くの会社が方向性を変える必要に迫られましたが、経営者が対応できなかった。そういったケースが非常に多く見られます。既存のルールや慣行が変わることによって、経営者が経営判断も変えなければならないのですが、その経営判断に遅れが出てきてしまっているわけです。
そう言うと、再生が必要な企業は、ある意味で「被害者」のように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。物を売っている先、物を仕入れている先も、いろいろな意味での構造の変化やルールの変化を強いられているのは同じです。
永沢:続けてトレンドのお話をしたいと思います。企業破綻に対する抵抗感がかなり薄らいできているのです。私は一貫して法的処理をしていますから、会社更生、破産、民事再生という手続きの中で役割を担っています。かつてなら、破綻した企業の社長が責任をとって辞める。「迷惑をかけたのだから当然だろう」と、私財も投げ出して他の人に代わってもらうというのが、企業再生のあり方だと言われていました。
ところが去年あたりから、パンドラの箱が開けられました。DIP(Debtor In Possession)型の会社更生というトレンドが起きつつあります。経営者がそのまま留まって、会社更生手続きを行うスキームです。昨年、私もあるゼネコンのDIP型の会社更生の申し立てを行いました。経営者が残る形で申し立てをして管財人になり、我々はアドバイザーとしてサポートしました。おかげさまで多くの方の賛成を得て再出発して、今は非常に順調で、創業以来の最高益を出しています。厳しい中でも経営をスリム化して、得意分野に集中しています。
私的整理と法的な破綻処理の区別が付きにくくなってきました。私的整理手続きは、主に銀行が債権カットに応じて、取引債権を保護することによって、企業価値を維持するようなやり方が通常でした。しかし私が行った法的な破綻処理案件でも、取引債権はすべて保護して、金融機関だけが債権をカットするというような会社更生を行いました。その究極がJALの破綻処理手続きです。何十億円もの商社の債権は保護されて、金融機関の債権だけがカットの対象になります。そういう意味では、道具としての「企業再生」は使いやすくなっている。企業破綻ということに対する抵抗が、かなり薄らいできています。
相澤:スキームとしても、選択肢がかなり増えてきて、やりやすくなっている環境にあるのだろうと思います。今年もまた星野さんの案件が増えているように聞いていますが、トレンドについてはいかがでしょうか。
「破綻は組織が変わるきっかけに」(星野)
星野:リゾート業界では、既存のオーナーが、運営を私たちのような専門企業に任せようという動きが、進んでいます。そこそこの業績を出していてキャッシュが回っている企業も、私たちに運営を委託して、業績をさらに伸ばしていくような案件が増えています。高知県の「ウトコ・ディープシーテラピーセンター&ホテル」(室戸市)、三重県の「タラサ志摩ホテル&リゾート」(鳥羽市)などがそうです。
それから再生に関して。なかなか組織は変わりません。先ほどのセッションで「自分の会社に停滞感がある」という質問に、手を挙げた人の多い事。勢いを感じない職場にいながら、みんな頑張っているわけですね。そういう環境に置かれた人に、何ができるんだろうか、どうすべきだろうか、と先程からずっと考えています。
今日の一貫した僕のメッセージになるかもしれませんが、破綻は、組織が変わるきっかけになります。破綻でどうにもならない状態になると、文化が変わるんです。覚悟が決まります。崖っぷちに立たされたような状態になると、全員で乗り越えるしかなくなるわけです。そういう環境のほうが、大きな組織になればなるほど、変わる可能性があります。今の永沢さんのお話ですと、疲弊した文化や制度をそのままに、温存してしまう可能性があるのかなとちょっと危惧を感じます。
永沢:経営責任を押し付けられると、万策尽きるまで頑張ってしまうという弊害があるんです。その点で、「破綻は素晴らしい」ということを示すためには、「DIP型でやろう」というメッセージが重要になります。ただし経営者がそのまま残るといっても、実は私がやった案件でも、社長と会長には退任していただき、専務取締役が申し立ての日に社長になりました。少なくとも債権者に理解を得られるだけの仕組みづくりはしています。
経営資源を有効に活用するか。特に人ですね。このことに関しては、産業別に難しさがあるのかなと考えています。旧役員は全員退いてもらって、新たな経営者を連れてくるとなると、リゾートであれば請負人をきちんと用意できそうですが、ゼネコンでは非常に難しい。企業に眠っていた人材を有効活用できるという意味で、DIP型の企業再生は決して逆行ではないと考えています。
相澤:そろそろストレートトークに移ろうと思います。私は取締役としてダイエーの再生に携わりました。今から考えるとその頃は甘かったんです。何が甘かったかというと、産業再生機構という公の機関が株主としていてくれる。だから実は、給与カットもあまりしなかった。例えば部長クラスは、小売業の中では非常にいい給与体系だったんですが、ちょっとだけ減っただけで大騒ぎされたぐらいです。
今から考えるとぬるかったですね。一度地に落ちるというのは、すごく重要だと思います。そういう状況になったときに人間は頑張るし、文化を変えられる。そういうことだと思うんですね。しかし気を付けなければならないのは、リーダーが地に落ちた人をつついてはいけないということ。人格は否定せず、やり方だけを否定する。そして新しいやり方を指南しなければならない。これ結構大変なんです。20年、30年、その会社でやってきている人たちを、部分的には否定しなければならない。一度腹をくくってもらうということが、再生においてはとても大切ではないかと思います。
最近、JALが経営破綻しましたが、正直遅すぎます。アメリカでは1978年、つまり30年前に航空産業の規制緩和をしました。そして1991年にパンナム(パンアメリカン航空)が破綻しました。アメリカの航空産業は戦前の1938年から40年間やってきて、その膿を出すというのが、1978年の規制緩和策でした。
主導したのは国です。航空産業は外国で戦っている。日本にも多くの外国のエアラインが就航していますね。国外で戦っているのに国内で守っていたら、コスト構造がまったく矛盾してしまいます。国外で戦っているのだから、国内でも戦わせなければならない。つまり自由化です。国がそれを見極めて、先手を打った。そういう意味では、日本の航空産業はアメリカに遅れること30年です。
というわけで、後半はもう少し大きく、「日本再生のための企業再生」というテーマで議論したいと思いますが…。
「大都市圏から地方へ大引っ越しをすべき」(佐藤)
永沢:私は日本を再生する管財人ではありませんので…(会場笑)。たしかにJALに関しては、「遅すぎた」という意見に賛成です。もう少し前に破綻していれば、今頃は最強のエアラインになっていたかもしれません。ただ、あれが法的再生、会社更生になったという判断は、正しかったと思っています。
今までであれば、だらだらと政策投資銀行が融資をし続けるということがありました。私的整理を長引かせたり、支援機構がお金をつぎ込み続けて、法的破綻を免れるようなことをしなかった点に関しては、私は評価しています。本来潰れるべき会社が、無理に支えられて、リビングデッド(生ける屍)になるのは、好ましくありません。潰すべきものは潰す、というような政策判断が大事でしょう。
星野:過去の歴史を見ると、日本は奇跡の大成功を遂げた国ですね。それが今、大企業病にかかっている。例えば大企業の場合、日産自動車のカルロス・ゴーンさんのような人が入ってきて、大改革をしていくことがあり得ます。株主の強い支持があるからです。ところが国全体の場合には、いうなれば組合が選挙でトップを決めるようなところがあって、国民にも既得権益を持っている人がいるので、なかなか本来の改革に踏み出せません。地方自治体や我々を含めて、既得権益的に国のお金を使ってしまう人たちが諦めて、国が破綻宣言することが、私はプラスになるのではないかと思います。JALの破綻と同じように、それを遅らせれば遅らせるほど、問題が大きくなるでしょう。
佐藤:構造の問題が、一貫して話に出てきていますね。地方の中堅企業、およびオーナー企業の経営者と話すと、彼らには「悲痛な叫び」があります。我々が再生している企業の平均年齢は、40代中盤なんです。社員の多くが50歳以上です。企業の業績が悪くなっていますから、新卒採用がなかなかできない。過去数十年、会社内で何があったのか、1対1で話をするようにしていますけれども、経営者の叫びの要因の1つは、「人がいなかった」ということです。
ここから、日本をどう活性化していくかという話につなげていきたいと思います。過去40年間、誰が日本のグランドデザインを描いていたのか考えると、田中角栄元首相に辿り着くと私は思っています。日本は田中角栄さんが発表した『列島改造論』の通りに、ある程度は動いてきました。全国に高速道路を造ろう、それから港を整備しようと。
その中で、実は彼は、「インフラを使って東京に集まった人を地方に戻せ」ということも記している。国内には空港が98カ所もあります。おそらく先進国の中で、これだけ狭い国で、これだけインフラが整備されている国はないと思います。ところが田中角栄さんの主張した、そのインフラを使って人を戻すということには失敗しました。大都市圏にありとあらゆる人を集めてしまったんですね。
私は「大引っ越し」をするべき時期に来ているのではないかと思っています。もし企業の活力がこの国の活力の大きな源泉だとすれば、地方の企業にはまだまだやり残していることや、これからやれることが沢山あるんですね。その証左として、私が再生をしている会社の経営者には、実は大手町や丸の内一部上場の大企業で働いて、部長などの役職に就いていた人が多くいます。地方の社長をやってもらうと、皆さん嬉々として働きます。50代60代になってもすごく元気です。何とかしてこの形態を変えるぐらいの大きな変革をしないと、なかなかこの国の活性化は、おぼつかないのではないかと思います。
最近、企業活性化、国際競争力アップの為の法人税減税が話題に出ています。極論すると、5年間、法人税タダにする。その条件は、本社及び事業所を地方に移転するということです。大手町や丸の内に置いたままで法人税減税をしたときに、残った内部留保を何に使うか。このアイデアに反対する人は沢山いると思います。しかし、反対されることにチャレンジするくらいでないといけない。この国にはそのぐらいインパクトのある構造改革が必要になっていると思います。。
相澤:破綻は素晴らしいというのと同様に、地方は素晴らしいということですね。東京の大手企業で働いていた人が地方企業のトップになると嬉々として働く。そういう意味では、いろいろなギャップがありますね。首都圏と地方のギャップもその1つ。世代間のギャップもあるでしょう。それから産業間のギャップもある。星野さんがよく言われるのは、リゾート業界ではなかなか高い給料を払えないんだけれど、その中で工夫をしてやりがいを見出すということですね。産業間のギャップに絡んだ話を、星野さんのほうからお願いします。
星野:一番苦労するのは、やっぱりリクルーティングです。人材の確保が、我々の業界において最も大きな課題です。例えば長野県の軽井沢の近くには、工業団地のある佐久市があります。日本全国、観光地のそばには必ずと言っていいほど工業団地があります。日本の工業ですから、世界トップの生産性があるんです。かつそこでは週休2日で労働時間が決まっていて、福利厚生も充実しています。我々の業界は、生産性が世界の中でまだまだ低いと言われています。したがって、福利厚生にしても職場環境にしても、なかなか整備できないですね。この生産性の格差からくる職場の環境ギャップが、一番大きいかもしれません。
相澤:永沢さんからもギャップについてお願いします。
永沢:私自身も地方の出身でありながら東京に長らく住んでいるので、偉そうなことは言えませんが、たしかに東京など大都市に人材が集まっています。しかし、実は地方の破綻した企業にも、いい人材はいるんですね。なぜ破綻したかというと、人材を活かし切れていなかったからです。そこに問題があるのではないでしょうか。トップがいなくなることで、原石だった人材が磨かれて、光輝いてくるという事例が多くあります。
福島県のある通信機器の会社の管財人を手掛けたとき、地元の高校を出て就職し当時はまだ課長になったくらいの従業員が、代表に就きました。この人材を活かすことで、会社は活性化できた。吉野家は近頃、業績が低迷してはいますが、30年前に一度倒産して、再生を遂げましたね。もともとはアルバイトで入社して、倒産時には責任者レベルだった安部修仁さんが、破綻後に取締役に就任して、長らく社長として手腕を振るっています。もし吉野家が破綻しなかったら、彼は多分社長になれなかったでしょう。そういう意味では、実は人材がいるけれども、活かすパイプラインがないという側面があります。破綻することをきっかけにして、活躍の場が与えられることが、「破綻は素晴らしい」ということの1つの表れなのでしょう。
相澤:ギャップということで言えば、社内の意識ギャップやスキルギャップもありますよね。イノベーターとオペレーターの割合でいうと、オペレーターが多すぎます。時代が代わり市場環境がこれだけ変わっている中、イノベーターがもっと多くいるべきです。今までのやり方に追従するオペレーター的な方が多くて、イノベーターはいるんだけれども活かされていない。
私も大手企業のコンサルティングをしていて思うのは、昭和50年代入社組が障壁になっていることがとても多いんです。自分が昭和60年入社なので、ぎりぎり排除しているわけではないですけれども(会場笑)。要するに彼らは、高度成長も経験している。この会社はあと5年持てばいい。といった意識があります。そういう人たちが障壁になっているケースを、会場の皆さんにも聞きたいと思います。
「破綻を待てなければクーデターを起こそう」(星野)
会場:私は33歳なんですけれども、会社には社員が16万人ぐらいます。前任の社長は非常にいい意味でのリストラを行ってきたんですけれども、院政などの事情を含めて降ろされてしまいました。周りの人も前任の社長がいいと思っている人が多いにもかかわらず、トーンダウンしてしまっているのが現状です。破綻は素晴らしい。落ちてきたナイフを拾う。その通りだと思います。私が勤めている会社は、まだ破綻はしていない。ナイフが落ちてきているのは分かるんだけれども、見込みが甘くて閉塞感に覆われています。そういう中で、私のようなミドルの世代はどうしていけばいいのか。破綻を待つのか。変わらなくてはいけない状況の中で、どう持っていくべきなのでしょうか。
佐藤:大学を卒業して銀行に勤めていたんですね。ちょうど私も33歳あたりに、閉塞感に覆われていました。やはり悶々としている中では、行動するべきだと思います。私はクーデターを起したらどうなるであろうと考え、何人かの人と話をしました。実行に移すまでには至らない程度の話でしたが。年功序列をやめて、経営陣の若返りが必要、40歳台の若い経営陣に刷新する案を考えました。Eメールも携帯もない時代で、「今から宛名なしのファックス送るから待っとけ」などと言って、組閣表を送ったりしていました。バレたら一発で首ですよね(会場笑)。その後銀行は破綻しました。そして、外資系の投資ファンド運営会社が入ってきたんですね。クーデターを起こそうとしたときに、そんな若い者に経営ができるわけがないという懸念があったんですが、実はスポンサーが送り込んできたオーナーは、昭和55年の入社にあたる人だったんです。忸怩たる思いがあります。
破綻に持っていくことは、組織を変えるだけの大きな起爆剤になるのはたしかです。こっそりクーデター計画を立てても、おそらくうまくいきませんが、そんなことを考えていたら、何も変えることはできません。本気でそれにトライしてみると、必ず自分の将来に何らかの形で返ってきます。
相澤:早くやった方がいいですよね(会場笑)。その昭和55年入社組というのは、先程私が言ったように、今や障壁になってるんですから。別に世代間の闘争をあおるわけではないんですが、当時は変えていこうという気概のあった昭和55年入社の人が、50代になって守りに入っているわけです。だから早くやらなくてはいけません。
星野:日本経済の奇跡の大成長というのは、太平洋戦争で負けて破綻したことで始まった。それまでのモデルをゼロベースにして、先代の人たちが必死にやってきた。その前の大変革は明治維新です。これはクーデターですね。やはりこの2つしかないんじゃないでしょうか。そのリスクを取ってそれを実行することが、「創造と変革の志士」には必要かもしれません。
永沢:まったく賛成です。破綻は素晴らしいですが、ただ本当に破綻しなくてはならないわけではなく、破綻もまたありなんだと割り切ることで、破綻しないシナリオが描けることがあるのではないかと思っています。債権者との交渉でも、「このままでは破綻します。しかしこれを飲んでいただければ、会社更生になるんです」という切り札を使います。結果的には破綻しなくて済んで、佐藤さんの会社のようなところにお世話になることがあります。経営者が腹をくくれるかどうかです。「破綻に向かっているが破綻しないシナリオも有り得る」という気合いが債権者に伝わるかどうかで、すごく違ってくるでしょう。
「腹を切って会社を辞める覚悟を持て」(相澤)
会場:破綻の後、どうしていけばいいのか、ご意見を伺いたいと思います。日本は明治維新や太平洋戦争で、何かを捨てても、何かを守り続けてきたと思います。いま日本は何を捨てて何を守っていくと、再生につながっていくとお考えでしょうか。
佐藤:年功序列の制度はやめるべきだと思います。やめること自体が目的なのではなくて、数十年続けた大きな制度を変えるためには、年齢や性別を外した評価システムを定着させるしかないのではないでしょうか。
永沢:必要な人が必要な仕事をするということです。人的資源をいかに適材適所に有効活用できるのかが、企業再生の神髄だと思います。これは破綻企業の再生に限ったことではありませんね。企業再生というものは、別に特別なことをやるわけではありません。真っ当なことをできない環境だったところで、阻害要因を外すために破綻処理するのが、非常に有効だと思います。
星野:捨てなければならないのは、「お上意識」です。国や県に頼るのではなくて、自立していかなければなりません。では何を守るべきか。日本の文化性だと思っています。これはとても大事です。私たちのアイデンティティーは、最終的にはやはり「日本人」ということであって、我々は互助会にいるわけではありませんね。それぞれが自立しているんだけれども、一つの文化でつながりを維持していく。今は、文化性が薄まる一方で、互助会制度の意識が強くなってしまっているので、お互いに依存し合ってしまっている。そこにすごく問題があると思っています。
相澤:私は1985年に就職しました。25年前です。就職から2005年までの20年間は、日本の人口は5%しか伸びていないんです。2005年をピークに減り始めていますね。日本がそういう状態の中で、小売業全体がこの20年間で何をしたかというと、床面積、いわゆる販売面積を58%も増やしたんですね。つまり人口という需要が5%しか増えない中で、床面積という供給が58%も増えている。要するに過去20年間、あるいは25年間の小売業というのは、効率悪化の歴史なんです。その結果としてダイエーが破綻しました。
まだチキンレースをしているので、何となく他の小売りもおかしくなってきている。業界全部で倒れそうです。6月30日付の日本経済新聞に、すごく不思議な記事が出ました。2009年、日本の小売業が初めて減収したという内容なんですが、出店増加を考えている経営者は46%いるとも書いてある。まだチキンレースをやろうとしているんです。「みんなで揃って潰れるのか」という感じですね。
いろいろな業界において、人口減経済の中で生きていくために、グランドデザインが必要です。それを描けるプレーヤーが、あまり見当たりませんね。昔ならもしかしたら通産省が描いたかもしれないし、メインバンクが描いたかもしれないけれども、今はそういう存在がないのではないでしょうか。各産業で次世代のグランドデザインを描くということが、とても重要です。そうしないと、チキンレースで共倒れになってしまうことになりかねない。そういう視点で学んでいいただいて、是非ビジネススクールに通っている皆さんには、学ぶだけではなくて、グランドデザインを発信していただければと思います。
会場:イノベーターとオペレーターの比較が、とても面白いと思いました。しかし、ミスをしてはいけない職場環境の中でイノベーター的なチャレンジをすると、失敗する確率のほうが高いので、どうしても負けてしまうと思います。オペレーターが重視されている環境の中において、イノベーターがオペレーターと戦うため、またはクーデターを起こすためのテクニックがあれば教えてください。
相澤:そのテクニックはあまりありません。覚悟だけだと思うんですよね。もしクーデターを失敗したら、「俺は腹を切ってこの会社を辞める」というぐらいの覚悟です。私は転職を繰り返している中で、その覚悟だけが妙に成長してしまいましたが、今はそのおかげで何も怖いものがありません。
永沢: 辞める覚悟を持つのはいいと思いますが、日本の労働法では非常に従業員が保護されていて、クーデターを企てたぐらいでは懲戒解雇にはできないんです(会場笑)。これは非常に恵まれた立場なので、辞める覚悟を持っても、実際にどうするかは、慎重に考えたほうがいいと思います。
星野:先日安保闘争の話を聞いていたところ、「あの頃の学生のエネルギーはすごかったな」と言っていた人がいました。それから日本経済が発展してきて、労働訴訟の時代になって組合を構成していくというときには、労働者にすごいエネルギーがあったんです。国に対して学生がものを言おうと徒党を組んだり、会社に対して労働者の権利を守ろうという運動に比べて、いま我々が起こそうとしている会社の変革は、よっぽど良い動きだと思います。その仲間を増やしていくことがすごく大事です。当時のエネルギーを考えれば、会社の戦略を変えるということ賛同者を集めることくらいは、やればできるのではないかという印象を持っています。
相澤:自分の力では変えられないと言って、日本の大企業を辞めていく人は、今、すごく多いと思うんです。自分もそうだったのですごくよく分かるんですが、このままだと大企業がだめになってしまう。中で残ってクーデターを起こす人がいないと、良くなっていかないですよね。大企業が支えている経済があるし、大企業が持っているアセットは無視できない。名刺持っていけば大体の人に会える。転職を何度もしている私が言うのもなんですが、辞めないでクーデターして下さい。
会場:破綻をする企業の兆候というのは、どういうところに現れるのでしょうか。
佐藤:例えば破たん直後の経営者に会うことが多いんですが、「これ一個売っていくら儲かるんですか」という質問に答えられる人が意外に少ないんです。口ごもってしまう。そういうことがないように、商品をどこで売ればいくら儲かるのか、社長はもちろん、全社員に行き渡っていないといけない。基本的なことが社内に浸透していないところは、ちょっと危ないです。
永沢:破綻企業の社長室に入って、「またか!」と思うのが、「大理石の法則」です。不要な大理石を散りばめている。後は有名人とのツーショット写真。自分の業種には関係のない、女優やスポーツ選手との写真ですね。それからフェラーリや社長しか使えない保養所。こういったことは、破綻企業に共通しています。経営資源を有効に配分できていないというのが、如実に表れているわけです。
相澤:みなさん、会社に帰って、社長室に大理石があったら、即クーデターですよ(会場笑)。


.jpg?fm=webp)