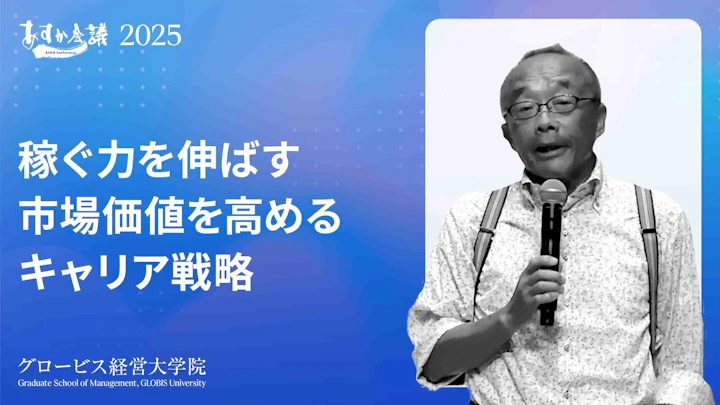昨夏、北米で端を発したトヨタ自動車のリコール問題は、同社ならびに日本製品の安全神話まで揺るがす事態に発展した。これについて、戦略コミュニケーションの第一人者である田中慎一氏は、「非のないところにも煙は立つ」。それがクライシス・コミュニケーションにおける重要な一側面であると力説する。
問題発生時に、非があるや否やという事実究明や「理」にのみ基づく説明は意味を成さず、ステークホルダーを正しく見極めたうえでの「情」に基づくコミュニケーションが、世論を味方につけ、ソーシャル・コンプライアンスに寄り添う一助となる。ところが過半の日本企業は、外形的な法令遵守、即ちリーガル・コンプライアンスのみに捉われてしまう、と。
リスクを正しく測り、管理する「リスク・アセスメント」「リスク・マネジメント」から、それを最適な対話によって伝え、理解を求める「リスク・コミュニケーション」に推し進めよとのこと自体は、語られ始め久しい。しかし一方で、これを危機感とともに真に迫って捉える企業は少なく、実現する具体的な手法や、経営責任についても不明瞭な部分は多かった。
それだけに、日本を代表する企業の問題に照らし、「対話力を高めよ」「最後は経営者の責任である」とする田中氏の提言は重く、また貴重なものとして響く。
「コミュニケーションは最小の反作用で人を動かす力」
田中:今日はトヨタ自動車のリコール問題を例に、有事の際にとりわけ強く求められる「企業の対話力」について考えていきます。日本を代表するグローバル企業が、なぜあのようなクライシスに陥ったのか。外から伝わってくる情報を中心に検討しましょう。
誤解のないよう申し上げたいのですが、今回のケーススタディは、トヨタのどこが間違っていたかを検証し、追及するものではありません。ただ、トヨタのケースは、日本企業の多くが抱える問題を象徴しています。その一つが、対話力に乏しいということです。そして対話力が一番試されるのが、有事、クライシスのときなのです。
はじめに簡単にコミュニケーションとは?というところから整理しましょう。コミュニケーションとは、「人を動かす力」です。仲良くするとかお互いに意思疎通を図るとかいうことではなく、人を動かす力だというふうにまず認識することが肝要です。コミュニケーションの力学は、相手が何らかのメッセージを受けて、それによって意識が変わり行動が変わるものです。自分が発信した内容が、必ずしも意図したとおりに伝わるわけではなく、相手に伝わったものがメッセージになります。
人を動かす力にはほかに、いわゆる武力・財力・権力があります。コミュニケーションの力というのは、これらと異なり、相手が共感し納得して動くために、反作用が少ないことが特徴です。例えば武力というのは、物理的な力や意図を使いますが、その場合、反動、妬み、恨みを買う。財力というのは、「金の切れ目は縁の切れ目」という言葉もある通り、持続性があまりない。対して、コミュニケーションの力というのは、反作用が少ないわけです。反作用が少ないだけに、非常に投資対効果が高い。ですから人類は有史以来、人を動かすということに関しては、このコミュニケーションの力を最も多く使っています。
ところがコミュニケーションというのは、武力や財力や権力と違い、厄介な力でもあるんです。何が厄介かといえば、意識しなくても作動してしまうんですね。武力・財力・権力は、意識して使います。例えば相手を殴るとき、意識せずに殴るということはほとんどないですよね。相手に動いてほしいからと、100万円の札束を無意識に渡すこともありません(会場笑)。コミュニケーション以外の力というのは、意識して使われるんです。しかしコミュニケーションは、意識しなくても作動します。
黙ってさえいればメッセージが伝わらないかといえば、そんなことはありません。黙っていることそのものが、メッセージになってしまうこともあります。自分の職場に異動で新しく人が入って来たが、その人はほとんど話も何もせずに黙っている。そうすると本人はメッセージを一切発信していないと思うかもしれないけれども、その事実を見ている周りが「こいつは付き合いにくい野郎だな」とか、「今日は奥さんと喧嘩してきたんじゃないか」とか、勝手にいろいろ解釈してメッセージを受け取ってしまうんです。厄介なのは、そういう勝手に受け取ったメッセージで周りの人が動いてしまうことです。「この人とは一緒に仕事したくない」とか「ちょっと距離を置こう」といった具合になるわけです。このように、コミュニケーションというのは意識しなくても作動してしまう。人間は、自分のいる場に別な人間がいる場合、そこでは、自分のメッセージが、垂れ流しの状況にあると思ったほうがいい。
とりわけ企業のクライシスのときは、周囲が一挙手一投足に注目しているわけです。だからある意味、あらゆるメッセージが流れ出てしまっているんです。そこでどんなメッセージが伝わっているかを意識することが、実はクライシスのとき非常に重要な企業の対話力の要になります。よく言われる「空気を読む」ということですね。空気を読むというのは、相手のメッセージを読み解くことではありません。自分がどういうメッセージを伝えてしまったかということを、読み取る能力です。特にクライシシスでの企業の対話力は、空気を読むことがとても重要になります。それを踏まえて、話を進めていきたいと思います。
「有事においては当事者のみならず世論もステークホルダーとなる」
クライシス対応は3点に大別できます。1つ目は、まず火を消すこと。2つ目は、法的責任への対応。そして3つ目は、影響を受けた相手とのコミュニケーション対応です。過去10年にわたり、諸々の事例を振り返ってみると、過半の日本企業が、1つ目と2つ目はしっかりやっています。しかし、ほとんどが、3つ目で墓穴を掘っているんです。
このときの“影響を受けた相手”は、3者に分けられます。まず1人目ですが、クライシスである限り必ず被害者がいます。2人目は、クライシスを早く収束させるために協力を取り付ける人が必要になるわけですね。そして3人目は、世論です。ここは世論が非常にぶれる中で、世論とどう対応していくのかが重要になります。
具体的にいうと、JR西日本の福知山線の脱線事故ケースがありました。JR西日本の場合、どういう対応をしたかというと、まず「被害者」ですね。事故が起きてから2時間後に記者会見をしています。その中で社長が、「お客様第一の対応させていただきます」と言っていました。それ以外に被害者に対するメッセージがなかったんですね。ただ、ここで言う“お客様”、“被害者”は、いったい誰だったのか。
クライシスが起きたときの“被害者”というのは、その時点で一番困っている人なんです。事故が起きて2時間後の被害者、それは、事故に遭った人たちだけではないんです。事故に遭った人たちの元には、もう救助隊が行っているんです。むしろ、より問題なのは、「もしかしたら自分の知人、あるいは家族が事故に遭ってしまったんじゃないか」という安否情報を求める人が、突然のごとく何万人何十万人と出るわけですよ。それが一番困っている人たちなんです。であるならば、一番重要な記者会見のときに、単にお客様第一と言うだけではなく、「安否情報をお求めの方は、こちらにお問い合わせください」というように、困っている人たちに対するメッセージを出すべきだった。JR西日本は、そこを見誤りました。
2つ目の「協力を取り付ける相手」についてもお話しします。その後、JR西日本が「不適切行為」という言葉で糾弾され始めました。事故が起きた当日に、社員がボーリング大会や飲み会に繰り出していたことが明るみに出たためです。これはある意味、社員の中に危機意識の醸成ができなかったということです。クライシスのときに、本当に支持を取り付けなければいけない相手というのは、実は身内に在ることも多いのです。社員に危機意識醸成をしっかりすることによって、第2、第3のリスクを摘み取っていくわけですね。ですから、2つ目の相手というのは、ここでは社員です。JR西日本の場合は社員だけではなく、当局との関係もおかしくなりましたね。クライシスを収束させるためには、一緒になって協力してくれる相手にしっかりとメッセージを出すことが重要で、JR西日本の場合はそれができなかった。
最後の「世論」については、当事者意識欠如と思われたら、終わりです。そして、これがクライシスの際に実は最も怖いものとなります。
「非のないところにも煙は立ち、沈黙は禁ながら、出る杭は引っこ抜かれる」
よく「火のないところに煙は立たない」と言いますよね。しかしクライシスの場合には、「非のないところにも煙は立つ」のです。どういうことかというと、弊社は悪くない。商品の構造的欠陥はない。商品そのものは問題ない。問題はユーザーで、ユーザーが想定外の使い方をしたために事故が起きた・・・。しかし、そうした場合でも、「企業側としての責任はない」では済まされないということです。自分に非がなくても、燃えてしまう。クライシスというのは、そういう世界なんです。
「おかしいよ、こっちには非がないんだよ」といっても燃えてしまう。これが非常に難しい部分です。自分たちに非がないからといってメッセージを出さないと、どんどん炎上していきます。「沈黙は金なり」と言いますが、沈黙してはいけないんですね。「沈黙は禁なり」で、何らかのメッセージを出さなければいけない。「出る杭は打たれる」とも言いますが、クライシスのときは「出る杭は引っこ抜かれる」。下手なメッセージを出すと、それはそれで炎上します。
今回のトヨタのケースには、この3つがいろいろな形で混ざり合っています。
実際にクライシスを経験すると、よくぶつかるジレンマがあります。どういうジレンマかというと、先程言った第3の相手、世論や世間というのは一番怖い存在なんですけれども、有事において企業は2つの法廷で勝つことを求められます。1つは、損害賠償などを巡り、裁判所で勝たなければいけない。もう1つは、社会という名の法廷です。この社会という法廷で勝たないと、下手をすると裁判所で負けるよりも大きな損害を受けることになります。例えばブランド、あるいはレピュテーション(評判・名声)の毀損です。それが企業価値にとても大きなダメージを与えるわけです。
裁判所で勝つのか、社会の法廷で勝つのか、最終的に決めなければならないのはCEOです。どちらを選択すべきかに正解はありませんが、ただ、2つの話がしっかりと示されたうえでCEOが判断することが重要なんです。とかく日本の企業は、裁判所の法廷に引っ張られる傾向がありますが、グローバルな流れでいうと、最近は裁判所で勝つよりも、社会という法廷で勝つことを優先する経営者が欧米では増えています。いずれにしてもクライシスが起こると、リーガル・コンプライアンスとソーシャル・コンプライアンスのぶつかり合いがあるということを、理解しておいていただきたいと思います。
議論をわかりやすくするために、トヨタのケースを3つのステージに分けてみていきましょう。第1期は、2009年8月28日から2010年2月4日。去年の8月28日にレクサスが暴走し、それによって4人の家族が亡くなりました。そこから今年の2月4日までは、どちらかというと「沈黙を守る」というスタンスを通しています。しかしその後2010年2月4日〜2月23日の第2期は、「発信する」に切り替えました。ただ、そこでのメッセージは逆に世論を炎上させてしまいます。最後の2010年2月24日〜3月8日の第3期が、「覚悟する」。公聴会に豊田章男社長が出て来て、そこから一気に流れが変わりました。それぞれ簡単な映像資料にまとめましたので、まずはご覧いただきましょう。
<ビデオ1概略>
今回問題になったのは、アクセルペダルの根本になる樹脂製の部品。最悪の場合、アクセルを踏み込んだ状態で、戻らなくなる恐れがある。アメリカで230万台、ヨーロッパで180万台など、合わせて440万台あまりがリコール対象となる。トヨタは2009年11月にも、大規模リコールを行っている。フロアマットがずれてアクセルが戻らなくなり、暴走する恐れがあるとして、535万台のリコールを発表。創業来の最大規模となっている。2つの数を合わせると延べ900万台以上で、年間の販売台数を上回る異常事態として、米メディアは連日大きく取り上げた。トヨタは不安の解消に躍起で、リコール対象となる車種の生産と販売を全米で一時停止。米議会は公聴会を開くことを決定し、トヨタの幹部から直接説明を受ける方針。米政府としてトヨタに制裁金を課す方針も示した。
まとめますと、2009年の8月28日に交通事故が起こりました。この事故は、所有者が修理のために車を預けて、代車に乗っていたんですね。そのときに自分の車にあったフロアマットを取って、元々ある代車のフロアマットの上に置いたらしいんですね。フロアマットを2枚重ねにしたことによって、アクセルペダルが戻らなくなってしまったというのが、最終的な事故原因の調査結果です。ですからある意味、製品そのものの構造欠陥ではないということだったんですね。ところがトヨタがメッセージを発信したのは11月25日で、外から見るとかなり時間が掛かっています。これをリコールにするのかしないのかという議論が、当局との間で長引いたためです。トヨタはその間、沈黙したままだった。なぜかというと、変な企業メッセージを出すと、当局との話し合いに影響するからです。つまり、ソーシャル・コンプライアンスより、リーガル・コンプライアンスを優先したんですね。しかし結局は世論の力に負けて、11月25日にこれは構造上の欠陥ではないという前置きをしながら、部品交換を発表しました。ところが今年2010年の1月21日になって、今度は構造上の問題でアクセルが戻りにくいということで、これは本当の意味での商品に対するリコールとして、230万台が対象になりました。さらに同じようなケースが中国、ヨーロッパでも出てきた。そういう中でトヨタは2月1日に工場閉鎖などの方法、あるいは社長がビデオに出てリコールの説明をして謝罪する、佐々木眞一副社長が日本から海外向けに、アクセスペダルの不具合について謝罪会見をする。こういう流れなんです。
「一貫性のないメッセージは当事者意識の欠落と映る」
ここでのポイントは、製品の構造的不具合ではないという主張をし、自らがそれに呪縛されてしまったということです。自分たちに非があるわけではなく、あくまでもそれは想定外の使われ方だったのだから、リコールではないんだという主張に、当初は呪縛されたという感じだったんですね。そのために企業姿勢として、何かを具体的に大幅に打ち出すことができなかった。当局であるアメリカの運輸省交通安全局と交渉していたことが、さらに足を引っ張られる要因となりました。結果としてそこで沈黙してしまったわけです。加えてこの期間、トップの姿がまるっきり見えなかった。今年になってから佐々木副社長、および現場の販売ヘッドが出てきましたけれども、本当の意味でのトップの姿がなかった。こういう状況が半年近く続いたうえで、ようやく「発信」のモードに転じます。
<ビデオ2概略>
横山裕行常務が記者会見で、ブレーキが一時的に効かなくなるという苦情は、運転者の感覚的なもので、車両の欠陥ではないという認識を示し、ただ、お客様の不満は改善すべき問題として方策を検討するとしていた。リコールを届け出た後の記者会見には、豊田章男社長が出席。「“抜ける”という表現が、私自身はすっきりすると思う」と語った。豊田社長は英語でもメッセージを伝えたが、公聴会への出席については言葉を濁した。これに対し欧米のメディアは、「豊田社長の証言拒否が怒りを招く」などと批判した。結果、社長本人が公聴会に出席することになった。
当初はアクセルペダルの構造問題でしたが、追い討ちをかけるようにプリウスのブレーキ部分について問題が起きました。そこで急遽、2月4日に横山常務が話をしたのですが、「感覚的なもの」という表現で、あくまでも欠陥ではないという説明をした。ところがそれで収まらず、その翌日には豊田章男社長が緊急謝罪会見を開きました。これが今回のクライシスで、初めてトップが出てきた場面です。しかし、リコールは認めなかったんですね。2月5日は金曜日だったんですが、次の週の9日火曜日に、前原誠司国交相がトヨタに対して批判しました。それで急遽、9日にリコールを申請したわけです。豊田社長は、その謝罪会見にも出てきました。これは、外から見ていると、リコールを巡って一貫性のない感じがしますよね。米国で公聴会に出席するか否かが問題においても17日の段階では、公聴会には出ないことを示唆していたのですが、それが海外のメディアで報道され、今度は下院から来るようにと要請があり、19日には一転して出ることになりました。
ここでのポイントは第1期とも似ていますが、感覚的な問題であるとか不具合ということで、製品の構造上の欠陥ではないという意識が出てきます。この意識が発信そのものを、まだ呪縛しているという印象を受けます。それから、せっかくトップが出てきたのに炎上してしまったんですね。なぜかというと、発信しているメッセージに一貫性が見えないからです。リコールを認めるのか認めないのか、公聴会に出席するのかしないのか。それが一転二転する。クライシスのときに一貫性がないと、当事者意識がないと見られます。あらぬ疑惑にも発展していきます。
メッセージの一貫性に関し、非常に重要なのは、問題への対処や情報発信のイニシアティブを取れないとどんどん状況に対して後追いになっていくということです。当事者は何とか誠実に対応しようとしているだけで、意図的にメッセージをぶれさせたりしようとしているわけではないのですが、何か外から言われるたびに回答が変わっていくのでは、ぶれていると言われて仕方ない。それから、この時点の課題として、火中の北米市場への発信が生半可ということも挙げられると思います。真っ芯から対処すべきだったのは、台数的に見ても、日本というより北米市場なんですよね。ところが日本で記者会見を行い、英語で半端なメッセージを出す。それよりも現地に行って発信するというのが、本来のあり方だったのではないかと思います。
<ビデオ3概略>
公聴会を終えた豊田章男社長は、販売店や工場の従業員を集めた会合に出席し、「自分は一人ではない」と涙ながらに語る。その後、アメリカのテレビ局・CNNに向かい、トーク番組に生出演した。中国の北京でも謝罪会見を行い、日本に帰国した直後にも報道番組に出演した。
この第3期では、公聴会に出席してメッセージ性が変わってきています。ある程度、イニシアティブを取れるようになってきた。公聴会の後に話をする。人気番組に出る。ケンタッキーの工場にも行って、従業員を激励し、泣くシーンもありました。それから北京まで行って謝る。最後には報道番組に出演する。第2期のトヨタとは、明らかに違ったメッセージになっていますよね。
ポイントとしては、クライシスには必ず「ターニングポイント」があるんですね。理想はクライシスが起きたときに、一挙にイニシアティブを取りに行くこと。こちらからメッセージを出してイニシアティブを取ると、後手後手に回らないんですが、なかなかそれはできない。でも、クライシスで火が燃えている間にも、必ずターニングポイントになり得る時点があるんですね。それをうまく使ってイニシアティブを取ることが重要です。トヨタの場合は、本来は、アクセルペダルに構造的な不具合が見つかった時点で一挙にイニシアティブを取るべきだったと思うんですね。ただ、やはり、さすがトヨタさんだと私は思うんですけれども、公聴会をターニングポイントにしましたよね。公聴会のところから、ある種の覚悟が決まった。それがトップのメッセージ性を変えています。そういう中でリーダーシップを維持しながら、このクライシスを乗り切れるかどうかについては、予断を許さない状況とは思いますが、私の目には、今はイニシアティブを取り、うまく状況をコントロールしているように見えます。
「クライシスの際には、理より情が支配的になる」
クライシス・コミュニケーションのポイントを整理します。クライシスに陥ったときには、「当事者意識」を持つことが最大の武器になるんですね。逆に当事者意識が欠如していると、周りが襲い掛かってきます。当事者意識をどう持つか。トヨタの場合、車という商品は安全・安心が第一ですね。いかに想定外の、例えばユーザーの勝手な使い方であっても、そこで事故が起きたとき、安全を売っている企業にとっては、商品の欠陥に起因するものではない、というだけではすまないんです。もっと違った形のメッセージを出さなければいけない。そういう意味では当事者意識を持つことが重要ですね。
この当事者意識を感じるためには、すべてを「相手視点」にすること。JR西日本のケースで、その時点で一番困っている人に対してメッセージを出すべきだという話をしましたけれども、対象車種に乗っている人がアメリカに沢山いるわけです。そういう人たちの気持ちになって、今どういうメッセージを出さなければいけないのかと考えれば、もう少し工夫ができたのではないかと思います。
それから、「主張」ではなく「受け入れ」。必要なのは「商品には問題ないんです」という主張じゃないんですね。理由はどうあれ、事故が起こってしまった。安全を売っている企業として、その現実を受け入れていくという姿勢を示すしかない。
そして「理」ではなく「情」。クライシスの際には、情が支配的になります。理屈を言えば言うほど炎上します。かつてパロマという会社が製造した湯沸かし器を、ユーザーが改造したために起きた事故がありました。あの時、彼らはどうやって改造されたかというプレゼンをしたんですね。つまり、改造はこうして行われた。裏を返すと、我々の責任ではないんだというメッセージが出てしまった。そういう理屈をこねたんです。それによって、世論はさらに炎上しました。
あとは先程から申し上げている通り、「メッセージの一貫性を死守する」ことですね。繰り返しになりますが、これにはどの段階でイニシアティブを取れるのかがとても重要となります。とりあえず行うと、後手後手になって、結局のところ一貫したメッセージが出せなくなるんですね。とにかく次から次に来るものに対して、一所懸命対応することで精一杯になります。すると、一貫性のない発信をせざるを得ない状況に追い込まれていく。結果、当事者意識がないと思われるようになっていきます。
それから、「余計なおしゃべりはご法度」です。先程出てきた“感覚的な問題”という釈明は、失言に近いですね。お客様としては、アクセルの感覚がちょっと違うなlということさえ、やはり心配なわけです。それを「あなたの感覚的な問題ですよ」では、火に油を注ぐようなものです。
最後は、「切り返し点を見つけること」が、とても重要です。そして、「覚悟」が必要ですね。企業の覚悟を示すのは、トップの動きです。よくトップが「覚悟」という言葉を口にしますが、覚悟というものは言葉で言った途端に、信憑性を失う。覚悟というのは、自分の動き・行動で示すものです。トヨタのケースでは、トップが去年の段階でアメリカに行く。そこで、しっかりとメッセージを発信するという動きを示すことが必要だったように思います。
「ソーシャル・コンプライアンスVSリーガル・コンプライアンスの視点を持つ」
最後のまとめです。企業の対話力とは、空気を読む、空気をつくる、クライシスに対する立ち位置を明確にすることです。空気を読むということは、言い換えると期待を読むことです。トヨタほどの会社になると、事故への対処一つをとっても、「トヨタさんだったら、これくらいのことはしてくれるだろう」と世間全般から高い期待を背負わされる。そして、これにミートできないと、期待が疑問になる。疑問はさらに疑惑になる。これが一気に襲い掛かってくるんですね。今回のケースではトヨタが沈黙を守ってしまったために、期待が裏切られた。そこに疑問が発生し、疑惑というところまで行ってしまったのです。
期待を読んだら、今度は空気をつくる。これは、期待をマネージすることですね。昨年の民主党のようにすごく期待が上がったのにもかかわらず、その後それをマネージしようとせずに、普天間問題で「最低でも県外」という言葉で期待をもっと上げてしまったんですね。そして、立ち位置を明確にする。クライシスを収束するための具体的なアクションを提示します。これが企業の対話力という意味では、非常に重要になってきます。
それから先程もお話ししたように、ソーシャル・コンプライアンスVSリーガル・コンプライアンスの視点を持つことです。これを具体的に言えば、例えば当局と話をしているから、いま企業として社会に対してメッセージを発信できないという視点。いま社会に対してメッセージを発信しないと、後々痛手を被るという視点。この2つのせめぎ合いが必ずあるんですね。その中で、どちらに寄る辺を求めるかについては、CEOが判断するしかありません。
危機に際しては、いつにも増してトップのリーダーシップが鍵を握ります。欧米の企業に比べて日本の企業のトップには、クライシスを自分の専権事項だと意識している方が少ないです。副社長に任せたりする。でも欧米の場合には、クライシスは自分の専権事項だということで、トップが必ず出てきます。そういう意識があります。
ただトップが幾らそういう意識を持っても、仕組みがないとうまくいきませんね。つまり、情報受信・状況分析・メッセージ発信をトップのもとで一元化する体制が不可欠です。欧米では、情報受信・状況分析・メッセージ発信が1つの組織になっています。しかもその組織が、CEOに直属になっています。日本の場合は、例えば広報や渉外、調査を行う部署が、バラバラになっています。それが一体化されていないだけではなく、CEOの直属になっていないんですね。これからは、こういう機能を一元化し、コストセンターや間接部門ではなく、1つのトップのメッセージ性を守る戦略部隊として、あるいは企業のレピュテーションを守る戦略部隊として、トップ直属に位置付けられるようになるのではないかと考えています。
それと大切なのは、レピュテーション・マネジメントの発想を持つことです。ブランドというものは、認知度のないものをある程度認知させて、商品の良い点を上げていくわけですが、ここで気をつけなければならないのは、ブランドが上がるとそれ以上に期待値が上がることです。この期待に対してしっかりと応えていかないと、一気に期待が疑問、疑問が疑惑に変わってしまいます。ですから、ブランドをどんどん上げてビジネスを展開する中で、その背後に期待値がそれよりも大きな形で生まれていく。それをどうマネジメントしていくかというのが、企業の対話力に求められていることを、心に留めていただければと思います。
質疑応答「しっかりとした立ち位置をつくるだけの対話力を持つこと」
嶋田:以前、田中さんから「メッセージの99%は曲解される」という話を伺いました。それだけ自分たちが発しているメッセージというのは、間違って伝わっている。クライシスの場合は特にその傾向が強いと思うのですが、その中で空気を読むとか、客観的に自分たちがどう見られているかが鍵になると思います。そうした空気を読むこと、自分たちを客観視することについて、何か良い方法論はありますか?
田中:1つは、情報受信・状況分析・メッセージ発信を一元化し、他部門から独立させてトップの直属にすることが非常に重要なんですね。なぜなら、現状の日本の企業の構造というのは、縦構造でワン・オブ・ゼムなんですよ。そうすると何が起こるかといえば、正確な情報がトップに上がるまでに色が付いてしまうんですね。ですから、各部門のいろいろなしがらみや影響力を排除した、トップだけのための戦略部門が求められます。トップにとって、目であり耳であり鼻であり口であるような機能を担う組織が必要なんです。
もう1つは、第三者を活用することです。社外取締役など第三者を入れる。あるいは我々のようなクライシス・コミュニケーション・コンサルタントを入れる。それから事によっては、当局を入れることですね。当局と話をすることによって、客観的に物事を把握するというのは、組織的には良いことです。個人的なビジネスリーダーとしては、このあすか会議を含めいろいろな人の意見を聞く中で、自分自身のメッセージが第三者から見たときにどうなのかということをチェックするのも1つのやり方だと思います。
嶋田:なるほど。日本で今おっしゃったような仕組みを持っている参考事例はありますか?
田中:全般的に遅れていますが、日産やソニーのようにトップが外国人の企業は、その意識が強いですね。組織形態を一元化した戦略部隊の発想で捉えている企業は、日本にもいくつかあります。
会場:不祥事があるとマスコミは面白おかしくセンセーショナルに報道する傾向がありますが、正しい姿を伝えるために何か施策あればお聞かせください。
田中:繰り返しになりますが、今どういうことを言ったらどういう反応が出るかということを、メッセージを出す前にしっかりと精査するしかない。そのためには仕組みが大切です。メディアは当事者意識を示す際に、うまく活用できる存在でもあります。心から申し訳ないという気持ち、一番困っている人たちを何として救おうという気持ちがトップにあれば、そういうメッセージは、たとえ非言語だけであっても伝わると思います。
無論、メディアには言われるような問題が確かにあります。午前中のメディアに関する議論のときにも、「いまマスメディアはワイドショー化している」という意見がありました。つまり、なるべく多くの人に“ウケる”ことを前提に発信活動がされている。これをどうするべきかという「べき論」ではなくて、それが実態としてあるんですね。そうならば、こちら側も、その実態に対して精査しながら出していくという努力が必要になります。それも単に広報部長の技とかトップの技といった個人技ではなく、組織としてしっかりやっていくことです。組織としてのコミュニケーションの発想を持つことが、すごく重要になると思います。
会場:リーダーシップについてお伺いします。クライシスの際にはリーダーシップが最も顕著に出ると思いますが、特に日本という国のアイデンティティが同時に試されているのではないでしょうか。例えばはっきり言わないとか、トップ個人が責任を持たないといったことがクローズアップされたと思うのですが、その中でこれから日本人はどんなアイデンティティを活かして、どういうリーダーシップを見せていったらいいのか、お聞かせください。
田中:アイデンティティの発想はまず自己視点から出てきがちですが、実はアイデンティティは周りとの関係から生まれてくるものだと私は考えています。つまり周りから評価されないのに、自分のアイデンティティが確立することはあり得ないと思います。周りから「よくやってくれた」とか「よく貢献してくれている」と認知されるところから、自分のアイデンティティは出てくるのではないでしょうか。ですから日本の政府も、日本の企業も、あるいはビジネスリーダーにしても、アイデンティティを確立するというのであるならば、どういうところで周りに対して貢献しているのかを可視化して、周りに認知してもらう。そういう中で自分のアイデンティティというのが確立されてきます。
私の解釈では、アイデンティティというものは立ち位置なんです。立ち位置も自分から出てくるものと思われがちけれども、そうではなくて周りから生まれてくる。周りに対して自分がどう貢献できるか、どうやったら相手に役に立てるのか。そこが基本的にはアイデンティティであり、立ち位置をつくるスターティング・ポイントだと思うんですね。ですからこれからの日本のビジネスリーダーというのは、どうやったら世界に貢献できるのか。それを考えながら、リーダーとして、企業として、国としてのアイデンティティを確立すべきです。
そうすると、土俵をどこに置くかが重要になります。日本の国の利点ということであれば、環境問題ですね。例えばダボス会議などでは、一旦出てしまったCO2にどう制度的に対応するかという話が中心になっていますけれども、本来なら元から断たなければいけないものですよね。出させないことが重要なんです。環境技術は日本が優れているわけです。そういう環境問題も、元から断たなければだめだというところに土俵を置く。そこでしっかりと立ち位置をつくって、それによって世界に貢献する。そこから日本のアイデンティティが生まれる。そういう認識をつくることが大切です。また水産資源、日本の農業、それからいろいろな形での食の捉え方、こういうものも、もしかすると世界に冠たる土俵になるのではないか。人口増加の中で、食糧問題は大きな問題になっています。そういう中で、水や食糧を土俵にして、そこで日本のユニークな立ち位置をつくれるのではないか。ですからこれからは国にしても、企業にしても、あるいはビジネスリーダーにしても、まず自分がどういうところで役に立つのかという土俵を設定したうえで、そこで自分の立ち位置をつくっていくという発想が、重要ではないかと思いますね。
嶋田:周囲との関係性が、これからのリーダーには必須となる。しかし、それをなかなか持てないでいるということでしょうか。
田中:一言でいえば、空気を読む、空気をつくる。そして、自分の立ち位置をつくること。空気を読まなければ、空気をマネージメできませんよね。空気というのは、すなわち期待です。マネージしたうえで、つまりその期待を頭に入れたうえで、自分の土俵を置いて、自分の立ち位置をつくる。こういう発想に尽きると思いますね。
会場:企業の国籍には、どういう意味合いがあるのか。そしてまたその国籍とは、定義できるものなのか。このトヨタのケースでは、間違いなく日本国籍の会社ですよね。それによって、被害が大きくなった側面もあるかもしれません。日産やソニーだったらどうなのか、というところがよく分かりません。日産はどこの会社なのか。企業活動におけるアイデンティティとしての国籍の持つ意味合いについて、考えを伺いたいと思います。
田中:とても重要な質問です。ビジネスリーダーにとって、企業にとって、国籍とは何なのかは、これから皆さんが直面する問題でしょう。自分の立ち位置をつくるのに国籍が役に立つ、あるいは土俵を置くうえで国が提供してくれるのであれば、どの国籍でいるかが鍵になります。それが日本であれば日本、アメリカであるならばアメリカ。そういう考え方が重要と思います。
それは業種によって異なります。自動車産業の場合は、日本の国籍を持っている、あるいは日本にアイデンティティを持っているから強みがある部分が濃厚だと思います。ただソニーのようにグローバル展開しながら、日本そのものがビジネスモデルに資する存在かというと、自動車産業に比べて圧倒的に薄い。そうするともっとグローバルな発想になります。日本で生まれたグローバル企業は、日本の強みを活かして出て行きました。それが引き続き強みとして持続できる業界なのか、あるいは企業風土なのか。あるいは、もう海外に行ってしまったほうがいいのか、これはそれぞれの会社のビジネスドメインや業界によって、かなり違ってくると思います。だから土俵をつくるうえで、国籍に価値があるかどうかがで私は判断します。
会場:国籍でさえ、意味のないこともあり得るということですね。
田中:あり得ます。ただスタート地点として日本から出て行くわけだから、日本の強みを活かさないと、なかなか独自の立ち位置を世界でつくるのは、現段階では難しいと思います。これが50年後には、そうではない時代が来るかもしれませんけれども、少なくともこの時代を考えたときには、日本の強みを活かして、国も企業もリーダーも日本基点の立ち位置をつくるべきだろうと考えます。
嶋田:発展著しい中国とは、不幸にも歴史上の軋轢があります。今までの先進国である欧米と異なるコミュニケーションであったり、空気の読み方の難しさが出てきたり、曲解されることもあるでしょう。そのとき、日本人、日本企業はどう対応すればいいのでしょうか。
田中:これは企業で考えたときに、空気を読む、空気をつくる、立ち位置をつくる専門部隊を欧米では持ち始めているんですね。特に中国戦略になると、官の問題が出てきます。日本のグローバル企業は欧米で育っているから、それほど官を意識せずに済むわけです。しかし今やグローバリゼーションの主戦場は、中国に移ってしまいました。中国で勝てなければ世界で勝てないという流れにおいて、中国の中でどのようにして成功するかを考えたときに、欧米やインド、韓国企業の多くが何をしているかというと、ビジネス部隊が行く前に、そうした一種のデルタフォースのような専門部隊を先に送り込んでおいて、そこにどういう期待があるか、どういう期待をマネジメントしないといけないのかといったことを、事前に把握する。中国は特に官が強いので、民間企業と官では勝負にならないんですね。そうしたときには、自国政府をも動かすわけです。そういう戦略部隊というのは、土壌をつくって本体を迎え入れる体制をつくるだけではなくて、自国の政府をどう動かして、中国政府に対してプレッシャーをかけるかということを戦略的に、CEO直轄で行っているんです。これからの日本というのは、そういう発想で動くというのがとても重要になると思います。
会場:私は数か月前に業務停止を食らった製薬会社に勤めています。現場でお客様に接してリスクを背負っているのは組織の中に社員ですが、今回のクライシスでどういう心持ちで対処すればいいのか、残念だったのはトップがなかなかメッセージを出してくれなかったことです。危機に陥ったとき、トップや私たち社員はどうすべきか、何かご意見があればお伺いしたいと思います。
田中:かつては「鬼は外、福は内」という世界だったんですね。今は「鬼は外、鬼は内」という時代で、実は後ろから刺されるケースが多いんですね。前のセッションで「いわゆるソーシャルメディアは予言ではないか」という話がありましたが、私もそう思っています。内部告発の温床になりつつあるのが、ソーシャルメディアなんです。そこをしっかり見ていると、だいたい半年前に分かりますね。そういう意味で帰属意識が薄れているわけではないですが、帰属意識のあり方が変わってきているということなんでしょうね。何に対してロイヤリティを感じるかというのが変わってきているのであって、希薄化しているのとはちょっと違うと思います。実はそこがおそらく、これからの日本では気をつけなければいけないところです。昔は終身雇用とかいろいろな仕組みがあって、帰属意識を担保していたんですね。それが崩れて労働の流動化が激しくなる中で、帰属意識のあり方が変わり内部告発が連発されたことで、企業不祥事が明るみになってきた。
だからこれからは、社内の意識をどう固めていくのか。ある意味でトップが発信する外に対するメッセージというのは、自分たちに向けて発信しているものでもあるんですね。例えば昨夜、中締めのスピーチをさせていただいたんですけれども、そのとき「ナイトキャップは素晴らしい」と言ったんですね。それは皆さんに言うと同時に、自分に聞かせているんです。なぜなら、初体験の去年のナイトキャップは、かなりハードだったんですね。だから、これは自分に覚悟を決めさせるうえで、皆さんの前であえて言ったんです(会場笑)。そのように、これからのトップの発信は、外に出すと同時に中の人々の意識を引き締めるという意味合いがあります。先程お話しした3人の相手のうち、2番目の協力を取り付けなければならない相手に危機意識を醸成することが、クライシスの際にはとても重要なんですね。JR西日本が事故からわずか2時間で記者会見を開いたことは素晴らしかったんです。もったいないのは、その場にあらゆるメディアがいるわけだから、そのメディアを利用して社内に危機意識を醸成するという手立てがあったかもしれないということ。被害者だけではなく、社内に対して気を引き締めるという発想が重要になってきます。
会場:ソーシャル・コンプライアンスとリーガル・コンプライアンスのバランスが大切という整理に感銘を受けました。空気を読んで謝ってしまえば簡単なんだけれども、企業としてはそれに対する賠償責任であったり、コストが発生するでしょう。それによっておそらく、トヨタの場合も回答が遅れたりしたんだと思います。訴訟社会の米国と日本ではバランスが違うと思いますが、国の文化とバランスについてお考えがあれば伺いたいと思います。
田中:非常にいいポイントです。クライシスが実際にあると、必ずここにぶつかるんですね。我々はソーシャル・コンプライアンス、社会の法廷で勝つために動く。リーガル・コンプライアンスは逆です。裁判所で勝つために動く。両方で勝てるメッセージ発信ができればいいんですけれども99%食い違うんですね。ですからこのバランスが重要なポイントなんですが、裁判所で負けたときの被害総額はある程度算出できるんですよね。ところが社会の法廷で負けたときの被害総額はなかなか算出できないんです。だから日本の企業の場合は、リーガル・コンプライアンスに比重を置きがちなんですね。しかしこの10年の世界の流れを見ると、特にアメリカ企業の発想というのは、見えない被害をより注意する。そちらのほうで勝つことを優先する動きがあるのは、事実だと思います。
ただバランスの問題なんですね。特にアメリカのような訴訟社会では、とてつもない額になるわけですね。短期的には大きな額になるんだけれども、3年や5年のスパンで見たときに、本当に裁判所で勝つのがいいのかは、判断が分かれますね。それはCEOが決めることです。周りとしてはその両方の視点をクリアにして、トップに明示できているかどうかが重要です。日本の企業の場合は、リーガル・コンプライアンスのほうばかりが色濃く出て、ソーシャル・コンプライアンスの部分が非常に薄くて、黙っていてもわかってくれるという感じが強いですね。
嶋田:どんどんCEOの仕事が難しくなっていきますね。最後の質問、いかがですか。
会場:立ち位置、メッセージについて、謝ればいいというものでもないと思います。例えば中国では絶対に謝ってはいけない、それがすべての終わりだという調査も来ています。先程のお話にもありましたが、国によって違うことを感じています。それから出すべきメッセージは、期待に応えるところに主眼を置いて選ぶ、という考え方でよろしいでしょうか。
田中:そうですね。謝罪はあくまでも手段に過ぎません。謝罪することによってその期待に応えられるのであればそうした方がいいし、別のことで期待に応えられるのであればその方法でいいと思うんですね。今おっしゃったように、空気が国によって違います。それだけに主戦場を中国、インドに置くと、空気を読む力がますます求められていくと思います。コミュニケーションというと、個人的なものと捉えられがちですが、組織のコミュニケーション力、組織の対話力があるんです。これからの CEO というのは、自らの対話力、自らが空気を読む、立ち位置をつくる能力を、持たなければなりません。それと同時に、組織的にそういう仕掛けをビルトインするのことも、CEOの役割になってきます。トヨタさんは元々、そういう仕組みを持っているはずなんです。そのトヨタでさえあのようなクライシスに陥ったことが、日本のほかの企業に警鐘を鳴らすことになったでしょう。奇しくもトヨタがビジネスの世界で、民主党が政治の世界で、対話力の重要性を私たちに教えてくれたように感じています。
嶋田:最後に一言、田中さんからこれからの日本のビジネスを引っ張っていく「創造と変革の志士」に向けて、コメントをお願いしたいと思います。
田中:一重に対話力です。立ち位置をつくるためには、対話力がないとできません。対話力をつけるためには、自己視点ではいけません。相手に何ができるのか。相手を知ることが、対話力の基本です。日本を世界に冠たるものにしていくためには、国にとっても企業にとっても一番重要なのは、ビジネスリーダーの方々です。しっかりとした立ち位置をつくるだけの対話力を持つことがすごく重要だと思います。このあすか会議はいろいろな人と出会うことができて、私は自分の立ち位置を再確認できる場にしています。今日が皆さんにとって、立ち位置をつくるための対話力を認識していただけるきっかけになったのであれば、私はとてもうれしく思います。どうも有り難うございました。